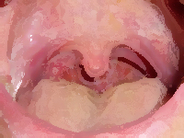現在、ルーヴル美術館は26歳未満のEU居住者、もしくはEU圏外の18歳未満は入館料が無料であるものの、原則有料だ。ただし例外があり、毎月第1日曜だけは、ルーヴル含むパリの国立美術館が無料解放されていた。その「無料の日」が、ルーヴル美術館のみ4月から9月までの観光客が多い時期に、適用されなくなった。
原因の1つは急激な来場者数の増加だ。
ル・モンド紙が伝えたルーヴル関係者のコメントによれば、2001年に500万人だった来場者数は2013年には930万人まで膨れ上がり、その7割を外国人観光客が占めているそうだ。第一日曜についても、通常の日の来場者が約2万人であるのに対して、第一日曜は3万人から3万8000人が来館する。
今回の無料制度の廃止に異を唱えるのが、美術館のあり方を考える団体「ルーヴル・プール・トゥース(みんなのためのルーヴル)」だ。ルーヴルに対する補助金は年2.5%ずつ下がっており、文化・通信省は公共文化施設に対しメセナ(企業などによる文化・芸術活動への支援)、チケット、館内スペースの賃貸などで、美術館の財政的自主性を上げよと要求している。そのため有料化の目的は、主に美術館の財政的な理由からだというものの、無料化してもルーヴルに実入りがないわけではない。増えた観光客が館内の本屋や土産物屋で多くのお金を落とすため、そこから利益は上がる。ルーヴルは仏美術館のシンボルであり、今回の決定が他の美術館にも波及するのではと危惧する。
現状はどうなのか。じつは意外に多くの人が無料でルーヴル美術館を訪れている。イル・ド・フランス地域会計検査院が出した報告書では、2013年にルーヴル美術館は70万人の児童を受け入れ、来館者の4割に当たる人が何かしら入館料を免除されているそうだ。
ベルトラン・ドラノエ前パリ市長は任期中に市立美術館を無料化した。先月新しく選出されたアンヌ・イダルゴ新市長は、その無料化を維持すると述べている。一方で今後、国立美術館はどのような形を取っていくのか。
(加藤亨延)