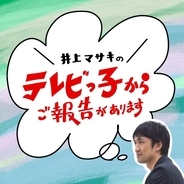《葬儀に立ち合うのは気が重い。だからいつも葬儀の関係者側について、忙しく振る舞いつらい気持ちを押し殺すことに徹してきた。弔辞なんか詠んだら泣いちゃうんじゃないか。泣いて詠めなくなるんじゃないか。
そんな高平が、放送作家でのちには小説家として直木賞もとった景山民夫が亡くなったときだけは弔辞を引き受けてしまった。中学以来の友人で、ともにテレビのバラエティ番組の制作に携わってきた2人。しかし80年代には景山が雑誌やテレビで高平を批判したこともあって、高平は彼と距離を置くようになる。それが1997年、仕事の打ち上げで行った焼肉屋で、高平は偶然にも景山と再会、そこで和解を果たすのだった。景山が自宅での火災で急死するのはその翌年のことである(このあたりの経緯については、以前紹介した高平の著書『今夜は最高な日々』にくわしい)。高平が景山に向けた弔辞の冒頭、《民夫、とんでもないことになっちゃったな》という言葉は、上記のような突然の死を受けてのものだ。
『大弔辞』にはこのほか、多くの著名人による弔辞が収録されている。なかには、芥川龍之介の師である夏目漱石への弔辞(厳密には弔辞ではなく、文芸誌『新思潮』に発表した「葬儀記」という随筆だが)、その芥川が亡くなったとき友人で作家の菊池寛が詠んだ弔辞も収録されていたりするのだが、やはり面白いのは高平が自分とゆかりの深い人たちの弔辞について、個人的なエピソードを交えつつ解説しているところだ。
たとえば、タモリが恩人であるマンガ家・赤塚不二夫(2008年死去)に向けた弔辞は、そのなかの《私も、あなたの数多くの作品の一つです》というフレーズがその年の新語・流行語大賞にノミネートされるなど話題を呼んだ。赤塚とは飲み仲間だった高平も葬儀に参列し、タモリの弔辞のあとで映画監督の山本晋也から《いやぁタモさんの弔辞は泣かせましたねェ。
タモリが赤塚に詠んだ弔辞は、テレビで中継されたこともあり一言一句たがわずに人々に知られることになった。しかし一方で、誤った形で伝えられてしまった弔辞もある。
しかし新聞では前半部分が「三沢さん、今、私達の前にある君の遺影は、レスラーのそれではなく、エメラルドグリーンの……」となっていて、《まるで、徳光さんが、レーシングスーツを着た三沢の遺影で語っているように編集されていた》という。
それにしても、こうして一冊にまとめられると、弔辞というのはそれを詠む人の人柄が如実に出るものだなとつくづく思う。たとえば、いかりや長介がかつてのドリフターズでの同僚である荒井注に向けた《出発間際の忙しい時に、とあんたは大変怒るかもしれないけど、ちょっとお話ししましょうや》なんて弔辞は、思わず声に出して(もちろん長さんのモノマネで)読みたくなる。この場合の語り口は、コントでの長さんよりもドラマ「踊る大捜査線」の和久刑事の口調こそふさわしい。
この本には、送る側と送られる側と両方の立場で登場する人も少なくない。前出のいかりや長介(2004年死去)は加藤茶の弔辞で送られ、谷啓(2010年死去)は同じくクレージーキャッツのメンバーである犬塚弘の弔辞で送られた。あるいは淀川長治についても、53歳にしてくも膜下出血で急逝したフランス映画社副社長・川喜多和子(1993年死去)への弔辞とともに、淀川が亡くなった際(1998年)に黒柳徹子が詠んだ弔辞が収録されている。生前、多くのヨーロッパ映画を日本に配給するとともにすぐれた日本映画を世界に紹介した川喜多に向けて、《亡くなられたのは五三歳でございましたが、あなたは百歳以上の業績を残されております》《映画の美しさをこれだけ守って、とうとう……。守って、守って、守って、守って亡くなったあなたに、私は、映画の、ほんとうの文化の豊かさのなかの戦死を感じます》と詠んだ淀川は、黒柳の《アフリカの国では、お年寄りが亡くなると大きな図書館が一つ消えたようなもの》という言葉で送られた。2つの弔辞をあわせて読むと、川喜多と淀川はともに映画という文化を守り続けた“戦友”だったのではないかと思えてくる。
さて、淀川長治とは1974年に雑誌「宝島」の編集者として出会って以来、交流を続けてきた高平は、訃報を聞いて打ち合わせの最中だったにもかかわらず涙が止まらなくなってしまう。このとき、打ち合わせの相手は《そういうときは、とにかく会いに行け、どこにいるんだ?》と高平に訊ね、《全日空ホテルです》との返事を聞くや《よし、今日はお開きだ。俺は高ッピラをタクシーで送ってそのまま帰るから》と残った人たちに言い残し、ホテルまで送ってくれたという。この機転を利かせた人物こそ誰あろう、先ごろ亡くなった落語家の立川談志であった。このエピソードからは、高平の淀川への想いばかりでなく、談志の人情の篤さも伝わってくる。
本書は自分が弔辞を書く際にはおそらく役に立たないだろう。下手に真似すると、参列者を感動させてやろうといった思いが先走り、結局失敗してしまうような気がする。それでもひとつだけ実践上で参考になりそうなものをあげるなら、《いい弔辞には必ずあるもの。それは弔辞を詠む人の、故人への「愛」にほかならない》という著者の言葉に尽きよう。もっとも、その「愛」をどう表現するかが難しいわけだけれども……。(近藤正高)
※高平哲郎氏の「高」は正しくはいわゆる“はしご高”ですが、機種依存文字のため、本稿では「高」の字を使用しました。