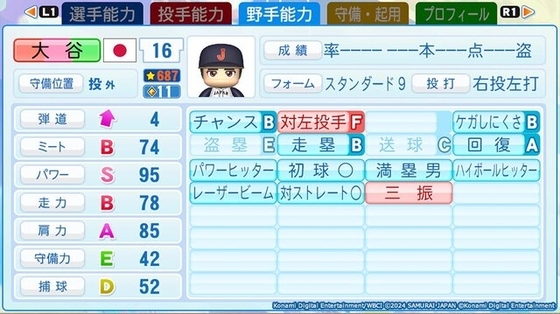負けたら毛を剃る。
1960年のローマオリンピックに、日本アマチュアレスリング協会(現・日本レスリング協会)は全階級出場、すなわちフリースタイル8名、グレコ8名のフルエントリーを目論んだ。後に日本オリンピック委員会の委員長を就任する竹田恒徳は、当時日本スケート連盟の会長の座にあり、日本体育協会理事を務めていた。その竹田に日本レスリング協会会長の八田一朗は、もし負ければ上も下も毛を剃る、あなたはスケートで入賞できなかったらこれができますか、と言って詰め寄った。八田の迫力に負けた竹田は、しぶしぶながら16名のエントリーを認めることになる。
結果は惨敗。
「私もですか? と八田会長に聞いたら『君ね、金メダル以外はメダルじゃないよ』と。
柳澤健『日本レスリングの物語』は、いかにしてレスリングというスポーツが日本に根を下ろし、黄金時代が築かれていったかを綴るノンフィクションだ。著者の名前をご記憶の方は多いだろう。『1975年のアントニオ猪木』に始まる数々の著作は、ここ数年で書かれたプロレス関連の書籍でもっとも興味深いものである。
関係者にインタビューを行い、数々の証言から全日本女子プロレスという過激派集団の姿を浮かび上がらせた『1993年の女子プロレス』、10代の女子ファンをとりこにした稀代の天才レスラー2人を主役とする『1985年のクラッシュ・ギャルズ』は、プロレスファンならずとも読むべき傑作である。後者は第43回大宅荘一ノンフィクション賞の最終候補作にもなった。
その柳澤が、日本レスリング界の正史を描いたのである。日本レスリング協会は、前身の大日本アマチュアレスリング協会発足の1932年から数えて、ちょうど今年で80周年を迎える。その記念年であり、同時にオリンピック・イヤーでもある2012年にこういう本が出たことはたいへんに意味がある。当然ながら協会関係者の談話が満載されており、その豪華な顔ぶれには目が眩む思いがするほどだ。
その「正史」の一部を紹介しよう。
ごく単純に言ってしまえば、日本レスリングの原点には「黒船来襲」の史実がある。時間は1921年3月のある時点にさかのぼる。ドイツ出身のプロレスラー、アド・サンテルは、アメリカ西海岸で日本人柔道家と柔道衣マッチを行い、ことごとく勝利して味をしめていた。そして「世界ジュードー・チャンピオン」を名乗り、柔道発祥の地である日本の講道館に挑戦状を叩きつけてきたのである。これに対して講道館の総帥・嘉納治五郎は拒否の姿勢を示した。門人に他流試合を許さなかったのである。
この庄司彦雄が日本にレスリングを根付かせた功労者となった……とできれば非常に美しいのだが、史実はそこまで単純ではない。どうやら庄司はヤマっ気の強い人物だったらしく、レスリングで外敵と戦ったという名声を足がかりにして政界に進出しようという野望があったらしい(柳澤は、サンテルとの闘いもリアルファイトではなくプロレス、すなわち事前の取り決めがあった試合の可能性があると書いている)。
以降の流れは、日本にレスリングという競技を根付かせようとする大志に燃える八田と、彼の足を引っ張ろうとする者たちとの政争の歴史といってもいい。身近な敵には、八田自身も段位を授かっている講道館がいた。レスリングという競技を牛耳れば、オリンピック代表として公費で海外に行くことができる。まだ洋行が夢の出来事であった80年前、それは大きな利権となるほどの魅力だったのである。早稲田の先輩である庄司もまた、八田の足をひっぱろうとした。こうして内外の人間を敵に回しながらも、八田は最終的には勝利を収めていった(講道館は専修大学レスリング部に人材を送り込んでいったため、八田率いる早稲田勢と専修とは宿敵の間柄にもなった)。だが時代は八田には微笑まなかった。日本は絶望的な全面戦争へと突入し、レスリングは敵性競技として禁止に追いこまれたからだ。日本レスリングが真の夜明けを迎えるのは、1945年の敗戦以降のことである。
ここまででなんと全14章のうちの第1章の内容しか紹介できていない。おそるべき密度だ。第2章以降は文字通り1からの模索で八田率いる協会がレスリング競技の「幹」を作り上げていく過程が描かれる。もちろん八田だけの手柄ではない。たとえばレスリングに必要なマットとシートを守ったのは正田文男である。戦災によって早稲田の道場は消失したが、正田によってマットとシートは運び出され、地下倉庫に保管されていたのだ。この正田は正田醤油の御曹司であり、かの美智子妃陛下の従兄弟にあたる。また、八田が姻戚関係にあった野口一族は、三笠宮崇仁殿下と深い結びつきがあった。その縁から三笠宮殿下はレスリング協会の大きな後ろ盾となられたのである。日本レスリング界繁栄の裏面にそうした宮家の尽力があったことは、あまり知る人の多くない事実である。
本書の内容は前後で大きく2つに分かれている。言うまでもなく、八田一朗時代とそれ以降だ。戦後の八田は、文字通り私財を投げ打って日本レスリング協会(1946年改称)のために尽くした。協会の進展は「八田イズム」の浸透・実践とともにあったと言っていい。その中で偉大なレスラーが次々に育っていく。競技で実力を発揮するばかりではなく著書によって自らの技術を体系づけ、世界のフリースタイル・レスリングの技術向上に貢献した天才・笹原正三(メルボルン・オリンピック金メダリスト)、1964年の東京オリンピックで金メダルを獲得した5人のレスラーたち、そのうちの1人上武洋次郎はオリンピック後にアメリカに留学し、カレッジ・レスリング関係者の投票で1960年代最高の選手に選ばれた(ちなみに1950年代はプロレスラーのダニー・ホッジ)。1976年のモントリオール・オリンピックで金メダルを獲得した高田裕司は、身体能力だけでいえば日本レスリング界の生んだ最高の才能の持ち主かもしれない。なにしろ試合で下になることがほとんどないため、ブリッジの練習の必要がほとんどなかったというほどだ。
しかしそうした好調の裏で、引き潮の時代は徐々に始まっていた。最初のつまづきは1980年、モスクワ・オリンピックのボイコットだといえるだろう。それに続く歯車の狂いが後半では克明に描かれていく。『1985年のクラッシュ・ギャルズ』で見せた柳澤の、語りの魔術を堪能していただきたい。
引き潮の時代とはすなわち、八田一朗亡き時代のことでもある。八田は1983年4月15日に生涯を終える(享年76)。その後の日本レスリングは迷走を続け、1988年のソウル大会を最後に、男子は金メダルから遠ざかっている。
ポスト八田の最右翼にいるのは、八田イズムの最後の弟子ともいえる福田富昭だ。先見の明のある福田は、早くから女子レスリングに目をつけ、FILA(国際レスリング連盟)に働きかけて各種大会への採用の道筋を作った。2004年のアテネ・オリンピックで吉田佐保里・伊調馨が16年ぶりに日本に金メダルを持ち帰ってきたのも、福田の長年にわたる努力が実を結んだ結果である。八田イズムの後継者として、福田も私財を投げ打つことを辞さないほどに日本レスリング協会の運営に尽くしている。日本レスリング界の未来を占う上で重要な施策がどのように行われ、未来への布石がどう打たれたのかは、本書の12章以降に書かれている。
それにしても驚異的なノンフィクションである。はじめに書いたとおり関係者への豊富なインタビュー量によって支えられているのだが、その裏表のなさにも驚かされてしまう。だって、協会内の派閥抗争、感情の行き違いに発した喧嘩の数々についても、赤裸々な証言が連ねられているのだ。たとえば1992年のバルセロナ・オリンピックの舞台裏である。この当時、協会内には人間関係のもつれが生じ、ほぼ崩壊寸前の状況だった。具体的にいえば、日本体育大学の藤本英男とそれ以外のコーチたちの間に修復不可能な亀裂が入っていたのだ。バルセロナ最後の試合が終わったあと、控室では藤本を囲んで一触即発のムードが漂っていたという。強化委員長の平山紘一郎が「みんな一生懸命やったんやないか。金メダルは取れなかったけど、日本代表として、応援してもらってここまできた。だから羽田で解散するまでは、日本チームとして行動してほしい」と懇願してなんとか収まったのである。いや、そこまで身内の問題をあけっぴろげに言うのも珍しい。すごいぞ、日本レスリング協会!
海外ではレスリングは花形スポーツの一つだが、日本ではまだまだマイナーだ。競技人口の数では柔道に圧倒的に及ばず、レスリングで身を立てるということも難しい。その理由の一つは、日本においてはまだスポーツが運動「教育」の管轄下にあるものと見なされ、それとは無関係に娯楽として楽しむという考えが定着していないことにある。柳澤は最後に視野を大きく広げ、この国におけるスポーツのありようについて一つの提言をしてこの意義ある本の記述を終えるのである。レスリングの経験者ではなく、インドア派でスポーツの経験もあまりない私でも、本書は興味深く読むことができた。間もなく開幕するオリンピックの前に、ぜひとも絶対に読んでおきたい1冊だ。
(杉江松恋)