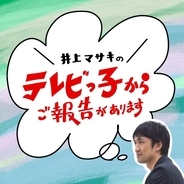映画『マイ・フェア・レディ』『プリティ・ウーマン』のように、「理想の女性を作り上げる」といった筋立ての物語は少なくない。もしかしたら、世の男性には、多かれ少なかれ潜在的にそうした欲求があるのかもしれない。
『理想の花嫁と結婚する方法』の主人公トマス・デイは、奴隷制度廃止論者で、児童文学の先駆けとして知られる18世紀イギリスの偉人だ。自由や人権に関して進歩的な意見を持ち、頭脳明晰で高い教育も受けている。その上、たいへんな資産家。本来であれば、モテモテであってしかるべき男である。
もっとも、世間からズレているとはいえ、自らの力と才能と財産を善行のために使おうというデイは、尊敬を集めるのに十分な「徳の人」であり、興味を持つ女性も少なからずいた。しかし、彼の理想主義は、自分の伴侶となる女性の資質にも向けられた。そして、それが彼を結婚から遠ざける。
デイの考える理想の花嫁像とは、聡明で博識で機知に富み、純粋で清らか、若く美しくたくましい女性であり、農民のようなつましい生活を好み、デイを主人として、教師として、自分より優れた人物として尊敬し、彼の要求や気まぐれに応え、彼の意見や信念に完全に同調してくれる女性ーーということになる。
「無理……」男の私でもそう思う。
そんなデイにも、相手の理想に合わせて、自らを変えようと試みた時期があった。上流階級の文化や、表面的に着飾る風習を「下らない」と憎んでいたにもかかわらず、ある女性のために、頑張って「一般的な洗練された紳士」になろうと努めたのだ。フランスまで出向き、ファッションやらダンスやら社交やらを「自己嫌悪に陥りながら」学んだ。そして「本物のジェントルマン」となって凱旋するのだが……悲しいかな、待っていたのは嘲笑だった。
完璧な紳士になるために送りだしたはずのデイが、完璧な愚者となって帰ってきた。
なんてヒドイことを書かれていて思わず気の毒になってくるが、自分を曲げてまで変身したにもかかわらず、あっさりと婚約は解消されてしまう。
デイは悟った。理想の花嫁は、自分の頭のなかにしか存在しない。であれば、それは自分で作るしかないのではないか、と――。
かくして、デイの「理想の花嫁作り」がスタートする。そして、その過程に大きな影響を与えたのが、自由と平等について大胆な学説を打ち立てた『社会契約論』で知られるフランスの哲学者ジャン=ジャック・ルソーによる『エミール』だ。架空の生徒エミールに、幼年時代から大人になるまで理想の教育を施していく過程を描いたこの小説は、当時、ヨーロッパで用いられていた教育法とはまったく異なる内容だったため、大きな物議をかもした。しかし、一方で熱狂的な信者も生んだ。友人に『エミール』を紹介されたデイも、あっという間にその1人となる。
デイは、「人は善なるものとして生まれてくるが、文明に影響を受けて堕落するから、本来の純真無垢な性質を守り育てる教育をすべし」というルソーの教育論を基に、理想の花嫁を生み出そうと考えた。
18世紀のイギリスでは、他のヨーロッパの国々同様に、非摘出子の数が増加していた。常にパンク寸前の状態だった孤児院は、早急に孤児たちを奉公に出すことを迫られていた。そんな施設の1つ、ファウンドリング・ホスピタルに現れたデイは、アン・キングストンという「鳶色の巻き毛と茶色の瞳を持つ、華奢でかわいらしい」12歳の少女を、既婚の友人宅のメイドとして働いてもらうという名目で引き取る。デイは、この花嫁候補第1号を、すぐさま「サブリナ」と改名させる。
と、「第1号」という言葉に「あれ?」と思った方もいるかもしれない。そう、教育を施す少女は1人ではなかったのだ。過去の苦い経験から、女性に対する不信感が強かったデイは、万全を期したかった。
デイは、幸せな結婚をすることを運任せにしたくはなかった。そこで、貴族の家長が息子をふたり(跡取りと補欠)もうけるのと同じ方法を採用することにし、ひとり目が期待にそぐわなかった場合のためにふたり目の孤児を連れてきたのだ。
サブリナの教育開始から数週間後に、孤児院を再び訪れたデイは、1人目の時と同様に、友人宅のメイドとして金色の髪と青い瞳を持つ11歳の少女、ドーカス・カーを引き取り、「ルクレティア」と改名させる。
デイはふたりをルソー流で教育し、成功したほうを将来の妻に選び、失敗したほうはあっさり捨てるつもりだった。
こうしてスタートした花嫁育成計画は、順調に進んだ。そう、最初のうちは。
2人は禁欲的な生活に耐えた。「家のなかの仕事はすべて妻がすべき」というデイの信条に基づき、家事の大半を2人でこなした。「重要な問題についても話し合えるように」という理由から、地理や物理学、天文学の基礎原理も学んだ。教師(デイ)を喜ばせたい2人の生徒は、彼の教えの数々を熱心に吸収した。
そして、最初の決断の時が来た。デイが選んだのはサブリナだった。ルクレティアは「勉強面でも忍耐力に関してもまったく進歩がなかった」ため、お払い箱となる。婦人帽子屋に400ポンド(今で言えば6万ポンド)の餞別付きで奉公に出された。
対象を1人に絞ったデイは、プライバシーを守れる地に引越し、計画を次の段階に進める。ここにきて、デイの「教育」はより異様なものになっていく。
デイはサブリナに袖をまくりあげ、肩を出すように命じた。それから棒状の蝋燭を手にとって蝋燭の炎で熱し、サブリナに動くことも声をあげることも禁じたうえで、むきだしの背中や腕に蝋を垂らした。(中略)蝋の代わりに針を突き刺されたこともある。
SMにはあらず。これはデイの考える「丈夫な身体を作るため」の試練の1つである。しかも、サブリナは痛みだけでなく、暑さや寒さにも耐えなければならなかった。
デイは家の前の土手へサブリナを連れていき、服を着たまま池のなかに入らせた。サブリナを池に投げ込んだという説もある。
サブリナが泳ぐことができなかったにもかかわらず、である。さらに、恐怖への耐性をも鍛えられる。
ピストルをとりだし、声を出さないでじっと立っているよう命じた。(中略)撃鉄を起こして狙いを定めると、スカートを撃った。弾丸が装填されているのかどうかサブリナは知るよしもなかったし、デイも教えるつもりはなかった。
「弾がスカートを貫通したが、怪我はなかった」そうだが、どう考えてもやり過ぎだ。それに、そもそも花嫁とか関係なくないか?トンデモ花嫁修業は、まだまだ続く。
贅沢や虚栄心を排する力を試す際は、サブリナに大きな箱をプレゼントした。サブリナが蓋を開けると、なかには美しい服がたくさん入っていた。(中略)しゃれた服をもらって喜ばない一〇代の娘などいない。ところが、デイはその服を箱ごと火にくべ、高価なシルクやレースの服が燃えて灰になるまで見届けるようサブリナに命じた。
サブリナの忠誠心や服従心を試す試練もあった。(中略)「サブリナが秘密を守れるかどうか試すために、自分に危険が迫っていて、事態に気づいていることがばれたらさらに危険な目に遭うはめになるという作り話をした結果、サブリナが使用人や友人に秘密を打ち明けていたことを知った」。
ここまでくると、滑稽で、もはや冗談のようだが、もちろんデイは本気だ。しかし、こんなことを「教育」などと称してされる方はたまったものじゃない。しかも、サブリナにはこの試練の目的(理想の花嫁を育成する)は知らされていなかった。月日が経つにつれ、不満や疑問が蓄積していったのも当然である。それらが、彼女を反抗に駆り立てるのは時間の問題だった……。
前代未聞の「計画」の行方やいかに? デイは、理想の花嫁を手にすることができるのか?
ということになるわけだが、この奇妙奇天烈な物語は、この後、医師・詩人・自然哲学者のエラズマス・ダーヴィン(進化論で知られるチャールズ・ダーヴィンの祖父)や、発明家・教育家のリチャード・ラヴェル・エッジワース、当時台頭してきたアンナ・シーワード、フランシス・バーニーといった女流作家らを巻き込み、驚きと苦笑にまみれた怒涛の展開を見せる。
ゴシップ趣味的な面白さ満載だが、有名人たちのアナザーサイドを垣間見られる、歴史的な貴重さもある。膨大な資料と、皮肉たっぷりのユーモアでもって書かれた、快作にして労作である。あなたは、本書『理想の花嫁と結婚する方法』を読んだうえで「僕の理想の女性はねー」なんて語れますか? 私は無理だなぁ……。
(辻本力)