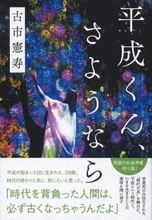悪魔「このままネコババしちまえよ……、だれも見てないんだぜ!」
天使「なにを考えているんだ。ちゃんと交番に届けなきゃダメだろう」
我欲と良心のこういう葛藤を、アニメ『トムとジェリー』や喜国雅彦さんの漫画でよく見た。
塚本晋也が映画化した大岡昇平の『野火』(角川文庫)では、日本兵が飢えに突き動かされ、死体を解体しようと剣を抜いたそのとき、〈剣を持った私の右の手首を、左の手が握った〉。右手が左手を止めたのだ。
就寝前にラーメンなんか食べちゃ体に悪い、と頭で知っていても、食べたくなってしまうことがある。親友の彼女だと知っていて、好きになってしまうこともある。
ここまで挙げた葛藤は、自分のなかに喰い違う複数の考えが存在していることを自分で自覚しているから、まだマシなほうかもしれない。
人はしばしば、自分のなかにある複数の考えかたが食い違っていることそれ自体を、意識できないのだ。
たとえば米国で妊娠中絶に反対する人は、だって人工中絶は〈殺人〉だよ、と言う。
ところが、ロバート・クルツバン『だれもが偽善者になる本当の理由』(高橋洋訳、柏書房)によれば、人工中絶が殺人であると主張する人は、人工中絶は禁止したいが、中絶することを決定した親に殺人罪を適用することは考えていないのだそうだ。
しかし殺人罪を適用できないというのであれば、そもそも人工中絶は殺人ではないということになるのではないだろうか?
この矛盾を指摘したからといって、クルツバンは、殺人罪を適用せよといっているわけではない。中絶の自由を認めよと主張しているわけでもない。
クルツバンはただ矛盾が存在するということだけを指摘しているのだ。
かつて古典的な経済学が考えた「人間」像は、経済的な合理性に基づいて行動する人間だった。ところが、じっさいには人間は、どんなに頭がよくても、あるいはどんだけ金の亡者であっても、経済的な合理性に反する行動をとってしまう。
ほんとうは「どうしたい」のか? 「ほんとうの自分」が望んでいるのはどの行動なのか?
クルツバンによれば、そういうのは「問いがそもそも悪い」ということになる。
心のなかに「ほんとうの自分」が単体で核のように存在している、という考えかたは、心と体を分けて考える西洋近代の心身二元論の特徴だ。
このことはすでに、哲学者で認知科学の研究者でもあるダニエル・C・デネットが『解明される意識』(山口泰司訳、青土社)で述べていた。
体が知覚・経験するものごとを、「精神」という小人さんが脳内の劇場・映画館で鑑賞している、というこのモデルを、デネットは〈カルテジアン劇場〉(デカルト劇場)と名づけて、それは妥当なモデルではないと批判した。
デカルト劇場はおもに知覚・認識における隠喩だが、クルツバンは意思決定・行動における隠喩として、かつてディズニーランドにあった「クレイニアムコマンド」(直訳すると「頭蓋骨指令」)というアトラクションを引き合いに出す。
「クレイニアムコマンド」のプレイヤーは12歳の少年ボビーの脳内にいる小人のバジーとなって、ボビーを操縦する。
映画『パシフィック・リム』や昭和の特撮番組『ジャンボーグA』の巨大戦闘メカみたいな人間観である。
そんなことあるかい!とクルツバンは言う。
クルツバンの人間モデルをざっくり説明すると以下のようになる。
──人間を含む動物の脳機能は、無数のモジュールが複合してできている。その全体を把握する大統領みたいな責任主体を、脳機能の一要素として特定することはできない。
「私」が意識する「私」というものは、「私」という国家の最終決定権を持っている大統領なんかではなく、ホワイトハウス全体で揉んだ案を公表する報道官みたいなものだ、ということらしい。
──モジュールの働きには、意識で把握できるものもあれば、できないものもある。
報道官はホワイトハウスのどの部署がどう動いて案が決定したのかというすべての細部を把握してはいない、ということ。
──すべてのモジュールが連関しているわけではない。てんでに動いて、結果として矛盾することだってある。
ミュラー・リヤー錯視において、「棒の長さが違う」と感じるモジュールと「棒の長さは同じ」と知っているモジュールとが、それぞれ勝手に自分の仕事をしている。
就寝前の食物摂取が体に悪いとか、親友の彼女を奪うとあとで面倒なことになると知っているモジュールがあるからと言って、飢えないように栄養を摂取しようとするモジュールや、自分の遺伝子をより広く残そうとするモジュールの活動が止まるわけではない(←クルツバンがやっている学問の名称は「進化心理学」)。コンフリクトして当然なのだ。
──人は、ほんとは自分(のなかのある種のモジュール)がしたいことを「するな」と他人に禁止したがる。
だから、米国でドラッグや食品安全基準や賭博や臓器売買や銃規制や人工中絶をめぐって交わされる議論で、論争している人たちが出す「理由」はしばしば筋が通らない。
クルツバンは心を、〈さまざまなモジュールの協調の産物〉としてモデル化する(第8章)。
そういえば、インドの仏教哲学者ヴァスバンドゥの『阿毘達磨倶舎論(あびだつまくしゃろん)』にかんする概説書で読んだんだけど、仏教ではこの2000年くらい、心はひとつの実体でなはく多数の力の相関としてとらえられている、という話を思い出した。よく似てるし、実態に即している気もする。
クルツバンはこの『だれもが偽善者になる本当の理由』のなかで、経済学や心理学の先行モデルを強い口調で(煙たいアメリカンジョークも多々まじえつつ)批判し続ける。
また〈自己欺瞞〉とか〈自己コントロール〉といった"self"がつく言葉は非科学的で、使うと碌なことがない、と繰り返す。アクの強い本だ。
それにしても、「首尾一貫するべき自己」という像を、クルツバンはなぜこんなに強く否定し続けなければならないのか? 「人間は勝手に動く部品の集積である」ということを言うために、ここまで強く、かつ噛んで含めるように書かなければならないのはなぜだろうか?
つまり、「首尾一貫した自己像」をキープしなければならないプレッシャーが、それくらい米国では強いということなのだろう。このあやふやな日本では考えられないくらい。それは気を張って生きるのが当たり前の文化ということなのだ。
「あなたは生物学的個別機能の集成なので、各機能どうしが矛盾して、自前の根性だけではあなたの意志を首尾一貫できませんよ」
と言われたとしても、日本人はたいしてショックも受けず、
「あー、そうなんだー。やっぱりね」
とかえって安心してしまうくらいだろう。
でも、そんな無責任というかだらしない日本人の僕でも、責任を問われる決定の場面では、自分のなかのホワイトハウスの複数意見からひとつをチョイスしなければならないことがある。
せめてそういうときだけは、本田圭佑に〈どこのクラブでプレーしたいんだ?〉と訊ねられて〈ACミラン〉と答えたという「心のなかのリトル本田」みたいなものを、嘘でも無理矢理「存在していることにしておく」ことにしておいたほうが便利かもしれないわけで、いやー人生って、ほんっとうに無理ゲーですね。
(千野帽子)