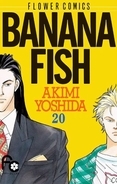現在、再ブームと言われているプロレスの現状とは? プロレスの面白さとは一体何か? プロレスの人気が低迷していた原因とは? などについて、三田さんに縦横に語っていただきました。

──三田さんは20年間、世界唯一の女性プロレスキャスターとしてプロレスを見続けてこられたわけですが、今はどれぐらいのペースで観戦しているのですか?
三田 今は月に10大会ぐらいですね。年間で120大会、20年見ているので、優に2000大会は見ている計算になります。
──ひとつの大会につき5試合はありますから、プロレスをライブで1万試合以上見てきたことになりますね。
三田 数字にすると、すごいインパクト(笑)。

プロレスの観戦スタイルが変わってきた
──今またプロレスが盛り上がっていると言われていますが、実際はどのような感じで盛り上がっているのでしょう?
三田 ダントツなのは新日本プロレスで、“プロレスの聖地”と呼ばれている後楽園ホールは1800人から2000人ほど入りますが、月に3回ほどの興行をすべて超満員札止めにしています。DDTや大日本プロレスのようなインディー団体も、後楽園ホール大会はほぼ満員。新日本、DDT、大日本は5000人ほど入る両国国技館も満員にしていますね。試合のクオリティも高く、会場はどこも大変盛り上がっています。苦しい団体もありますが、新日本プロレスがお手本になって、プロレス界全体を引っ張っている感じですね。
メディアへの露出も増えていて、新日本プロレスの棚橋弘至選手や真壁刀義選手などはバラエティ番組への出演も目立ちます。特に棚橋選手は、かつての無口で怖いプロレスラーのイメージを覆した、プロレス再ブームの立役者と言ってもいい存在です。
──プロレスの客層が変わってきたということでしょうか?
三田 新しいお客さんが本当に増えました。
──以前は「猪木の謎かけ」を一生懸命考えるようなファンが多かったと思いますが、今は“陽性のエンターテインメント”になったわけですね。
三田 「選手がキラキラしていてカッコいい!」という感じで入ることができるようになったのが今のプロレスの特徴です。象徴的なエピソードがありまして、棚橋選手に「どんな準備をしてプロレス観戦に行けばいいですか?」とお聞きすると、「何も準備しないで、手ぶらで来てください」と答えるんです。「そしたら、僕がたくさんお土産を持たせて帰しますよ」って。
──いいこと言いますねえ!(笑)
三田 予備知識がなくても、試合を見れば「わぁ、すごいなぁ!」と楽しめるのが今のプロレスです。ただ、入口はライトでも、どんどん深みにハマっていく人も多いですよ。インターネットなどで過去のことを調べれば、「あ、この選手と選手の間にはこんな因縁があったのか!」とわかります。プロレスには後から反芻する楽しみもあるんです。
プロレスの人気が低迷した本当の原因とは?
──三田さんがプロレスを見ていた20年は、新日本プロレスがドームツアーをするなど、まさに絶頂期にあった90年代半ばから、PRIDEやK-1などの格闘技に押されて一気に人気が凋落し、そこからゆっくりと回復していった歴史とぴったり重なっています。
三田 『プロレスという生き方』を書きながら、自分でも「ああ、そうだったんだな」と思いました。この本の「はじめに」は東京ドームの高田延彦VSヒクソン・グレイシー戦の思い出で始まっているんですよね。
──まさにプロレス人気が低迷するきっかけとなった試合でしたね(1997年)。プロレス人気が低迷していた時期と現在とでは、どのような違いがあるとお考えですか?
三田 総合格闘技やK-1に押されてプロレスの人気が落ちていったと言われることがありますが、私はそうは思わないんです。
──と言いますと?
三田 プロレスラーが総合格闘技のリングに上がって負けてしまったのは残念な事実ですが、プロレス人気が落ちたことをそれだけの理由にしてしまってはいけません。一番良くなかったのは、総合格闘技の登場でプロレス団体の考え方がグラグラと揺らいでしまったことだと私は思います。
たとえば、総合格闘技側が話題づくりのためにアントニオ猪木さんを取り込み、さらにたくさんのプロレスラーをリングに呼びました。あのときの新日本プロレスは、オーナーだった猪木さんとの関係もあって、「ウチはウチでプロレスをやっていく」という路線を貫くことができなかった。プロレスラーが総合格闘技で負ければ、プロレスファンはがっかりしますし、プロレスをやりたいプロレスラーは団体を離れてしまいます。
プロレス団体の考え方が揺らいでしまい、そこから起こった悪循環がプロレス人気を落としてしまったんだと、今、思いますね。
──逆に今、プロレスの人気が上がってきたのは、迷わずプロレスという本業に打ち込んだからだと言うこともできそうですね。
三田 プロレス団体とプロレスラーが一番何をしなきゃいけないのかと考えると、「ちゃんとプロレスをやる」「プロレスは面白いということを知らしめる」、この2つに尽きると思います。それを一心不乱にやってきたのが棚橋選手だったんです。
──ああ、総合格闘技の時代は、プロレスが異業種に進出して失敗したということだったんですね。たしかに一般企業でも異業種に進出して失敗する例は、枚挙に暇がありません。
三田 近年、プロレス団体が新規のお客さんを得ることができたのは、プロレスをしっかりやったことと、それを周知したこと、あとは団体側がファンサービスをしっかりやったからだと思います。
新日本プロレスの親会社、ブシロード社長の木谷高明さんは大変面白い方で、「すべてのジャンルはマニアが潰す」とおっしゃっています。ちょっと強い言葉なのですが、たしかに業界全体がマニアのことだけ考えていたら、お客さんは広がりませんよね。
でも、やっぱり新しいお客さんだけでなく、マニアも満足させなければいけないと思います。プロレスが一番ダメだった時期には、新規のお客さんを掴もうといろいろなことをしていましたが、失敗の連続でした。芸能人をリングに上げてもマニアは満足しませんし、プロレスファンは広がりません。プロレスファンを満足させるには、プロレスラーがしっかりとプロレスをやるしかないんですよ。
東京ドームから電車まで、これがプロレスの豊かさだ
──先ほど「ダントツ」と表現されていましたが、昨今のプロレス界は新日本プロレスが中心です。ところが、三田さんの『プロレスという生き方』には、新日本の棚橋選手や中邑真輔選手と同時に元DDTの飯伏幸太選手、プロレスリングNOAHの丸藤正道選手、女子プロレスの里村明衣子選手やさくらえみ選手なども取り上げられています。なぜこのような構成になったのでしょう?
三田 「プロレスが面白くなったよ!」ということをみなさんにお伝えしたいと思ったとき、「プロレスってこんなに幅広いんだよ」ということをこの本で書きたかったんですね。新日本プロレスはもちろん面白いのですが、他の団体や選手もみんなが自分のできる頑張り方をしたから、今これだけプロレス全体が面白くなっているんだと思います。
不遜な言い方になりますが、プロレスの幅広さ、プロレスの豊かさを伝えることができるのは、私しかいないんじゃないかとも思っています。
──なにせ1万試合以上見ているわけですからね。
三田 東京ドームで行われている試合から電車プロレスまで見ている人は、そんなにいないという自負があります(笑)。メジャー、インディー、女子問わず、面白い人を出していきたかったというのが、この本の出発点です。
──プロレスの幅ということについて、もう少し教えてください。そもそも電車プロレスって何ですか?(笑)
三田 まず、プロレスの幅についてお話しすると、『週刊プロレス』の2016年版選手名鑑に載っているプロレスラーの数が528人です。でも、これで全部ではなく、ローカルのインディー団体を含めるともっと多くなります。プロレス団体も30~50と言われていますが、本当に小さな団体や地方の団体を含めると、もっと多くなるでしょうね。
電車プロレスは文字通り電車の中で行うプロレスです。廃線の危機にあった山形のローカル鉄道会社が街おこしのためにみちのくプロレスを呼んで、本当に狭い電車の中でプロレスの試合をしたんですよ。私も見に行きましたが、「プロレスって何でもできるんだなぁ」とあらためて思いました(笑)。
──リングがなくても試合ができるんですね。
三田 リング以外で行う「路上プロレス」が有名になったのは、2008年の本屋プロレスからです。路上プロレスで活躍しているのが、この本でも取り上げた飯伏幸太選手。路上だから地面はアスファルトだし、周囲もコンクリートだらけなのに、リング上と変わらぬ美しさでプロレスを繰り広げる飯伏の姿にファンは魅了されているんです。なにせ自動販売機の上からムーンサルトを決めますからね(笑)。
──その後、飯伏選手は新日本プロレスでも活躍しました。本屋から東京ドームまで、本当に振り幅が広い選手ですよね。
三田 何でもできちゃうところが、プロレスの懐の深さですね。
かつて新日本プロレスと全日本プロレスが2大メジャー団体として君臨していた時代は、路上プロレスどころかインディー団体すらプロレスとして認めないという空気がありました。でも、今はメジャー、インディー問わず「いいものはいいよね」と認め合えるような感じになっています。だから、飯伏のような選手が活躍できるんです。
──プロレスの幅の広さ、懐の深さは、すなわち豊かさでもあるということですね。
三田 はい。それはプロレスの優しさでもあり、温かさでもあります。これだけ幅が広ければ、どんな人も必ず自分にぴったりの団体や選手を見つけることができると思いますよ。ストイックな戦いが好きな人、イケメンをたくさん見たい人、凄絶なデスマッチを見たい人……。読んだ人が自分にぴったりのプロレスを見つけることができればいいな、と思いながらこの本を書いたんです。
(後編につづく)
三田佐代子・著『プロレスという生き方──平成のリングの主役たち』(中公新書ラクレ)は全国書店にて好評発売中。なお、本書は発売後わずか3日で重版出来! おめでとうございます!