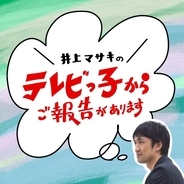助六の背中を追い続けた菊比古だったが、実はその助六にも、陽気な表の顔とは裏腹の弱い一面があった。
そうした具体に大きな変化のあった第9話だったが、そのきっかけは、菊比古と助六がそろって真打昇進を果たしたことだった。雲田はるこの原作では第3巻から第4巻の序盤にかかる部分である。
真打興行の季節だ
東京の寄席では1月を上中下の3つに分け、10日ずつで興行が組まれる。この3月下席からは、いよいよ落語協会の真打披露興行が始まるのだ。
1年の中でも真打披露は人気の興行の1つだ。
口上で有名だったのは、八代目桂文楽(先代。故人)だ。落語協会会長を2回務めた文楽は披露目に上がる機会も多かったはずだが、そのたびに述べるフレーズがファンにとってはお楽しみだったのである。
──師匠(文楽)の口上には、いくつかのパターンがあって、それは今でも楽屋の語り草になっている。(中略)
「なにか奥の方にピカッと光るものがございますので」
とか、
「まことに親孝行でございますので」
などと入るので、楽屋でも、
「どうだい、ピカッと光らすかい」
などと云いながら、口上の座に向うのであった。(柳家小満ん『べけんや わが師、桂文楽』)
真打披露興行はマラソンだ
上に書いたように、落語協会ならば約50日間、切れ目なく披露興行は続く。それだけでも大変なのに、助六は高座に掛ける演目を毎日変えたという。
落語協会の若手真打で現在もっとも注目されている春風亭一之輔は、2012年3月に21人抜きで昇進を果たした(過去には春風亭小朝が1980年に36人抜きをした例がある)。このときは複数ではなく1人だけの昇進であり、50日間連続で興行の主任(トリ)を務めたのである。掛けた噺の数は24席だが、最初の11日間は毎日違うネタだった。師匠である春風亭一朝もそれにつきあって毎日違う噺を掛け続けたため、あらぬ噂が立ったのである。
──それで、十二日目の四月二日、(春風亭)正朝師匠からも「師弟で五十日間変えるって評判になってるよ」って言われまして。
師匠が「おまえ、今日何やるんだよ」
「師匠、私、先に降りますから楽にならせてください」って、一度かけた「欠伸指南」をやりました。
あとから聞いたら、師匠は、そのまま五十日五十一公演、毎日違うネタでもいいってその気になっていたようなんです。(春風亭一之輔『一之輔、高座に粗忽の釘を打つ』)
こうした噺の選択以外にも、祝賀パーティがあったり、着物を新調したり、演者によっては後ろ幕を作ったり、と何かと物入りなのが昇進というものらしい。披露興行はもちろんのこと、気に入ったらその後の高座も聴いて、ぜひ贔屓にしてもらいたい。
真打は興行のボスだった
真打という言葉は「芯打ち」から来ているという。興行の最後、もう後に上がる者はいないということから、高座を照らすろうそくの芯を打って消し止めたのだ。
現在の定席はそうではないだろうが、戦前の興行においては、出演料を各人に払うのも真打が責任をもってやっていた。
──そうすれば、それァみんな商売人ですから、高座から見れば、お客はどのくらい、楽屋入りがどんくらいだろうなんということは、たいていわかっていますから、七、八十だな、と思ってもらったワリを、ひょいッと見ると、一ソク(百)出ている。
「おゥお、これァ真打がなかなかがまんをしているのえ」
なんてんで悪い気はしない。それにまた、席亭のほうでも、それを決けば、
「やつも大分苦しいのにがまんをしていいワリを出してる……かわいそうだから、じゃァ今度ァもっといい時期に、おれンとこでまた打ってやろう」
なんということになる。(三遊亭圓生『寄席楽屋帳』)
このへんはかつてのアメリカン・プロレスが、チャンピオンになれる者は興行に人を呼べなければならず、ただ強いだけでは駄目だった、というのと同じ呼吸だ。
今回の噺
今回の噺は、真打披露興行で助六がかけた「居残り左平次」、そして破門になった助六の影を感じながら菊比古がかけた「紙入れ」の2席である。
「居残り左平次」は、以前に触れた「品川心中」と同じ品川宿を舞台にした噺だ。遊廓で勘定が払えず、算段がつくまで留め置かれる客を居残りと呼んだそうだが、これは自ら進んでその居残りとなる男の噺である。勘定を踏み倒すどころか、祝儀をかすめたり、旦那の着物を奪ったり、と散々に荒しまくるふてぶてしさが主人公の見事なところで、最近の演者では故・立川談志が自らの分身のような左平次を創造していた。昭和の名人と呼ばれた六代目圓生、五代目志ん生など、名だたる演者が十八番にした大ネタである。難はオリジナルの落ちがわかりにくいことで、詐欺を働くことを昔「おこわにかける」と言ったのを、旦那の頭が胡麻塩なので、だから「おこわ(強飯)にかけた」となる。談志をはじめ、さまざまに演者は改良しており、聞き比べも一興である。
談志の孫弟子に立川左平次という落語家がおり、「居残り左平次」と師匠・立川左談次をかけたいい名前である。先年真打を果たした後、各所で真打披露興行を開いてきたが、来る3月19日、横浜にぎわい座のそれが最後となる。気になる方は行ってみては。「居残り左平次」がかけられるか否かは保証の限りではないが。
「紙入れ」は、亭主の留守の間に間男に入った男が、間抜けなことに紙入れ(財布)を忘れてきてしまい、それで足がついて浮気がばれたかどうか、と思い悩む噺だ。浮気の相手であるおかみさんが、男を手玉に取るような凄みのある女性で、これは若僧などひとひねりにされてしまうだろう、と納得してしまう。そのものずばりではないが結構際どい台詞などもあるので、いわゆる艶笑噺と呼ばれる一席だ。落ちが通常のものとどんでん返しのあるものと2通りあり、後者のほうにたまに行き当たることがある。
次回予告では、小さな女の子が登場することが明かされた。みよ吉と助六の間に生まれた子供だろう。言うまでもなく、後の小夏である。加速する物語の次回にも注目だ。
(杉江松恋)