「AI(人工知能)元年」といわれた2017年。今も多くのメディアでAIが導く素晴らしい未来が語られているが、同時に注目されているのが「AI脅威説」だ。
AIで仕事が効率化されるということは、AIに仕事を奪われる職種が出てくるということでもある。筆頭はタクシーや宅配便などの運転手だろう。すでに小売業にはAI導入で売り上げをアップさせた企業が存在し、製造業もAIによって検品が劇的に変化し、同作業を行う従業員が必要なくなるともいわれている。
そして、「AIに仕事を奪われる」とされる職種のなかでも、意外なのが弁理士である。弁理士といえば超難関資格として知られるが、ある研究で「AIに代替される可能性が92.1%」という試算が出ているのだ。
この研究結果について、当の弁理士側はどう考えているのだろうか。
●「AIによる代替可能性92.1%」には根拠がない?
少し前の話になるが、イギリスの名門・オックスフォード大学と日本のシンクタンク・野村総合研究所が共同研究を行い、「10~20年後に、AIによって自動化できるであろう技術的な可能性」という試算データを発表した(2015年12月)。
そこには「AIに代替されかねない職業」として、弁護士・公認会計士・行政書士などの「士業」も含まれており、なかでも「AIで自動化できる士業」として92.1%という高い確率が示されたのが弁理士だ。
弁理士は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの知的財産権(特にこの4つの権利を産業財産権という)を取得したい人の代理として、特許庁への手続きを行うのが主な仕事だ。超難関資格のひとつに数えられ、弁理士試験の合格率は、おおむね10%以下。
そんな狭き門を突破してせっかく弁理士になったのに、AIに取って代わられてしまってはたまったものではない。では、弁理士は本当に「AIに代替されかねない職業」なのか。
その点について、日本弁理士会副会長の梶俊和氏(ブライトン国際特許事務所所属)は、「『AIによる代替可能性は92.1%』という数字を算定した根拠には具体性がない、というのが日本弁理士会の見解です」と反論する。
「というのも、研究に参加していたオックスフォード大学のマイケル・オズボーン准教授が書かれた関連論文を紐解いてみると、『どのような業務がいつ頃代替されるのか』『どのような計算に基づいて算出された代替率なのか』などの分析が不明確で、判然としない部分が多いんです」(梶氏)
梶氏によれば、今回の研究結果の背景にあるのは「弁理士業務への理解度の低さ」だという。
「弁理士の主な業務は、特許、実用新案、意匠、商標という4つの産業財産権について、出願人の代理人として特許庁に出願し、権利化を目指すことです。しかし、実際の仕事はそれだけではありません。特許の出願を例にすると、まず発明者へのヒアリング、過去に同じような知的財産がないかを調べる『特許調査』、実際に特許が設定されれば権利の活用法の提案、ライセンス契約を結ぶときの代理業務、模倣されたときの差止めなどの対応策の提案など、多岐にわたります」(同)
権利取得だけでなく権利化後の活用についてもサポートし、また産業財産権以外の知的財産権(著作権など)についてのアドバイスも行うことがあり、ひとつの案件に関わる期間は長いときで3カ月以上を要することもある。しかも、同時に数十もの仕事をひとりでこなさなければならないという。
それだけ多岐にわたる弁理士の業務をそう簡単にAIが代替できるはずがない、というのが弁理士側の主張だ。
●AIの意外な“盲点”とは?
もう少し、弁理士の仕事内容を詳しく見ていこう。今回、梶氏が特に強調していたのは、弁理士業務における「コミュニケーションの領域」だ。
「新たな発明や考案の権利を取得するには『どのような権利を取るべきか』という“概念”を明確にする必要があります。ところが、発明者にはその概念が明確になっていない方が少なくない。その場合、弁理士が発明者にしっかりとインタビューを行い『どのような権利を取りたいのか』という依頼人の“想い”を汲み取らなければなりません」(同)
発明者へのヒアリングをはじめとするコミュニケーションの領域を、本当にAIが代替できるのか。
また、ヒアリングでは依頼者との会話の中から本人も言語化できていない思想を汲み取り、何度も打ち合わせを重ねて出願書類を作成するといった高い“対人スキル”も要求される。依頼者が的外れな思い込みをしていることもあるため、間違いを指摘してアドバイスをすることも求められるという。
相手の意図を汲んで一歩先を見据えたアドバイスをするには「人間の直感や創造力」(同)が必要だ。これをAIが代替できるかどうかは、iPhoneの音声アシスタント「Siri」や「Google Home」「Amazon Echo」といったAIスピーカーを使ってみたことのある人ならわかるだろう。
さらに、知的財産の分野へのAI導入にはもうひとつ、根本的な問題が存在する。
「AIには自ら学習して効率化し、正解を導き出す『ディープラーニング』という技術が使われています。しかし、知的財産の分野には圧倒的に『教師データ』の数が少ないという問題がある。たとえば、特許侵害訴訟の場合で年間100件強、意匠や商標では年間数十件程度と事例が少ない上に“和解”で終わることもあり、結果が曖昧になりがちです。そのため、事例を学ばせてもAIが賢くならない可能性が高いのです」(同)
昨年、人間は2つの知的ゲームでAIに完膚なきまでに叩きのめされた。ひとつはグーグル系の企業が開発した囲碁プログラムの「アルファ碁」。
もうひとつは、プログラマーの山本一成氏が開発した将棋プログラムの「ポナンザ」。昨年11月に現役最高峰の名人との3番勝負に連勝で完勝し、コンピュータと将棋のプロが戦う「電王戦」もAIの全面勝利に終わった。
このように知的ゲームでAIが圧倒的な強さを発揮するのは、対局を重ねれば重ねるほど、AIが打ち手の数を数千万通りにも増やすことができるからだ。しかし、知的財産の分野では、こうした教師データがあまりにも少なすぎるのである。
「もちろん、弁理士の業務がAIに代替されることが『ない』とは言い切れません。しかし、代替されるまでにかなり時間がかかるのは確かでしょう」(同)
●AIをうまく使いこなせる人が生き残る時代に
ただし、AIはあくまで効率化のために人間がつくり出したものであり、人間の敵ではない。要は、AIと争うのではなく、お互いの得意分野を生かして協力し合えばいいのだ。
「たとえば、弁理士業務のひとつである『調査』の一部は、AIによって効率化できる可能性があります。依頼者が考えた技術と似ているものを、現存の特許技術のなかからAIが拾い上げる。そのデータを基に、弁理士は出願をして権利になる見込みがどれくらいあるのか、権利侵害になっていないかを判断して発明者にアドバイスする。そうすれば、業務全体の効率化が図れます」(同)
また、AIには定型的な書類作成や統計的な分析などの業務を任せ、最終確認や最終判断を弁理士が担うという方法もある。こうして得意分野で協力し合えば、AIを補佐役とする新たなビジネスモデルが生まれる可能性もあるだろう。
そして、AI導入で業務が効率化すれば、弁理士はそれによって得た時間を使い、新たなサービスの開発やより質の高い仕事をこなすことができるわけだ。
「その点については当然、検討していく必要があります。いずれにせよ、AIの進歩に対して油断をしているわけではありませんが、現時点では『脅威』とも考えていません。これからは、『AIをうまく使って補完することで質の高いサービスを提供できる人が生き残る』という時代が来るのかもしれません」(同)
「人間の仕事が奪われる」という文脈で語られがちな「AI脅威説」。しかし、少し視点を変えれば、これは新たなビジネスが生まれるチャンスでもあるのだ。
(文=真島加代/清談社)



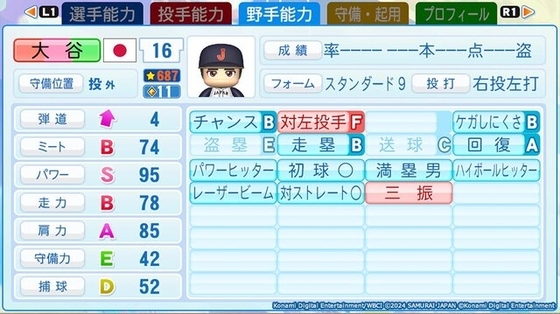






















![[2023年秋冬限定] SALONIA サロニア ストレート ヘアアイロン 15mm 【シンフォニーグリーン】 耐熱ポーチ付 SL-004SSG](https://m.media-amazon.com/images/I/21Shf+ZD69L._SL500_.jpg)


