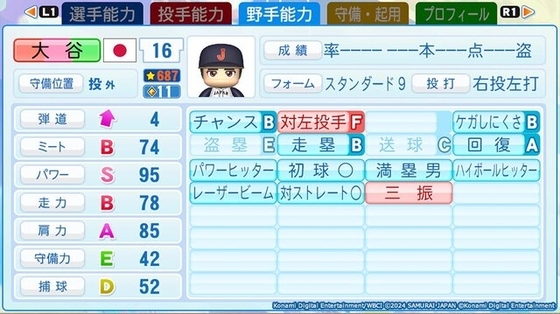いまの私たちから見れば、話し言葉をそのまま文章にするなんて、わけないじゃん(←こんなふうに)、と思うのだが、当時は落語の速記本でも参考にしないことには、どう書いていいのやら皆目検討もつかなかったのだろう。考えてみれば、伝統芸能のなかでも、話し言葉で演じられるのはぜいぜい落語ぐらいなものではなかろうか。
それにしても、小説を書くのに落語の速記本を参考にしたというのは興味深い。よく考えたら、二葉亭四迷というペンネームも語感的に落語家っぽいし、文学に理解のない父親から「くたばってしめえ」と罵倒されたことからつけたというのも、洒落っ気が効いている。文学とお笑いというのは案外、近いところにあるのかもしれない。
文学とお笑いの関係については、最近、峯尾耕平・著『松本人志は夏目漱石である!』という本が出た。おそらく漱石の『吾輩は猫である』をもじったのであろうそのタイトルは、本書の第9章からとったものだが、このほかの章(序章を除く)も同様に、萩本欽一―坪内逍遙、志村けん―二葉亭四迷、横山やすし―国木田独歩、ビートたけし―尾崎紅葉、明石家さんま―幸田露伴、タモリ―泉鏡花、島田紳助―森鴎外、とんねるず―島崎藤村、ダチョウ倶楽部―田山花袋、太田光―谷崎潤一郎、木村祐一―志賀直哉、千原ジュニア―芥川龍之介、ケンドーコバヤシ―太宰治といった組み合わせで、「○○○○は●●●●である!」という題名がつけられている。
タイトルと目次だけ見ると、何だか奇をてらったような印象を受ける。ちょっと意地の悪い人なら、お笑いを文学に重ね合わせることで妙な箔づけをしようとしているのではないか、と考えるかもしれない。だが、実際に本文を読んでみると、著者とほぼ同世代のライターとして、やられた! と思わされることが多かった。まさに「その発想はなかったわ」(by.板尾創路)である。
本書において著者は、明治以降の小説(家)と戦後のテレビのお笑い(芸人)とのあいだに、その成り立ち、表現、受容のされ方など多くの共通点を見出し、その理由を丁寧に説明してみせる。具体的にはまず、小説が明治の新興メディアである新聞から生まれたこと、同様にお笑いというジャンルが昭和の新興メディアであるテレビから生まれたという共通点があげられる。さらに興味深いのは、両者とも時代を追うごとに、送り手と受け手の共同体意識が強固に形成されていき、それぞれ「私小説」と「フリートーク」という日本独自ともいうべき表現形態が隆盛をきわめたということだ。
そんな本書の趣旨が、とくにわかりやすく示されているのは第12章の「木村祐一は志賀直哉である!」だろう。この章では、志賀直哉と木村祐一がそれぞれ、私小説とフリートークの一つの頂点をなした存在だというふうに位置づけられている。
彼らが登場する前提には、夏目漱石とダウンタウンの業績があった。
著者はその出てきた背景だけでなく、表現者としての両者の共通点として、直哉の文体も、木村のトークも洗練され、余分なところが一切ないところをあげる。それを裏づけるためここでは、松本人志が企画したテレビ番組『人志松本のすべらない話』の初のゴールデンタイム放映時に木村が披露した「車屋さんのキクチ」を例に説明されている。
「車屋さんのキクチ」は、木村が車を買いにいったさい、担当となったキクチから不合理な目にばかり遭わされたという体験をおもしろおかしく語ったものだ(現在ではDVD『人志松本のすべらない話 ザ・ゴールデン』に収録されている)。
ただ、著者によれば、受け手は、彼らの表現する「不愉快さ」に共感したわけではないという。受け手の共感はむしろ、人物がいること、そういうことと接しなければならない些事に満ちた現実を描き出すことによって生み出されている、というのだ。それは言い方を変えれば、受け手が「表現者によって生み出される人物に対してすら共同体意識を欲したことを意味」し、そして直哉と木村は「それに応えたからこそ(……)私小説やフリートークで一つの頂点を極めることができた」といえる。
いまやテレビがメディア界を独占していた時代は確実に終わり、テレビバラエティの終焉も近づいている。
本書で面白かったところといえばもう一つ、巻頭に載っている「〈文豪と芸人〉相関図」がある。本書では女流作家と女性芸人はとりあげられていないが、この相関図を見ているとつい、樋口一葉が山田邦子、与謝野晶子は友近あたりになぞらえられるだろうか(すんません、テキトーに言ってます)……などとあれこれ妄想を広げてしまった。もし続編が書かれるとしたら、そのへんについても言及をお願いしたい。(近藤正高)