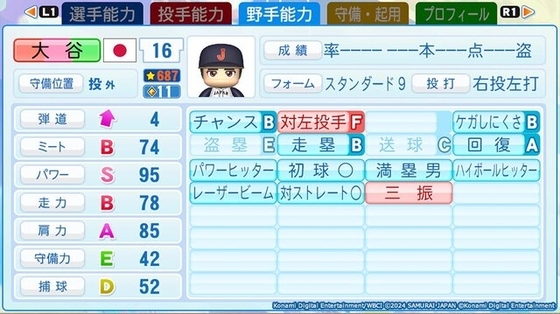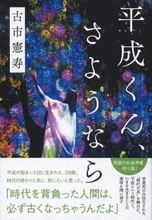しかし、最近もっぱら話題となっているのは、佐賀県武雄市が運営をカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC。DVDレンタルチェーン「TSUTAYA」などを展開する企業)に委託して、この4月にリニューアルオープンした武雄市図書館だろう。年中無休で朝9時から夜9時までの12時間開館というだけでなく、館内には図書コーナーと併せてCD・DVDのレンタルや本の販売を行なうコーナーが設けられ、またコーヒーチェーンのスターバックスも営業し、そこで買った飲み物は館内のどの席にも持ちこみが許されている。
武雄市図書館はたしかに目新しさに満ちている。
あらかじめ断っておくと、この本が出たのは2011年10月なので、武雄市図書館については触れられていない。ただ、この図書館の出てくる背景をうかがわせるような記述はいくつか見られる。たとえば、本書の137ページには、2005年における住民一人あたりの貸出し数の多い都道府県を並べた表が掲載されている。それによると、佐賀県は「6.4冊」と、「8.4冊」の滋賀県、「7.7冊」の東京都に次ぐ全国3位にランクインしていることがわかる。もっとも、滋賀県が県立図書館を中心に、県全域で貸出しサービスを充実させるという図書館振興策をとってきたのに対し、佐賀県の事情はやや異なる。
《県全体の年間貸出し数五六〇万点のうちの四五%にあたる二五〇万点が佐賀市立図書館一館で貸し出されている。また、佐賀市の活動と相互に刺激し合いながら、貸出しを中心とするサービスを展開させている鳥栖市、伊万里市、鹿島市、武雄市などの市がある。一言で言うなら、佐賀市立図書館を中心にして県域にほどよく利用しやすい図書館網がつくられている。これが県の特別の政策なしに行なわれていることが注目されるが、町村での図書館の設置率は低い。都市部中心である》
佐賀県がもともと図書館利用者の多い県であったこと、武雄市図書館が県内の図書館網の一端を担っていたことは、CCCが図書館運営に乗り出したこととけっして無関係ではないだろう。すでにこの地域には、図書館がビジネスとして成立する土壌があったというわけだ。
ところで前出の表のように、貸出し数を図書館が機能しているかどうかを示すバロメーターと見る発想は、それほど古いものではない。これというのも、いま私たちが図書館というとまず思い浮かべるような、貸出しサービスを中心とした図書館像というのが、少なくとも日本では、たかだか40年ほど前に成立したものにすぎないからだ。それ以前の日本の図書館は、開架式ではなく閉架式(館員に閲覧を申請して、書庫から目的の本を出してきてもらうというシステム)が一般的であり、本を読むよりもむしろ閲覧室で勉強する来館者のほうが多かったという。
市民に開かれているとはとうていいえないそんな状況から、より多くの市民の利用を可能にするべく改革に乗り出したのが、戦後、日本図書館協会に集まった図書館員たちだった。そこで1950年代末から60年代にかけて検討され、一部の図書館での実践を経て定式化された運営方式は、1970年に『市民の図書館』と題する冊子にまとめられ同協会から刊行された。この冊子を出発点に、70年代から80年代にかけて、現在見られるような貸出しを中心にした図書館サービスが確立されていくことになる。
こうした開かれた図書館をめざす動きは、それまで大都市か地域の中核都市ぐらいにしかになかった図書館が、全国各地で設置される契機となった。図書館の数の増加とともに、貸出し数も著しく増加していく。かつて『市民の図書館』で掲げられた理念は、かなりの水準まで達せられたのだ。
ただ、時期的に高度成長にともなう消費社会の到来と重なったため、図書館もまた、市民の消費的ニーズに応じるがままに資料を提供するという道を選ぶことになる。このことは、たとえばベストセラーを何冊も購入するといった風潮を生み、「無料貸本屋」などという批判にもつながった(もっとも、図書館での貸出し数に占めるベストセラー本の割合は1パーセント以下にすぎないらしいのだが)。
バブル期の前後に建設された図書館には、ホールなどが併設され、複合的な文化施設として大型化する傾向も見られる。
思うに、こうした貸出しサービスを中心に発展し続けてきた図書館の最終型こそ武雄市図書館といえるのではないだろうか。その意味で、同図書館は、現れるべくして現れたともいえる。ただ、レンタルチェーンを経営する会社に図書館の運営を委託することによって、貸本屋やレンタル店とほとんど区別がつかなくなっているのではないか、と批判することも可能だろう。
《図書館の無料貸出しは貸本屋やレンタル店とどこが共通し、どこが違うのか。有料か無料かは重要な違いだが、むしろ市場的なニーズに依存するかそれと一線を画するかの違いである。公費をつかって市場的なニーズに対応するだけなら、公立図書館よりも公設民営の貸本屋やレンタル店をつくればよい》
では、市場的なニーズへの依存とは一線を画したうえで、公立図書館はどんな道を選ぶべきなのだろうか。これについて著者の考えはきわめて明確だ。それは貸出しサービスを中心とした図書館から一歩進めて、図書館に課せられたいまひとつの役割であるレファレンスサービスを充実させ、「地域の情報拠点」となることをめざそうというものだ。
図書館の利用者というとたいていは、本や雑誌を読みに来る人たちである。地域の情報拠点としての図書館ではそれを、ビジネスや生活のさまざまな場面で必要とされる情報や資料を提供することで、これまで図書館を利用していなかった人にも、その有用性をアピールしようというのだ。
もちろん、こうした大幅な軌道修正を行なうには、予算もいるし、専門知識を持った職員をそろえる必要もある。多くの自治体が財源不足に悩んでいるいま、それを実行するには限界があるだろう。そこで著者が提案するのは、従来より公立図書館が蓄積してきた地域資料(かつては郷土資料と呼ばれていた)をもとにしたサービスの展開である。
じつはこうした取り組みはすでに一部の地域では行なわれている。静岡市が都心部の再開発ビルに設置した図書館では、とくにビジネス支援サービスに力を入れ、《市民の起業のために必要な資料や情報を提供したり、市内の企業に対する専門的な産業情報データベースを提供したりしている》という。また、鳥取県でも、《県庁のなかに県立図書館の分館を設置して、来庁する県民だけでなく県の職員や県会議員に対して行政関係の専門的な情報サービスを行なった》。
ただ、これらの実践例は正直に言えば、いかにも地味だ。武雄市図書館のようなニュースバリューに乏しく、そのサービスを目当てに人々が押しかけるといった事態はちょっと想像しにくい。長期的に考えれば地域振興への貢献を期待できるとはいえ、短期的にはっきりと成果を出すことは難しいだろう。しかしだからこそ、公立図書館にしかできないのだともいえる。
ここまで批判的なことを書いてきてなんだが、私が武雄市図書館に実際に足を運んでみたら、それなりに楽しめるような気はする。近年リニューアルされた図書館では、冒頭にもあげた日比谷図書文化館には行ったことがあり(しかも開館初日に)、従来の図書館にはないさまざまな趣向にワクワクしたものだ。たとえば、民間が営業委託を受けた館内のレストランの料理は、その前身である旧日比谷図書館の食堂とくらべたら段違いにおいしかったし、館内に設けられた書籍などを販売したショップ兼カフェでは、武雄市図書館と同様にそこで買ったり図書フロアで借りた本を、コーヒーなどを飲みながら読むことができた。本に親しむには申し分ない空間であることは間違いない。ただ、日常的に調べ物のために使えるかどうかとなると、やはり何か違うと感じてしまった。武雄市図書館に関する報道から私の抱く違和感も、まさにそのあたりにある。
もちろん今後、地域社会とのかかわりのなかで同図書館も、貸出しサービスにとどまらず多様なニーズにこたえるものへと変わっていく可能性は十分にあるだろう。何より、公立図書館のあり方を多くの人に考えるきっかけをつくったという点で、武雄市図書館は早くも大きな役割を果たしたといえそうだ。(近藤正高)