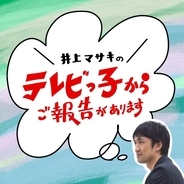そういえば、私の通っていた高校の二学期の終業式で、校長が「新政権が発足したのと入れ替わるように、旧時代の遺物である田中角栄が亡くなり……」みたいなことを話していたのを思い出す。それを聞いて私は、「何言ってやがる、細川護熙も新生党の羽田孜も小沢一郎も、みんな元はといえば田中派じゃねえか」とツッコミを入れたものである。心のなかで。
この20年のうちに、田中派の流れを汲む自民党の平成研究会は、かつて党内最大派閥だったことが信じられないほど縮小するとともに、田中の愛弟子である小沢一郎が自民党を飛び出して進めた政界再編の動きは、2009年の総選挙での自民党から民主党への政権交代を最大の山場として、1年前の総選挙における自民党の政権復帰により大きな区切りを迎えたといえる。
こうした流れだけ見れば、政界における田中角栄の継承者たち(実の娘の眞紀子も含め)の勢力は、衰える一方だといえる。しかし、だからといって角栄の影響力が跡形もなくなったのかといえば、けっしてそうではない。
田中を語るうえでは、ロッキード事件の関与などに代表される金権政治や、自民党内での激しい派閥抗争など、さまざまなキーワードがあげられる。この記事では、とくに彼が首相時代に手がけた政策、それも現在の政治・社会が抱える課題にも大きく影響をおよぼしている「エネルギー政策」と「日中国交正常化」についてとりあげたい。
■エネルギー危機の回避策が招いた危機
田中は、それまで日本がアメリカの国際石油資本(石油メジャー)に大きく依存していた石油供給ルートを、より多様なものへと拡散するとともに、石油依存そのものから脱却するべく原子力発電を推進、それに必要な濃縮ウランの確保をめざした。そのため、東南アジアや当時のソ連を含むヨーロッパ諸国をまわり、積極的に資源外交を展開している。その経緯については、ノンフィクション作家の山岡淳一郎の『田中角栄 封じられた資源戦略』(2009年。
田中が資源外交を展開した背景には、資源のほとんどない日本がエネルギー危機を回避するため、エネルギー供給源をできるだけ分散し、どこかのルートが寸断されてもほかで補えるよう、安定的なモデルをつくっておかねばならないとの考えがあった。田中がこうした危機感を、1973年10月に起こった第一次石油危機の前から持ち、具体的に行動していたことは十分評価できるだろう。
ただ、ウラン資源の調達に関していえば、山岡が指摘するとおり、それは《「原発は安全で、放射能漏れによる環境汚染の心配はない」という神話の上でのみ成り立つ大仕掛けなゲームであった》(『田中角栄 封じられた資源戦略』)。
安全神話を信じていた田中は、過疎化した地域を振興するため、積極的に原発建設を進めていった。佐藤栄作首相の後継を狙った田中が、自民党総裁選を前に1972年6月に刊行したマニフェスト的著書『日本列島改造論』では、原発の建設について次のような記述が見られる。
《原子力発電所の放射能問題については海外の実例や安全審議委員会の審査結果にもとづいて危険がないことを住民が理解し、なっとくしてもらう努力をしなければならない。しかし、公害をなくすというだけでは消極的である。
地域社会の福祉に貢献し、地域住民から喜んで受入れられるような福祉型発電所づくりを考えなければならない。たとえば、温排水を逆に利用して地域の集中冷暖房に使ったり、農作物や草花の温室栽培、または養殖漁業に役立てる。豪雪地帯では道路につもった雪をとかすのに活用する。
さらに発電所をつくる場合は、住民も利用できる道路や港、集会所などを整備する。
このような地域振興と一体となった原発建設のため、田中は首相在任中の1974年に「電源三法」が成立させた。詳細は省くが、この法律にもとづいて、原発の立地自治体には交付金などの形で資金が流れこみ、それが地域振興に使われるしくみができあがる。だが、この制度は、原発に依存しないと成り立たない地域を各地に生み出すこととなった。しかも交付金で地域経済が持ちこたえられるのは30年が限度とされるため、兵糧が尽きそうな自治体は、破綻を避けるべく、原発を増設し続けなければならないという悪循環に陥ったのである。
「脱原発」と言うのはたやすいが、いざ原発をなくそうとしたとき、立地自治体に新たな産業を育てようにも、上記のような体質ゆえ、かなりの困難がともなうことは間違いない。一昨年の福島第一原発の事故は、安全神話を打ち砕くとともに、田中のエネルギー政策から生まれたシステムの欠陥をあらためて浮かび上がらせたといえる。
■日中交渉のなかでの尖閣発言
田中角栄の業績といえば、首相となって2カ月後の1972年9月に日中国交正常化を実現したことがあげられる。政治学者の服部龍二の『日中国交正常化』(2011年)では、このときの一連の交渉を、近年公開された外交文書や関係者への聞き取り調査などによって、綿密に分析・考察している。
日中国交正常化は、田中が政権発足時に掲げた「決断と実行」を強くアピールするものであったが、同書を読むと、田中の外交能力を疑ってしまうような場面もちらほら出てくる。たとえば、ときの中国首相・周恩来との会談中、田中は唐突に「尖閣諸島についてどう思うか?」と発言している。これに対し、周恩来は「尖閣諸島について、いま話すのはよくない。石油が出るから、これが問題になった。
近年加熱している尖閣諸島の問題は、1970年代に入ってから中国や台湾が領有権を主張し始めたことに端を発する。自民党外交調査会はこうした情勢を受けて、1972年の沖縄返還を前に、尖閣諸島が日本領であることを確認していた。
田中が唐突に尖閣諸島のことを周に訊ねたのは、日本国内の反発を抑えるためにも、言質を取っておきたかったからだ。だが、合法的に実効支配する領土について日本側から発言することは、相手に揚げ足を取られかねない。最悪、田中は言質を得るどころか、将来に禍根を残した可能性すらあった。
しかし周がこの話を受け流したのは、議論をすれば収拾がつかなくなると瞬時に判断したからだろう、と服部は推測する。隣国・ソ連の脅威に対抗するため、アメリカや日本への接近をはかっていた周は、領土問題を後回しにしてでも日中共同声明の調印を急いでいたのだ。田中は周に救われたといえる。
このエピソードからは、外交において、国内政治の文脈で軽々しい言動をとることは得策ではなく、むしろ危険性が高いという教訓を読み取ることができるのではないか。
日中国交正常化は、しかし田中だからこそ早期に実現できた面ももちろんある。首相に就任して2カ月後に自ら北京に飛び、5日間の首脳会談で国交正常化までこぎつけた。服部は、《首脳会談で一気に進めていなかったら、交渉は長期化したに違いない。そうなれば、中国が尖閣諸島の領有権を主張するなど対日要求を強め、国交正常化は暗礁に乗り上げたかもしれない》と書く。
もちろん、政策のなかには早急に進めるべきものがある一方で、時間をかけて慎重に進めていくべきものもある。たとえば、新幹線などの高速交通網・通信網の整備や大規模開発により、地方と大都市との格差をなくすことを目指した「日本列島改造」は田中政権の最大の目玉であったが、本来、10年ほどかけて進めていく計画だったにもかかわらず、具体的な地名をあげてしまったがゆえに、当該の地域では土地の買い占めが行なわれ、地価が暴騰する結果を招いた。このことは物価の高騰、ひいてはインフレの昂進をうながし、そこへ来て石油危機が起こったため、日本経済は大混乱に陥った。
そうした失敗も数あれど、田中に対して、死後も彼のような存在を求める声が根強く存在するのも事実だし、それはやはり、すばやい決断と実行でリーダーシップを発揮したからだろう。
人の評価は棺を蓋うて定まると言うが、田中角栄の場合、死後もなお評価は賛否両論、真っ二つに分かれたままだ。しかも「この行ないは功で、この行ないは罪だ」というふうに明確に分けることも難しく、前出のエネルギー政策のように、多くの業績が功と罪の両面を併せ持っていたりする。このことこそ、田中の手がけた仕事がいまなお影響力を持ち、私たちに課題を残しているという何よりの証しではないだろうか。
※田中角栄の生涯と業績について総論的に振り返ったもので、現在も入手しやすいものとしては、保阪正康の『田中角栄の昭和』(2010年)と早野透『田中角栄』(2012年)がある。いずれも長年、田中本人も含め多数の関係者の取材を行なってきた著者だけに、エピソードも豊富である。
(近藤正高)