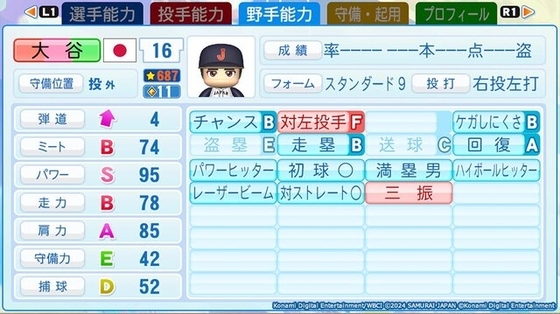先週金曜放送の連続テレビ小説「マッサン」第23回、鴨居商店の「太陽ワイン」の新しいポスターを撮影する場面で、モデルのみどり(柳ゆり菜)の口から出たこのセリフに、ドキッとした視聴者も多かったのではないか。ドラマではこのセリフに、大将こと鴨居商店社長の鴨居欣次郎(堤真一)も「そうしよう!」と応じ、モデルは大胆にも着物をすべてはだけてしまう。
鴨居欣次郎のモデルとなったのは、現在のサントリーの創業者の鳥井信治郎である。1899(明治32)年に大阪で鳥井商店を創業し、太陽ワインならぬ「赤玉ポートワイン」で当てた鳥井は、1921(大正10)年に店を株式会社化し、その名も寿屋(ことぶきや)と改めた。大将という呼び名もこのときからのもので、小さな会社で社長と呼ばせるのはおこがましいからと、鳥井は社員にそう呼ぶように命じたのだという。
鴨居商店がワインを売るためヌードポスター(実際にはヌードというほどでもないのだが)をつくったという話も、史実に沿っている。ただし発案者は鳥井信治郎ではない。
鳥井から宣伝の一切をまかされた片岡は、移籍当初より意表を突いたアイデアで皆の度肝を抜く。掲載済みの新聞の社会面1ページをそのまま使い、その上にわざと稚拙な文字で赤玉ポートワインとだけ墨書した広告は、賛否両論を呼んだ。例のヌードポスターが制作されたのは、1922年(ただし1921年、あるいは1923年とする資料もある)のことである。
モデルとなった松島栄美子は、「赤玉楽劇団」という、このころ赤玉ポートワインのPRのため全国を興行してまわっていたオペラ団のプリ・マドンナだった。片岡は彼女に「無理は承知で」と頼みこみ、承諾を得た。そうして連れて行ったのが、ドラマにも出てきたような旅館の一室である。片岡は彼女に、肩から胸のあたりを出してほしいと指示すると、あとは襖の隙間から覗きながら、デザイナーで画家の井上木它(もくだ)とカメラマンの3人で、彼女の肌がポスターに適当かどうか検討した。
この日はそれで終わり、撮影は翌日から写真館で開始された。写真館も初めは驚いたが、スタッフの熱意に打たれ、撮影のあいだは表戸を下ろして休業したという。
こうしてできあがった写真は、井上木它の画筆のよって丹念にレタッチされ、印刷に回された。全体は黒みがかったセピアで、モデルの持つグラスのワインだけは鮮やかな赤というその色調を出すのに、印刷屋は苦心惨憺した。
制作は時間をかけながらも、企画が漏れないよう秘密裏に進められた。やっと完成したポスターは大評判を呼び、赤玉ポートワインの名をますます高めた。ドイツで開かれた世界ポスター展でも一等に入選している。「日本初のヌードポスター」といわれるこのポスターだが、実際にはモデルは半裸ですらない。だが、裸体画の伝統もなければ、胸を露出する習慣もなかった当時の日本にあっては冒険だった。
■「ヌードポスター」モデルと仕掛け人のその後
赤玉ポートワインのポスターでモデルを務めた松島栄美子は、しばらくして大阪の寿屋本社を訪問、このとき彼女を一目見ようと大勢の人が店の前に集まったという。ただし親族からは、若い娘のやることではないと批判され、親からも勘当されたらしい。そのことは、松島の甥の妻が近年ブログで明かされた。同じブログのエントリーには、松島は1983年に90歳で亡くなったと書かれている。
赤玉楽劇団が予算の理由で1年ほどで解散したあとも、松島は浅草オペラで活躍を続けたという。結婚もしており、その相手の飛島常矩は、開局まもない東京放送局(現在のNHK)の文芸・娯楽番組の担当者で、のちに松竹シネマ(現・松竹)の監査役となった人物だ。評論家の塩沢茂は、1970年前後に夫妻の家を何度か訪ねたことがあった。その際、松島はヌードモデルになった経緯を次のように話していたという。
《やはりちゅうちょしまして、再三お断りしたんです。でも、片岡さんがわざわざ何度もおみえになり、“評判を落とすようなポスターには絶対にしないから……。私を信じ、まかせてほしい”とおっしゃいましてね。それに宣伝の必要性についても丁寧に話され、ひとことでいってしまえば、引き受けざるを得ない状態に追い込まれてしまったんです。熱心な方でしたよね》(塩沢茂『ドキュメント サントリー宣伝部』)。
片岡敏郎は、コピーライターとしても「不景気か? 不景気だ! 赤玉ポートワインを飲んでるかネ? 飲んでない! そうだろう!」「出たオラガビール 飲めオラガビール」などの名作を生むなど、寿屋でその才能をいかんなく発揮した。だが、片岡のインテリぶった気取りは、鳥井のあまり好むところではなかったらしい。そのせいかどうか、鳥井は、1934年に練り歯磨き「スモカ」の事業を他社に譲渡した際、片岡を取締役として移籍させている。
■宣伝への情熱は創業以来衰えず
宣伝に熱心だった鳥井は、はっきりとした好みと意見を持っていた。前出の井上木它には、毎年正月に得意先へ配るカレンダーに使う絵を選ばせていたが、冬に枯れ木の絵を使おうものなら、すぐに文句をつけた。1月には昇る太陽はどうかという鳥井の提案を受けて、井上は富士山に太陽を描いたところ、今度は手を打って喜ばれたという。
赤玉ポートワインを1907年に発売したときも、さっそく新聞に広告を出した。ワインの宣伝に新聞を使うのは珍しかったのだろう、同業者には嘲笑する向きもあったようだ。その後も新聞には広告を出し続け、赤玉ポートワインが体にいいことをアピールするため、医者の有効証明を添えたりもした。
新聞だけでなく、赤と黒で「赤玉ポートワイン」と書いたあんどんを、夜ともなるとはっぴ姿の青年に持たせて、街を回らせたこともあった。火事さえも宣伝の機会ととらえ、やはり赤玉ポートワインの文字の入ったはっぴと提灯を身につけた社員を現場に急行させた。その際、類焼した店には多額の見舞金を贈ったという。
鳥井は、宣伝に芸者を使うことも考えた。といっても、ポスターのモデルやキャンペーンガールに起用したわけではない。芸者たちは、正月ともなれば稲穂に白鳩の根付をあしらったかんざしを髷に挿して座敷に出る。鳥井はこの稲穂かんざしをつくって、石清水八幡宮で祈祷をしてもらうと、暮れのうちに検番やお茶屋に配ったのだ。白鳩の目に、赤玉ポートワインにちなんで赤い玉を入れた「鳥井はんの稲穂かんざし」は、たちまち有名になったという。
芸者相手でいえば、彼女たちが月経のことを隠語で「日の丸」と呼んでいたのを、鳥井が半ば冗談で「赤玉」と呼ぶように頼んだというエピソードも伝えられる。いまからすれば、宣伝のためにそこまでやるか!とも思うが、これもたちまち大阪中の花街に広まったというから、鳥井の意気に感じ入る芸者は多かったのだろう。
鳥井の広告・宣伝にかける情熱は、終生衰えることはなかった。戦時下の国による酒類の販売統制が1950年に解除されると、寿屋はふたたび宣伝に本腰を入れるようになる。このときにはすでに次男の佐治敬三(苗字が違うのは母の実家に養子に入ったため)が専務取締役となり、宣伝についても陣頭指揮にあたっていた。それでも鳥井は頻繁に宣伝部に顔を出しては、「おそろしく細かく、専門的な」アドバイスをして立ち去って行ったという。
あるとき、一人のデザイナーが、トリスウイスキーの瓶に鳥の羽を描き加えて「とぶような売行き」とダジャレめいた広告をつくったことがあった。鳥井はそれを見て激怒したという。ただし、怒ったのはダジャレだからではなかった。彼が許せなかったのは、デザイナーがトリスの瓶を斜めにして描いていたことだった。
《商品を“曲げて”宣伝してはならぬというのが彼の信仰であった。だから彼は最後まで広告のなかでは瓶を直立しておかせた。彼は信仰に近い心からそれを遂行したのであったが、現在の商業宣伝学の心理学からすると、寿屋の広告では瓶はいつもまっすぐたっているという印象をしらずしらず読者の潜在意識にしのびこませたということで、“デザイン・ポリシーが一貫している”という讃評となることであろう》
そう書いたのは、作家の開高健である(山口瞳との共著『やってみなはれ みとくんなはれ』)。1954年に寿屋の宣伝部に入った開高は、前後して入社したイラストレーターの柳原良平や山口瞳などとともに、広告制作やPR誌「洋酒天国」の編集を手がけ、戦後の寿屋宣伝部の黄金時代を築くことになる。名作といわれるトリスのキャッチコピー「『人間』らしくやりたいナ」を書いたとき、開高はすでに芥川賞を受賞していた。このコピーの生まれた1961年には、山口も直木賞を受賞している。
寿屋は1963年にサントリーと社名を変更した。山口と開高は70年代以降、古巣のテレビCMにもたびたび出演し、ときには文明批評的なメッセージを発した。同社の広告にはこのほか、大原麗子主演によるオールドのシリーズCM(1979~88年)や、子犬が雨降る街を行くトリスのCM(1981年)、あるいは放浪の詩人ランボーをとりあげ、その奇抜さにサントリー社内でも賛否評論があがったローヤルのCM(1982年)など名作も数多い。いずれも酒類の広告であるにもかかわらず広い層の心に訴えかけ、ある世代以上にはいまなお記憶に残るものばかりだ。鳥井信治郎は社名変更の前年に83歳で死去したが、広告・宣伝に力を入れる社風はその後も継承されたのである。
(近藤正高)