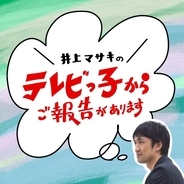えーと、カツ丼、浅蜊(アサリ)、鰹(カツオ)、茄子(ナス)、トマト、鰻(ウナギ)、海老(エビ)、コロッケ、タコ焼き、豆腐、すし、すき焼き、カステラ……。
…………!
まるで絞れてない! と自分でも思うが、これでも全力で絞っている。だって、目次に旨そうなものが並びすぎている!
『食彩の文学事典』はこれらの郷愁を誘う食べ物や、なじみ深い和食が、小説やエッセイのなかでどのように描かれてきたか、世にあまたある膨大な小説・エッセイから「食」のシーンを紹介している。この一冊に取り上げられた作家は160人以上! 池波正太郎や開高健といった過去の「食の名手」はもちろん、まだまだ現役の山本一力や田辺聖子、角田光代や、若手では綿矢りさの作品まで幅広く取り上げられている。
■食べ物と作家。
例えば東海林さだおの『親子丼の丸かじり』からはこんな一節が切りだされている。
<カステラは、フォークで切ったりして食べるとおいしくない。カステラは手づかみ。手で持つとペタペタと手に付くが、それでも手づかみ。>(「大掃除のカステラ」『親子丼の丸かじり』文春文庫)
実際、食べ方でものの味はかなり変わる。僕もカステラは手づかみ派だ。
読み進めると、ときどき目を捕らえて離さない文章や表現がある。そしてそこには必ず2本の補助線が引かれている。ひとつは食べ物、もうひとつは作家という補助線だ。引用された表現を指し示す、この2本の補助線は絡み合いながら「旨そう!」を刺激する。
順番としてはたいてい、好きな食べ物の項目で好きな作家が登場するが、一方、同じ項目でも、それほど親しんでいなかった作家の表現にも出会うことができる。例えば、僕にとってはカステラほどには親しんでいなかった作家に向田邦子がいる。今回いくつかその表現に触れて、「食」への深い愛情を知った。
<羊羹でもカステラでも真中よりも端っこが好きだった。(略)
カステラの端の少し固くなったところ、特に下の焦茶色になって紙にくっついている部分をおいしいと思う。雑なはがし方をして、この部分を残す人がいると、権利を分けて貰って、丁寧にはがして食べた。
「雑なはがし方をして」という表現にはカステラに対する愛おしさが込められているし、「権利を分けて貰う」という仰々しい言い方に、その裏にあるだろう気恥ずかしさが感じ取れる。僭越ながらとてもかわらしい。僕は食べ物も文章表現も、過度にかた苦しかったり、壮大なまでに叙情的なものは苦手だ。気取りと濁りのない、ストレートな言い回しのなかに、換えの効かない表現を忍ばせる。そんな作家や表現が好きだ。そのうえで食べ物なら、おいしそうに描いてほしい。
<私は十六から二十一歳くらいまでの間、つまり敗戦後の乱世の頃に、ばくちを打ち暮らしたことがあるが、人形町の裏通りの家で夜半にとって貰うカツ丼がすばらしくうまかった。あの頃はまだ銀シャリという言葉が生きていた時代である。カツが揚げたてで、卵が煮詰まっていなくて、タレの飯に染まり具合がよい。そのうえに米粒そのものがおいしい。
「唾が出る」を飛び越えて腹が鳴る。好みとしては、色川武大名義より『麻雀放浪記』の著者、阿佐田哲也名義のほうが好きな作品が多いが、このくだりは本当に旨そうだ。特に「卵が煮詰まっていなくて、タレの飯に染まり具合がよい」というフレーズのなんと見事なことか。前後に「カツが揚げたて」「米粒そのものがおいしい」と必要な情報をきっちり入れたその間に、まさに「染」みる表現で、具合がいい。
■作家というフィルターを通せば、未知の食体験が自分のものになる
ちなみにこの部分を受けて本書の著者は「現代の若い人には、この至福の時というか充足感が理解できないかもしれない」と言った。前出の向田邦子の「カステラの紙にくっついている部分がおいしい」についても「なんとなく貧乏たらしくて、うしろめたいところがいいのだ。おそらく昨今の若い人たちには理解できないだろう」と言及している。
ところどころに「近頃の若いもんは」的コメントが顔を出すが、お若い方も特に気にする必要はないだろう。小説やエッセイの楽しみはその世界に没入し、その世界を追体験・疑似体験できるところにある。僕自身、戦後の混乱期などはまったく知らないが、上記の色川武大の文章を読めば、当然のように腹は減る。カステラの紙にくっついている部分にしても、焼き目ならではの香ばしさが当たりを引いたようで、「こっそり自分だけが獲得した、おまけのような楽しみ」がうれしいのだ。感覚として著者が言う「貧乏たらしくて」「うしろめたい」と似ているかはわからないが、“現場”を知らなくても、作品世界には十二分に入り込むことはできる。
作家というフィルターを通して、物語や作家の世界観に潜れば、未知なる食体験を我がこととして捉えることもできるし、逆に好きな食べ物という入り口から入れば、新たな作家・作品との出会いという楽しみを得ることができる。
坂口安吾はアンコウのドブ煮についてこう残している。
<コッテリと複雑微妙。実にうまい食べ物だ。ちょっと、しつこいけれども食ってるときにはそのしつこさが、またよい。翌日になると、しつこさが鼻について、二日つづけて食うきにはならない。>(「アンコウのドブ煮」『坂口安吾全集 18』ちくま文庫)
実際、肝を使う料理はどこまでくさみを抜くかの加減が難しい。あん肝にせよ、フォアグラにせよ、パテ・ド・カンパーニュにせよ、作り置きすると翌日以降、確実に匂いは強くなる。ただその一方で、においが多少強くなる頃を「味が乗った」と好む人もいる。いずれにしても、坂口安吾は、2日目以降のドブ煮にも、口をつけたのだろう。食いしん坊である。
ほかにも珠玉の調味料となる表現はあまたある。浅田次郎の以下の記述などは、強制的に空腹スイッチが押されるようだ。
<あれは実にうまかった。どのくらいうまかったかというと、ひとことで言うなら、日本そのものだった。わが国の二千年の文化は、鰻の蒲焼に凝縮されているといってもいい。しかも俺は、その二千年間に焼き続けられた無数の鰻のうちの、たぶん最高傑作に違いない蒲焼を食べてしまった。>(「雪鰻」『月島慕情』浅田次郎)
最高傑作でなくてもいい! こんなに煽られては、鰻を食べざるを得ない……。
ちなみに、ここまで僕がピックアップした表現は個人的な好みによるものだ。念のため、違うタイプの作品も紹介しておく。まずは現代のグルメ表現にも通じるものから。牡蠣の項でとりあげられていた、神吉拓郎の『洋食セーヌ軒』ではカキフライについて、こう記していた。
<ラードのにおいが高く香ばしい。金茶色の、少し濃すぎる位の揚げ色は、もう数秒で揚げすぎという位の、きわどい手前で、上々の仕上がりになっている。それでいて、なかの牡蠣の粒は、まだ生命を残して、磯の香をいっぱいに湛(たた)えている。>(新潮社)
現代のグルメ誌に掲載されていてもおかしくないような表現である。そして同じ牡蠣の項にはシングル・モルトを味わうべく、アイラ島を訪れた村上春樹の一文も登場する。
<他の土地で食べる牡蠣とは、ずいぶん違う。生臭さがなく、こぶりで、潮っぽいのだ。つるりとしているがふやけたところはない。「そこにシングル・モルトをかけてたべるとうまいんだ」とジムが教えてくれた。「それがこの島独特の食べ方なんだ。一回やると、忘れない」>(『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』新潮文庫)
やっぱり、牡蠣の項はどこか気取っている気がするが、こうした表現に惹かれる人もいる。またここに紹介しなかった表現に「刺さる」人もいるだろう。もし本書で自分に合う表現を見つけたら、その作家の他の表現を探しに巻末の「さくいん」に飛ぶといい。作家によっては複数作品のタイトルと掲載ページが載っている。「食の名手」を中心に160名以上もいるのだから、食べ物が好きならどこかに好みに合う人はいるはずだ。ページを行きつ戻りつしているうちに、「食彩の文学」世界は自然に広がっているはずだ。
と、ここまで書いたところで気がついた。そうか。この本は、食のロールプレイング本なのだ。実際に食べた経験があれば、その項をより楽しめるだろう。しかし、それはこの本を楽しむための必要条件ではない。むしろこの本を楽しみたければ、未食の一皿に対して「うまそう!」と思える欲望を貪欲に育てることである。もちろん、心にいつも食欲を飼っている人ならこの一冊、すぐさま「買い」である。
(松浦達也)