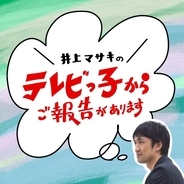魚醤とは、醤油よりも古い歴史のある調味料だ。杉村は最近出た書籍版『醤油手帖』のなかで、次のように説明している。
《そもそも醤油の「醤」の字は、「ひしお」と読み、さまざまな食べ物を塩漬けにして保存、発酵させたものになります。肉を発酵させると「肉(しし)醤」、大豆を発酵させたら「穀醤」、魚を発酵させると「魚醤」になるというわけです。醤油はもともと「穀醤」なのです》
杉村が醤油に興味を持つようになったのも、魚醤がきっかけだったという。
ちなみに、「あかし魚笑」は、いかなごという瀬戸内海で獲れる魚でつくられた魚醤だ。日本の各地には古来よりさまざまな種類の魚醤が存在したが、大豆と小麦という入手しやすい材料でつくられる醤油が普及すると、その多くは消えていった。いかなごの魚醤はそのなかで残った「三大魚醤」と呼ばれるうちのひとつである(ほかの2つが何かは本書でご確認を)。
書籍版『醤油手帖』には魚醤も含め、日本各地でつくられている醤油が多数紹介されており、杉村が書くとおりそのバラエティの豊富さに驚かされる。
地方によっても、日常的に使われる醤油の種類は異なる。なぜ、そんな違いが生まれたのか? そこには風土や歴史が深くかかわっているというのがまた面白い。たとえば、関東は濃口、関西は淡口という違いは、江戸時代にまでさかのぼって説明される。
当時の江戸の水はミネラルの多い硬水だったのに対し、関西の水は軟水だった。軟水は昆布のダシをとるのにすぐれているが、硬水はそれには不向きで、むしろかつおダシをとるのに適している。
地域別にいえば、中部地方ではたまり醤油がよく使われている。その理由もまた江戸時代にあった。幕府の開かれた江戸と、徳川家によって名古屋城の普請の始まった名古屋と、いずれの都市にも人が集まり、醤油の需要が高まる。
このたまり醤油からは、最近になって新たなバリエーションが生まれている。岐阜県の山川醸造がつくっている「アイスクリームにかける醤油」はそのひとつだ。昔から、アイスクリームに醤油をかけるとよりおいしくなるとはよく言われるところ。その理由について私は、スイカに塩をかけると甘さが引き立つのと同じ理屈だろうと単純に考えていた。
魚醤が原料は異なれど醤油とイトコだとするなら、味噌は同じく「穀醤」から生まれたので醤油の実の兄弟、そして同じ成分を持つバニラとはハトコぐらいの関係とでもなるだろうか。こんなふうに、本書を通して読んでいると、日本の食文化の系統図が浮かび上がってくる。
それにしても、著者の杉村は、現在市販されているさまざまな醤油について、じつにわかりやすく丁寧に教えてくれる。
※『醤油手帖』の書名の「醤」の字は正しくは旧字体です。
(近藤正高)