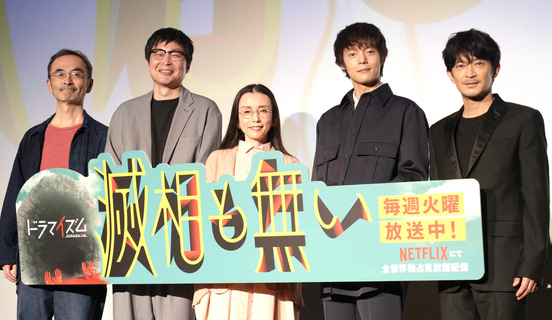田畑が図らずも開いた政界への道
緒方は二・二六事件から3ヵ月後には、朝日新聞主筆と代表取締役専務に就任し、実質的な最高指導者となる。太平洋戦争中の1943年には副社長に就いた。だが、翌1944年に発足した小磯国昭内閣に情報局総裁として入閣し、朝日新聞社を退社。以来、政治家としての道を歩む。敗戦後の東久邇宮稔彦内閣でも国務大臣を務めたのち、1946年から5年におよぶ公職追放を経て、1952年の総選挙で初当選、衆院議員となった。その後、吉田茂内閣で官房長官と副総理を兼任し、吉田退陣の翌年、1955年11月の保守合同による自由民主党の発足でも大きな役割を果たしている。

本来、緒方は「一人一業」をモットーに生涯新聞人を貫こうとしていた。
緒方が情報局総裁として入閣した小磯内閣は、1944年7月、東条英機内閣の総辞職を受けて発足した。組閣に際して小磯は、元首相の米内光政と連立を組む。もともと米内と小磯のあいだをとりもったのは、両者と親交のあった緒方であり、組閣人事の相談にも乗っていた。
もちろん緒方は固辞。朝日新聞社内でも、社長の村山長挙は「社として立場もいい」と入閣を熱心に勧めたものの、緒方と親しかった政治部関係の記者たちの多くは、彼を外部にとられることを懸念し、情報局総裁就任に反対した。
そんななか政治部員だった田畑は、緒方が国務大臣にはならないとの条件で情報局総裁を引き受けたという話を耳にする。情報局総裁はそれまで正式な閣僚ではなかった。田畑は緒方の入閣にはもちろん反対で、国務大臣にするよう条件をつければ、相手も飲みこめず、緒方の情報局総裁就任はご破算になるだろうと考えた。
その夜、帰宅した緒方が床に入って休んでいると、米内の側近から「国務大臣と情報局総裁を兼務することは制度上差支えないそうだ」との電話を受けるが、まさか田畑が裏で動いたとは知らず、そのまま聞き流して寝てしまった。翌朝、緒方はあらためて米内に入閣を断ったところ、「すでにきのう朝日の政治部の者が、これこれ言ってきたじゃないか、それでもなお社のほうに異存があるというのなら、これから社長に会って談判してくる」と怒られてしまう。すでに小磯も米内も親任式のため参内の準備をしているところだった。ここへ来て緒方もついに入閣を決意したのである。
緒方は小磯内閣発足の約1週間後、33年にわたって勤めた朝日新聞社に別れを告げた。
新人記者時代に新元号「大正」をスクープ
ここで緒方竹虎が小磯内閣に入閣するまでを振り返っておきたい。緒方は、内務官僚だった父親の赴任先の山形県にて1888(明治21)年に生まれた(部下の田畑政治は1898年生まれだから、ちょうど10歳上ということになる)。父は1892年に福岡県に転勤、緒方は当地で中学時代まですごした。県立修猷館中学(現・高校)の1年上には、のちに朝日新聞に緒方を誘い、彼に先んじて政界に進出した中野正剛がいた。
東京高等商業学校(現・一橋大学)を学校騒動のため退学したのち、早稲田大学専門部に編入。卒業後の1911年、中野正剛の推薦で大阪朝日新聞社に入社した。翌年、明治天皇の崩御直後、枢密院顧問だった三浦梧楼から新元号は大正に決定したと聞き出し、入社2年目にして大スクープをものにする。
緒方は革新派だった大阪朝日の前主筆・池辺三山を尊敬していたが、保守派の主筆・弓削田(ゆげた)精一の指導を受け、独特のバランス感覚を身につけた。その感覚は、仕事だけでなく、私的な人間関係にもうかがえる。結婚にあたっては右翼の総帥と目された頭山満に仲人を依頼したが、緒方としては、頭山は個人として尊敬していたが、右翼を嫌っていた(三好徹『評伝 緒方竹虎』岩波現代文庫)。
1920(大正9)年、緒方は欧米留学に出かけ、イギリスで議会政治の実態を学んだほか、1921〜22年にはワシントン軍縮会議を取材するなどして帰国する。1923年4月には東京朝日新聞社に転じて整理部長、さらに関東大震災直後の10月に政治部長に就任。1925年に東京朝日新聞の編集局長となって以降は、副社長に就任するまでの18年間、新聞社の編集部門・方針を掌握する最高責任者である「筆政」として君臨した。
戦争とともに権力と手を結んだ新聞
編集局長就任直後には、右翼の暴漢に襲われている。その後も緒方にはテロの影がつきまとった。1931(昭和6)年、中学の先輩で友人の広田弘毅が駐ソ連大使として赴任するにあたり、東京駅へ見送りに行ったときには、偶然にも浜口雄幸首相が狙撃される現場に遭遇、すぐさま社に戻ると記事を書いて号外を発行した。1932年には、犬養毅首相が海軍の青年将校に射殺される(五・一五事件)。学生時代から親しく接していた政治家だっただけに、緒方にとっては二・二六事件以上にショックが大きかったという(『評伝 緒方竹虎』)。
五・一五事件の前年の1931年には満州事変が勃発する。緒方はその直前、元老・西園寺公望の秘書・原田熊雄の招待を受け、要人たちとの会合に、大阪毎日新聞主筆の高石真五郎と招かれていた。このとき、陸軍省から出席していた小磯国昭が満州独立論をぶち上げたのに対し、緒方はとんでもない話だと強く反対する。しかし小磯は「いや、日本人は戦争が好きだから大砲を撃ってしまえば、それで勝負が決まるのだ」と返し、高石もそれに賛成したという。緒方は自分と同じ新聞人である高石が小磯に同調したことに驚いた。戦後には、この会合が戦争に踏み出した「権力と新聞の関係」の分岐点だったと繰り返し発言している(『新聞 資本と経営の昭和史』)。
二・二六事件では、事件発生の翌日の朝刊用に、軍の直接行動を否定する社説を緒方自ら書いたが、社内での検討の末、都心の占拠を続ける反乱軍を刺激しかねないとの理由で、急遽、日英両国の職業紹介制度を比較するという内容の社説に差し替えられた。いま起こっている非常事態とはおよそ無関係の社説に、当時朝日の論説委員だった歌人の土岐善麿(読売新聞の社会部在籍中に東海道駅伝競走を発案したことで「いだてん」にも出てきた)は、「物言はぬ新聞あはれ社説には 外国のことを書きて済ませり」との一首を書いて同僚にまわしたという(『新聞 資本と経営の昭和史』)。
緒方自身もその後、権力に接近していくことになる。1937年、前出の広田弘毅が首相になると、それまでの不偏不党の社論を翻し、同内閣支持を打ち出した。二・二六事件で暴発した軍部を抑えることを新政権に期待しての社論変更だったが、これに反対して、前田多門など緒方の信頼していた論説委員があいついで退社する。結果的に広田内閣は軍部の威圧を前に萎縮し、軍国主義への道を開くことになった。
日中戦争下の1938年には、近衛文麿内閣が国会に国家総動員法案を提出する。同法案には、「政府が国家総動員のため必要あるときは、新聞記事の制限または禁止をすることができる」との条文が設けられ、罰則としては発売禁止、原板差押えに加えて、新聞の廃刊を意味する「発行禁止処分」が盛り込まれていた。これに新聞各社は反対決議で応じ、発行禁止条項の削除は認められたとはいえ、多くの新聞社はすでに「言論報国」の方針を出しており、国策である国家総動員体制そのものには反対するわけにはいかなかった(『新聞 資本と経営の昭和史』)。
1940年に米内光政内閣の退陣を受けて首相に返り咲いた近衛は、政党に代わる組織によって国民の総力を結集しようという「新体制運動」を提唱、緒方も「新体制準備委員会」の委員となった。緒方は委員を受諾するに際し、朝日の社論としても近衛支持を明確化するように求めた。しかしこれも裏目に出る。近衛内閣は日独伊三国同盟を調印、朝日社内には同盟はヒトラーの戦争に巻き込まれるとの強い意見もあったが、結局社論にしたがい、これを容認する態度をとった。なお、先述のとおり、のちに緒方が総裁に就任する情報局は、第二次近衛内閣が国策遂行に関する情報収集や報道・啓発宣伝などを目的に1940年12月に設置したものである。
はたして日中戦争の泥沼化に加え、日独伊三国同盟の締結で米英との関係が悪化する。これにより戦時体制の強化の一環として言論統制の徹底が図られ、ますます新聞から自由な報道は奪われていった。1941年には東条英機内閣が成立、同年12月、日本は米英と開戦、太平洋戦争に突入する。
新聞人の戦争責任とは?
緒方は小磯内閣に情報局総裁として入閣するに際し、「言論統制を満州事変の頃までに引き戻したい」と語り、「言論暢達(ちょうたつ)」という政策を掲げた。暢達とはのびのびとしているさまを指す言葉だが、言論暢達は言論統制の緩和策、あるいは情報公開政策だった。緒方は「戦争の実相を出来るだけ国民に知らしめ、同時に言うことを言わせて戦争をもう少し国民の身近に考えさせること」で国民の支持を取りつけようとしたのである(栗田直樹『緒方竹虎──情報組織の主宰者』吉川弘文館、佐々木隆『日本の近代 第14巻 メディアと権力』中央公論新社)。そのために、彼は内閣記者団に対し連日共同会見を行ない、情報局の得た情報を可能なかぎり話した。これに対し記者のあいだからは、色々なことを話していただくのはありがたいが、どの程度まで記事にしてよいのかわからなくなると苦情が出たこともあったという(『緒方竹虎──情報組織の主宰者』)。
しかしもっとも重要な戦局の情報は、情報局に上がってくるまえに陸海軍の各情報部で精査され、しかも戦局の悪化にともない都合よく改竄することが常態化していた。緒方は正確な情報を得ることに苦慮し、首相・外相・陸軍相・海軍相・陸海の幕僚長によって構成される「最高戦争指導会議」への出席を求めるも、結局陸軍の反対で認められなかった。言論暢達政策はこうしたこともあって失敗に終わる。
戦後、緒方は戦争責任について、戦時内閣で大臣を務めた責任ではなく、自分の半生を投入した新聞記者ないし新聞主筆として責任を感じるとして、次のように書いている。
《如何なる国内情勢があったにせよ、日本国中一つの新聞すらも、腹に反対を懐(いだ)きながら筆に反対を唱えなかったのは、そもそも如何なる悲惨事であったか。それは誰に向って言うのでもない。日本一の新聞の主筆であっただけに、自分は自分を責めねばならないのである》(『評伝 緒方竹虎』)
それだけに政界に復帰してからも、言論の自由こそ民主主義の基盤であることを主張し続けた。
緒方は、吉田茂が辞職し、鳩山一郎が首相に就くのと前後して、吉田から自由党総裁の座を引き継いだ。自民党の結成後には、鳩山の後継首相と目されたが、その矢先、1956年1月28日、67歳で急逝する。
なお、『遥かなる昭和 父・緒方竹虎と私』という著書もある緒方竹虎の三男・四十郎は、戦後、長らく日本銀行に勤務し、日本開発銀行副総裁も務めた。元国連難民高等弁務官の緒方貞子は、四十郎の妻である。(近藤正高)
※本稿執筆にあたっては、本文中にあげた書籍以外にも、緒方竹虎傳記刊行會『緒方竹虎』(朝日新聞社)、今西光男『占領期の朝日新聞と戦争責任 村山長挙と緒方竹虎』(朝日選書)、吉田則昭『緒方竹虎とCIA アメリカ公文書が語る保守政治家の実像』(平凡社新書)なども参照しました