この度アニメ!アニメ!では監督を務めた佐藤信介氏に話をうかがった。映画『GANTZ』シリーズ、映画『図書館戦争』シリーズ、映画『アイアムアヒーロー』など、人気原作を一級品の映画作品へ仕上げる優れた手腕を持った監督だ。
[取材・構成:細川洋平]
「デスノート Light up the NEW world」
http://wwws.warnerbros.co.jp/deathnote2016/
――大ヒットとなった前作から時間も経っての企画となりました。企画の話を聞いた時はどのように感じられましたか?
佐藤
企画を聞いたのは3,4年前でした。前作の『デスノート』シリーズの佐藤貴博プロデューサーは僕の監督作品でもある『GANTZ』のプロデューサーもやっていたんです。『GANTZ』という大きな仕事を終えた後、次はオリジナルで何かやろうかと考えていた時に、「数年後に来る映画『デスノート』の10周年に合わせて、もう一回『デスノート』を作るのはどうだろうか」という話が佐藤プロデューサーからあって。最初に聞いた時は「え?!」と驚きましたが、前作の結末が結末なので、その続きということはほとんどオリジナルになる。
――『デスノート』をオリジナルで作り上げるという難しさはありませんでしたか?
佐藤
映画『GANTZ』の2作目『GANTZ PERFECT ANSWER』は映画ならではの終わり方にするというテーマがありました。原作は続くとしても、映画をそこで閉じるというのはオリジナルを作ることと同じなんですよね。『GANTZ』を例に出しましたが、他の作品に関しても同じです。原作があってもある種のオリジナリティーというのはどうしても映画を作るなかで加味されていく。
――今回監督がこだわった部分はどういったところなのでしょうか。
佐藤
異界のものやフィクション性の高いものを見せる時に、映画的なスタイルに添ったリアリティーを重んじています。特に今回は死神が出てきます。
――ノートとしてのデスノート自体の存在感も際立っています。
佐藤
脚本を作っている時に、何よりもまずデスノートだけができたんですよ(笑)。
――本作では三島創、竜崎、紫苑優輝それぞれが前作のキャラクター、つまりキラとLの意志を継いだ人物として登場します。
佐藤
キャラクターは最後の最後まで作っていたような気がしますね。竜崎なんかは前作の松山ケンイチさんが演じたLがすごく強力なキャラクターでしたから、それをマネするわけにもいかないという思いもあり、脚本作りの段階から練り込み、現場で池松壮亮さんにいろいろ演じてもらいながら徐々に作り上げてもらったという感じでした。結果、竜崎は死神に全く引けを取らない感じというか、「こいつが死神じゃないのか」という雰囲気になったと思います。僕は原作でリュークが「今の死神界は腐ってるんだよ」みたいに愚痴るところがすごく好きなんです。死神の方が退屈してて、死神からすれば「人間っておもしれえな」というくらいの、死神も舌を巻くような感じ。竜崎だけでなく三島、紫苑の3者がそれぞれ、それを体現しています。しかも3者で誰が悪で誰が善なのか全く分からなくなる。
――それぞれの価値観で正義がある、ということでしょうか。
佐藤
そうですね。前作は2軸体勢で善と悪がぶつかるということだった。けれど今回は三つ巴になっていて、善悪がぐるぐる回る、すごく今っぽい感じがしています。今日的な『デスノート』を作りたいという気持ちはすごくあったので、それは果たせたかなと思っています。
――善悪の対立ではなく、ぐるぐる回るという部分は“今の空気感”として佐藤監督も感じられている。
佐藤
そうですね。脚本を作っていると「あ、そうだ」と思いつくことの連続で、結果的に「今、この時点」で思っていることが微妙に反映されているのはおもしろいところだなと思います。脚本はもちろん、いろんなことを思って、つぶさに作っていったものですが、できあがって読み返していく時に、自分たちの足跡を見つけることもあれば、新しく発見することもあったりする。それが作品作りのおもしろいところだと思うんです。僕らが違う時代に生きて、作っていたらストーリーも違っていたと思うんです。そういう何かを拾い上げる部分、というのはオリジナル要素が強い作品には反映されがちかもしれませんね。
(次ページ:監督の中でCGの位置づけとは)
――佐藤監督の作品ではCGが多く登場します。特に本作は死神自体がCGと顕著ですが、そもそも監督のなかでCGというものはどういう位置づけなのでしょうか。
佐藤
CGを使う率は段々高くなってきてますね。ただ、CGありきで考えているわけではなくて、それはひとつの手段でしかない。やっぱりモノの美しさ、光なり絵面の美しさを表したいという思いが大元にあるわけです。本当にそこに死神がいてくれるのであれば、いてもらって撮りたいくらいで、実際に作って撮ることもあります。その作れない部分はCGでやろうと。だからCGに対する良さはもちろん感じていますが「CGじゃない方がいいんじゃないか」ということはいつも考えているんです。今回の死神もどうやって映像化するか話し合うなかで、CGじゃないところから始まって、半分作るとか、皮膚は実際のものを作って、など検討していきました。で、「やっぱりCGでやるべきだ」となった。CGは年々技術が革新していくし、その速度がすごく速い、だから見ていて楽しいし、やりたいなと思う事の手助けになっています。
――映画『デスノート』としては10年ぶりの新作となります。作っていくなかでこの映画に込めた思いというのはどういうものだったのでしょうか。
佐藤
10年前には死神が映像化されたことだけでも、見た人にとって驚きだったと思うんです。でもその驚きはもう二度と体験できません。じゃあ今回、別種の驚きを見せられないか考えました。それは原作にある「次のページをめくると次に何が起こるのか全く分からない」というところにあるのではないかと。原作に添ったストーリーだと見る人にとっては照らし合わせになってしまう。「今までの『デスノート』は結末まで知っているけど、今回の『デスノート』はどうなるんだろう」という楽しみ、今しか味わえない楽しみをこの映画のなかで与えられたらいいなと思っています。
それからもうひとつ。死神がいて、息をして、生身の人間と向かい合っているということ。昔、アニメと人間が同じ世界で共演する『ロジャー・ラビット』という作品があって、当時は「そんなことがあっていいのか!?」と思いましたが、今回の『デスノート』でやっているのもそれでした。人間と死神が普通に共演していて、死神がどんな感情を抱いているのか見ている方が想像する。死神に対しても人間と同じように見てもらえたらいいなあと思っています。
――実存感のようなものですね。
佐藤
あと、今回はオリジナル要素が多いので少し違いますが、原作ものを映画化する際によくあるのは、そのまま描いてもビビッと来ない時です。原作となる小説や漫画はいろんな機微も含めて絶妙なバランスで作り上げられた傑作だったりするので、それをちょっとでも変えるとぜんぜん違って見える、ということがあります。特に映画化というのはメディアが変わってしまうのでいろんなバランスが一度グチャッと崩れてしまう。そこに映画の時間の流れや絵の運び方を当てはめて、映画そのもののおもしろさを加味していくと、もう一回蘇ってくるんです。だから最後の最後は「映画としての良さを追求していくこと」で原作ファンにも、よかった、と思ってもらえるものになっていくのかなと思っています。
今回の『デスノート』は長い会議のシーンがあるのですが、一見、止まった世界、静的な絵と見えるかもしれません。でも実はそこに動きは溢れていて、連続的な絵、カメラの動き、それから役者の動き、登場人物の心理の積み重ねが連綿と流れている。大規模な市街地でのシーンと同じくらい、会議のシーンにも動き、映画的な躍動感があって、それをどう撮っていくのか、というのも僕にとっての映画のおもしろさでもあります。脚本段階では絶対に入れられない「動きの世界」を、僕は実際に撮りながら実感してワクワクする。この映画が見る人にとっても、動きに溢れているといいなと思いますね。






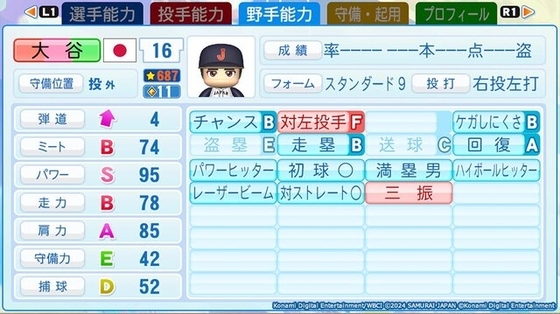











![【Amazon.co.jp限定】ブルーアーカイブ The Animation 第1巻 (Amazon限定特典:1巻~4巻全巻購入特典 描き下ろしA5キャラファイングラフ+アクリルキーホルダー(カヨコ、ハルカ)引換シリアルコード付き) (メーカー特典:フォトカード(超ティザー)(アロナ)1枚 引換シリアルコード付き) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41YtHqlE4xL._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ブルーアーカイブ The Animation 第2巻 (Amazon限定特典:1巻~4巻全巻購入特典 描き下ろしA5キャラファイングラフ+アクリルキーホルダー(カヨコ、ハルカ)引換シリアルコード付き) (メーカー特典:フォトカード(場面写)1枚 引換シリアルコード付き) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41x-B2KDAKL._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ブルーアーカイブ The Animation 第3巻 (Amazon限定特典:1巻~4巻全巻購入特典 描き下ろしA5キャラファイングラフ+アクリルキーホルダー(カヨコ、ハルカ)引換シリアルコード付き) (メーカー特典:フォトカード(場面写)1枚 引換シリアルコード付き) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41wfsFWEHLL._SL500_.jpg)








