2025年の年金制度改革で、iDeCo(イデコ)の仕組みが大きく見直されます。主な変更点は2つあり、掛金の上限が大幅に増えること、そして加入できる年齢が70歳未満まで拡大されることです。
現在iDeCoに加入している人も、これから利用を考えている人も、自分に合った活用法を見つけられるよう、メリットとデメリットを整理してわかりやすく解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の主な変更点
2025年6月13日に年金制度改正法が成立し、それに伴ってiDeCoの制度も見直されることになりました。主な変更点は次の2つです。
1.掛金拠出限度額が引き上げられます
自営業者などの第1号被保険者は、月額6万8,000円から月額7万5,000円に引き上げられます。会社員や公務員などの第2号被保険者は、企業年金あるなしにかかわらず、月額6万2,000円に引き上げられます。
2.加入可能年齢が70歳未満に引き上げられます
働き方にかかわらず、70歳未満までiDeCoに加入できるようになります。ただし、老齢基礎年金やiDeCo老齢給付金を受給していないことが加入の条件となります。
現行のiDeCoは、原則60歳未満まで、厚生年金加入者や国民年金の任意加入被保険者は65歳未満まで加入ができます。今回の改正により70歳未満まで加入年齢が引き上げられたことで、より長期にわたって税制優遇を受けながら老後資金の積立が可能となります。
いつから実施される?
iDeCoの拠出限度額の引き上げと加入可能年齢の引き上げは、2027年の控除分から実現を目指して準備を進めるとしています。
これに先立って、企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額の拡充が2026年4月1日に予定されています。現行では会社が出す掛金に加入者が上積みできる「マッチング拠出」は、会社分を超えた金額を加入者が出すことができないという制限がありましたが、これが撤廃され、拠出限度額まで出すことができるようになります。
月6万2,000円を積み立てると将来いくらになる?
企業年金のない会社員がiDeCoで拠出限度額の月6万2,000円を積み立てたら、将来いくらになるのかシミュレーションしてみましょう。
20代から始めればおよそ40年間、30代なら30年間といったように、始める年齢で積立可能な期間は変わってきます。50代から始めても10年程度積み立てが可能です。
月6万2,000円の積立額による将来の資産額
40代から始めても3%以上の運用利回りがあれば、20年後には2,000万円以上の老後資金を作ることができます。ただし、月6万2,000円を積み立てる必要があるので、この点が厳しいのではないでしょうか。
言い換えれば、40代でスタートしてiDeCoだけで老後資金を2,000万円以上用意するためには、拠出限度額までの積立額が必要ということです。
一方で、20代・30代であれば、老後資金2,000万円の準備に拠出限度額まで増やす必要はありません。20代であれば月2万円、30代であれば月3万円程度の積立で、2,000万円の資金を準備できる可能性が高いでしょう。
iDeCoのメリット・デメリット
iDeCoを始めようか迷っている人のために、メリットとデメリットを分かりやすくまとめておきます。
iDeCoのメリット
掛金が全額所得控除の対象になる
運用益が非課税になる
受取時に控除がある
掛金の全額所得控除はiDeCoの最大のメリットです。
受取時の控除は、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。ただし、「退職所得控除」については今回の改正で見直しがあったため、次項の注意点で詳しく説明します。
iDeCoのデメリット
原則60歳まで引き出せない
口座管理手数料がかかる
運用リスクがある
iDeCoは原則60歳まで引き出せません。そのため、途中で資金が必要になっても解約できないので、生活資金や教育費とは分けて準備する必要があります。
また、口座管理手数料がかかること、運用リスクがあることにも留意しましょう。リスクを取りたくない場合は元本保証型の商品を選ぶこともできますが、その場合も口座管理手数料はかかるので、運用益よりもコストの方が上回ってしまうことがあります。そのため、手数料以上の運用益を期待できる商品を選んで運用を行うことが大切です。
iDeCo受取時の注意点
iDeCoの受取は、一時金で受け取るか、年金で受け取るかによって税金が変わってきます。一時金として受け取る場合は「退職所得控除」が適用されますが、今回の改正では「退職所得控除」の見直しも行われました。
2026年1月から「退職所得控除」の適用期間の計算ルールが「5年ルール」から「10年ルール」に変更となります。
現行制度では、iDeCoの一時金を先に、会社の退職金を後で受け取る場合、受け取り時期を5年以上空ければ、それぞれに対して別々に退職所得控除が適用できるので税負担を軽減できました。
これが10年ルールに変更となり、iDeCoの一時金を受け取ってから10年以上空けて退職金を受け取らないと退職所得控除をそれぞれ満額で使うことができなくなります。
つまり、60歳でiDeCoを一時金で受け取った場合、70歳まで待って退職金をもらわないと控除がまるまる使えないということです。実質的に、iDeCoの一時金と退職金にそれぞれ別々の退職所得控除を適用するのは難しくなったと言えます。
iDeCoを上手に活用するには
iDeCoを上手に活用するポイントは、「無理のない金額で長く続ける」ことです。拠出限度額が引き上がるからといって、生活費を圧迫してまで掛金を増やしてしまうと、途中で継続が難しくなります。家計に余裕のある範囲で積み立て、収入や支出に変化が生じた場合は、金額を見直していくことも必要です。
また、元本保証型の商品だけに偏ると運用益がほとんど得られません。長期的なコストも考えて、運用益を期待できる投資信託を一部取り入れるなど、自分のリスク許容度に合わせた商品選択をすることが大事です。運用状況は年に1回程度チェックし、必要に応じて配分を調整しましょう。
さらに、退職金や企業年金との受け取り時期の関係も踏まえて、税控除を最大限活かす受取方法を検討することも重要です。退職所得控除のルール変更によって、iDeCoは課税の繰り延べに過ぎないという声も出ていますが、減税効果が少なくなるのは、退職金が多い人や年金額が多い人なので仕方がない面もあるでしょう。
iDeCoの受取を一時金と年金の併用にするなど、退職金や公的年金の受取額を踏まえて、最も税負担を抑えられる方法を事前にシミュレーションしておくと安心です。
石倉博子 いしくらひろこ ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP認定者)。“お金について無知であることはリスクとなる”という私自身の経験と信念から、子育て期間中にFP資格を取得。実生活における“お金の教養”の重要性を感じ、生活者目線で、分かりやすく伝えることを目的として記事を執筆中。 この著者の記事一覧はこちら





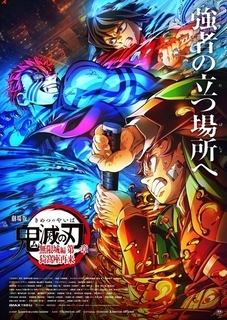

































![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)