第91回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたドイツ映画『ある画家の数奇な運命』より、本編冒頭映像が公開された。ドイツアート界の“負の歴史”として知られる<ナチスドイツVSモダンアート>を象徴する場面を収めている。
【写真】ドイツアート界の“負の歴史”を描き出す『ある画家の数奇な運命』冒頭シーン写真
本作は、長編初監督作『善き人のためのソナタ』(2006)でアカデミー賞外国語映画賞を受賞したフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督が、現代美術界の巨匠で、ときにオークションで数十億円の価格がつくアーティスト、ゲルハルト・リヒターの半生をモデルに、祖国ドイツの“歴史の闇”と“芸術の光”に迫った作品。
本編冒頭映像は、少年時代の主人公クルトが、叔母エリザベトに連れられてモダンアートが展示されている展覧会を訪れた場面。彼らはほかの見物客とともに、案内の男性から、それらの作品について「彼ら(作者)には草原が青、空が緑、雲が黄色に見える」「(もしそれが障害であれば)子孫に遺伝していくのを阻止しなくては」などと解説を受ける。ひととおり解説を受けた後、モンドリアンとカンディンスキーの絵画の前で「絵描きになるのはやめた」と言うクルトに対し、エリザベトは「好きな絵よ。内緒ね」と微笑みながら告げる。
当時のナチス政権は、国内の美術館や画廊などから近代芸術作品を“堕落した作品”として押収し、それらをまるで芸術の公開処刑のように晒しものにする、本映像のモデルにもなった展覧会「退廃芸術展」を開催。
●現代美術界の巨匠をモデルに描く『ある画家の数奇な運命』ストーリー
ナチ政権下のドイツ。少年クルトは叔母エリザベトの影響から、芸術に親しむ日々を送っていた。ところが、精神のバランスを崩したエリザベトは強制入院の果て、安楽死政策によって命を奪われる。終戦後、クルトは東ドイツの美術学校に進学し、そこで出会ったエリーと恋に落ちる。
映画『ある画家の数奇な運命』は公開中。




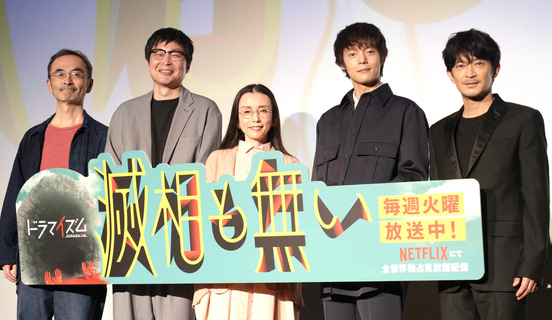












![ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE ブルーレイ+DVD(ボーナスブルーレイ付き) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cUwTw9XaL._SL500_.jpg)
![バタリアン [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51rhSJzkiVL._SL500_.jpg)
![ジャン・ユスターシュ ニューマスターBlu-ray BOX【5枚組】 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41LYbID32SL._SL500_.jpg)
(Amazon限定グッズ:ムービーモンスターシリーズ (クモオーグ、コウモリオーグ、ハチオーグ、サソリオーグ、カマキリ・カメレオン(K.K)オーグ)+Special 収納 BOX(Amazon ver.)付き)(メーカー特典:クリアしおり(ランダム 全 3 種)付き) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/316mitukrDL._SL500_.jpg)





