前回述べたように、ジンバブエはもともとイギリスの植民地で、第二次世界大戦後は宗主国であるイギリスの反対を押し切ってアパルトヘイト国家、ローデシア共和国として独立した。
[参考記事]
●ジンバブエ、最悪の独裁といわれるムガベ政権と欧米植民地主義の負の遺産
ムガベは反植民地闘争の英雄で、国民を人種差別的な白人権力から解放したのだから、きわめて大きな道徳的正当性を持っている。欧米諸国もムガベの「偉業」を認め、過去の人種差別について「反省」するほかはない。これが、アフリカ諸国と欧米との「歴史問題」の基本的な構図だ。
当然のことながら、これは白人社会に大きなストレスを与えている。
白人がアフリカについて語る際には、「政治的に正しいPolitically Correctness」手順が厳密に決められていて、そこから逸脱してはならないのだ。
農地の大半を所有する白人農家の物語『The Last Resort: A Memoir of Mischief and Mayhem on a Family Farm in Africa(ラストリゾ-ト――アフリカの家族農園の破壊と混乱の記録』は、ジンバブエでゲームロッジ(観光サファリのための宿泊施設)を経営する白人一家が、ムガベによる土地の強制接収に対抗して自分たちの「ラストリゾート」を守るために奮闘する物語だ。
著者のダグラス・ロジャーズはローデシア共和国の中流白人家庭に生まれたが、大学でジャーナリズムを勉強したのち、この国では自分の人生に未来がないとイギリスに渡った。ロンドンで新聞や雑誌に旅行記を書くようになったあと、2003年には仕事の拠点をアメリカに移している。
ダグラスの父は首都ハラレ(ローデシア共和国時代はソールズベリー)で法律事務所を営み、母親は演劇教師をしていたが、2人は退職後にジンバブエ東部の山岳地帯に土地を購入し、外国人観光客が動物たちを観察できるゲームロッジを始めた。
ムガベが白人農園の占拠を認めるようになる経緯は前回書いたが、これによってロッジDriftersも危機にさらされる。ジンバブエに戻ったダグラスは、両親にロッジを明け渡して国を出るよう懇願するが、2人はあくまでも自分たちの土地を守るといってきかない。こうしてダグラスは、土地を追い出されて逃げ延びてきた白人農家や反体制派の黒人活動家、旅行者の来なくなったロッジを定宿にするダイヤモンド取引業者や彼らを目当てに集まってくる売春婦たちとともに、はちゃめちゃ(Mischief and Mayhem)な日々を過ごすことになるのだ。
これも前回書いたが、ジンバブエ(旧ローデシア)の農地の大半は白人農家に所有されている。彼らはイギリス植民地下で政府から土地を与えられ、開拓民としてアフリカにやってきた。
「ラストリゾート」を黒人の無法者から守る物語が成立するのは、彼らの土地がこの「歴史問題」から切り離されているからだ。ダグラスの両親はアパルトヘイト時代は都市知識層で、ジンバブエとして“解放”されたのちに、正式な売買契約にのっとってロッジの土地を購入している。もちろん元をただせばその土地も白人によって不法に奪われたものかもしれないが、植民地時代から大規模農業を営む白人たちに比べて、所有権の正当性をはるかに強力に主張できるのだ。
著者のダグラス・ロジャーズは、土地を奪われるジンバブエの白人が“被害者”で、農場を占拠しようとする黒人が“加害者”という構図を巧妙に回避することでPC(政治的正しさ)のハードルをクリアした。
このようにして、権力に翻弄され、痛めつけられた高齢の夫婦が、勇気と才覚によって自らの権利を守り、生き延びるためにたたかうという、白人読者にとってきわめて心地よいストーリーが生まれたのだ。
「白人社会の信頼を裏切った」アレクサンドラ・フラーの『Don't Let's Go to the Dogs Tonight(今夜は犬のところに行くのを止めなさい)』は、白人少女の視点からローデシア紛争を描いた回想記だ。著者のアレクサンドラはイギリス生まれで、3歳のとき(1972年)に両親とともにローデシアに移住し、そこで“解放戦争”に巻き込まれる。ジンバブエ建国(1979年)は著者が10歳のときだから、主人公は「黒人差別の歴史」についてイノセントだ。
ピーター・ゴッドウィンの『Mukiwa: A White Boy in Africa(ムキワ――アフリカの白人少年)』では、少年の立場からローデシア紛争が回想される(“Mukiwa”は「南アフリカの白人」を意味するバンツー族の言葉)。著者は1957年生まれだから、紛争は8歳から22歳までにあたる。
ピーターの父はポーランド系ユダヤ人の技師で、母はイギリス系の医師だった。彼は17歳で黒人の反乱軍とたたかうために警察官として徴集され、21歳のときに姉と婚約者が反乱軍の待ち伏せにあって殺されている。その後、イギリスに渡ってケンブリッジ大学で法律を、オックスフォード大学で国際関係論を学んだピーターは、『サンデイタイムズ』の記者となった――この経歴からわかるように、彼の場合は黒人差別にイノセントとはいえないものの、両親は都市知識層で、家族はローデシア紛争のなかで相応の代償を支払っている(そのうえピーターの父方の一家は、ナチスのホロコーストを逃れてアフリカに渡ってきた)。
『Mukiwa』でジンバブエでの少年時代を回想したゴッドウィンは、その後、『When a Crocodile Eats the Sun: A Memoir of Africa(クロコダイルが太陽を食べるとき――アフリカのメモワール)』や『The Fear: Robert Mugabe and the Martyrdom of Zimbabwe(恐怖――ロバート・ムガベとジンバブエの苦難)』など、ムガベ政権の汚職と腐敗を批判する著作をつづけざまに出版する。新生ジンバブエは黒人と白人がなんとか共存してやってきたのに、権力にとりつかれ“モンスター”と化したムガベがなにもかもぶち壊してしまったのだ。
ムガベが欧米諸国、とりわけイギリスから激烈な批判を浴びたのは、彼が「白人社会の信頼を裏切った」からだ。1980年にジンバブエを解放したムガベは、当初は白人への報復を抑え、その融和政策は「アフリカでの黒人による国家建設のモデル」と賞賛された。その功績により、1994年にエリザベス女王からバス勲章を授与されてもいる。
それにもかかわらず、2000年代になると、自らの政治的失敗を糊塗するために白人農場の強制収用などの不寛容政策に転じ、欧米や白人社会に対する憎悪を煽るようになった。「飼い犬に手を噛まれる」とはまさにこのことで、欧米諸国からすれば、ムガベはずっと“悪魔”の正体を隠し、善良な白人たちを欺いてきたのだ。
興味深いムガベの生い立ち南アフリカに生まれ、(旧)ローデシアで育ったヘイディ・ホランドはジャーナリストとしてアフリカ問題を精力的に報じた。そんな彼女が2008年に出版したのが『Dinner With Mugabe: The untold story of a freedom fighter who became a tyrant(ムガベとのディナー――独裁者となった「自由の戦士」の知られざる物語)』だ。この本でホランドは、欧米社会から「モンスター」と呼ばれるムガベの興味深い人物像を描写している。
この本についてはアフリカ地域研究の小倉充夫氏が簡潔に要約しているので、それを紹介しよう(「植民地支配と現代の暴力」小倉充夫編『現代アフリカ社会と国際関係』(有信堂)所収)。
――ムガベは1924年2月21日にカトリック教会の大工の子として生まれたが、幼少の頃に長兄が死に、その後、出稼ぎにいった父が家族を見捨て、一家は貧困の苦しみを味わうことになる。ようやく父が戻ってきたとき、彼は3人の異母兄弟を連れていた。そんな父を、ムガベは許すことができなかった。
若い頃に尼僧になろうとした母はしつけに厳格で、ムガベはその期待を背負って学業に励んだ。弟は兄ムガベについてこう語っている。
「彼は友達をつくることに関心がなかった。本が友達だった。私はその反対で誰とでも話し、また喧嘩をした。私は早く走れたが、兄はできなかった。動作がのろく、いつも本を読んでいた。祖父にいわれて牛を草地に連れて行く時には片手に鞭を持ち、他方に本をもっていった」
ムガベは教員資格を取得後、奨学金を得て南アフリカの大学に留学し、そこでマルクス主義とガンジーの思想から影響を受けた。学士号取得後は帰国してミッションスクールの教師になり、ロンドン大学の通信教育を受け、1958年にガーナの師範学校に赴任することになる。ガーナは前年にサハラ以南のアフリカで最初の独立国になり、アフリカの統一とその象徴たるアフリカ合衆国を目指していた。
ムガベはガーナで、社交的で知的な女性サリー・ヘイフロンとめぐりあう。彼女はムガベの同志となり、彼が唯一心を開くことのできる人になった(サリーが1992年に腎不全で死去したことが、ムガベの人格が豹変する理由のひとつとされた)。
ガーナからの帰国後、首都ソールズベリー(現在のハラレ)で開かれた抗議集会での演説で注目され、ムガベは次第に民族運動の担い手になっていく。11年間投獄されたあと、遅れてゲリラ活動に加わったものの、解放闘争初期の有力者たちが暗殺や事故で死亡したことで指導者となり、ついには首相に就任する。
妻サリーの姪によると、「彼(ムガベ)は誰にでも学校に行くことを薦め、公邸の庭師にも通信教育を薦め、授業料を払ってやった。ある時期には公邸の従業員全員に定期的に授業を開いた」。
牢獄にいたときもムガベは時間を無駄にせず、ロンドン大学の通信教育で法学と経済学の学位をとった。そればかりか受刑者の勉強会を開き、他の仲間に学習させていた。
首相になってからも、ムガベは常に丁重で時間に正確だった。
「遅れそうな時には部下があらかじめ電話をしてきた。約束の時間より少し遅れると、それがたとえ5分であっても、来るなりすぐに遅れたことを彼は謝った」
「ムガベは今でもイギリス紳士の服装をしている。それが彼の変わらないスタイルだ。彼のふるまいもイギリス紳士のようで、面と向かっていると素晴らしい人です。同じ人だとは信じられないでしょう」
「一対一だと彼はどぎまぎして、ぎこちないようにみえ、実際恥ずかしがり屋であった。公式行事や宴会に出なければならないが、彼はけっして楽しんでいなかった。水の入ったグラスを持って彼は悲しげに見えるか、ワインを啜っていた。しかも最後まで半分は残っていた」
との証言もある。
独立直前の選挙で勝利したあと、ムガベは次のように述べた。
「私は、黒人であろうと、白人であろうと、悲惨な過去を忘れ、他の人々を許し、新たな親交のもとに手に手をとって、共にジンバブウェ人として人種主義、部族主義、そして地域主義を忘れ、かつ無視して経済機構を再生するために、我が社会を再建し、復興すべく懸命に働くことを私と共に誓約するように切に訴えるものである」
実際、ムガベはローデシア最後のイギリス総督夫妻と親密で、民主選挙によって権力を制したあと、「誰か話のできる人が必要なのであなたにとどまってほしい。私は国を統治することについては何も知らないし、それを知っている者はいない」と総督に頼んだ。そして、次のように約束したという。
「即座に大きな変化はない。産業や土地の急速な国有化も、白人の追放もない。白人にとどまってもらいたい。彼らがいないと経済は破滅する。ウォールス(ローデシア軍総司令官ピーター・ウォールス)にもとどまってもらいたい。そうすれば白人の恐怖が減り、ローデシア軍と解放勢力から統制のとれた軍隊を創設できる。我々には時間が必要であり、総督にはできる限りとどまってほしい」
またムガベは、白人のデニス・ノーマン(独立前は商業農家組合議長)を初代の農業大臣に任命した。
1990年の南部アフリカ開発調整会議のためムガベとノーマンがスワジランドに滞在していたとき、マーガレット・サッチャーが辞職したというニュースが入った。ムガベの周りにいた閣僚たちが歓声をあげると、ムガベはいった。
「なんでそう浮かれ騒ぐのだ。彼女が去ることがそんなによいことなのか。君たちに思い出してほしいことがある。誰が我々の独立を認めたのかね。保守党のサッチャーか労働党のキャラハンか」
そして、次のように続けた。
「君たちに大事なことを言おう。彼女の政策には賛成しないが私は尊敬している。彼女が果敢に戦ったことに敬意をもつ。彼女はもっとよい終わり方をするのに値する」
ノーマンはムガベと強い信頼関係で結ばれたものの、当の白人社会から批判にさらされ、農業大臣を罷免されることになる。ノーマンは後に、ムガベが白人と黒人の共存を試みたにもかかわらず、白人の強い人種差別意識と、ローデシアにおけるこれまでの経済発展への自負が融和を阻んだのだと回想している。
「当時のムガベの政策は明らかに彼ら(白人)にとってもよいものだった。ムガベが政権を掌握した時、白人に軍を指揮させ、私を農業大臣に、デビット・スミスを商工大臣にした。黒人による支配への白人の恐怖を和らげるためにムガベはあらゆることをした。彼は近い人間を重要な地位につけるようなことをしなかった。彼のあらゆる努力によるこうした状況にもかかわらず、白人がスミス(ローデシア共和国をイギリスから分離させアパルトヘイトを主導したイアン・スミス)を支持したので彼は本当に失望し、そして何より傷ついたと私は思う」
ムガベが20年後に“モンスター”になった理由とは?独立直後のムガベは人種の融和を説き、黒人に自制を求める、ネルソン・マンデラと同じような穏健で賢明な黒人指導者だった。そんな彼がなぜ、20年後には“モンスター”になってしまったのか。
これにはもちろんさまざまな要因が考えられるだろうが、小倉氏は前掲書で、冷戦の終焉と97年のブレア労働党政権の登場を指摘している。
ニューレーバーを旗印に地すべり的な大勝を収めた労働党政権は、外交に「倫理的要素」を持ち込み、人道支援のためには他国への軍事的介入をも辞さないと明言した。イギリスの、そして西欧の民主主義と人道思想を広めることは道義的責任であるとするブレアは、9.11同時多発テロによってこの考えをさらに強固にし、テロとの戦いとアフリカの開発にのめりこむことになる。
それに対してムガベは、2002年にヨハネスブルグで開催された開発に関する世界サミットで次のようにブレアを批判した。
「我々はヨーロッパ人ではない。ヨーロッパのわずか1インチ平方の土地でさえ要求したことはない。だからブレアよ、イングランドをくれてやるから、我がシンバブウェは私のものだ」
このサミットでムガベは喝采を博し、ブレアには野次が投げかけられた。これをきっかけにイギリスなど欧米のメディアはジンバブエの土地改革を「土地強奪」、支配政党を「腐敗した残忍な独裁」と非難するようになった。
だが真の問題は、ブレア政権が植民地支配を過去のこととして扱おうとしたことにあると小倉氏は述べる。「今日のジンバブウェの状況を過去と切り離す姿勢と、ジンバブウェ問題をムガベ問題に矮小化する態度とは大いに関連している」。すなわち、植民地問題の「責任」を否認するために、イギリス(ブレア政権)にはムガベという「独裁者」が必要だったのだ。こうして、「人格の破綻したモンスター」というイメージが意図的につくられていく。
もちろんこれは、ムガベや政権幹部たちが清廉潔白だということではない。だが同じように腐敗している権力者はアフリカ諸国には(残念ながら)いくらでもいる。そのなかでなぜ、ジンバブエだけが極端な経済制裁の対象になるのだろうか。
それは、ムガベが植民地問題の過去を清算するために白人の土地を接収したからだ。黒人同士の土地争いであれば、彼らはなんの関心も持たなかっただろう――これが、ジンバブエから欧米に突きつけられている「歴史の責任」なのだ。
<橘 玲(たちばな あきら)>
作家。「海外投資を楽しむ会」創設メンバーのひとり。2002年、金融小説『マネーロンダリング』(幻冬舎文庫)でデビュー。「新世紀の資本論」と評された『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』(幻冬舎)が30万部の大ベストセラーに。著書に(以上ダイヤモンド社)など。中国人の考え方、反日、政治体制、経済、不動産バブルなど「中国という大問題」に切り込んだ最新刊
![ジンバブエ、ムガベ大統領が“モンスター”になった理由とは? [橘玲の世界投資見聞録]](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FDiamond%252FDiamond_71922_1.jpg,zoom=600,quality=70,type=webp)





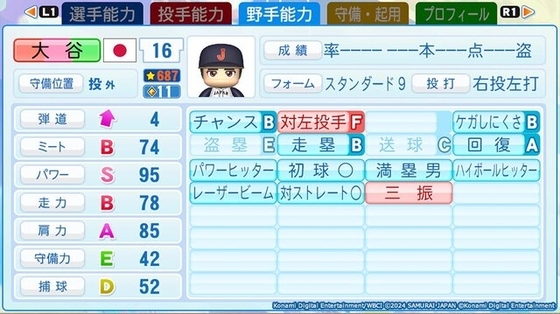







![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








