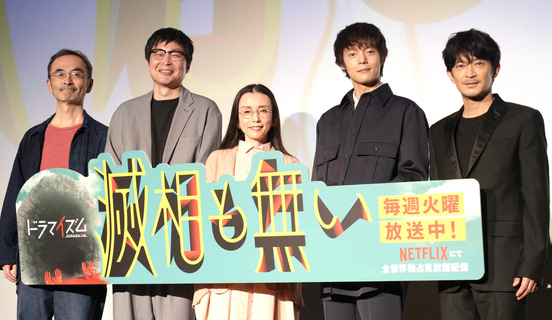健次郎は兄・猪一郎(1863-1957)とともに明治プロテスタントの原点のひとつ、熊本バンドの出身。優秀な兄(中村蒼)にたいする劣等感と闘う一生を送った作家です。
18歳の健次郎が兄や新島夫妻の反対を押し切って恋した山本久栄は、健次郎がまじめに書いた恋文を友だちの前で読んで聞かせるような子だったそうです。一説には新島夫妻が手紙を検閲していたとも。
お固いキリスト教の道徳と自分の性欲の折り合いがつけられず苦悩する蘆花は、たちまち成績ガタ落ち。翌年、二葉亭四迷のふられ男小説『浮雲』(新潮文庫)を途中まで読んで「これってほとんど俺と久栄ちゃんみたい!」と怖くなって読了できなかったけど、「小説ってものを書いてみたい」と思いました。
久栄への思いを断ち切るため同志社を退学し、鹿児島まで2か月のオンザロード的放浪生活を敢行。道中は買春しまくってたらしい。
その後郷里で教師をしたのちに再上京、兄が徳富蘇峰という名で主宰するイデオロギー系出版社「民友社」に身を寄せます。新島襄(ドラマではオダギリジョーが演じる)が結核闘病の末亡くなったときには、見舞いにも葬儀にも行きませんでした。
健次郎は、政界に影響力を持ちつつある兄を俗物視しながらも、生きるためにその兄の下で働くしかない鬱憤を溜めていきます。久栄への思いはまだくすぶっていて、翻訳していた外国雑誌の記事の写真の女が久栄に似ているのを見て、それを下宿の机に拡げて、毎晩帰宅後に久栄との恋バナを手記に書いてたりしていたとか。
久栄が亡くなった翌年、トルストイやゲーテやユゴーを愛読する25歳の健次郎は、小学校教師をしていた同郷の原田愛子と結婚(恋愛感情なし)、勝海舟(ドラマでは生瀬勝久)邸内に住んで、兄の《国民新聞》の平社員を続け、蘆花という筆名を使いはじめます。
名士である兄の世界一周視察に同行を許されなかった蘆花のひがみは頂点に達し、妻にDVを働いたり、部屋で日本刀を振り回したり、女中を手込めにしたりと狼藉の限り。兄貴は贅沢旅行で俺の尊敬するトルストイ先生に会ったりしてるのに、俺は妻に着物を売らせる貧乏生活じゃねえか!
蘆花は病んだ心を抱えて逗子の、同僚・国木田独歩がかつて最初の妻と住んでいたことのある家に移り、最初の本を出しますが、評判になりません。
静かな生活と妻の支えで精神が安定してきた蘆花の隣室に、日清戦争に出た大山巌大将(ドラマでは反町隆史)の副官の未亡人が避暑に来ます。彼女から蘆花夫妻は、大山大将の娘・信子についての消息を聞きました。
蘆花の妻愛子は女学生時代に信子を見たことがありました。
信子は継母捨松に愛されず、追い出されるように薩摩出身の政財界の若き大物・子爵三島彌太郎(のち貴族院議員・日銀総裁)と結婚してから結核になり、離縁されて死んだというのです。信子の非運に衝撃を受けた蘆花は、この話にインスパイアされて『不如帰〔ほととぎす〕』(岩波文庫)を書きます。
無情にも離婚しべつの女性とさっさと再婚した三島彌太郎は、出征したり負傷したりして妻のそばにいられない好青年「川島武男」に変更。丸顔で薮睨みだった信子は腺病質の美人「浪子」となり、実家を継母にいびり出され、嫁ぎ先では姑にいじめられるかわいそうな展開で、《国民新聞》に連載されました。
連載はそこそこ好評ではあったものの、黒田清輝の口絵をつけた単行本(1900年)は、民友社としても大して売れるとも思ってなかったようです。
〈しばしば涙のこぼるるを覚えず。読み終つて、純潔の血が湧く心地いたし候〉
と熱い手紙を寄越し、信州の島崎藤村もこれを愛読するなど、大好評。
増刷につぐ増刷、尾崎紅葉の『金色夜叉』(新潮文庫)と並んで新派劇になるというメディアミックスも話題となり、満都の善男善女の紅涙を絞る大ヒットとなりました。難病純愛小説『不如帰』はまさに明治の『セカチュー』だったのです。
自然のスケッチを書いてみたら? という独歩の助言を受けて出した『自然と人生』(岩波文庫)も大ヒット。兄の会社の社員待遇をやめ、帰京して家もべつに構え、自伝的な小説を刊行し、人気作家にはなったのですが、版元である兄の会社が払った印税には大いに不満でした。
また政界入りした兄が遠回しに「なー健次郎、オレをモデルにカッコいい政治小説書いてくれよ」と言ったので書き出した『黒潮』のなかで、伊藤博文・大隈重信・榎本武揚(ドラマでは順に加藤虎ノ介・池田成志・山口馬木也)をモデルにしたと露骨にわかる人物を悪しざまに書きまくり、兄が慌てて「おいおいちょっと待てや!」となって中断。
またエッセイの文言をデスクが一部削除して蘆花が激怒するなどの事件もあり、このころから兄弟の不仲は業界で有名になります。そしてとうとう兄弟絶縁。
蘆花は富士山の頂上でブランデーを飲み干して急性アル中の人事不省となったり、かと思えば妻に、自分の過去の女関係を洗いざらい告白して、妻がキレて(そりゃそうだ)心身症を発症したり……壮絶な展開です。
このあと夫妻は家財を断捨離し、日記を焼き、食事をベジタリアンに切り替え、伊香保に移りました。蘆花は新約聖書トルストイを読む生活を送ります。
もうトルストイ先生も長くないかも、と思った蘆花は1905年、意を決してロシアを訪れようと決心します。船を見送りながら、愛子は夫が愛した別れの賛美歌「主よ、みもとに近づかん」を口ずさんでいたとか。ホントーに偉いのはこの愛子では!?
神戸から門司まで同行していた出版社社長が、船中でロシア旅行記をぜひ我が社から!と依頼すると、蘆花は彼に言います。
〈あなたには、いいものを上げます。私の原稿よりかずっといいものを〉。〈神を信じなさい。ただそれだけです〉(伊藤整『日本文壇史9』講談社文芸文庫)。
カッコいいこと言ってんじゃねえよこちとらビジネスなんだよ……版元社長の握りこぶしが怒りでプルプル震えてそうです。
トルストイに会って帰国した蘆花は、千歳村(いまでこそ世田谷区粕谷ですが当時は北多摩郡の、文字どおりの武蔵野)のボロ家に移って、一帯を恒春園と命名し、みずからの手で肥桶かついで農業に取り組む〈美的百姓〉生活に突入。この前書いた『ごちそうさん』室井幸斎の名前の元ネタ・村井弦斎もそうですが、売れた作家は自分で農業するものなんですねー。
スローライフを綴った『みみずのたはこと』(岩波文庫)がまた大正のロングセラーとなりました。私が読んだ蘆花の本ではこれがいちばんおもしろかった!
この時期は兄とも仲よかったようですが、1911年になると前年の大逆事件を受けて、幸徳秋水らの早すぎる死刑執行にたいする悲憤慷慨の思いを一高での講演『謀叛論』(岩波文庫)で吐露しまたも物議を醸します。
中野好夫『蘆花徳冨健次郎』第3部[筑摩書房《中野好夫集》第11巻]によれば、遅くとも講演の翌朝には文部省が講演内容を把握していたといいます。当局の隠密が聴衆に紛れていたのか?
これだけが原因ではないようですが、また兄と絶縁! そのあとヤケクソになったのか、『黒い眼と茶色の目』(岩波文庫)という小説で、30年近く前の山本久栄との恋愛事件について赤裸々に書いてしまいます。新島八重が太っていて、同志社の学生に〈鵺〉〔ぬえ〕と呼ばれて煙たがられていたとか、ひどい話です(八重、綾瀬はるかみたいなスラっとした人じゃなかったんだよね……)。つぎに兄と和解するのは十数年後、死の直前の1927年でした。
……忙しき哉人生!
5歳下の弟の死後、兄・蘇峰はさらに30年生きて、着々と名士の道を歩みます。1940年の日独伊三国同盟締結建白書、翌年には大東亜戦争開戦詔書の作成にタッチし、戦時下に文化勲章受賞。
戦争協力活動のせいで戦後にはA級戦犯となり議員辞職、文化勲章も返上したそうです。文化勲章って返上できるんだ!
村井弦斎の回で引用したとおり、
〈日本で能〔よ〕く売れた本と言へば蘆花の『不如帰』に弦斎の『食道楽』〉(内田魯庵「よく売れた小説と文士の収入及び生活」[1911]、黒岩比佐子さんによる『食道楽』岩波文庫版上巻解説から孫引き)
とのことで、大衆の人気は兄より弟のほうにあったようです。これを書いた内田魯庵も民友社で蘆花の同僚でした。
蘇峰は、戦後は戦争協力への批判もあって、日本中の蘆花ファンから「ひどい兄」呼ばわりもされた失意の晩年だったようです。
〈まだ死なぬか、死ぬのが楽しみだ〉と言いながら95歳で蘇峰が死んで40年後の1997年、蘆花を回想する蘇峰晩年の口述記録が発見され、『弟 徳冨蘆花』として緊急出版されました(のち中公文庫)。蘇峰の台詞は同書序文で孫の徳富敬太郎さんが報告したもので、敬太郎さんはこの翌年(1998)山中湖文学の森に開館した徳富蘇峰館の館長となりました。
『弟 徳冨蘆花』のなかで蘇峰は、弟の幼時から不和のいきさつまで、無愛想ながら温かい口調で淡々と語っています。新派の芝居は見ないが、『不如帰』だけは何度見たかしれない、なんて書いてあって、ほろりとします。
兄はジャーナリスト、言論人として活躍、のちに政界入りし、つねに「公」の陽のあたる道を堂々と歩いて行った重厚な人です。初期の代表的著述『将来之日本』(筑摩書房『現代日本文学大系』第2巻所収)はいまも一読の価値あり。
いっぽう弟・蘆花健次郎は、ロマンチックな小説でアーティストとして大ブレイクしながらも、自ら苦難の道ばかり選んで、兄より先に死んでしまいます。
蘆花の小説・エッセイはおもしろいし(小説なら『不如帰』、エッセイなら『みみずのたはこと』)、本人の人生も強烈かつ滅茶苦茶で、近代日本のお騒がせ知識人だったんですね。
この兄弟はほんとうに大物どうしですから、ぶつかり合いも尋常ではない。対照的な兄弟の、長くて派手な兄弟喧嘩が、近代日本を串刺しにしてるかのようだ。
なお、京王線の芦花公園こと蘆花恒春園は、蘆花の歿後に愛子夫人が東京市に家・耕地ごと寄贈したものです。もう一度書くけど、ホントーに偉いのは兄でも弟でもなく、弟の奥さんなんじゃないの?
(千野帽子)