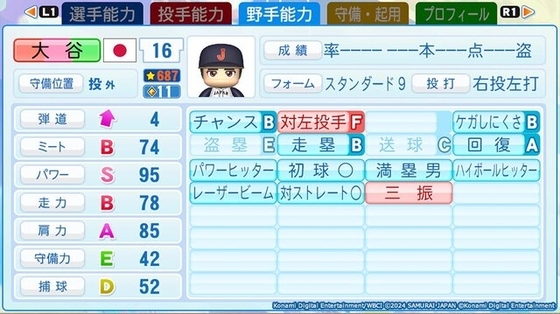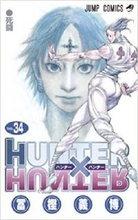芥川賞の予想はこちら。
■『あとかた』千早茜(初。新潮社)
今回、芥川賞は5人中2人が初ノミネートだが、直木賞は6人中3人と、なんと半数が新人である。節目の回に新しい風を入れようという意図であれば喜ばしいことだ。
初ノミネートの千早茜は、デビュー作『魚神』でいきなり第37回泉鏡花文学賞を獲得するなど、早熟の印象がある作家である。
『あとかた』は6作からなる短篇集である。巻頭の「ほむら」は結婚を間近に控えている恋人がいるにも関わらず無頼な印象の中年男と知り合った女性が主人公、続く「てがた」ではその男の元部下だった男が語り手になる。男は結婚を機に妻の実家に近い郊外のマンションを購入、妻との距離がだんだん開いていくことを感じながらも、その日常になんとか足場を見出そうとしている。そして次の「ゆびわ」は男の妻が主役、といった具合に少しずつ登場人物が重なりながら展開していく連作なのだ。
「ほむら」の主人公は「互いが思っていることを明確な言葉にするのは怖い」「今あるかたちを壊さないように、結婚という枠にはめておくのだろうか」「留めたいと思った時点で、ものごとは膿んでいってしまう」と自身の結婚について思いを巡らせる。
■『伊藤くんAtoE』柚木麻子(初。幻冬舎)
こちらも初ノミネートとなる柚木麻子は2008年デビュー、2013年には女子会社員を主人公にした『ランチのアッコちゃん』も話題になった。本書は1人の男を中心に配することで、彼と関わった女性たちの人生を側面から照射することを企図した連作短篇集だ。
「伊藤くんA」から「伊藤くんE」までの5篇で成る作品集である。冒頭の「A」は新宿の百貨店に入居している革製品専門店で働く島原智美が主人公だ。智美は社会人に成り立てのときに合コンで伊藤と知り合った。しかし五年間で実際に会った回数は数えるほど、店にある20万円の鞄が売れたら伊藤と正式なカップルになれる、と願をかけている日々なのである。しかし彼女のモノローグを見ると、なぜそんな男に惹かれるのだろうか、と思ってしまうほどに伊藤の言動はひどい。
その智美がなんとか男を振り向かせたいと『ヒロインみたいな恋しよう!』というハウツー本を買い(本の著者である矢崎莉桜は売れっ子の脚本家なのだが、彼もまた伊藤ワールドの住人であることが後にわかる)なんとか生き方を変えようとする話が「A」で、智美の行動の歯がゆさにイーッとなる読者が続出するはずである。そうなったら作者の思う壺で、もうコントロール下に入っている。5篇それぞれに人生をこじらせてしまったヒロインが登場するので、誰か1人は共感するキャラクターが見つかるはずだ。男性読者向けには「D」がお薦め。
楽しい作品だが、キャラクターの類型性などは選考時につっこまれるかも。初候補だし、ちょっと割り引いて★★☆。
■『王になろうとした男』伊東潤(4回目。文藝春秋)
これで候補になるのは4回目の伊東潤。作品は相変わらず抜群におもしろい。今回も連作短篇集で、覇王・織田信長の家臣団から武将たちが選ばれている。
巻頭の「果報者の槍」の主人公は毛利新助、戦国ものに関心がない人にはあまり馴染みがないかもしれないが、信長の運命を切り拓くことになった桶狭間の合戦で、敵将・今川義元の首級を上げた武将だ。彼はその働きを評価され、信長の親衛隊というべき黒母衣衆に取り立てられた。しかしその後は目立った働きをすることがなく、歴史の表舞台から姿を消してしまうのである。
伊東はこういう、一瞬だけ輝きを放った人物に焦点を当てるのが本当に上手い。通好みともいえるが、伊東の小説がいいのは単に埋れた人物を掘り起こしてくるだけではなく、その人々が埋れた理由、逆に一瞬の輝きを放つことができた理由を論理づけ、小説の骨格としてそれを再現している点である。毛利新助の場合でいえば、すでに武辺一辺倒の侍が存在価値を失っていた時代だったのだと結論づけ、時代から取り残されたなりの働きを彼にさせるのだ。その潔さが気持ちよく、「果報者の槍」の結末には爽やかなカタルシスがある。
全5篇が収録されているが、もっとも意外な主人公は表題作のそれだろう。すでに書評などは書かれていると思うが、短篇集で読んだ場合、知らずにページを開いたほうが発見もあって楽しいはずなのでここでは書かない。おもしろいことは5人の主人公のうち、もっとも信長に接近したのは彼だったことで、本書は5人の視点を使って織田信長という人物の輪郭を形作っていく趣向になっているのだが、この表題作によって信長像に魂が入れられることになるのである。
危惧されるのは、過去3回の候補作がいずれも連作短篇集だったため、同工と取られる可能性があるということだ。上に書いたような趣向が認められれば、受賞はありだろう。逆に言えば誰かが「また連作ですね」と言い出したら危険ということ。不安要素もあり、予想は★★★どまりにしたい。
■『昭和の犬』姫野カオルコ(5回目。幻冬舎)
今回最多のノミネート回となるのは姫野で、候補に上がるのは第143回以来だから3年半ぶりということになる。そのときの候補作『リアル・シンデレラ』と、作品を通読すると戦後昭和史になるという趣向は似ている。
主人公のイクは1958(昭和33)年生まれである。物語は彼女が5歳のときから始まる。ララミーハウスと呼ばれる奇妙な家にイクの一家は越してくるが、そこではめいめいが寝るために集まってくるだけのような、紐帯の弱い家族生活が営まれるだけなのである。イクの父親は10年のシベリア抑留から帰還した人で、突如感情を爆発させることがある(割れる、という表現が秀逸)他は自分の殻に閉じこもっており、母親もそんな夫を忌避する態度をとるだけではなく、娘に対しても愛情薄くしか接しない。父親は家族よりもむしろ、飼犬のほうに関心を示すのである。イクも自然と動物たちと向き合う時間が長くなり、自然と犬好きに育っていく。
巻頭の「ララミー牧場」で描かれるのは、家族の関係や、人間とペットとの間柄が今とはまったく異なっていた復興期の日本である。そこから現在へと向けて時代は移り変わっていき、イクは縁遠かった家族と郷里の滋賀を捨て、学生として東京に出てくる。東京では借り間住まいを送るのだが、家主や周囲の人々と彼女との関係が、彼らの飼犬を通じて描かれるのがおもしろい。犬には飼い主の人間性を反射するのである。間借り人のイクには「自分の犬」を持つということができず、犬好きであるのにその愛情は常に「他人の犬」に向けられる。「所有」に固執することからかけ離れた人物像は、昭和の末期に日本という国を変えた経済の狂奔のアンチテーゼとして描かれているようでもある。そこにイクというキャラクターの独自性があるのだ。自分を「持たない」、閉じた世界の住人である。
昭和の事物を多く参照し、脚注も豊富に入れられている。主人公の人生に時代を反映させ、かつそれを、犬と仲介させるという入り組んだ回路で行うという凝った小説である(「よい話」として無理に着地させていないのもいい)。ただ戦後史観にクレームをつけられたら、ちょっと危ない。心配だが、あえてここは★★★★。
■『とっぴんぱらりの風太郎』万城目学(4回目。文藝春秋)
エキレビ! インタビューで「現代の京都を舞台にした青春小説はもうやり尽くした」という理由から時間軸をずらしたことを明かしていたが、作者初の時代小説となる作品である。ただし、登場人物たちは過去の作品から大きくずれてはいない。主人公の風太郎は伊賀忍者だが、活躍の機会も与えられずに無為の日々を送っている。つまり現在で言うところのニートであって、伊賀を舞台とした導入部の後は、彼が京都でぶらぶらと暮らすさまがまず描かれる。ニート忍者にどんな契機で転機が訪れるのか、誰との出会いが彼の運命を変えていくのか、というように主人公と同じ高さの視線から物語は展望されていく。戦国末期に主人公を置いてはいるが、俯瞰しての叙述は一切行われないのである。
物語の重要なアイテムになるのは第2章で出てくるひょうたんである。道行の途中でひょうたんを預けられ、それを清水寺門前町にある瓢六という店に届けるように言いつかる。そこから慌しく事態が動き、風太郎の眼前の風景も変わっていく。その展開のさせ方は、伝奇小説の正統を受け継いだものである。小さくまとめるのではなく、風呂敷を広げられるだけ広げた上で結末へ向けて収束させていく。現代の作品というよりは中間小説誌全盛のころの大衆小説のような気配があり、物語の横幅も広い。直木三十五の名を冠した賞を授けるとすれば、もっともふさわしい作品は、今回は本書である。
物語の後半で風雲急を告げる転調の瞬間があり、そこから疾風怒濤のアクションが始まる演出は、これまた伝奇小説としては二重丸をつけられる展開だ。ラスト100ページは一気に読んでしまった。
本来ならば★★★★★でもいいところなのだが(勧進元の出版社の作品でもあるし)、心配なのはこの長さ。週刊誌連載2年分のページ数はやはり長い。優れた伝奇小説は長ければ長いほど楽しいものだ。しかしこれを余計なふくらみと取る選考委員もいるのではないか。また、自身も伝奇小説を手がける委員が「オレならこうする」と言い出したら厄介そうだ。よって★1つを減じて★★★★とする。当たれ、この予想!
■『恋歌』朝井まかて(初。講談社)
作者は2008年デビューで、これまでは主に人情ものの作品を手がけていた。少し毛色が違うのはシーボルト医師が登場する『先生のお庭番』で、史実に題材をとった作品である。『恋歌』は明治の歌塾・萩の舎を主催した中島歌子の生涯を描く歴史小説である。門下には作家に転じた樋口一葉などもおり、同じく門人で作家の三宅花圃(評論家・三宅雪嶺の妻でもある)が、臨終間近くなった歌子の手記を発見し、読み始めるという作りの冒頭になっている。手記小説の形式をとっているのである。よって、小説の大部分は「私」と名乗る歌子の一人称で進んでいく。
歌子の生家は水戸藩御用達の宿屋だった。そのために縁があって水戸藩士との交流があったが、その中の一人である林忠左衛門以徳を歌子は見初め、母親の反対を押し切って林家へと嫁いでいく。しかし当時の水戸藩は激動の中にあった。攘夷過激派の天狗党とそれに反対する諸生党の二派に藩中は二分され、内紛が続いていたのである。天狗党の中で人望も篤かった以徳も、否応なくその中に巻きこまれていく。夫婦の間にもやがて運命の日が訪れるのである。
天狗党の乱に題材を採り、非情な史実が描かれる。前半での歌子はおきゃんな町娘という印象だが、それゆえに後半の深刻な展開における悲劇性が際立つのだ。おだやかな人情話を期待して読むとびっくりする内容だが、後半部にはたまらないスリルがあり惹きつけられる。主人公である歌子と小説の水先案内人になる花圃はともに天真爛漫な性格として描かれるのだが、それぞれにライバルというべき女性が配されている。主義主張の論争に明け暮れる男たちと、それを不毛と感じながら平凡な幸せを願う歌子という対比も効果的だ。そうした具合で人物配置に隙がないのである。萩の舎の主宰者の小説らしく、要所に歌が置かれている点もそれらしくて良い。
プロット重視の小説読みとしては終章の展開を蛇足と感じたのだが、全体としてはページ数の過不足もなく、まとまりのよい佳作と評価したい。主人公に肩入れする選考委員が出るかどうかが受賞の鍵だろう。予想は★★★。
(杉江松恋)
第150回芥川賞へ