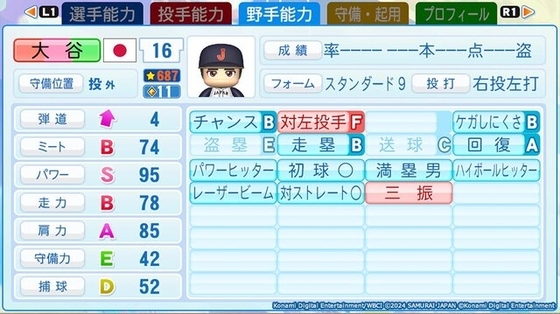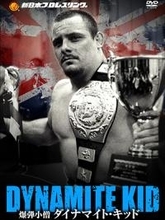東京都新宿駅西口。
火を放った男は住所不定の元建設作業員、丸山博文(当時38歳)。通行人によってその場で取り押さえられ、駆けつけた警官により現行犯逮捕された。
今日2月28日午後10時初回放送のNHKスペシャル「聞いてほしい 心の叫びを ~バス放火事件 被害者の34年~」は、この事件で全身80%の火傷をおい、生命の危機にさらされた女性、杉原美津子さんを中心に取材した番組である。
事件当時36歳だった杉原(旧姓、石井)さんは、約1年間の入院、10回以上の手術を経て、1983年に『生きてみたい、もう一度』という本を出版している。
その手記は、事件の翌年、杉原さんが拘置中の丸山に宛てた手紙から始まる。抜粋しよう。
「私は一度だって、あなたのことをうらんだりにくんだりしてきませんでした。
あなたをさばく気持も全くありません」
「会いたいです。会ってくれますか」と綴る杉原さん。
手紙を出したその二日後、彼女は東京拘置所へ向かった。
【丸山博文の犯行動機について――検察側と弁護側の主張】
新宿西口バス放火事件は、犯人と犠牲者らとの間に接点のない、いわゆる無差別の犯行である。個人的怨恨が動機ではない。
朝日新聞1980年9月7日朝刊の記事では、調査本部の調べに対し「幸福そうな通行人をアッと驚かせてやろうと思ってやった」と自供したとある。
また、検察の冒頭陳述による犯行動機は、以下のようにまとめることができる。
日雇労働者だった丸山は「惨めな境遇」を思い、「世間に対してねたみや恨みの感情」を抱いた。
つまり丸山は、高度経済成長の安定期にあった社会一般への逆恨み感情から犯行に及んだという主張になる。
第一審で検察側は死刑を求刑。これに対し、弁護側は無罪を主張。
弁護人は後に、オウム真理教事件、和歌山毒物カレー事件、光市母子殺害事件などで弁護をつとめる安田好弘である。当時弁護士一年目だった彼から見た丸山の姿は、著書『死刑弁護人』(文庫版2008年)に詳しく記述されている。
報道を見た安田は「もしかして、犯人ではないかもしれない」と思い、自ら丸山を訪ねて弁護をかってでた。だが弱々しく口にするのは「申し訳ないことをした」「死んでお詫びしたい」という反省や後悔ばかりであった。
丸山は息子を施設に預けたまま引き取りに行かない自分を責めていた。事件の核心にあるのは「貧困と福祉の問題」だ。そう安田は考えた。
しかし、法定でも彼は自分で弁明することはなかった。安田が「福祉」の問題を切り出しても、「もうやめてください」と拒絶したのである。
精神鑑定人の1人である福島章は、軽度の精神遅滞、妄想形成、軽度の単純酩酊を理由に、限定責任能力(心神耗弱)に相当すると判断した。(『現代の精神鑑定』1999年 ※本書では被鑑定人の更生や社会復帰の妨げにならないようにという配慮から仮名で表記されている)
もう1名の鑑定人も事実上、福島と同様の結論であった。
福島は後に「文藝春秋」2001年7月号のインタビュー記事内で、丸山の印象を「素朴な田舎の人という感じ」と表現している。
1984年4月。
東京地裁は、犯行当時の被告人に殺意があったことは認めたが、両鑑定を採用し、減刑した。
宣告を受けた丸山は傍聴席を振り返り、「ごめんなさい」と土下座したという。
検察側は控訴するも、東京高裁は一審判決を支持。刑が確定し、彼は千葉刑務所で服役することになった。
【杉原さんの手紙と面会――刑務所のなかでの丸山博文】
1981年、杉原さんは東京拘置所にいる丸山に会いにいった。
だが、刑務官は「彼は、今日は、逢いたくないと、言っています」とし、彼女は引き下がる。実際に丸山がそう言ったのかは不明である。
翌日、返信が届いた。そこには、ひらがなばかりの文字で、謝罪と後悔の言葉が連ねられていた。
その後も、杉原さんは何度か手紙を送り、公判にも足を運んでいる。
杉原さんの著書『炎のなかの絆』(1992年)の「あとがき」。91年に千葉刑務所での面会が特別に許可されたとある。そこで「元気な様子に、うれしい思いがした」と杉原さんは綴っているが、当の丸山は刑務所で何を思ったのだろうか。
1982年の「スパイ静粛事件」で殺人犯の一人として逮捕された見沢知廉は、著書『囚人狂時代』(1996年)のなかで、刑務所での丸山の様子を描いている。
千葉刑務所内に「八工」と呼ばれる工場がある。老人や心身障害者が集められるというその場所で、丸山もまた紙細工や模型をつくる作業を行っていたようだ。
八工には、見沢の共犯者であった男性がいた。彼によれば、という伝聞調で見沢は叙述する。
「丸山は皆から可愛がられていたという。普通、足りないやつはいじめられたりするのだが、丸山の場合、バカにされても爆発しない。無口なのでホラも吹かないし、人の悪口も言わない」
ただし、いきなり他人の頬を叩くという奇行が見られたとも書いている。また、普段は大人しく「ボーッとして」いたが、ときおり大声で叫ぶことがあったという。
「皆が寝静まった深夜、突然、悲鳴をあげて蒲団の上に立ちあがるのだ。
どんな夢に怯えたのか、それを丸山が言葉にしたことは一度もない」
1997年、10月。丸山は千葉刑務所内で死んだ。
昼食時に「メガネを仕事場に置き忘れた」と言って食堂から作業場に向かい、空気配管にビニール紐をかけて首を吊った。このことがおおやけになったのは、その約半年後のことであった。(毎日新聞1998年4月16日朝刊)
彼が自身について語る機会は、永遠になくなってしまった。
【作家・杉原美津子――「私」から発せられる言葉】
杉原美津子さんは、今日までに8冊の本を上梓した。現在、処女作『生きてみたい、もう一度』を含む多くの作品が絶版となっている。私は図書館を巡り、彼女の全作品に目を通した。
杉原さんが全身に火傷を負ったのには、もう一つの理由がある。
当時、杉原さんは、16歳年上で妻のある杉原荘六さんと不倫関係にあった。バスに火が放たれたとき、一瞬死ねると思ったことで、杉原さんは逃げ遅れたのだという。
生死の淵をさまよった後、奇跡的に一命を取り留めた杉原さん。彼女は荘六さんを激しく求めるが、彼は多額の借金を抱えていた。
苦悩の末、杉原さんと荘六さんは心中を試みる。しかし杉原さんは、以前取材に応じたことのあるNHK社会部記者に電話した。駆けつけた彼の説得により、二人の心中は未遂となる。
荘六さんの妻は事件の後に胃癌で他界。杉原さんと荘六さんは結婚し、夫婦となった。
彼女はその後、障害者施設、老人ホーム(マンション)への取材ルポや、福祉に関する本を書いてゆく。(『老いたる父と』1989年 『命、響きあうときへ』1995年 『他人同士で暮らす老後』1999年 『絆をもとめて』2006年)
また『夫・荘六の最期を支えて』(2009年)には、夫の看取りが描かれている。その年の7月。杉原さんは肝癌と診断された。治療の際の輸血で使われた非加熱製剤が原因であるという。その後の『ふたたび、生きて、愛して、考えたこと』(2010年)は、彼女の生涯の総集編とも言える内容のエッセイである。
丸山の自殺に関して、杉原さんは著書のなかで多くを語っていない。
『他人同士で暮らす老後』の終章で触れられている部分を引用する。
「『被害者』と呼ばれた私は人の温かさを力にして事件後を生きてきた。だが『加害者』であった彼は、自らの命を断って死んだ。生まれてきたとき、人は皆、『しあわせ』に生きていく権利と責任を平等に託されたはず。彼に伝えたかった。あなたも同じだったのだ。あなたは、なぜ、死んだ――と」
また、写真週刊誌「FOCUS」1998年7月22日号で、杉原さんは「生きて償う義務があったのに、自殺したと聞いたときは強い憤りを感じました」とコメントしている。
「被害者」から「加害者」への「赦し」ともとれる手紙。しかし、彼女は事件から解放されたわけではなかった。多くの後遺症、火傷の痕は現在も残り、精神的にも不安定だった。
父との葛藤。夫との愛憎、そして自殺が頭によぎったという罪の意識。杉原さんの不安を支えてきたものは何か。
「『私』とは、誰か――という、その原点に対峙し、自己確認していくために『書く』という、その行為であったと思う」
そう彼女は述懐している。
杉原さんの複雑な心境の全てを、私は理解したとはいえない。だが、彼女の作品を読むことを通じて、私は安易に想像していた「被害者像」にヒビを入れられた。
もちろん、事件の当事者は杉原さんだけではない。
事件に関する資料を探しまわっているとき、あるルポが目にとまった。「週刊大衆」1989年8月21・28日合併号。新宿西口バス放火事件で、顔や手にケロイドを刻んだ女性(当時20代)はこのように記者に答えている。
「肉体的にも精神的にも、一切がひっくり返ってしまう苦痛を丸山に味わわせてやりたい」
「被害者」という抽象的な言葉からは見えてこないものがある。
今夜放送のNHKスペシャル「聞いてほしい 心の叫びを ~バス放火事件 被害者の34年~」では、「被害者」ではなく「私」としての言葉に耳を傾けてみたい。
(HK 吉岡命・遠藤譲)