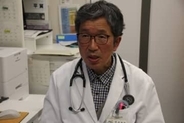メジャーレーベルからデビューすれば大会社からのサポートを受け、大々的にプッシュしてもらうことができるだろう。と同時にクリエイティブ面では大人から口出しされ、自身のやりたい事とイコールの形で作品を世に出すことは難しくなるかもしれない。
一方、インディーズはどうか? 「インディーズ(indies)」とは英語の「independent(自主の)」を語源とする言葉。その名の通り、ミュージシャン本人が運営するケースが少なくなく、意図したそのままの形で作品をリリースすることは難しくないはずだ。
誰もが「すぐに潰れる」と踏んでいた大仁田厚の新団体
90年代のプロレス界でも、実は「インディーズ」が業界を席巻している。
全日本プロレスと新日本プロレスの2大団体が業界を統治し、UWFが既存のプロレスにアンチテーゼを唱え、それ以上は付け入る隙が無いように見えた80年代末。1988年、元国際プロレスの剛竜馬によって「パイオニア戦志」という団体が旗揚げされるも、ファンからの支持を獲得するまでには至らなかった。
そして1989年、あの大仁田厚が新団体「FMW」を旗揚げしている。
その時の大仁田の全財産は5万円。そのお金で電話線を1本引き、事務所を開いた……という真偽不明のエピソードは半ば伝説化している。どうにも判官贔屓してしまいそうになるが、実のところ「すぐに潰れる」というのが大方の予想であった。
ライバル団体には天才・タイガーマスク
FMW以前の大仁田だが、中学卒業後の1973年に全日本プロレスへ入門している。同団体の“新弟子第1号”は、何を隠そう大仁田だ。
1981年には海外修行に旅立ち、テリー・ファンクの薫陶を受けてNWAインターナショナル世界ジュニアヘビー級王座を奪取。
……が、同時期にライバル団体・新日本プロレスで一大ブームを巻き起こしていたのは初代タイガーマスク(佐山聡)である。驚異的な身体能力を駆使した“四次元殺法”は魅力的で、ダイナマイト・キッドや小林邦昭といった強豪勢がひしめく新日ジュニア戦線と比較すると、どうしても大仁田の試合は見劣りした。
その後、試合後のアクシデントで左膝を粉砕骨折してしまった大仁田は、引退を賭けたマイティ井上戦に敗れ、1985年に(一度目の)引退を発表した。
プライドを傷つけられた冷たい一言がFMW旗揚げの遠因に
プロレス界を去った大仁田は事業に手を出し、または芸能界入りを狙ったり、精力的に多方面へのチャレンジを試みた。(後に政界入りする姿勢からも、この辺りの貪欲さが窺える)
しかし、結果は芳しくなかった。様々な失敗を経た数年後、大仁田は肉体労働に従事していたという。
「あの日は、雨が降っていたんですよ。ずっと穴を掘ってたんですけど、掘っても掘っても、何度掘ろうとしても穴に水が溜まっていって、その繰り返しなんです。その時、『俺の人生、どうなるのかな?』って思った」
大仁田はその後、ジャパン女子プロレスのコーチに就任。しかし女子プロレス団体にもかかわらず、なぜか元新日本プロレスのグラン浜田と遺恨が勃発。観客の罵声のなか男子選手同士(と言っても大仁田は引退中)のシングルマッチが組まれ、顰蹙の中で現役復帰を果たしてしまう。
その後、フィクサーである新間寿から渡された“挑戦状”を持参し新生UWFの会場へ入ろうとするも、UWF・神新二社長(当時)から「大仁田さん、チケット持ってますか?」と門前払いされる憂き目に。大仁田はのちに「この時に受けた仕打ちがハートに火をつけ、FMW旗揚げを決意するきっかけになった」と述懐している。
誰にも望まれず復帰した大仁田厚が「涙のカリスマ」となった
1989年、真樹日佐夫氏が主催する「格闘技の祭典」に出場した大仁田は、空手家の青柳政司と対戦。この日の試合はノーコンテストになったため、「青柳との決着の場を」という名目で、ついに自らFMWを旗揚げした。
事の経緯もあり、また当時はUWFがプロレス界を席巻していたため、FMWも「総合格闘技団体」を名乗っていたが、次第に団体は“デスマッチ路線”をひた走ることとなる。有刺鉄線グルグル巻きのロープに四方を囲まれた状況で空手家とタッグマッチを行なったり、リング下に敷かれたバラ線マットに放り出され血まみれになったり。
この方向性には、大仁田の「俺は強くない。
そんな大仁田に転機が訪れる。1990年8月4日に行われた「ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ」。四方にはロープ代わりに有刺鉄線が張り巡らされ、しかも電流が流されているという極限状態の中での一戦だ。
当日、会場には「何をやろうとしてるんだ?」と下世話な興味本位で駆けつけたファンも多く、ある種、見世物小屋的な雰囲気が場内を漂っていた。
果たして、試合が始まると会場全体が息を呑む。有刺鉄線に飛ばされ、選手が接触するや本当に飛び散る火花。「パーン!」「バチバチバチ!」という想像以上の爆発音は、鼓膜を通じて観客の体の芯に届いた。大仁田と対戦相手のターザン後藤による数度の爆発は観客の度肝を抜き、客席からは「わかったから、もうやめてくれ!」という声が飛ぶほど。
それまで、試合後に嗚咽する大仁田を“泣きの大仁田”と揶揄混じりに呼ぶ声は少なくなかった。しかしこの日から、大仁田には“涙のカリスマ”という呼び名が定着し始める。
このデスマッチは、1990年度「プロレス大賞年間最高試合賞」を受賞。同年はUWFの分裂騒動があり、また天龍源一郎が全日本プロレスを離脱し旗揚げしたSWSはファンからの支持を集めることができず、UとSの隙を突いた形で大仁田がプロレス大賞のMVPを受賞している。
1989年のMVPが前田日明で、1991年のMVPがジャンボ鶴田である。一度引退したインディー団体の選手がMVPを獲得することがどれほどの快挙であったか、理解していただけるだろうか?
もはや「インディーズ」ではない規模に
その後の大仁田は知名度を広く拡大させ、一般メディアへも頻繁に露出するように。テレビ番組や講演会にも数多く呼ばれ、若者からの圧倒的な支持を獲得した。
プロレス村内では相変わらず冴え渡る“プロレス頭”を駆使し、数々のデスマッチを考案。“デスマッチの教祖”の名を欲しいままにし、世界的にも「数々のデスマッチを発明した敏腕プロモーター」としてその名を馳せていく。
インディー精神を糧に地位をドンドン向上させていった大仁田。FMWの業績も好調。インディペンデントとは名ばかりで、ビジネス的には完全にメジャーの領域に分類されるほどのサクセスを手にしていた。
1994年には、大メジャーである天龍源一郎をデスマッチのリングへ上げることに成功。「ノーロープ有刺鉄線金網電流爆破デスマッチ」を川崎球場で行うも、この試合で敗北した大仁田は二度目の引退を発表。
1995年5月、愛弟子のハヤブサを相手に「ノーロープ有刺鉄線金網電流爆破時限爆弾デスマッチ」という形式で引退試合を決行。そして、再びプロレス界を後にした。
……が、1996年12月にニ度目の現役復帰。それからは数えきれないほどの引退→復帰を繰り返し、現在に至っている。もちろん、いまだ現役である。
(寺西ジャジューカ)