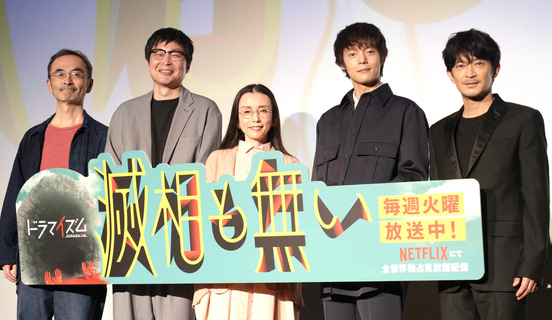工場跡地に埋まっていた22万缶
社員70名程度の小さな会社である木の屋石巻水産の名物は、サバの缶詰。ただし、そんじょそこらのサバ缶とはわけが違う。三陸・石巻漁港水揚げのブランドサバとして名高い脂ノリ抜群の金華サバを、刺し身でも食べられる鮮度のまま、手作業で詰められたサバ缶だ。
経堂で「さばのゆ」という居酒屋を経営している須田さんは、缶詰博士・黒川勇人氏の紹介で、木の屋のサバ缶と出会う。これが2010年のこと。90年代末からウェブサイト「経堂系ドットコム」を主催していた須田さんは、経堂の商店街でサバ缶を使った街おこしに取り組んでおり、サバ缶を使ったオリジナルメニューを出す個人商店が十数店舗に達していた。抜群の味を誇る木の屋のサバ缶と出会った須田さんが、さらに街おこしを進めていこうと思った矢先に発生したのが東日本大震災である。
経堂の人々は必要な物資と義援金を集めて届けるなどの支援活動をスタート。と同時に、津波で流されてしまった木の屋の缶詰工場跡地で拾い集められた、泥まみれの缶詰が経堂の街に持ち込まれるようになった。支援物資を運んだ車の空きスペースに、泥まみれの缶詰を積んで持ち帰るピストン輸送が始まったのだ。
ボランティアで集まった人たちの手によって、重油と腐った魚が混じったような臭いがたちのぼる手強い泥が洗い流されれば、ラベルのない金色に光り輝くサバ缶が現れる。中身はまったく問題なし。旨みたっぷりのサバがみっしり詰まったサバ缶だ。
毎週、大量のサバ缶が経堂に持ち込まれ、収益はそのまま木の屋の売上になった。その数、実に22万缶! 気の遠くなるような数だが、須田さんをはじめとするボランティアの人たちはわずか数ヶ月で掘り尽くし、売り尽くしてみせた。
現在、木の屋は新工場を再建し、復興への道を歩んでいる。また、木の屋の缶詰を使ってメニューを開発し、個人飲食店の売上をアップさせる「木の屋モデル」は全国に波及しつつある。
経堂という街の“長屋感”
本書を読み終えて印象に残ったことが2つある。1つは経堂の街の「長屋感」だ。石巻への支援物資は、須田さんが顔なじみの店に必要な物資のリストを持っていき、事情を話すとまたたく間に集まった。
また、缶詰は掘り出して洗うだだけではなく、売らなければいけない。週に1000缶もの缶詰の受け皿になったのは、経堂の商店街にある個人経営の飲食店だ。次々とサバ缶を買い、それまで以上に新メニューの開発に力を入れてくれた。サバ缶を使ったラーメンを提供していた店は、そのサバ缶ラーメンの売上を全額寄付にまわしてくれた。
震災以降、あっという間に助け合いモードになった商店街を、須田さんは「落語の長屋のような人情の街」と表現している。
長丁場の支援を行うことができたのは、経堂の街ぐるみで木の屋と交流を持っていたことが大きかった。それは街の長屋感あってのことだ。
本書に出てくるたくさんの「人の名前」
もう1つ印象的だったのは、とにかく人の名前がたくさん出てくることだ。
ほかにも、経堂在住の落語家の春風亭昇太さんや松尾貴史さん、西郷輝彦さん、四谷シモンさんらの著名人をはじめ、サバ缶メニューを開発した個人飲食店のオーナーたち、缶詰を洗ったボランティアの人たち、石巻まで支援物資を運んだ人たち、木の屋の復興支援に協力したクリエイターたち、経堂の支援活動を取材したメディアの人たちのほとんどの名前が、ちゃんと本の中に固有名詞として記されている。象徴的なのは本書の表紙だ。そこには経堂の街の人たちの顔がしっかりと写されている。
それだけ、須田さんは常に相手の顔が見える付き合いを大事にしてきたということだ。「街」とか「企業」などの大きな主語ではなく、大事なのはそこにいる「人」と彼らが営む「日常」。
しかし、東日本大震災では、多くの人の命が奪われ、彼らの日常が破壊され、そこにあったはずの人の輪も断ち切られてしまった。サバ缶を通した復興支援は、木の屋で働く人たちの日常を取り戻す復興支援だった。そして、人と人、街と企業のつながりは今後も続いていくことだろう。『蘇るサバ缶』という本は、その貴重なモデルケースでもあるのだ。
(大山くまお)