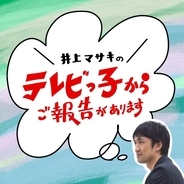まず大前提として、ニホンウナギはとっくに絶滅危惧種である。2014年に国際自然保護連合(IUCN)から「絶滅する危険性が高い絶滅危惧種」のレッドリストに指定されているし、さらに2019年に開催されるワシントン条約の締約国会議ではニホンウナギを含む全19種のウナギすべてが国際取引の規制対象になる可能性もある。
そんな危機的状況の中「ウナギの代わりになる魚はないか?」と「ウナギ味のナマズ」の開発に着手したのは、近畿大学・有路昌彦教授。近畿大学はクロマグロの完全養殖を成功させ、かの「近大マグロ」を世に送り出したことでも有名な大学で、市場に即した研究をしている印象が強い。

1年前に刊行された『なぜ「近大発のナマズ」はウナギより美味いのか?』(2017年7月19日発売)は「ウナギ味のナマズ」開発の舞台裏はもちろん、ウナギとナマズ、双方の生態や食の歴史を紹介するのと同時に、我々が囚われがちな食の常識についても疑問を投げかける。
肝心の「ウナギ味のナマズ」開発についてもっと読みたかった感はあるものの、学術書のような小難しさもなく、ウナギ問題の入門書としても読みやすい。本書の内容からいくつか紹介したい。
コウノトリやパンダを食べているような状態
人間の手でウナギの卵を孵化させることは難しく、ここ数年人口孵化成功の報告は増えているものの、コスト的な面など採算の取れる実用化レベルにはまだ到達していない。
なので、親ウナギが延々海を南下しグアム島付近で産卵、そこで孵化した稚魚が台湾方面に泳ぎ着き、さらに黒潮に乗って日本沿岸に上がってくるのを捕まえ、大きく育てる。これが現状の日本でのウナギの「養殖」だ。
この「養殖」は、人工的に産卵や孵化させられないという点において完全な養殖とは言えず、天然資源に依る部分がとても大きい。そして、我々が口にする9割以上はこの「養殖」ウナギだ。
つまり「養殖」で成長させてから食べているとは言っても、結局我々は絶滅危惧種の「天然」ニホンウナギの稚魚を採って食べてしまっていることに変わりない。
筆者の山下柚美は、「ウナギの蒲焼を食べる行為は『コウノトリを食べる』とか『パンダを食べる』といった出来事と同じ次元になりつつある」と表現しているが、本書の発売から1年経ってさらにリアリティを増している。
そこで登場するのが「ウナギ味のナマズ」だ。
ナマズの臭いの原因は?
ウナギに変わる蒲焼の材料を探すため有路教授は、ドジョウやコイやブラックバスまでも20種以上の魚を片っ端から蒲焼にし食べたという。その結果ナマズが、焼いた時の皮の香りや脂質など含め最もうなぎの蒲焼に近づけそうだと確信する。
が、どうにも臭い。
だが有路教授は井戸水のような綺麗な水で育ったナマズは泥臭くないことを突き止める。
当初は脂質も少なくその旨味も弱かったが、配合餌を成長に合わせて変化させ与えることでウナギの脂の旨味に近づけた。
こうして完成した「ウナギ味のナマズ」は発売初年度(2016)に結果的に準備できた3000匹を大きく上回る8000匹の注文が。話題先行で発注に追いつけなかったのは痛い誤算だが、潜在需要はもっとありそうだ。


ナマズを食べないのは日本くらい
そもそもナマズ種は日本以外の国では非常に多く食べられているポピュラーな食材で、世界の内水面(海以外の場所)での養殖量はコイ、ティラピアに次いで堂々の3位。
アメリカではチャネルキャットフィッシュ(最近テレビでもよく見かける霞ヶ浦水系で増えてしまっている外来種のアメリカナマズ。
ではなぜ世界でも指折りの魚食いの日本人が(一部地域では食べるものの)ナマズ種を食べる習慣がないのか?
本書によると、かつてはがっつり食べられていたようだ。
そもそも西日本に生息していたナマズ(おそらくマナマズ)が、江戸時代までに現在の千葉県・手賀沼に移植され、その後水害の際に逃げ出し、江戸のあちこちに広まった。当時食べられていたうな丼よりもナマズ丼の方が4割ほど安かったというが、ある出来事からナマズの値段はウナギの6倍にも跳ねあがる。
それは1855年の安政の大地震。マグニチュード6・9の揺れは火災を招き数千人の死者を出した。
ではこれほど広まったナマズ食がなぜほとんど廃れてしまったのか?
それは戦後の高度成長期の河川や湖沼の汚染などで、水質の影響を受けやすいナマズに「臭い」というイメージがついてしまったから。
汚染に強い魚ほど汚染環境下でヘタに適応し生き残ってしまい(現在、都心のドブ川のような河川にも意外とマナマズは生息してる)、その個体を食べた人から「不味い」「臭い」という不名誉な印象が広まった。
綺麗な海で育ったものは臭みもなく好んで食べられているのに、港湾部(特に東京湾)の運河などでヘドロごと餌を吸い込み、たくましくも生き残ってしまった結果「臭い」と嫌われてしまってるボラと同じパターンだ。
だが前述のパンガシウスなどは最近日本に輸入され、スーパーでも「クセのない白身魚」として受け入れられつつあるし、昨年からはこのパンガシウスも蒲焼にされ、「近大ナマズ」のライバルとして売られており、今後はナマズ種も日本で食材として認知されていくだろう。

とはいえやはり、食感(ややしっかりしてる)や脂の薄さを嫌う人もいるだろう。あくまでウナギに寄せるのか、それとも独自の到達点を目指すのか、今後に期待したい。

世界のうなぎの7割を消費する日本
もともとうなぎ(蒲焼)はハレの日に食べる料理で、少なくともコンビニ・スーパーや低価格外食チェーンなどで気軽に食べれるものではなかった。それを可能にして「しまった」のは、バブル期に外国種を海外で養殖したり加工品として輸入してきたからだが、それによりヨーロッパウナギは絶滅危惧種となり2009年に輸入が規制(条件付き)された。その後需要は東アジアに生息するニホンウナギに集中する。
昨年、共同通信の集計(6月14日)では国内外で採られた二ホンウナギの稚魚のうち、なんと45パーセント以上が違法採取の疑いがあると報道された。
輸出が禁止されている台湾から香港へ稚魚(ニホンウナギ)が密輸された事件(2016)なども「うなぎ」界隈の闇の一端だ。稚魚のままにしろ成長して蒲焼に加工してからにしろ、それは日本人の胃袋目指してやってくる。
ここ数年で値段は上がったものの、それでもそこそこ「手頃な」値段で売られているウナギは、密輸や違法採取など非合法ルートのものが含まれている可能性が否定できない。
この現状を踏まえて山下は、「ウナギを『ハレの日のご馳走』に戻そう」という、ウナギ研究の第一人者・塚本勝巳の提案を紹介している。
「ウナギはこうした大量消費に耐えられるような野生動物ではありません。日本人のウナギ狂いは異常とも言えます。安いウナギを大量に飽食するのではなく、少し高いお金を払ってでも、(専門店で)極上のウナギを特別の日にしみじみと味わう、そんなかつてのウナギ食文化のスタイルに戻ってはいかかでしょうか」(『うな丼の未来』青土社)
あわせて「土用丑の日」のウナギ食自体をやめようという提案も紹介。同じ時期に一斉に大人数が食べることで過剰な稚魚の高騰を招き、それが乱獲を煽っている現状を踏まえての提案だが、最近では丑の日にあえて休業を宣言する意識的なうなぎ店も現れるなど風向きは変わりつつある。
万葉集の頃から夏バテ対策にうなぎは食べられていたようだが、土用丑の日にウナギを食べるという「イベント」は江戸時代に平賀源内が知人のうなぎ屋を助けるために打ち出したビジネス上の「戦略」。言い出しっぺの平賀源内もウナギの現状を知ったらとっくに方向転換しているのではないだろうか?
ここ数年はナマズの他、サーモンやサバなど脂の強い魚や豚肉などを蒲焼に見立て売り出すのも見慣れてきた。やはりウナギには敵わないとの声も多いが、だからと言ってウナギを絶滅させてしまっては元も子もない。
「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されてから早5年。各国から多くの人が訪れる2020年の夏、日本のウナギ食はどうなっているのだろうか。
(柿田太郎)