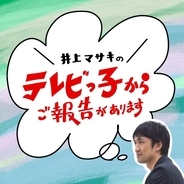いよいよ今夜が最終回。先週放送された第8話では、ついに広島に原爆が投下。玉音放送によって日本の敗戦が告げられた。

原爆投下、そして……
広島の江波から呉の北條家に嫁いできたすず(松本穂香)は、いつも自分の居場所を探していた。自分で選んだわけでもない夫と、自分で選んだわけでもない家。だけど、北條家の人々も近所の人たちもすずを優しく受け入れてくれた。
しかし、戦争は激しくなる一方。
「あんた、広島から飛んできたんかね。うちもじゃ」
「うちは強うなりたいよ。優しうなりたいよ。
「この町の人」は強くて優しい。径子(尾野真千子)は娘を失っても「すずの居場所はここじゃ」と言ってくれた。義母のサン(伊藤蘭)もいつも優しい。なにより、親友の幸子(伊藤沙莉)と志野(土村芳)がいつもすずを受け止めてくれる。夫の周作(松坂桃李)はちょっと影が薄い。
同時に、すずは米軍に対する憎悪を募らせていた。
「ああ、うるさいねえ! うちは負けんよ!」
「冗談じゃない。なにが降参じゃ、馬鹿にしくさって!」
すずは米軍の爆撃機の音や伝単(ビラ)に対して強い怒りを表す。彼女はこれまで戦時下にあって、まったく敵(米軍)のことを意識していなかった。竹槍訓練のときも、空襲に遭ったときも、米軍に怒りを感じることなど一度もなかった。晴美を失ったときでさえ、自責の念にかられるばかりだった。
しかし、原爆を落とされ、故郷の家族の生死が不明となった今、すずの内面には米軍に対する敵意が明確に湧いてきたと考えられる(もちろん、晴美のことも関係しているだろう)。
戦争に負けても生活は続く
そして昭和20年8月15日。玉音放送を聞くため、北條家に近所の人々が集まってきた。ラジオの前に並んで座っているのは全員女性。ドラマオリジナルキャラクターの幸子と志野が加わったことで、さらに女性感が増している。女たちのドラマを紡いできたこの作品らしい光景だ。唯一の男性、堂本のじいちゃん(塩見三省)は一人で庭に立っていた。
神妙な顔をしているけど、ノイズ混じりの玉音放送にムズムズしてくる一同。
しかし、そんな中、すずが立ち上がって激昂する。
「戦えるじゃろ、まだ! 今じゃって、ここにこんなけおるのに! こんなに生きてるのに! まだ左手も、両足も残っとるのに! 戦えるじゃろ、まだ!」
このくだりは劇場アニメが公開された折も話題になった。徹底抗戦を主張したすずを「愛国婦人」と賞賛する人々もいたが、くだらないとしか言いようがない。
「うちは、うちは納得できん! うちはこんなん納得できん! 絶対できん!」
このセリフは原作どおりだが、ドラマでのすずはセリフの前に晴美の遺骨に視線を送っている。すずが吐き出しているのは、人の命を軽々しく扱う戦争そのものと、その戦争を勝手に起こし、勝手にやめた日本という国へのやるかたのない怒りだ。
原作ではすずが日本の「聖戦」の正体に気づく様子が印象的に描かれている。怒りにまかせて水汲みに飛び出したすずの「この国から正義が飛び去っていく」というモノローグの後、太極旗が写って「暴力で従えとったいう事か」と呟く。そして「じゃけえ暴力に屈するいう事かね」と涙した後、「それがこの国の正体かね」と言い、「うちも知らんまま死にたかったなあ……」と慟哭する。強烈なメッセージである。
ドラマではこのくだりはすべてカットされていた(劇場アニメでも一部のセリフが改変されていた)。カットされて浮かび上がるのは、残された人々の哀しみである。
水汲みに飛び出したすずの脳裏に浮かぶのは、戦争によって失われたものたちだ。戦死した兄の要一(大内田悠平)、死地に向かった水原哲(村上虹郎)、あどけない表情の晴美、そして自分の右手。
すずは「納得できません」と呟き、地面に突っ伏して慟哭する。ふわっと手が現れてすずの頭を撫でるのは原作どおり。その後、周作が現れるのはドラマオリジナルの展開だ。泣いているすずに、自分も泣きそうになりながら周作が言う。
「すずさん……腹減ったわ」
腹が減るというのは生活のこと。戦争に負けても生活は続く。人は居場所があれば生きていける。生活の舞台であり、居場所となるのが家族。家族の最小単位が夫婦である。原作にあった強烈なメッセージはなくなったが、その分、「戦時下のホームドラマ」としての側面が強く打ち出されていた。
刈谷家の物語
刈谷家の世話焼き、タキさん(木野花)が近所の人たちを集める。幸子の婚約者・成瀬(篠原篤)もやってきた。タキが語り始めたのは、広島に新型爆弾が落ちてすぐの頃、近所に兵隊の行き倒れがいたことだった。行き倒れは顔も服も溶けていて身元がわからないまま処理されていた。
その兵隊とは、タキの息子だった。必死になって広島から呉の家に帰ってきたが、家族は誰も気づくことができなかった。
「うち、気づいてやれんかったんや……。母親なのに、うち……。あの子は、どんな思いで呉まで……。うち、うち……」
タキの言葉を聞いた成瀬は、幸子との祝言の話を撤回する。幸子に嫁いでもらうのではなく、自分が呉にやってくるというのだ。
「わしには兄がおりますけ。じゃけ、わしがこちらに来ます。息子になりますけ。幸子さんも出ていかんでもすみますけ。じゃけ、幸子さんと一緒におれりゃ、わしゃどこでもえんです。じゃけ、さびしゅうないですけ」
原作ではタキの告白は非常にさらりと描かれていた。成瀬のくだりはドラマオリジナルのもの。刈谷家の悲しみに寄り添い、新たに家族の一員になろうとする成瀬の優しさがしみる。
食卓にはタキが用意した心づくしのおはぎが並んでいた。これを食べて息子を弔ってもらいたかったのだろう。時代考証の山田順子氏は「もち米や小豆はタキさんが全財産をはたいて闇市で買ってきたか、あるいは何かあった時のために大事にとってあったものを大供出したんでしょう」と説明している(公式サイトより)。
『この世界の片隅に』と西日本豪雨
出張に出かける周作を見送ったすずは、周作からリン(二階堂ふみ)のいた遊郭の場所を教えられる。すずはリンの消息をたしかめようとするが、そこには無残な廃墟とりんどうの茶碗のかけらが残されていただけだった。
一人で抱えた秘密は、その人が死んでしまえば消えてしまう。それをリンは「それはそれでゼイタクな事」と表現していた。しかし、すずはリンのことを周作と共有した。これからもリンについての記憶は消えず、2人の間で残ることになる。ドラマ版では重要人物として描かれていたリンだったが、ちょっとあっさりした終わり方だったような気がする。
平成30年8月。北條家の場所にやってくる佳代(榮倉奈々)、浩輔(古舘佑太郎)、節子(香川京子)。坂道のあちこちには土のうが積み上げられている。家を見て驚く佳代と節子。浩輔は佳代に内緒で、北條家の片付けを行っていた。
「ちょっと片付けてたら、近所の人、みんな手伝ってくれて。みんな、それどころじゃないのに」
はっきりとは明言していないが、浩輔の「それどころじゃない」という言葉は、今年7月に広島県を中心に甚大な被害をもたらした西日本豪雨(平成30年7月豪雨)のことを指している。ドラマの舞台となった呉市だけでも土砂崩れなどで24人の方が亡くなった。それほどの災害があっても、人々は助け合って生きていく。そうすることによって、その土地がその人の居場所になる。
「好きな人の好きな場所は好き。それでいいですよね」
初めて現代編の意義を感じたエピソードだった。本日放送の第9話はエピローグとなる最終回。すずと節子の出会いも描かれるはず。今夜9時から。
(大山くまお)
「この世界の片隅に」
(TBS系列)
原作:こうの史代(双葉社刊)
脚本:岡田惠和
演出:土井裕泰、吉田健
音楽:久石譲
プロデューサー:佐野亜裕美
製作著作:TBS