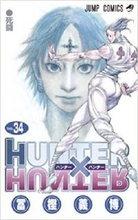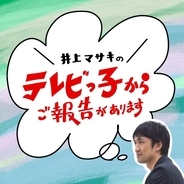木村友祐『幼な子の聖戦』(「すばる」11月号)
高尾長良『音に聞く』(「文學界」9月号)
千葉雅也『デッドライン』(「新潮」9月号)
乗代雄介『最高の任務』(「群像」12月号)
古川真人『背高泡立草』(「すばる」10月号)
それぞれの作品について簡単にレビューするので、結果発表を待つ間の暇つぶしにでもお読みいただだきたい。最後に簡単な私自身の予想を書いておくので、当たったらお慰み、である。

木村友祐『幼な子の聖戦』
初候補の作家が三人いるが、木村はその一人だ。『幼な子の聖戦』は、青森らしき東北の村で行われる村長選挙を巡る顛末を描いた作品である。全篇で作者自身の故郷である青森県の方言が駆使されており、それが特徴にもなっている。
視点人物の〈おれ〉は東京に出たものの失意を抱えて帰郷することになり、村議になったという人物だ。特に崇高な目的があったわけではなく、ぶらぶらしていると外聞が悪いからという理由で、父親の伝手によって補欠選挙に押し込まれたのである。
安部公房『飢餓同盟』などの系譜上にある作品で、選挙を通じて地方の空洞化や男性優位主義がはびこる精神土壌などが浮き彫りにされる。諷刺小説の常として人間関係などが図式的にならざるをえないのだが、追い詰められて極端な思考へと向かっていく〈おれ〉はヘイト・クライムに走る現代人の心性を凝縮したようで、その点に読みごたえがある。
なお、単行本版『幼な子の聖戦』にはビルの窓拭きを題材にした「天空の絵描きたち」が併録されるという。前回の芥川賞選考で候補作となった古市憲寿の『百の夜は跳ねて』が同作を下敷きにしていると一部の選考委員から指摘があり、酷評される結果になった。木村は、古市が自分の体験したビル清掃を取材してくれたのであって盗用ではないと火消しに回ったのだが。その因縁のある作者が今回の候補に挙がったことは興味深い。

高尾長良『音に聞く』
高尾にとっては3回目の候補作となる本作では、物語の舞台がオーストリアの首都ウィーンに設定されている。その地で音楽理論の大家として日本人ながらも地位を築いている喜多を訪ねて、娘の有智子と真名がやってくる。日本に残っていた母親が亡くなったためだ。
翻訳家である有智子の中にはもともと母語である日本語への失望があった。また、母音に束縛される日本語にはない魅力が多彩な子音を持つドイツ語にはあるという憧れも抱いている。一方真名は同じ音楽家の上位者として振る舞う父に対する嫌悪感を隠さず、性的虐待の可能性さえ示唆して彼を忌避しようとする。
小説の中心には喜多の「言葉とは底に穴の開いた器に等しい、不完全で出来の悪い玩具に過ぎない」という指摘がある。それでも人間は、論理を示すためには言葉を用いずにはいられない。しかし情感を表現するために音楽というものがある。音楽と言葉は必ずしも対立するわけではないのだが、音楽表現を鏡にすることによって言語表現の特徴がより際立ってくるのである。その関係を錬磨するために、人物配置を含めた本作の要素はすべて計画的に配置されている。
過去二回の候補作に比べ、中心軸が据えられたために主題は明確になった。何を書くかではなく何を試すかが求められる芥川賞には、今回いちばん「らしい」小説ではないか。

千葉雅也『デッドライン』
作者には哲学者として多数の著書があるが、これが初の小説作品である。物語内の時計の針は2001年に設定されている。名前を記す必要があるときには〇〇と書かれる語り手の〈僕〉が2001年に学部を卒業して院に進むところから小説は始まっている。作者は1978年生まれだから主人公像は自分自身の投影として読まれることを意識しているはずだ。〈僕〉はゲイで、しばしば新宿二丁目のハッテン場にも足を運ぶが、特定の恋人は作っていない。
もう一人、同期に知子という女性がいて、〈僕〉の語りにはしばしば彼女の視点が混入してくる。〈僕〉の指導教授が『荘子』を引いて自己/他者の二項対立は絶対かということを学生たちに疑問視させる場面があるので、作者が何かを意図しているのだということは判るが、前半部だけではその狙いはわからない。中盤で〈僕〉はジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリ『千のプラトー』を読み始め、マジョリティである男性という立場から離れるということについて考えるようになる。選択肢としては二つ、「動物」として他者に寄り添うか、もしくは「女性への生成変化」を経て男性の支配から逃れるか。〈僕〉がゲイであることについてのエピソードが主題と同等の重みづけで書かれてきたことの意味は、ここにおいてようやく判明する。
〈僕〉のこの思弁にすべてが回収されていく小説であり、ドゥルーズという主題をここまで真摯に取り扱ったこと自体を評価すべきである。誰とも固定された関係を築けず、実家の援助によって浮遊するように生きている主人公の姿は同世代人の丁寧なスケッチにもなっている。それまで絶対的だった男性中心主義の正統性に疑義が呈示され、新たな可能性の前で戸惑う2000年代の心性が的確に描かれているように思う。

乗代雄介『最高の任務』
これも初候補となった作品で、主人公たちが活動する主舞台が館林などの両毛線やわたらせ渓谷鐡道沿線に設定されている北関東小説であるのが個人的にはツボだった。語り手である大学生の女性、阿左美美景子こと〈私〉と両親、弟の洋一郎、そして最も重要な登場人物であるゆき江叔母が北関東をうろうろする話である。
あらすじについてはそれより説明しないほうがいいと思う。実は候補作中では最も展開がおもしろく、最後にそういうところに落ち着くのかという幕引きの驚きもある作品なのだが、もっと書いておくべきことがあるからだ。
小説の構造はとても凝っていて「最高の任務」という題名にもすでに仕掛けがある。〈私〉は小学校五年生のときにゆき江から日記帳を貰う。「お願いだからくれぐれも私に読まれないようにね」という叔母の言葉から、絶対に読むつもりだと判断した〈私〉ははりきって日記を書き始める。日記文学の、架空の「あなた」に対して語り掛けるという文体が彼女には面映ゆく、必ず「あんた、誰?」という書き出しで日記をつけるようになる。それが偶然に見たジョン・ランディス監督「スパイ・ライク・アス」のテーマソング歌詞と重なり合うのである。『最高の任務』という題名は、直接的にはスパイの負うもののことを指しているのだが、さらに〈私〉は「あんた、誰?」という自分に突き付けられた問いに答えることなのだと了解するようになる。この小説の中では日記と回想を通じて、自分に多大な影響を与えた叔母がとった奇妙な行動について主人公が考え続けることになるのだが、それが最終的には「あんた、誰?」という問いへと集約されるのである。拠って立つ地面が実は自分自身には見えておらず、何かを経由して客観的に眺めたときに初めて豊穣な地盤が見えてくる。その迂遠な回り道について書かれた小説なのだ。

古川真介『背高泡立草』
作者にとっては四回目の候補作となる。今回では最多だ。過去の候補作と同様、九州北部のある島を舞台として、一族のサーガが綴られていくという内容の作品である。その島には吉川一族の〈古か家〉と〈新しい方の家〉があり、また放置された納屋がある。納屋の周りに草が伸び放題になっているため、吉川家の生存者が島に勢ぞろいして刈ることになる、というのが本篇の主筋だ。前作『ラッコの家』では視点人物として目の弱くなった老婆を採用し、一族の者たちの語る声だけが空間に響き合うという趣向が試されていたが、読みづらいという声もあったように思う。
今回はその反省点からか、視点人物には若い世代の奈美を採用している。同世代の人として従姉妹の知香、二人の親である美穂子と加代子、彼女たちの兄である哲雄というのが草刈りのために集まった面々で、さらに島の住民として、奈美の祖父の妹にあたる九十歳の敬子婆。これで主要登場人物はすべてであるが、要所要所に建物や物が呼び起こす土地の記憶内の登場人物として、島を捨てて満州に渡る夫婦やカヌーで島にやってくる中学生といったひとびとも姿を現す。時間を超越して小説を立体的に構築したいというのは、第156回の候補作である『縫わんばならん』以来ずっとこの作者に感じている欲求で、今回は短い挿話を挟みこむことでそれを満足させているように見える。
若い奈美が母親の美穂に対して、なぜ人の住んでいない納屋の草刈りをしなければならないのか、と再三再四疑義を呈するのがこの小説の肝で、有限な個人の人生と、連綿と続いていく一族の時間の流れとが納屋によって対比されているのである。問答形式を導入したことによって、この主題もわかりやすく可視化された。背高泡立草は何度刈り取っても延びてくる雑草の代表格で、ライト・モチーフとして終盤に描かれる。
趣向はばらばらだが候補作にふさわしいものが並んだ
複数候補組では『音に聞く』と『背高泡立草』が前回までに選考委員が指摘した「宿題」をこなしてきていて、その点が評価されるように思う。特に『音に聞く』は小説についての永遠の命題といっていい、言語によって世界を表現すること自体について書かれた作品だ。初候補組の『最高の任務』が、表現者の中にある過去世界を題材にしたものであって、二作には共通点がある。『音に聞く』は文体実験の成果でもあるので、その分さらに加点もあるのではないか。『幼な子の聖戦』は現代人の心性を皮肉に描いた諷刺小説で、新しさという点では留保条件がつくが、熱気を帯びた語りがいい。逆に『デッドライン』は現代思想という導線を用いることで冷静に現代を俯瞰することに成功した作品である。さて授賞ということになると、どちらもやや図式的すぎるのではないか、という印象が私にはある。
個人的にいちばん好きだったのは『最高の任務』なのだが、加点要素の多い『音に聞く』を今回の本命◎とし、『最高の任務』は対抗〇どまりとする。大穴▲は『幼な子の聖戦』で、前回の選考事情もあって木村に同情票が集まりそうな気もする、とこれは下世話な見方なのだが。
さて、どうなりますことか。
(杉江松恋)
直木賞予想