2022年の不動産・住宅市況の展望について、中古住宅と賃貸住宅の市場はそれぞれどうなっていく可能性があるのか、考えてみます。
昨年末の税制改正大綱で概要が公表された通り、住宅ローン減税の控除率が従来の1%から0.7%に縮小されることに決まりました。
この制度が適用されるのは2022年4月からです。
住宅ローン控除を受けることが目的で、中古住宅を購入されるユーザーはいません。でも、購入動機の上位に挙げられるのが、住宅ローン金利が歴史的低水準であることと並んで、住宅ローン減税による恩恵です。
そのため、制度自体は維持・継続されたとはいえ、やはり「お得感」が薄れるのは否めず、その点では4月以降、中古住宅に対する需要の減退につながる可能性は十分考えられます。
住宅ローン減税控除率0.7%縮小...中古住宅市場への影響は?まず、中古住宅市場の展望について、述べたいと思います。
コロナ禍に日本が突入してからの約2年間、一時期を除けば中古住宅に対する需要はおおむね堅調、もしくは好調だったといえます。
その主な要因は、
(1)新築住宅がコスト高による価格高騰、および、供給の絞り込みで条件に合う物件が見つかりにくくなり、ユーザーが中古住宅も積極的に探し始めたこと、
(2)株価の安定推移によって利益を得た投資家が、現物資産である不動産にその資金を付け替え始めたこと、
が挙げられます。
つまり、都心や市街地中心部およびその周辺部に立地している条件の良い中古住宅は、実需と投資という二段重ねのニーズの受け皿となったのです。
日経平均株価は2022年に入っても大きな変化は示しておらず、おおむね安定した推移といえますが(4月の東証市場再編がどのような影響を与えるかは未知数です)、社会不安や日本に限らず世界で日々発生する事象によって大きく変動する可能性が常にあります。そのため、株式投資によって得た収益の付け替えを急ぐ投資家は、少なくありません。
その意味では、現物資産として、比較的早く取得可能な中古住宅に2022年もニーズが向くことは想定内といえるでしょう。
それでも投資と実需ではそのパイは大きく異なるため、住宅ローン減税の縮小の反動は、今後徐々に表れると見るべきです。
また、前回のコラムでも示した通り、中古住宅を購入して住宅ローン減税を受けるには(もちろん、投資目的の購入は減税対象となりませんが)、新築住宅よりもさまざまな制限が設けられていることも、需要減退の一因となる可能性があります。
中古住宅の価格高騰は、まだまだ続くのか?一方、価格面についてはどうでしょうか。
結論から述べると、私は中古住宅の価格(とくに、需要の旺盛な都市圏中心部および近郊エリア)は、住宅ローン減税が縮小されても下がらない。もしくは、上昇率が若干縮小するものの、引き続き安定的な価格上昇が起きる、と考えています。
その主な理由は、新築住宅の「価格推移」の見込みです。
これもまた、住宅ローン減税の話になりますが、新築住宅は2022年4月以降、中古住宅同様に控除率が0.7%に縮小されるものの、減税期間は13年に据え置かれます。
さらに、2022年度からは、長期優良住宅などの認定住宅は、ローン元本の上限が5000万円であることにくわえ、エネルギー効率の高いZEH(ゼッチ=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅は上限4500万円、省エネ基準適合住宅も上限4000万円とされています(これらが新設されたのは2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けた施策です)。
この条件に沿って、減税総額を単純計算すると、それぞれ最大で認定住宅は455万円、ZEH住宅は409.5万円、省エネ基準適合住宅は364万円となります。
つまり、新築住宅に関するローン減税の総額は、事実上大きく変わっていないのです。依然として、まとまった金額のローン控除という恩恵を受けることができるのです。
そのため、控除率が0.7%に縮小されただけでは、コスト高や住宅ローン金利が低水準であることも含めて価格が下がることはほぼイメージできません。
したがって、価格の高騰によって、新築住宅の購入をあきらめたユーザーが中古住宅を検討することになっても、(もちろん個々の条件次第ではありますが)価格が現状よりも弱含むという状況なることはほぼないといえます。
地域差はあるものの、テレワークの普及・定着によって、ニューノーマルといわれる新しい生活様式が選択されるケースが増えました。それに応じて、ユーザーの住まい、および、住まい方に関する考えの変化も生まれました。
そして、住宅を買い替えること、また、住み替えてコロナ後にも対応できる生活をイメージすることに関心が集まっています。
こういった傾向があることも背景として、2022年も中古住宅に対する需要は高い水準で続くものと考えておくべきでしょう。
賃貸マンションへの投資家の姿勢は、コロナ禍でも一貫して積極的次に、賃貸住宅市場についてはどうでしょうか。
2021年2月にLIFULL HOME'Sが公表した「借りて住みたい街ランキング」では、とくに首都圏で「ユーザー意向の郊外化」が発生しました。
それまで4年連続1位だった「池袋」が5位に転落し、代わって1位になったのは神奈川県央部に位置する「本厚木」でした。
また「本厚木」だけでなく、多くの首都圏郊外に位置する駅名が上位に登場しました。これまで人気の高かった都心やその周辺エリアの駅は、ランキングを大きく下げました。
実際に郊外方面に住み替えたユーザーは、このランキングの変化ほど多くない――ということが、その後の調査で明らかになっています。
しかし、テレワークやオンライン授業の普及および定着によって、毎日通勤・通学しなくてもいい環境に、徐々に馴染んできたユーザーは多いのではないでしょうか。
居住コストが軽減できるメリットと通勤・通学する時間的な負荷をトレード・オフの関係と考えれば、今後のコロナ次第で、需要が郊外化する可能性はある、と考えておくべきでしょう。
また、この「ユーザー意向の郊外化」はもっぱら首都圏のみで、近畿圏、中部圏、また地方4市といわれる札幌市、仙台市、広島市、福岡市などの大規模な事業集積地ではほぼ発生していません。コロナ前と同様に、市街地中心部への一極集中が継続しています。
これはテレワークの定着度合いの違いだけでなく、圏域の広さの違い、また、市街地中心部と郊外での賃料コストの格差の違いなどにも起因しています。
したがって、コロナ禍に見舞われた2021年も、コロナ慣れも手伝ってか、賃貸ユーザーの利便性や人気のある街であることを考慮したエリア選択には、(首都圏を除いて)大きな変化はなかった、と見ることができます。
この状況に対して、賃貸住宅運営に前向きな国内外の機関投資家は、安定したキャッシュフローを前提として、コロナ禍においても賃貸マンションの売買を活発化させています。2020年度の投資総額は、前年度から約40%増加して9000億円超に達しています。
つまり、需要堅調と判断した機関投資家が、安定的な賃貸マーケットに資金を投入しているということが明らかです。
とくに2021年は、賃貸マンションのバルク購入(まとめ買い)が相次いで発生しました。中長期のポートフォリオを組成したうえで、賃貸マンション数棟から20棟程度をまとめて購入するケースが目立ちます。
このような機関投資家による賃貸マンションへの積極投資は、少なくとも「コロナ後」を見据えて、当面継続することが見込まれます。
そのため2022年も、転売を前提とした賃貸物件の建設および取得も、増加する可能性があります。
賃料推移は、どの圏域も安定推移。需要堅調の証賃貸市場の賃料推移――とくに三大都市圏の賃料推移は、コロナ禍においても大きく変わっておらず、おおむね安定推移しています。
圏域によって多少の違いはあるものの、首都圏では都心および近郊を中心に、一時的にやや下げた後持ち直しています。近畿圏では安定上昇、中部圏ではいったん2020年春にピークがあって以降はわずかに弱含みという結果でした。
これはコロナ禍においても、他の地域から流入してくる人口があることが大きなポイントです。首都圏――とくに東京都および東京23区では、他地域からの流入が赤字(転出超過)となる状況が発生しています。もっとも、毎年春には、入学・就職によってまとまった転入超過が発生しているため、年間を通してみると黒字(転入超過)となります。
首都圏では周辺3県への転入超過はコロナ以前から継続しているため、コロナ禍で人口が減少するのではないか、との憂慮はあたらないといえるでしょう。
なお、同様に近畿圏では、大阪府も大阪市も転入超過が継続しています。中部圏では愛知県からの転出は多いものの、名古屋市への転入が続いているため、人口が全体として減少するような事態には至っていません。
以上のように、コロナ禍においても依然として、都市圏への人口流入は一定数発生し続けていることが、大都市圏での賃料動向をより安定させていると見ることができます。
このような賃貸住宅に対する機関投資家の需要、および賃料相場の安定を背景に、賃貸住宅の着工戸数も徐々に増加しています。
2018年9月から2021年2月までは月次ベースでは前年同月比マイナスでした。ところが、2021年3月以降は、最新統計公表月である11月まで9ヵ月連続でプラスに転じています。
賃料水準の安定推移を背景として、今後も賃貸住宅、特に賃貸マンションの着工戸数は2022年も増加していくものと考えられます。
コロナ禍にあっても需要堅調との判断によって、2022年の賃貸市場は安定的な拡大が期待できるのではないか、と見ています。
(中山登志朗)
















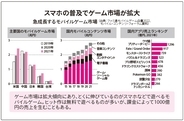









![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








