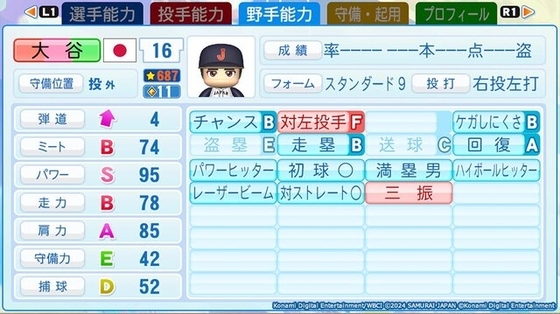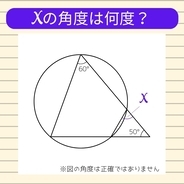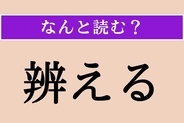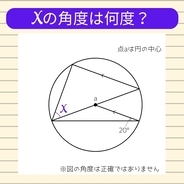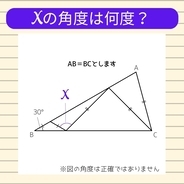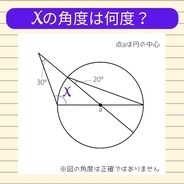Thomas Wolter / Pixabay
ほとんどの人は、自分がいつ死ぬかまったくわからない。100歳以上の長寿をまっとうするのか、明日にも悲惨な事故で死ぬのか、正確にそれを知る術はない。
それこそ神のみぞ知る世界だ。
しかし、一部の人たちは、説明のつかない不可思議な死の警告を受けることがある。こうした悲運の予兆はその家系に繰り返されることもあるが、たいていは単発だ。
ここでは自分の死、あるいは他者の死の予兆を感じ取ってしまった10人の物語を見ていこう。
【10. 災いをもたらすボダッチ・グラスを3度見た伯爵の末路】
[画像を見る]
CaptureLight/iStock
アーチボルト・ウィリアム・モンゴメリーは、エグリントン伯家の13代目伯爵で、ウィントン(1812~1861年)の初代伯爵としても知られている。
彼は領民からとても人気があり、1839年に民衆の娯楽として馬上模擬戦を再現させたことで知られている。
ところが、残念なことに、豪雨のために1万の群衆が会場から締め出されてしまい、翌日に再び試合は行われたが、見物人のほとんどは戻ってこなかった。
この話にはあまり知られていない裏話がある。1861年10月4日、エグリントン卿は、スコットランド東部ファイフのセントアンドルーズでゴルフをしていたが、突然、プレイを中断して仲間にこう言ったという。
「もうこれ以上はプレイできない。ボダッチ・グラスがいるから。見たのはこれで三度目だ。
なにか、怖ろしいことが私にふりかかってくる前兆だろう」
ボダッチ・グラスとは、スコットランドで特定の一族につきまとうと噂されている、ダークグレイの男のこと。エグリントンは、まさにその夜、おそらくは脳卒中が原因の内出血を起こして、突然死亡した。
【9. 骸骨に抱擁されていた女性】
[画像を見る]
AndreaObzerova/iStock
1924年、ミセス・ブリス・コールマンと夫は、カリフォルニア州オークランドに部屋を借りて住んでいた。ミセス・コールマンは毎日午後4時に、仕事の休憩で家に戻ってくるのが習慣だった。
ある日、いつものように午後4時に家に戻ってくると、3階に住む女性がロビーで大家の女性と話していた。
テナントの女性のそばに身長が180センチ以上もある骸骨が立っていて、その骨ばった腕で女性の腰を抱きしめているのに、当の女性も大家もまったく気がついていないようだった。
ミセス・コールマンは恐ろしくなったが、その奇妙な光景を説明することもできず、そのまま逃げるようにして自分の部屋へ駆けこんだ。
3週間後、3階のその女性は子供たちを残して死んだという。
【8. 城の窓辺に現れる赤毛の女性】
[画像を見る]
Alexas_Fotos / Pixabay
1642~1651年まで続いたイングランドの内戦(清教徒革命)は、詩人のサー・リチャード・ファンショーとその妻アンの生活を危うくさせた。
1649年、彼らはアイルランド、コークの住まいを引き払うはめになり、スペインへ向かう道中、何人かの友人の家に滞在した。その中で、レディ・ホナラ・オブライエンの城に泊まったときのこと。
夕食を済ませ、静かにおしゃべりをした後で、夫妻は自室へ退いた。
午前1時頃、アンが窓のほうから聞こえてくる声で目覚めた。
窓辺に近寄って、カーテンを開けてみると、白い服を着た赤毛の女が外から中をのぞきこんでいる。この世のものとは思えないほどぞっとするような顔色をしていたという。
アンが古いアイリッシュ語で"ochon, ohon, ochon(ああ、ああ!)"と呻くと、女の姿は雲のように消えた。アンはすぐに夫を起こし、このことを伝えた。
翌日、レディ・オブライエンが、同じ城内で病でふせっている従妹の介護で、昨夜はよく眠れなかったと話した。
その従妹は午前2時頃亡くなったのだという。
ファンショー夫妻の泊まった部屋は城で一番いい部屋だったようだが、家族の誰かが危篤状態になると、いつもこの部屋の窓辺に幽霊のような女性が現れることをすっかり忘れていたとのこと。ファンショー夫妻が、その城に宿泊することそれ以降なかった。
【7. 壁から現われる手】
[画像を見る]
FOTOKITA/iStock
1934年、作家のエリオット・オドネルは、スコットランドのマッケンジー家の若い女性の奇妙な体験について書き留めていた。
ある朝、その女性が家の二階へ行って、浴室から物を取って出てこようとしたとき、なにかが落ちる音が聞こえた。不審に思って、女性が音の原因を探ろうとあたりを見回すと、古めかしいシルバーの燭台がドレッサーの隣に落ちていた。
女性がそれを拾い上げたとき、なぜそれが落ちたのかその理由に気づいた。なんと、壁から腕が突き出していたのだ!
見えているのは肘から先だけだったが、透き通るように白い肌に長い指、きれいに整えられた爪が女性の腕であることを物語っていた。だが、体はどこにもない。ありえないこの異様な光景を唖然として見ていると、腕はゆっくりと消えたという。
女性はすぐに自分の母親のことを心配した。というのも、幽霊の手は家族の誰かが亡くなる前兆だという話を聞いていたからだった。
当時、女性の母親は病に冒されていたのだ。幸いなことに、母親は回復したが、腕が現われた数日後、その女性の従妹のひとりが若くして突然死んだという知らせが届いたという。
【6. 一族の呪い「首なし幽霊」】
[画像を見る]
VSanandhakrishna/iStock
事の発端は若いユアン・マクレーンの強欲だった。1538年、ロックビー地方のマクレーン家の跡取り息子であったユアンは、父親の財産をすぐに相続できないことがどうしても理解できなかった。
辛辣な言葉が口喧嘩になり、これが戦いへと発展した。この戦いはやがて一族を二分する戦争に発展し、父と息子は敵対した。
戦いが激しくなるさ中、父側の人間が一撃のもとにユアンの首をはねたが、その体は馬から落ちなかった。
それどころか、頭のない状態でその体は右や左へと撃ちかかり、近くにいた一族の者たちをなぎ倒して、馬もろとも戦場から城へと駆け抜けた。
馬がユアンの居城へ戻ると、召使たちは首なしの主人の姿を見て怯えた。遺体は時折、痙攣を起こしていたが、まだ鞍の上でまっすぐに座ったままだったのだ。
これは悪魔の仕業としか考えられないと確信し、召使たちは馬の首をはねて、ユアンの遺体を埋葬した。
それ以来、ロックビー地方のマクレーン一族は、ユアン・マクレーンの首なし幽霊と遭遇する恐怖と共に生きることになった。ユアンはいまだにお気に入りの愛馬にまたがり、戦場で最期に身に着けていたグリーンのマントをなびかせているらしい。その姿を見た者は、まもなく死ぬという。
【5. 翼をもった老婆の魔女「グーラハ・ア・フリビン」】
[画像を見る]
Jonny Lindner / Pixabay
ウェールズには、翼をもった醜い老婆の言い伝えがある。真夜中にもうすぐ死者が出る家にやってきて、その翼で窓を叩き、死ぬ者の名を叫ぶという。
グーラハ・ア・フリビンの訪問は、非常に怖れられている。ワート・サイツは、1880年に出した本『British Goblins』のために、ウェールズの農夫たちからこうした言い伝えを集め始めていた。
1878年11月14日、農夫がウェールズのランダフにいる古い友人を訪ねたとき、真夜中に窓を震わせるほどの恐ろしい金切り声で目が覚めた。
彼は驚いたが、好奇心もあって、窓に近づき、思い切って開けると、何者かが逃げていくのが見えたという。それが肩越しに彼のほうを振り返ったので、グーラハ・ア・フリビンであることがわかったらしい。
ぼさぼさの赤毛、白茶けた皮膚、翼、牙のような歯という奇怪な姿で、地面まで届く長い黒いガウンを後ろにたなびかせ、腕より下には体がないかのように見えたという。
老婆はまた、少しいったところの別の家の窓のところで金切り声をあげ、姿を消した。農夫がそのまま暗闇に目をこらしていると、老婆が再び現われて、近くのCow and Snuffersという宿屋の正面ドアから入って行った。
しばらく待ったが、それ以上なにも起こらなかった。翌日、その宿屋の主人が夜のうちに死んだことがわかった。
【4. 黒猫の亡霊】
[画像を見る]
fergregory/iStock
1800年代初頭、ミセス・ハートノルの家族は、あるマナーハウス(荘園領主が建設した邸宅)に滞在していた。とても広いので片側の棟だけしか使わず、あとはほとんど閉め切ってあった。
使っていない部分には、どこか不吉な感じのする回廊があったが、ミセス・ハートノルは若く冒険心が旺盛だったので、事あるごとにここを調べてみようとした。
彼女はこの回廊でさまざまな奇妙な体験をしたが、もっとも不気味だったのは、片眼で、足を失い、耳が裂けたずたずたの黒猫の亡霊だったという。
ミセス・ハートノルは、3度この猫に遭遇したが、初めてこの猫を見たとき、戸口から這い出てきて、ゆっくりと彼女に足に近づき、体をこすりつけようとして、そのまま床の中へと姿を消したという。
その夜、彼女の兄が死んだ。2年後、再び彼女がこの回廊を探っていたとき、なにか小さなものが背中にぶつかった。振り向くと、例の黒猫がいて、前と同じように体がひどく損傷して血みどろで、今にも死にそうに体を震わせていた。
ミセス・ハートノルは慌てて逃げ出したが、その夜、彼女の母親が死んだ。
4年後、再びこの回廊でミセス・ハートノルの前に影が現れ、またしても猫の姿が見えた。その午後、父親が突然死んだ。
父親を失い、ミセス・ハートノルと残されたきょうだいは、屋敷を立ち去り、自分たちでやっていかなくてはならなくなった。以来、このマナーハウスに戻ってきた者はいない。
【3. 謎めいた胸の白い鳥】
[画像を見る]
Ioannis Ioannidis / Pixabay
1641年、ロンドンで『セール・モナクロムに住むジェームズ・オクセンハムの子どもたちの死の床に現れた胸の白い鳥らしき幻影の本当の関係』というパンフレットが発行された。
これは、1618年から1635年の間に、作家ジェームズ・オクセンハムの身内の子ども5人が亡くなる前にそれぞれ、謎めいた胸の白い鳥が現われたという出来事をまとめている。
この話は広く知られるようになり、家族の死の予兆として有名な伝説になったが、実際は違った。
オリジナルのパンフレットの話は、売るために創作されたもので、5人の子どものうち3人は存在しないし、亡くなった日付も違っている。
この家族はタイトルにある"セール・モナクロム"に住んだこともない。パンフレットにとりあげられている目撃者も存在せず、話全体がもともと捏造だったようだ。だがこれが、出版後に起こったことを、さらに不可解なものにした。
1743年、捏造パンフレットが世に出てから1世紀以上たった頃、ウィリアム・オクセンハムが友人たちと自宅の部屋にいたとき、白い鳥が飛んできた。
オクセンハムはすぐに家系にまつわる死の予兆のことを思い出したが、自分はすぐに死ぬような病気でもないし、こんな鳥の予兆はまやかしだと一蹴し、一緒にいた友人たちも笑った。ところが、その2日後、オクセンハムは突然の病で死んでしまった。
【2. 城内での死を予告する若い女性の霊】
[画像を見る]
bonciutoma/iStock
1796年に準男爵になった、ドクター・ウォルター・ファーカー(1738~1819)は、1769年にロンドンに落ち着く前、若い医師だった頃に奇妙な体験をした。
デヴィンを訪れていたとき、ベリー・ポメロイ城の執事の妻を診察して欲しいと頼まれた。ファーカーが城に到着すると、別室で少し待つように言われた。
ファーカーが待機していると、おそらく身内らしい身なりのいい若い女性が、部屋に入ってきた。ファーカーは丁寧に挨拶したが、女性は彼の存在などまるで無視して、とても思い詰めた様子で、しきりと手でなにかをひねるような仕草をしていた。
部屋を横切て、階段のところまで来たが、一瞬昇るのをためらい、やっとのことで昇り始めた。太陽の光が上にあがる彼女の顔に当たり、絶望的な悲しみに苦悶する美しい顔に、ファーカーはショックを受けた。
いつの間にかその女性はいなくなってしまったが、病に苦しむ執事の妻の診療を済ませ、すぐに治療を施した。
翌日、ファーカーが再び患者を診ると、峠は越えたようで、昨日よりは明らかに良くなっていた。昨日案内してくれた若い女性のことを訊ねると、執事は真っ青になって、声をあげて嘆き始めた。
理由を訊くと、ファーカーが会った女性は幽霊で、城内での死を予告するために現れるのだという。その女性は前男爵ベリー・ポメロイの娘で、実の父の子どもを産み、ファーカーが待たされた部屋の上でその子どもの首を絞めて殺したという悲劇の過去があった。
執事の息子が溺死する前にも現われたというので、今度は妻が同じ運命になるに違いないという。奥さまは回復しつつあるので、心配はご無用とファーカーは慰めたが、執事の妻はその日の正午に死んだ。
【1. 親し気な笑みを投げかけた骸骨】
[画像を見る]
yuriyzhuravov/iStock
それは1974年、気持ちのいい夏の日のこと。ドクター・ジュリアン・キルチックは、自宅のプール脇の寝椅子に寝そべってすっかりくつろいでいた。
ゆっくりと日が傾きかけていて、涼しいそよ風と鳥の声に癒されていたとき、突然、近くの藪で音がした。キルチックは立ち上がって、何事かと見に行ったが、はたと足を止めた。
そこには、修道士のフードとローブをまとった骸骨のような姿があった。亡霊の目は落ちくぼんだ黒い穴だったが、キルチックはじっと見返されている気がした。
薄い皮膚が顔にピンと張りついていて頭蓋の形がはっきりわかり、見えている歯は一部欠けていて、まるで親し気に微笑みかけられているようにも見える。
この奇妙な人物が、骨ばった手で手招きしたので、キルチックは恐怖でその場で身動きできなくなった。そのうち、その骸骨は姿を消した。
このときキルチックが、この奇妙な訪問はなんだったのだろうと思ったなら、数ヶ月後に末期ガンと診断されたときに、その意味がわかっただろう。
References:10 Strange Omens That Warned Of Death - Listverse/ written by konohazuku / edited by parumo
記事全文はこちら:不可思議な体験は死の予兆だった。自分、あるいは他者の死の警告を受け取った10人の物語 http://karapaia.com/archives/52274629.html