* * *
外物(がいぶつ)篇に「至人(しじん)は乃(すなわ)ち能(よ)く世に遊びて僻(へき)せず、人に順(したが)いて己(おの)れを失わず」という言葉があります。「遊ぶ」はもともと「神」しか主語になれない動詞だったようですが、荘子は「人間だって遊ぼうよ、人間も遊に復帰しよう」と考えました。ちなみにこの「遊」という発想は、老子にはないものです。
「遊」とは端的に言うと、時間と空間に縛られない世界のことです。『荘子』では、たとえば、何物にもとらわれることのない無意識の境地であったり、役立たずだと思っていたものがじつは大きな価値を持っているという「無用の用」であったり、変えようのない互いの「もちまえ」を認めあうあり方であったりします。
ここでは、自在の境地に遊ぶ料理人庖丁(ほうてい)のエピソードを、養生主篇から紹介しましょう。
庖丁は魏の恵王(文恵君〈ぶんけいくん〉)のために牛を料理していました。その牛刀さばきは音楽的とも言えるほど見事なもので、「譆(ああ)、善いかな」と感嘆する恵王に、庖丁は自分が求めているのは技ではなく道なのだと言って、次のように語ります。
「牛の解体をしはじめた時、目に映るのは牛ばかり(どこから手をつけたらいいのか分かりません)でしたが、三年経つともう牛の全体は目につかなくなりました。近頃では、どうやら精神で牛に向き合っているらしく、目で見ているのではありません。感覚器官による知覚のはたらきは止み、精神の自然な活動だけが行なわれているのです。自然の筋目(天理)に従うと、牛刀は大きな隙間に入り、大きな空洞に沿って走り、牛の体の必然に従って進みます。
さらに庖丁は、自分の牛刀は刃こぼれもせず、もう十九年も長保ちしていると告げます。道を求め続けた庖丁には、刃先の厚みより遥かに広く、肉と骨の隙間が見える。だから刃を遊ばせるほどの余裕があるし、牛刀を動かすのもわずかで済むというのです。この名人とも言える境地は、たとえば野球で、バットで球を打つ瞬間に、小さく速いはずの球が大きく止まって見える、というのに近いものかもしれません。
庖丁は、感覚ではなく心で牛と向き合っている。そして牛刀は、自然の筋目に従って動いている。
無意識になるための方法は、反復練習しかありません。どんな行為も、それを何度も繰り返すことで無意識にできるようになります。ですから、茶道や華道など「道」のつくものには反復練習がつきものなのです。要するに、理屈は忘れる。忘れた時に、身に付く。逆に言えば、身に付いたら頭に置いておく必要がないので忘れるわけです。
■『NHK100分de名著 荘子』より
















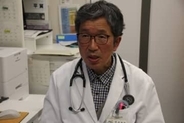










![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)


![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






