そしてこの年は、セドリック・ターボ以外にもうひとつ、あまり目立たないながらもエンジンに関して重要な動きがあった。トヨタの2T‐G型DOHCエンジンである。
1970年に登場した2T‐G型エンジンは、セリカ/カリーナ/カローラ・レビン/スプリンター・トレノに積まれ、日本を代表するスポーツエンジンとして一時代を築いたが、排ガス対策期に消滅の危機に瀕し、あの手この手と延命に努めた結果、電子制御燃料噴射装置の採用で生き長らえたという経緯を持っていた。最終的にこのエンジンは、71レビン╱トレノに積まれ真価を発揮するが、これがセドリック・ターボの登場した1979年だったのである。
日産L型ターボ、トヨタツインカム、そして双方から登場したのツインカムターボエンジン等、全ての【写真9枚】を見る
ところで、それまでのDOHCエンジンに対する考え方は、動弁系の慣性質量が小さいことから高回転化が可能であり、結果、回転馬力型の高出力エンジンに向くと考えられていたが、排ガス対策期をはさんで燃焼工学が進歩すると、吸排気も含めた燃焼制御が行いやすい形式のエンジンと、そのとらえ方も変わりつつあった。
ただし、この見方が浸透するのは80年代中盤のことで、まさに80年代に入ろうかという時期には、純然たるスポーツエンジンと捉えられ、2T‐G型がその最先端を走っていた。
その2T‐G型、原点は1970年に登場した1.4LのT型にあった。OHV方式だったが、燃焼効率を引き上げるため半球型燃焼室を採用し、クロスプッシュロッド方式とすることでクロスフローヘッドを成立させていた。当時はSOHC方式でもウエッジ型やバスタブ型の燃焼室を採用し、ターンフロー方式(代表例は日産L型)とするメーカーが多かっただけに、トヨタT型は画期的な構造だった。
2T‐G型とT型は、エンジンの要となる燃焼室の基本形状はほとんど同じで、効率的には同等と見なしてもよかったが、吸排気バルブの直上に独立したカムシャフトを配置するDOHC構造は伊達でなく、実際には、エンジンの回り方に雲泥の差があった。切れよく軽快に吹け上がるレスポンスは、排ガス対策期を耐えたファンに「これぞDOHC」と言わせるものだった。
トヨタのDOHC路線対日産のターボ戦略は、CMでおもしろい展開を見せていた。トヨタが、排ガス対策後のパフォーマンス低下に悩むスカラインGTを相手に「名ばかりのGT達は道をあける」(1979年8月、セリカ)とセンセーショナルに口火を切ると、1980年4月にジャパンターボを追加したスカイライン陣営が「今スカイラインを追う者はだれか」と切り返し、これを受けたトヨタが「ツインカムを語らずに真のGTは語れない」と応酬。
この論争(?)はさらに続き、4バルブDOHCのFJ20型エンジンを新開発したスカイライン陣営(RS・1981年10月)だった。いわく「4バルブなしにDOHCは語れない」というもので、スカイラインGT‐RのS20型に続き、4バルブDOHC方式しか手掛けなかった日産孤高の主張だった。
このFJ20型、1シリンダーあたり吸気2/排気2と4個のバルブを持ち、より高速燃焼に向くペントルーフ型の燃焼室が与えられていた。4バルブ化は、バルブ1個あたりの慣性質量が小さくなることで、より高速回転化が可能になること(一般論としてエンジンの高速回転化に伴う可動部位のストレスは、動弁系の追従不良が最初に起こると考えられていた)、ペントルーフ型燃焼室は、高圧縮比下で着火から燃焼完了までの火炎伝播速度が速いことに特徴があった。
その後の性能競争は、トヨタが2T‐G型の発展モデルとなる1.8Lの3T‐G型にターボを装着して「鬼に金棒」とDOHCターボの優位性を謳えば、スカイラインはFJ20型にインタークーラーターボを組み合わせ「史上最強のスカイライン」とカリスマ性を強調する訴求方法を採っていた。
こうしたトップレベルの性能競争が繰り広げられるなか、軽快さ、俊敏さというDOHC本来の特徴を生かした車両が登場し、ファンを喜ばせることになる。言うまでもなく1983年5月に登場したAE86型カローラ・レビン/スプリンター・トレノである。
いろいろな意味で伝説になってしまったAE86だが、搭載する4A‐G型は、後に、よく回る割には力がない、トルクの線が細い、と欠点を指摘されようにもなったが、前モデルにあたる2T‐G型と比べると、軽量コンパクト、高出力、ハイレスポンスとすべての面で進化を遂げていた。
4A‐G型の最も大きな特徴は、同じく最新型の4バルブDOHCである日産FJ20型と比べても、量産車用エンジンとして無駄のない合理的な構造となっている点にあった。
しかし、4A‐G型のもっとも評価されるべき点は、当時ごく少量でしか考えられなかった4バルブDOHCの生産を、量産ラインに乗せてしまった技術力と販売力だった。
しかし、本当の意味での4バルブDOHC革命は、1986年に登場するV20ビスタ/カムリの3S‐FE型で示されることになる。この後にも続くトヨタの型番末尾”FE”型エンジン、通称「ハイメカツインカム」は、狭角バルブ配置の燃焼室と2本のカムシャフトをシザースギアで駆動するシリンダーヘッドに構造的な特徴があり、中速域にポイントを置く実用型の4バルブDOHCとして作られていた。
燃焼室は、ピストンクラウン側に設けた大きなくぼみとヘッド側で形作る卵形の形状で、その中心にプラグ電極を置き、燃焼室中央から着火・燃焼させる手法を採っていた。ペントルーフの斜面沿いに火炎伝播を走らせ高速燃焼を狙う3S‐GE型とは異なり、燃焼性の向上に目標が置かれた構造だ。
燃焼室形状の自由度が高いこと、燃焼効率を引き上げやすいこと、幅広い回転領域の設定が可能であるという4バルブDOHCの特徴は、実用型エンジンに対しても非常に有効な構造だったのである。
旧タイプのDOHCを代表する2T‐G型の完成形からわずか数年。高出力型のスポーツエンジンと考えられていた4バルブDOHCは、設計自由度の高さから実用型エンジンの基本メカニズムとして浸透していくことになる。






















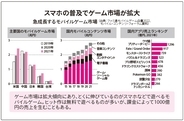









![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








