ケンドリック・ラマー、ドレイク、ザ・ウィークエンド、チャンス・ザ・ラッパー、カニエ・ウェスト、フランク・オーシャン、ビヨンセとソランジュの姉妹、そしてとどめのビリー・アイリッシュ……。彼/彼女たちがここ10年のポップミュージックの主流であり、かつ前衛でもあったことは、理解してもらえるはず。ブリティッシュ・インベイジョンは遠くなりにけり。
けれども、ここで言いたいことはただひとつ。
今、UKの音楽がアツい。
そう、現在のイギリス(とアイルランド)の音楽シーンは、本当におもしろい。
UK/アイルランド・シーンの注目曲を集めたプレイリスト。記事中でフォローできなかったアーティストも含めて、110曲をセレクト(筆者の天野龍太郎が選曲)
その先頭に立つのは、The 1975とブリング・ミー・ザ・ホライズンだろう。ともすればドメスティックな表現に陥りがちだった、ここ10年の英国ロックシーン(それは、ここ日本の状況ともどこか似ていた)。しかし彼らは、『A Brief Inquiry into Online Relationships』と『amo』というそれぞれの最新作で、「ロックバンド」という形態やスタイルを疑問視し、ポストジャンル化を推し進めながら再考することで、その可能性を改めて提示してみせた。さらにこの2組は、イギリスのみならず米国や日本でも成功をつかんでいる。
この話は、メインストリームやオーバーグラウンドに限ったものではない。
そのなかでも本稿では、2020年現在のUKおよびアイルランドにおける充実ぶりを、ロンドンを中心とするロックシーンを出発点に、あくまで俯瞰的に伝えていけたらと思う。
ロンドンシーンでもっとも注目すべきバンド、ソーリー
最初に紹介したいのは、北ロンドンから登場した異彩と輝きを放つ新鋭、ソーリー(Sorry)。
アーシャ・ローレンスとルイス・オブライエンという幼馴染を中心にしたこのバンドは、後述する南ロンドンの重要バンド、シェイムのチャーリー・スティーンに「彼女たちのパフォーマンスを見るためなら、僕たちはロンドンのどこにでも行く」とまで言わしめる存在。名門ドミノから力強いデビューアルバム『925』を発表したばかりで、百花繚乱のロンドンシーンでももっとも注目すべき存在だろう。その理由は3つある。

ソーリー。左からルイス・オブライエン、アーシャ・ローレンス(Photo by Sam Hiscox)
まず、その不敵な音楽性。彼女たちの汚れたオルタナティブサウンドは、90年代のベックやザ・ベータ・バンドと比較したくなるもので、「宅録グランジ風」と言ってもいい。しかし、ブルースロック調のシンプルな曲は奇妙なビートプログラミングやエディットで異化されており、ギターロックのくびきから解き放たれ、自由なサウンドを表現。アンニュイでダーティーなその音楽は一方で、抜けの良さと洒脱なムードをたたえている。それはサウンドの中心に、アーシャの不遜かつ涼しげな歌声が常にあるからだろう。
2つ目の理由は、アーシャとルイスの抜群なアイコン性にある。彼女たちのInstagramや、「Jelous Guy」「Right Round the Clock」のミュージックビデオにおけるシックかつユーモラスな装いをぜひ見てもらいたい。上掲した写真のとおり、ロンドンのチューブ(地下鉄)の座席にふんぞり返っている様もやたらと絵になる。
最後は歌詞。例の兄弟を思い出してしまう「Rock n Roll Star」という曲は、「一晩中ロックンロールスターとやりまくった」という歌で、「私の価値が剥がれ落ちてく感じがした」「私は古い心をロックンロールスターにあげた」と、なんとも悲観的でやけっぱちな言葉が歌われる。
ソーリーは2019年末に原宿のBIG LOVE RECORDSから7インチシングル『Starstruck / Jealous Guy』をリリースしたことで、日本でもじわじわと注目を集めている。今回の『925』は、バンドをローカルでもグローバルでも重要な存在へと飛躍させる決定打になるだろう。
独自の発展を見せる南ロンドンのロックシーン
続いては南ロンドン。ここ数年、日本でも話題になっていた同地では、ジャズミュージシャンからラッパーまで、様々なスタイルのミュージシャンがひしめくなか、ロックシーンも独特の発展を見せている。
焦燥に駆られたポストパンクを鳴らすシェイム、音もビジュアルも強烈なHMLTD、女性4人組の(という説明も時代錯誤的だが)ガレージバンド、ゴート・ガールなど、ここ2、3年はウィンドミル(The Windmill)というべニューを中心として、刺激的なバンドが多数登場している。
そんななか、新顔として注目されているのが7人組の大所帯であるブラック・カントリー、ニュー・ロード(Black Country, New Road)だ。バイオリンやサックスの音が舞う彼らの音楽は、アーケイド・ファイアと比較されるように、2000年代カナダのインディロックをほうふつとさせる。が、よりポストパンクに寄った、ひりついた音は英国ならでは。
彼らはウィンドミルで演奏しているが、もともとはケンブリッジ出身。先述したソーリーも北ロンドン出身でありながら、ウィンドミルなど南ロンドンのベニューの常連であるという。このように、南ロンドンは新たな才能を引き寄せる磁場になっている。
そんな同地の「親分」的な存在が、ファット・ホワイト・ファミリー。彼らは、2019年にアルバム『Serfs Up!』を、ソーリーと同じドミノからリリース。名門レーベルへの移籍デビュー作だからといって猫をかぶることなく、あいかわらず不穏でローファイなサイケデリックロックをやっているのが、なんとも「らしい」というか。
ウィンドミルでも演奏していたブリットスクール出身の4人組、ブラック・ミディも忘れてはいけない。彼らの『Schlagenheim』は多くのメディアやリスナーが2019年のベストアルバムに挙げていたし、来日公演も大いに盛り上がった。プログレ的、マスロック的とも評される複雑にツイストしたその演奏は、ロックのありうべき未来を照らす。
と、ここまで書いたところで、なんとスクイッド(Squid)がワープと契約した、というニュースが飛び込んできた。スクイッドは、ロンドンの真南にある海辺の町ブライトンで結成されたポストパンクバンドだ。クラウトロック、ノーウェイヴ調の演奏の只中、ひっくり返った声で歌うドラマー兼ボーカリストのオリー・ジャッジの存在が、なんとも際立つ。この先に控えているであろうアルバムには大いに期待したい(ワープから鳴り物入りでデビューするとなれば、2000年代のマキシモ・パークを連想させる)。
同じくブライトン出身で話題のバンドが、ポリッジ・レイディオ(Porridge Radio)だ。彼女たちの強みは、フロントに立つダナ・マーゴリンのカリスマ性、そして軋轢や混乱などを直情的に表現する演奏と歌唱が持つ緊張感。先日、アメリカのシークレットリー・カナディアンからリリースされた2ndアルバム『Every Bad』は、Pitchforkから絶賛されるなど、海を越えて高い評価を受けている。
スピーディー・ワンダーグラウンドとダブリン・シーン
話は前後するが、南ロンドンシーンといえば、プロデューサーのダン・キャリーが立ち上げたレーベル、スピーディー・ワンダーグラウンド(Speedy Wunderground)の存在も見逃せない。同地のローカルな若手をいち早くフックアップし、主に200枚限定の7インチシングルやコンピレーションで紹介しているこのレーベルは、先に紹介したブラック・ミディやスクイッド、ブラック・カントリー~らをいち早く取り上げてきた。
ちなみに、すべての録音は南ロンドンにあるダンのスタジオで、彼のプロデュースとエンジニアリングによってなされるという。まさにインディペンデントとDIYを地で行くその態度は、初期ラフ・トレードやチェリー・レッドなどを思い起こさせ、UK音楽文化の伝統を受け継ぐ姿勢に惚れ惚れしてしまう。
2019年のコンピレーション『Speedy Wunderground - Year 4』にはブラック・ミディ、スクイッド、ブラック・カントリー、ニュー・ロードなどのほか、フランツ・フェルディナンドのアレックス・カプラノスがオール・ウィー・アーの楽曲に参加。
そんなダン・キャリーは昨年、現在アイルランドの最重要バンドと言っていいフォンテインズ・D.C.を手掛けている。同国の伝統を受け継いだ複雑な詩作、勢いまかせのポストパンクサウンドとグリアン・チャッテンの吐き捨てるような歌を枯れた音で封じ込めたアルバム『Dogrel』は、ガーディアン紙が5つ星をつけるなど大いに絶賛された。
フォンテインズのみならず、首都ダブリンではザ・マーダー・キャピタルやジャスト・マスタードといった個性的なロックバンドが再び現れ始めている。2010年代中盤に登場したガール・バンドが火付け役になったとも言われており、ダブリンシーンには今後も注目したい。
キング・クルールとトム・ミッシュに続く音楽家たち
南ロンドンに話を戻そう。同地にいながらにして、シーンと距離を置く孤高の存在がキング・クルールだ。新作『Man Alive!』を世に問うたばかりの彼は、自身の作品でジャズ、ロックンロール、パンク、ヒップホップ、ダブなどを自在に織り交ぜつつ、エドガー・ザ・ビートメイカー名義でラッパーのジェイダシー(Jadasea)をプロデュースするなど、どこにも属さないまま、軽やかにシーンやジャンルを横断している。
10代でデビューしたキング・クルールは、寡作ながらその強烈なカリスマ性によって、ロンドンで大きな影響力を持つに至った。例えば、チェット・ベイカーがギタリストに転生したかのようなオルタナティブジャズシンガーのプーマ・ブルー。キング・クルールの兄とディック・ウーズ(Dik Ooz)として活動していた経歴を持つジャークカーブ。彼らの歌唱やギターの音色、ドリーミーな感覚からは、キング・クルールのそれに近いものを聞き取れる。
また、プーマ・ブルーとジャークカーブは、キング・クルールと同じブリット・スクールの出身という共通項も持つ。アデルやエイミー・ワインハウスを輩出してきた同校は近年、レックス・オレンジ・カウンティやコスモ・パイク、ロイル・カーナーといった新世代の才能を多く輩出しており、ここ日本でもWIREDやCINRA.NETで取り上げられるなど、その教育方針も含めて注目が高まっている。また、キング・クルールと親交のあるジェイミー・アイザックやレジー・スノウが2018年にブレイクしたのも記憶に新しい。
さらに南ロンドン、そしてポストジャンル的な音楽家といえば、トム・ミッシュを忘れてはいけない。2018年の話題をさらった『Geography』がロングヒットとなり、星野源との共作も話題となったギタリスト/シンガー/プロデューサーは今、新たな地平へと進んでいる。彼の次作は、ジャズ・ドラマーのユセフ・デイズ(Yussef Dayes)との共演から生まれた『What Kinda Music』(4月24日リリース)。ジャズ色と実験性を強めつつ、トム・ミッシュならではのメロディアスな作曲センスも発揮された同作は、彼のシリアスな音楽家としての姿勢を改めてアピールする作品となりそうだ。
さらに、当時19歳のトム・ミッシュが2014年に発表し、その才能を開花させたセルフリリース作品『BEAT TAPE 1』も、未発表音源を追加収録した日本盤がリリースされた。ラッパーのロイル・カーナーや、ジャズシーンにも属するマルチプレイヤーのジョーダン・ラカイらとの交流も含めて、トム・ミッシュもキング・クルールと同様、ジャズやヒップホップの境界線を跨ぎ越し、それぞれを繋ぎ止めるハブと言えるだろう。
それからもう一人、トム・ミッシュやFKJに続く逸材と目されるロンドン出身のブルーノ・メジャーも、最新アルバム『To Let A Good Thing Die』のリリースを6月に控えている。甘美な歌声とクラシカルなギタープレイで、ストリーミングサービスを通じて多くのリスナーを獲得し、渋谷WWWでの来日公演もソールドアウトさせた彼もまた、今日のイギリスを象徴するシンガーソングライターと言えるだろう。
エレクトロニック・ミュージックの現在
ここ10年のイギリスでは、それ以前のグライムやダブステップの文脈も受け継ぎつつ、ジェイムズ・ブレイクやジェイミー・xxのような才能を輩出してきた。この両者は冒頭で触れた北米の音楽シーンにも影響を及ぼしてきたわけだが、そこから数年を経て、The 1975やブリング・ミー・ザ・ホライズンといったバンドが、近作でダブステップのビートを持ち込んでいるのは興味深い。
それはまた、エズラ・コレクティブやモーゼス・ボイドといった、活況著しいUKジャズの代表格の作品からも聞き取ることができる。サウンドシステムカルチャーから地続きのベースミュージックの伝統が、UKの音楽文化にしっかりと根付いていることの証左だと感じる。
「伝統と革新」といえばXL Recordingsの総帥、リチャード・ラッセルが指揮を執るコラボ・プロジェクト、エヴリシング・イズ・レコーデッドによる2ndアルバム『FRIDAY FOREVER』(4月3日リリース)にも触れておきたい。ソウルフルだった前作を経て、レイヴ~グライムなどイギリスで育まれたダンス・ミュージックの伝統を再解釈した、実に意義深い作品となっている。
XLからは、シンガーソングライターのラプスリーによる最新アルバム『Through Water』も発表されたばかり。洗練されたエレクトロニックサウンドを軽やかに歌いこなすスタイルは、かのビリー・アイリッシュにも影響を与えたという。
エレクトロニック・ミュージックの領域では他にも、新たな才能が名乗りを上げている。ローファイハウスの質感とレイヴの記憶を携えたロス・フロム・フレンズは、フライング・ロータスに見い出されてブレインフィーダーからアルバム『Family Portrait』(2018年)を発表。ロンドンらしい折衷感覚と欧州的な実験精神でダンスミュージックをつくっているベアトリス・ディロン(Beatrice Dillon)も注目株として挙げておきたい。
Beatrice Dillonが2020年に発表したデビュー・アルバム『Workaround』収録曲「Workaround Two」
また、こちらもドミノからデビューしたジョージアは、「Started Out」と「About Work the Dancefloor」のヒットで、ニュー・オーダーからロビンまで連なるエレクトロポップの新しいスタンダードを打ち出した(彼女は90年代を代表するテクノユニット、レフトフィールドのニーク・バーンズの娘である)。キャッチーな作曲センスは、今年1月に発表されたデビューアルバム『Seeking Thrills』でも存分に発揮されている。
そのジョージアが客演しているのが、ムラ・マサの最新作にして問題作『R.Y.C』だ。英領ガーンジー島出身の彼は、洗練されたエレクトロニックアルバム『Mura Masa』(2017年)でグラミー賞にノミネートされるなどの成功をつかんだ。しかし、『R.Y.C』では刺々しいギターロック/ポストパンクに挑戦している。
ムラ・マサのギターロックへの転向ないし回帰には、スピーディー・ワンダーグラウンドのDIYな営為と、巨大なファンダムを抱えて挑戦を続けるThe 1975からの影響があるとか。「死んだ音楽を作り続けるなんて、ただの死でしかない」という彼の発言は、ここまで書いてきた生命力あふれる英国音楽シーンの裏付けにもなっている。
UKラップシーンの最前線
先に「問題作」とは言ったものの、ムラ・マサの『R.Y.C』はやはり重要かつ野心的な作品である。というのも、ここで彼はクレイロに象徴されるアメリカのベッドルームポップの潮流を引き込もうとしているし、ロンドン・インディロックの先頭を行くウルフ・アリスのエリー・ロウゼルも呼び込み、さらにはラッパーのスロウタイも参加させている。「ポストジャンル」的というか、1996年生まれの彼にとっては、ジャンルの境界線が初めから存在していないかのようだ。
ロンドンの南西に位置するノーザンプトン出身のスロウタイは、「ブレグジット・バンディット」を名乗る不敵なジョーカーである。ムラ・マサとの共作曲「Doorman」を含むアルバム『Nothing Great About Britain』は、英国社会や政治に中指を立て、徹底的に皮肉り倒した2019年の最重要作だと言っていい。
『Nothing Great About Britain』には、グライムシーンからマーキュリー賞を掴んだスケプタが参加。彼やストームジー、ロードラップシーンからのし上がったギグス、そしてアフロビーツを独自にアフロスウィングへと発展させたJ・ハスらは、現在のUKのラップシーンにおける最重要人物だ。
彼らに続くように、若きデイヴは傑作『PSYCHODRAMA』で2019年のマーキュリー賞を獲得した。コンシャスで内省的な表現を得意とする彼は、頭一つ抜けた存在だろう。
ギャングカルチャーと分かちがたく結びついたロードラップやUKドリル(その中心地のひとつは、ウィンドミルもあるブリクストンだ)を独自に培養し、発展させてきたUKラップ。だが、今は北米との相互交流が盛んになっていることも指摘しておかねばならない。
カナダのドレイクはスケプタやジェイミー(Jme)らによるグライム・レーベル、ボーイ・ベター・ノウン(Boy Better Known)と契約したことを2016年に明かした(しかしその後、目立った動きは見られない)。スケプタやR&Bシンガーのジョルジャ・スミスと共演するなど、北米のポップスターであるドレイクが英国のフレッシュな才能と積極的に交流してきたことは、かなり重要なことである。
もう一つ注目すべきはドリルシーンで、現在ニューヨークのブルックリンでは、UKドリルから影響を受けたラップシーンができあがっている。そのブルックリンドリルのラッパーたちはUKドリルのプロデューサーがつくったビートを用いており、彼らのフロウやライミングもUKから影響を受けている、という指摘もある。UK独自のラップミュージックが本国アメリカに影響をもたらす、というおもしろい動きが起こっているのだ。ドレイクも昨年末に発表したシングル「War」で既にドリルに取り組んでいるし、UKドリルのスタイルは北米で流行の兆しを見せている。これこそ、新しいかたちのブリティッシュ・インベイジョン?
ブルックリンドリルとUKドリルをつなぐ新世代ラッパー、ポップ・スモークは今年2月に20歳で死去。
フジロック出演のUKアクトにも注目
さらに今日のイギリスでは、シャバカ・ハッチングスを軸としたジャズシーンも盛り上がりを見せているわけだが、すでに相当な字数となっているため、そちらの詳細は他の記事に譲ろう。
シャバカ・アンド・ジ・アンセスターズの最新作『We Are Sent Here By History』収録曲「Go My Heart, Go To Heaven」
ということで、おおまかにロック、エレクトロニック、ラップと分けながら、2020年における英国とアイルランドの音楽シーンの盛り上がりぶりとその概況を描いてみた。ただ、「ポストジャンル」を強調することと、こういった区分けは、明らかに矛盾している。
様々な音楽ジャンルやスタイルが同時進行的に盛り上がり、見慣れぬ新顔がどんどん出てきている現在。あらゆる潮流は相互に絡まり合って、複雑にネットワーク化している。ロンドンを中心とする英国の音楽シーンは混沌としていると言ってもいい。しかし、時代や地域の混沌こそがおもしろいし、聞き手としてはその猥雑さに興奮を覚えてやまない。そんな状況下でこそ、新たな可能性を持った音楽が生まれるのではないか、と感じるのだ。

ソーリー(Photo by Sam Hiscox)
そんな混沌をするりとくぐり抜け、明快なポップさと不敵な歌でもって一太刀を浴びせるようなソーリーは、やはり注目に値する存在だと思う。荒々しい野心と、確かなアイコン性を携えたアーシャとルイス。彼女たちの1stアルバム『925』(「925」とはアクセサリーなどに使われる用語で、純度が高い本物の銀の含有率を表す)は、2020年の英国シーンにおける最重要作である、と言い切ってしまおう。
最後に、第1弾ラインナップが先日発表されたFUJI ROCK FESTIVAL 20では、本稿で紹介したトム・ミッシュ、ジョージア、フォンテインズ・D.C. 、ムラ・マサ(クレイロも!)に加えて、最新作『MAGDALENE』が絶賛を受けたFKAツイッグス、ディスクロージャーやフローティング・ポインツといったエレクトロニック系アクト、数々の賞に輝いた新進気鋭のソウルシンガーであるセレステ、さらに彼らの先輩格となるThe xxのロミーやメトロノミーの出演が決定済み。UK~アイルランドの今を知るうえでも見逃せない顔ぶれが揃っている。

ソーリー
『925』
発売中
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10790

FUJI ROCK FESTIVAL 20
日程:2020年8月21日(金)~8月23日(日)
会場:新潟県 湯沢町 苗場スキー場
時間:9:00 開場/11:00 開演/23:00 終演予定
https://www.fujirockfestival.com




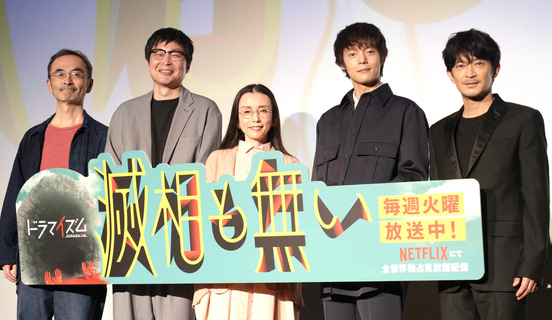


















![SCIENCE FICTION (生産限定盤)(3枚組)[Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/31rt4g7gE9L._SL500_.jpg)









