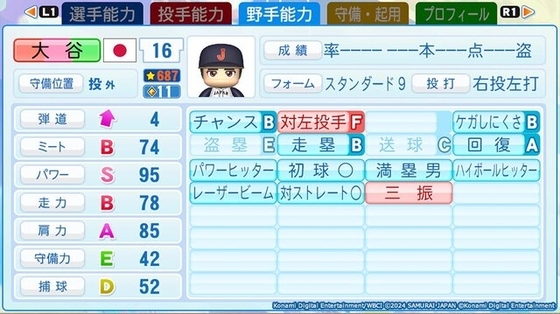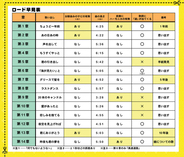【動画を見る】イギー・ポップ×エルヴィス・コステロ対談の模様
エルヴィス・コステロがイギー・ポップと出会ったのは、彼が初めてアメリカに降り立ってから24時間も経たない1977年11月のある日のことだった。元ザ・ストゥージズのフロントマンは、サンフランシスコにあるオールド・ウォルドーフのステージにいた。ロンドンから到着したばかりで目を充血させたコステロがクラブへ足を踏み入れると、ちょうどイギーが「ザ・パッセンジャー」を歌い始めるところだった。
「初めて観た時は、少しビビったよ」とコステロはイギーに語る。「ステージで小さな椅子の中に自分の体を突っ込んでさ。まるでロックンロールのバンドにマレーネ・デートリヒを加入させたようだった」
ライブ後にコステロはバックステージへ案内され、少しだけ会話できた。
そこから始まった長い友情は、2019年にひとつの実を結ぶ。イギーが、コステロのニューアルバム『ヘイ・クロックフェイス』に収録された「ノー・フラッグ」をフランス語でカバーしたのだ。そして今、イギーはマイアミの自宅から、そしてコステロはバンクーバーからオンライン対談に臨んでいる。
お互いの第一印象
コステロ:ストゥージズについては記事で読んで知っていたけれど、僕が曲を作り始めた1976年や77年当時は、イギー・ポップに似せようとするバンドが多かったのを覚えている。中には、ストゥージズの曲そのものをカバーしているバンドもあった。その頃の2枚のアルバム(1977年にリリースした『イディオット』と『ラスト・フォー・ライフ』)が皆の心を捉えた。
イギー:君の方は、70年代後半にイングランドから出てきたね。2つ驚いたことがある。ひとつはメロディーの豊かさだ。「なんだこいつは! 曲の聴かせどころをしっかり押さえている」と感じた。もうひとつは、(ジ・アトラクションズの)スティーヴ・ナイーヴのキーボードとオルガンの使い方だ。
コステロ:それはもう少し後かな。楽しかった。
イギー:食事しながら音楽の話をしたね。君はカレーを食べながらラガービールの大ジョッキを飲んでいた。
コステロ:ティーンエイジャーの頃は友だちとパブへ行って生演奏を聴きながら、自分が食べられる最も辛いカレーを食べていた。
イギー:イギリスの街角にある売店が好きだった。水曜の朝が楽しみで、朝起きたらサウンズ誌、NME誌、メロディーメーカー誌といった音楽誌を買いに行ったものさ。それぞれに特徴的な傾向があってね。
コステロ:その通り。僕について初めて書いてくれたのも、サウンズ誌だったかな。僕に眼鏡をかけさせて、名前を変えた。まるでクラーク・ケントのようだった。サウンズ誌に載るなんて、信じられなかったことだ。それからオフィスで仕事をしていたかと思えば、次の瞬間は逮捕されてメロディー・メーカー誌の表紙さ。
イギー:路上ライブの件だな!
コステロ:宣伝活動をしようとして逮捕されたんだ。警官がやってきて「おい若造、ここから立ち去れ」と言われた。彼は相手を間違えていたのさ。僕は止めたくなかったし、ちょっとカチンと来ていたかもしれない。「こうしろ」と言われたら、違うことをしたくなる。そうして僕は連行された。
イギー:君の音楽を聴いた時、ギターリフ一辺倒のイギリスから来たモンスターとは違うな、と思った。ギターリフ真っ盛りだったから。君はどちらかと言うと、例えが適当でないかもしれないが、(歌手の)ルルみたいだった。
コステロ:僕はルルが好きだ。
イギー:ルルはいいよね。でもレベルの低いことを半年毎に繰り返すのもくだらないし、退屈だ。お金を節約したければ、一度使ったティーバッグをもう一度使えっていう考えさ。君もイギリス人だから理解できるだろう。君はどこか違っていた。
過ぎ去りし70年代の記憶(1)
コステロ:長い年月が経っても、僕は「パンク出身だ」と言われる。
イギー:パンクではない。そういう時代だったのさ。
コステロ:ザ・ピストルズは自分たちをピストルズと呼んだ。素晴らしい名前だからだ。名も無いグループよりも名前があった方がいい。ザ・クラッシュはクラッシュだ。僕はこの奇妙なステージネームの恩恵を受けることもあれば、重荷になったこともある。でも名前の裏には個人が存在する。ただ、その人の部分を大切にしなければならない。
ロックンロールに関して、ティーバッグの使い回しの話はその通りだ。エルヴィス・プレスリーの最初のレコードには、ドラムが使われていない。ジェリー・リー・ルイスの場合はベースが無かった。それでも、その状況の中で自分たちのできる全てを注ぎ込んでいる。ジョニー・キャッシュの最初のレコードにもドラムが無く、ギターでリズムを刻んでいる。ドラムが必要だったかと言えば、答えはノーだ。これはロックでは無いかと言えば、それもノーだ。
イギー:だんだん必要なものが増えていくんだな。大きなドラムセットが必要になり、次はシャウトできる人間、と次々に欲しくなる。ウォー、ベイビー!(叫び声)
コステロ:(嫌味っぽい口調で)誰のことを言っているのか分からないよ! 誰のことだい?
イギー:(バンドの)シンデレラみたいなフォロワーを生んだ、あるグループのことさ。
コステロ:衝撃的だ。ロバート・プラントと初めて会ったのは、1980年のチャリティーコンサートだった。僕の方から彼に近づいて行ったが、僕は酒とドラッグで酷い状態だった。彼は僕が挨拶しに来たと思っただろうが、僕は思いっきり馬鹿にした感じで「天国への階段」と言ったんだ。あの頃は、世代毎にくだらない対抗意識があった。僕は彼と4つか5つしか変わらないんだけど。それでも歳上の彼がやっているのは年寄りの音楽だ、などと考えていたからね。
イギー:ロックンロールの世界では、5年と言えばひと昔前さ。
過ぎ去りし70年代の記憶(2)
イギー:俺の場合(ソロ活動を始めた時は)、既に先の無い感じだった。君の場合は、そもそもラジオでかかるような曲を作ろうなんて考えていなかっただろう。アメリカでは、野球帽を被った筋骨隆々の太っちょ野郎が仕切り始めて、やがてビジネス全部を持っていくんだ。皆が揃って「ロック・ゴーズ・トゥ・カレッジ」的な雑誌を読んでいた。俺には縁が無かったけどね。
コステロ:その手の雑誌でロック・クラブのことを知った。突然自分もウィスキー・ア・ゴーゴーなどに出演することになったが、全く華やかだとは感じなかった。
イギー:ちょっと時期が遅かったのさ。もうブームの終わり頃だったのだろう。1970年にロサンゼルスでアルバム『ファン・ハウス』をレコーディングして、ウィスキー・ア・ゴーゴーでライブをした。俺たちと同じホテルに、アンディ・ウォーホルと取り巻きも宿泊していたんだ。彼らは俺たちのギグにやって来て、後ろの方のブースに陣取っていた。ステージ上にはストゥージズがいて、周りはダンスフロアさ。ステージでは尻の見えそうなミニスカートとベルボトムのパンツを履いた3人のサーファー娘が、サーフダンスを踊っている。かなりスペシャルな状況だったよ。俺たち自身や俺たちの音楽とは全然かけ離れていたからね。
コステロ:そんな状況でもお構いなしに踊ってくれるなんて、素晴らしい。僕らの場合は、ステージに冷たい視線を向けられていたからね。僕らもトロピカーナに泊まったことがある。まだ営業しているよね。
イギー:素晴らしいホテルだった。
コステロ:ラスベガス・ストリップは馴染みの場所だった。こっちに洗車場があって、反対方向にはアイホップがあった。僕は運転しないから、ロサンゼルスでは移動に苦労した。バスも地下鉄も無かったからね。「お前は歩いて行こうとしているのか? 6kmも先だぜ」という感じだった。僕にとっては未知の世界さ。
イギー:俺は(音楽業界の生き残り方を)全く学習しなかった。ストゥージズは、エレクトラ(レコード)から始まった。ジャック・ホルツマンは、レコードショップのオーナーだった。彼が持っていたのは店1軒だけだったが、彼にはセンスの良さと学識があった。俺たちはエレクトラに見限られ、CBSへ移籍した(1973年のアルバム『ロー・パワー』)。そこにクライヴ・デイヴィスがいたが、彼は俺たちとの契約を後悔していた。その後デヴィッド・ボウイと進めていたプロジェクトの関係で、RCAと(ソロ名義で)契約した。RCAはボウイのプロジェクトに関わる人間を求めていたから、ボウイは他の幹部に俺の契約のことは隠していた。その後アリスタと契約した頃に、イギリス人のチャールズ・レヴィソンという素晴らしい人物に出会った。それからクライヴ・デイヴィスがアリスタの経営権を握って最初に言ったのが、「何をしてくれたんだ?! イギー・ポップと契約しただと? なんてこった!」だった。
コステロ:『ロー・パワー』に関してはとんでもない陰謀があった。
イギー:本当に酷かった。
コステロ:最初のバージョンは、まるでカセットからそのままコピーしたようなサウンドだった。ベースが聴こえず、妙なコンプレッションがかかっていた。君の内から出るエネルギーを失わせてはいけない。でもイギリスでは、寄ってたかってアルバムのことをあれこれ言われたと思う。辛い状況だっただろう?
イギー:良かった点は、デトロイト出身の俺たちの気を散らす全ての悪いものを断ち切れたことだ。曲を作ってリハーサルする場所を与えられ、最終的には立派なスタジオも用意された。本当に素晴らしいアルバムを作れる環境にあった。でも「俺たちはライヴができるのだろうか?」と思い始めた頃に、全てが狂い始めた。
それから俺は、カーツ大佐(訳註:映画『地獄の黙示録』の登場人物)のように引きこもり、頭の中でイメージしたサウンドをどうにかミックスしようと頑張った。最終的に、徐々に俺はその状態から抜け出さねばならなかった。俺はジェームズ・ウィリアムソンと一緒にロサンゼルスに2日間滞在し、デヴィッド・ボウイとミックス作業を終わらせた。その頃俺たちは、マスタリングが何かということも知らなかった。針がレッドゾーンまで振れそうになったら「おい、少し絞れ!」という感じだったのさ。俺たち自身がレッドゾーンだったよ。
過ぎ去りし70年代の記憶(3)
コステロ:初期の君らは、クイックシルヴァー・メッセンジャー・サービス、フレディ・キング、マイルス・デイヴィスなどといった面白い組み合わせでフィルモアに出演していたね?
イギー:最悪だったのは、J・ガイルズ・バンド、スレイド、そしてイギー&ザ・ストゥージズというステージだ。
コステロ:ワォ!
イギー:ギグの後に、ピーター・ウルフ(J・ガイルズ・バンド)のホテルの部屋でクスリをやったところまでは覚えている。ロン・アシュトン(ストゥージズのギタリスト)が言うには、俺は斧を持ったスレイドのツアーマネージャーに、廊下を追い回されていたらしい。「殺してやる!」ってね。
コステロ:当時はそんなことは日常茶飯事だったね。
イギー:俺たちとの共演は避けたいというロックバンドは多かった。俺たちの周りに人々も近寄らなかった。『ファン・ハウス』が出た直後の1970年、ストゥージズはアリス・クーパーとフィルモアのステージに立った。オリジナルのアリス・クーパー・バンドが結成されたばかりの頃だった。彼らはお揃いのスパンデックスの衣装を着て、女の子のように腰を振りながら蜘蛛の歌を歌っていたよ。アリスは自分でフットスイッチを使って照明を切り替えていた。奴らはクールだった。最前列にはザ・コケッツの面々が陣取っていた。彼らはドラァグ・パフォーマーの先駆けだな。カルメン・ミランダ張りのヘアスタイルやコスチュームで、コンサートの一部と化していたよ。
その後の低迷期に、サンフランシスコのビンボウズというところでもライブをした。
コステロ:僕もビンボウズは知ってるよ。
イギー:もう最高さ! またある時、ナッシュビルのマザーズという小さな会場でやった時は、正にナッシュビルと言う感じだった。共演したオールマン・ブラザーズ・バンドのローディーたちが、俺たちのサウンドチェックを見ながら大声で言うんだ。「あいつらのジーパンの下は女の子のナニが付いてるんじゃないのか? トイレに連れ込んで確かめてやろうぜ」ってね。奴らは俺たちをボコボコにしたかったのだろう。ところが俺たちのステージが終わると彼らがやって来て、「知らなかった。君らは凄くロックしている!」と謝ったのさ。
コステロ:そんな街へ行くと必ずレコードショップを探して、「地元のバンドのレコードはあるかい?」と聞いてみるんだ。アクロンへ行った時は、ロンドンでは手に入らないペル・ウブのシングル盤を見つけたし、ボストンではボストンらしいレコードを入手できた。僕らと同じく地元のレーベルから出ているレコードだ。でもテキサスだけは少し事情が違っていた。オースティンのアルマジロという会場には、モーズ・アリソンやフライング・ブリトー・ブラザーズのポスターが貼ってあるんだ。いったいどの時代に来てしまったんだ、という感じだったね。
イギー:70年代初めのデトロイトでは、凄いメンバーと一緒にやった。ストゥージズがザ・フーやクリーム、(レッド・)ツェッペリンのオープニングを務めたのさ。アン・アーバーでは、ボウリング場を改装した会場でジミ・ヘンドリックスを観た。彼と俺との間は2m位で、ステージの高さは20cmぐらいしかなかった。もう手の届きそうな距離さ。当時はどの街でも自己中心的な変わり者がビジネスを仕切っていたが、彼らは何かクールなことをしたいと考えていた。そんな彼らには、音楽がちょうど良いビジネスのネタだったんだ。
コステロとイギーのコラボ秘話
コステロ:お互いに学んだことは、恐れない心だと思う。特に今の時期には必要なものだ。君はフランスでアルバムを作った。君はフランス語で歌い、ジョシュ・オムともアルバムを製作した(2016年の『ポスト・ポップ・ディプレッション』)。BBCで彼らと一緒にやっているのを観た。最後に「ラスト・フォー・ライフ」を歌っていたね。カメラの前を通り過ぎて、観客へと飛び込んでいった。「楽しそうだな」と思ったよ。当局が観たら「問題を引き起こすからすぐに止めさせなさい」と言いそうだったけどね。自分の好きなようにやる。それがロックンロールだと思う。僕らの共通認識は、最初のプランに固執して他のアイディアが出ないのは危険だ、ということ。初めのうちに素晴らしい作品ができたと思い込んでしまうと、ますますサプライズを作り出せなくなる。
コステロ:僕ははるばるヘルシンキまで行って、(『ヘイ・クロックフェイス』向けの)3曲をレコーディングした。最初の曲が「ノー・フラッグ」だが、これが良いきっかけになったと思う。君の有名な曲「ノー・ファン」から、1ワードと1文字を引用しているのだけれど、気づく人はいなかった。僕が君からインスパイアされているなんて、誰も思わないからね。僕は「自分に必要の無いものはなんだろう?」と考えた。バンドにベーシストはいるけれど、レコーディングには同行させなかった。僕は君とは違ってドラムを叩けないから、自分でドラムパートを歌った。たった3つのコードでも、フレッシュに聴こえるようにする方法を見つけなければならない。
「ノー・フラッグ」には、君の作品の多くに見られる「崖っぷちに立つ」という哲学的思想が流れている。「サム・ウィアード・シン」が頭の中にあったんだけどね。
イギー:それを聞いた時、僕もその曲が浮かんだよ。
コステロ:君が歌う”ピンで留められて”(stuck on a pin)というフレーズが、まず僕の頭に浮かんだ。キャリアの中で、標本箱の中にピン留めされた蝶のような状況もあっただろう。そんなピンは自分で抜いてしまわねばならない。僕はあの曲がお気に入りだ。
(新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから)イングランドにいる母親を訪ねるのが難しくなってしまった。彼女は93歳で、体調が良いとは言えない。心配だ。ロンドンに息子がいる。彼のことも心配だし、無事でいてくれることを願っている。ロンドンの状況は少し厳しいからね。僕自身に関しては、この状況をありがたく思いながら比較的穏やかに過ごしてきた。
ダイアナ(妻のダイアナ・クラール)と一緒に過ごしている。いつもなら2人のどちらかがウィチタのような街へ向かうツアーバスに乗って、子どもたちとも一緒にいられないところだ。それが僕らの生活さ。僕は、彼女が自分の曲を仕上げる様子を眺めている。普段ならそんな機会はない。彼女はだいたい上の階にある音楽ルームでミックス作業をしていて、僕は『ヘイ・クロックフェイス』の次の作品に取り掛かっている。
イギー:今年はツアーの予定が入っていた。ところが「ボン!」だ。夏に入って、残りの夏も「ボン!」と消えてしまった。だからすぐに筋肉を鍛え始めた。「頑張れ! 止めるな!」という感じさ。喘息と気管支炎を患ったことのあるおじさんにとって、コロナウイルスはとても恐怖だ。
「よし、スケジュールを組み直そう!」ということで、全部2021年に延期した。ところが時間が経つにつれ、2021年に実現するかどうかも怪しくなってきた。その時点で、中止を決めた。でも、「俺は何をやっているんだ? これからどうなるんだろう?」と毎晩うなされることだろう。
コステロ:ステージへ戻れた時は、気分が良いだろうね。ステージ上でどんな騒ぎになるか、今から楽しみだ!
【関連記事】エルヴィス・コステロが語る、キャリア屈指の最新作と「過去に縛られない」自身の歩み
From Rolling Stone US.

エルヴィス・コステロ
『ヘイ・クロックフェイス』
発売中
視聴・購入:https://jazz.lnk.to/ElvisCostello_HeyClockfacePRF