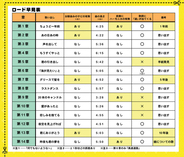エンパイア・ステート・ビルディングは現地時間10月8日(木)夜、世界的に有名なタワーをスカイブルーでライトアップし、鉄塔に白いピース・サインを周回させた。 0これは10月9日の金曜日に80回目の誕生日を迎える
ジョン・レノンの人生とレガシーをひと足早く讃えるために、ジョン・レノン財団とユニバーサル・ミュージック・グループの協力を得ておこなわれたイベント。
ライトアップは日没(東部夏時間で午後6時25分ごろ)からスタートし、東部夏時間の午前2時まで続いた。ライトアップのスイッチを入れたのは息子のショーン・オノ・レノン。 この祝典と時を合わせてリリースされるのが、ソロ時代のレノン作品のなかから、もっとパワフルで、もっとも愛されている36の楽曲を集めたニュー・アルバム『ギミ・サム・トゥルース.』だ。ヨーコ・オノ・レノンがエグゼクティヴ・プロデューサー、ショーン・オノ・レノンがプロデューサーを務めたこのアルバムの収録曲は、すべてゼロから完全にリミックスされ、音質が大幅に向上している。これを聞けば、今まで経験したことのない、究極のリスニング体験が味わえるはずだ。
数あるニューヨーカーのなかでも、とりわけ有名な住人だったジョン・レノンがイギリスからニューヨークに移ってきたのは1971年、
ビートルズ解散後のことで、彼は亡くなる1980年までこの街を根城にしていた。
ニューヨークへの愛を熱く語っていた彼は、移民局との厳しい闘いに勝利し、アメリカ、そして愛する第二の故郷に永住する権利を得た。レノンとオノはセントラル・パークにほど近いザ・ダコタに居を構え、今もオノが暮らすこのアパートでショーンを育てた。レノンは『マインド・ゲームス(ヌートピア宣言)』(1973年)、『心の壁、愛の橋』(1974年)、『
ロックン・ロール』(1975年)などのソロ・アルバム、そして『サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ』(1972年)、最後のスタジオ・アルバムとなった『ダブル・ファンタジー』(1980年)、没後にリリースされた『ミルク・アンド・ハニー』(1984年)といったオノとの共作アルバムを、ニューヨークで書き、レコーディングした。レノンのアルバム《イマジン》(1971年)のストリングスがレコーディングされ、最終的なミックスがおこなわれたスタジオも、ニューヨークの名高いレコード・プラントだった。 1980年、彼の逝去を受け、カメラマンのボブ・グルーエンは、セントラル・パークで徹夜の追悼式を開くファンのために写真を選んでほしいと頼まれた。彼が選んだのは、太い黒文字でNew York Cityとプリントされた、白い袖無しのTシャツを着ているレノンを撮った写真だった。
ニューヨークがこのリヴァプールっ子にとって、ひとつのシンボルだったの同じように、今やひとつのアイコンとなったこの写真は、レノンの代名詞になり、この街の誇りにもなっている。セントラル・パークのストロベリー・フィールズは、世界的に有名なシンガー、ソングライター、そして平和活動家でもあったジョン・レノンの生きた記念碑だ。
ショーン・レノンのコメント
「僕の父は1971年にニューヨークに移住してきました。彼はここがとても気に入りましたが、移住者としてここで永住権を取得するために大変苦労したことは、有名な話です。父はニューヨークが世界一素晴らしい場所だと常に語っていました。そんな彼が僕をこの街で育ててくれたことをありがたく思っています。ですから、このような機会に感謝すると共に、彼のメッセージである愛と平和、そして真実という言葉が皆様に届くことを願っています。」
ジョン・レノンが語るニューヨーク
「イギリスやヨーロッパからやって来る大半の人間にとっては、ニューヨークこそがアメリカだ。
つまり、ハリウッドを別にするとね。子どものころに見せられるのは、いつもその写真だったからさ。マンハッタンのスカイラインを見て育ったわけで、ここに来て、その一端を感じることが、まさしくひとつの夢なんだよ」 「本場はなんといってもアメリカだ。ぼくもニューヨークで生まれるべきだったと思う、ほんとに! ヴィレッジで生まれるべきだったんだ、ぼくの居場所はそこなんだから! なんであそこで生まれなかったんだろう? 18世紀はパリが〝本場〟だった。ロンドンはたぶん、一度も〝本場〟だったことはないと思う。文学的にはそうだったのかもしれない。
ワイルドやショウみたいな人たちがゾロゾロいた時代にはね。ニューヨークは〝本場〟だった! ぼくは自分がアメリカ人じゃないこと、グリニッジ・ヴィレッジで生まれなかったことを、心から後悔している。そこがぼくのいるべき場所だった。でも絶対、思うようにはいかない。誰もが中心に向かって行くものだし、ぼくが今、ここにいるのもそれが理由だ。その空気が吸いたくてね。
なにかがはじまるのはここなんだ」 「ニューヨークのよさをぼくに教えたのはヨーコだった。ここにいたころの彼女は貧乏暮らしをしていて、街を隅々まで知りつくしていた。ぼくは彼女に連れられて通りや公園や広場を歩き回り、くぼみや割れ目も全部チェックした。実際のはなし、ぼくは街角でニューヨークと恋に落ちたと言ってもいいぐらいで……今も新しく来た連中には、同じことをやっている。プラザの外で車から降ろして、セントラル・パークを歩かせるのさ。で、そこからイースト・リヴァーやハドソン川、とにかくあらゆるところをね」 「この街に文句を言うニューヨーカーには大勢会ってきたけれど、出て行くやつはひとりもいない! ここは地球で最高の場所だし、もしそれがローマだとしたら、ぼくはウェールズじゃなくてローマに住みたいと思うだろう」