我が国で深く愛される食材ながら、絶滅が危惧されているウナギ。保護のためには「食べ続ける」ことが必要であるという考え方があります。
(アイキャッチ画像提供:PhotoAC)
ウナギは絶滅危惧種!
今年の土用丑の日は7月19日と31日。これらの日に向けて、今年も「ウナギ商戦」が活発化しています。
江戸時代きってのコピーライター平賀源内が考えた「土用丑にはウナギ」の売り文句が数百年以上も生き続けているというのはすごい話で、それだけ我々日本人は夏になるとウナギが食べたくなるのでしょう。

しかし近年この「土用丑のウナギ商戦」は非難を浴びることが多くなっています。その理由はもちろん、ウナギの生息数が激減しているから。
2000年初頭と比べ、ここ数年のウナギの水揚げ量は数分の1程度しかない状態が続いています。ニホンウナギは環境省の指定する絶滅危惧種であり、喫緊の保護が必要とされているにも関わらず、我々日本人は乱獲して食べることをやめません。その最大の理由が「土用丑」にあることは間違いないでしょう。
「食べて守る」のが正解
一般的にある生物が絶滅危惧種に指定されれば、その生物はいったん採捕を慎み、生息数の回復を待つというのが保全における定石です。したがってウナギもいったん食べることを禁止し、生息数が回復した後に再び食べるようにすべきだ、という考え方があります。

しかし先日、長崎大学と北九州市立自然史・歴史博物館から発表された論文では、意外な形によるウナギの保全が提案されています。それはウナギを「食べ続ける」こと。
これは一体どういうことなのでしょうか。
土曜丑は保全のチャンス
ウナギ類が他の絶滅危惧動物と異なっている点の一つに、彼らがいまだ身近な存在であるというものがあります。
ある生物の保全を行うためには、まずその生物に対して「興味を持ってもらう」ということが非常に大切です。一般市民のウナギへの興味をもっとも喚起するものはウナギの「食べ物としての側面」であり、もし仮にウナギの食用が禁止されてしまうと、ウナギへの興味も失われてしまい、結果として保全活動が進まなくなってしまうのではないか、と論文では指摘されています。
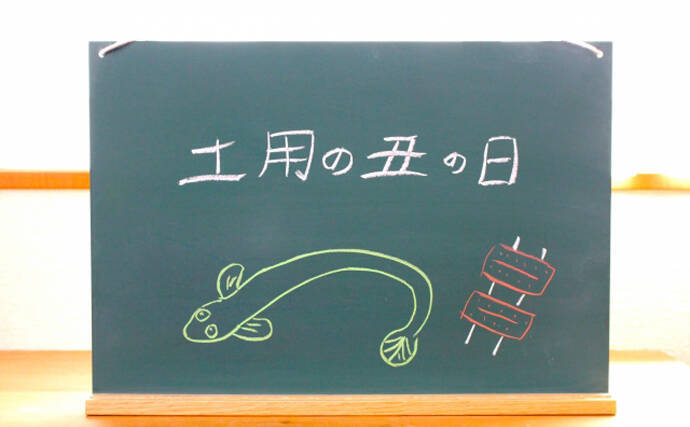
そして「食材としてのウナギ」への興味が最大になるのは、間違いなく土用丑の日です。そのため「ウナギを食べて、ウナギの絶滅を防ごう」という呼びかけがもっとも刺さるのもこの日ということになります。
土用丑が「ウナギ資源を濫用する日」ではなく「ウナギの保全を意識する日」に変わっていくよう、報道の仕方や流通の仕方に変化が起こっていくことが求められています。
<脇本 哲朗/サカナ研究所>
































![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



