追憶の欧州スタジアム紀行(23)連載一覧>>
オールド・トラッフォード(マンチェスター)
「柱谷哲二が語るドーハの悲劇」はこちら>>
1993年11月20日。オールド・トラッフォードを最初に訪れたのは、カタールのドーハで日本代表がアメリカW杯出場を逃した「ドーハの悲劇」の23日後だった。
マンチェスター・ユナイテッド対ウィンブルドン。密閉性の高いスタンドのせいか、あるいは、GKピーター・シュマイケルが投げるボールが、ハーフウェーラインを楽々越えてしまうせいか、オールド・トラッフォードのピッチは、とても狭く感じられた。
スタンドは満員に膨れあがっていたが、観衆は4万4748人だった。当時の収容人員は、現在の6割程度に過ぎなかった。シュマイケルがパントキックを高々と蹴り上げると、ボールは屋根を軽々と越え、上空に飛び出していった。
フィールドプレーヤーで最も異彩を放っていたのはエリック・カントナだ。
しかし、こちらが最もお目当てにしていた当時19歳の選手は、この試合には出場しなかった。ライアン・ギグス。背番号11をつけた左ウイングの雄姿を拝むことができたのは、その半年後だった。
2003年、チャンピオンズリーグ決勝ミラン対ユベントス戦の時のオールド・トラッフォード
1994年4月4日。
マンUは、そのとき2位につけていたブラックバーン・ローヴァースと、わずか2日前にアウェー戦を戦い、敗れていた。6あった両者の勝ち点差は3に詰まっていた。
選手入場の行進曲はビル・コンティの『ロッキーのテーマ』で、続いてクイーンの『ウィ・アー・ザ・チャンピオン』が流れると、オールド・トラッフォードは万雷の拍手に包まれた。スタンドはオヤジだらけ。女性はもちろん子供の姿を見かけることもほとんどない。
出場メンバーのアナウンスが始まるとオヤジたちは、紹介される選手の名前に合わせ、「ヘイ! ヘイ!」と、小気味よいテンポで合いの手を入れる。若さを振り絞るように。応援フラッグはない。
布陣は4-4-2。マイボールに転じると2-4-4に変化する。マンUの先制点は前半17分。ポール・インスのクロスボールを、左ウイングのギグスがヘディングで合わせた得点だった。
左にギグス。右には、アンドレイ・カンチェルスキスというウクライナ出身のロシア代表選手を配していた。
筆者が両ウイングを置くサッカーに好意的になる理由は、その昔、放送されていた名物サッカー番組『ダイヤモンド・サッカー』でお茶の間観戦したマンチェスター・ユナイテッドに起因する。ゴードン・ヒルとスティーブ・コッペルが両翼を張る、70年代のある時代のサッカーになるが、この時のギグスとカンチェルスキスも彼らと同様、こちらを虜にした。
ギグスは左利き。
ギグスの折り返しがアシストになった3点目のゴールは、8割方、オフサイドのように見えた。バックラインの背後を抜けだしたギグスにパスが出た瞬間である。しかし副審は、オフサイドフラッグを挙げなかった。挙げられなかったと言うべきだろう。正面スタンドに座る観衆が発露する殺気を、目一杯、背中に浴びていたからだ。副審が流さざるを得ないこの状況を作り出すオールド・トラッフォードの観衆に、ファン気質の真髄を見た気がした。
ギグスは終了間際にもドリブルで数十メートル前進し、決定的なチャンスを演出した。低い重心のフォームから、ボールを1回1回引きずるようにドリブルで前進すると、観衆は一斉に身を乗り出すのだった。
マンチェスター・ピカデリー駅からメトロリンクで、クリケットグラウンド脇にある駅まで15分~20分程度。試合日に限り、マンチェスター・ピカデリー駅からスタジアム駅直行の電車も運行されている。鹿島神宮駅から鹿島スタジアムに向かう電車のようなものだが、鹿島スタジアム駅がスタジアムから何百メートルか離れているのに対し、オールド・トラッフォード駅は正面スタンドのほぼ真横。数十メートルという近距離にある。
「ギグスと優勝を喜ぶ香川真司」はこちら>>
あまりにも近いので、スタジアム界隈の雰囲気を味わうなら、10分ほど歩くことになるメトロリンクを利用した方がいいのかもしれない。
スタジアムはユーロ1996開催にともない、1995年、約5万5000人収容のスタンドに改築。さらに2006年の改築では、約2万人増の7万5000人収容のスタンドに巨大化した。
その背景には、海外からの観戦旅行者が増えたことがある。加えて、女性や子供も取り込もうとした。オールド・トラッフォードは健全な娯楽施設へと様変わりした。
1993年に初めて訪問した時、少々危なっかしい雰囲気だった。
「禁煙」と書かれてあるのに煙草の煙がもくもくと立ちこめる不健全な場所。オールド・トラッフォードの正面スタンド階下にあるトンネル付近を歩けば、その暗闇にはいかにも人相の悪そうな人が、なんとも言えない視線を投げかけてくるのだった。スタジアムの売店で買ったチーズバーガーをひと口、口にした瞬間、口内に石油のような臭みが広がったことを覚えている。
だが、スタジアムが健全な娯楽施設になればなるほど、かつて漂っていた殺気は薄まっていった。熱烈なファンが占める割合が100%でなくなったことと、それは大きな関係がある。観光客というお客さんの割合が増せば増すほど熱は下がる。スタンドが大きくなりすぎてしまったことで消えてしまったものが垣間見える。
イングランドが開催したユーロ1996では、準決勝のフランス対チェコをはじめ5試合を行なっている。また、UEFA選定のカテゴリー4のスタジアムとして、チャンピオンズリーグ(CL)決勝も開催している。2003-04シーズンのミラン対ユベントス。イタリア勢同士で初めて決勝を争った一戦だ。
0-0、延長PKの末にミランがユベントスに勝利した試合だが、こちらの記憶の中では、CL決勝戦の中で最もつまらなかった一戦として刻まれている。CLになって28年。後にも先にも0-0の決勝はこの試合のみだ。
0-0の中にも面白い試合はある。だが、このミラン対ユベントスは、考えられる範囲において最も退屈な0-0だった。両チームとも攻めなかったからだ。マイボールに転じても、攻めの機会を意図的に放棄していた。
こちらもピッチの試合から幾度も目を離していた。そして延長戦のスタンドに目をやれば、寝ている観客が何人も目に止まった。これもCL観戦史上初の出来事だった。
これまでオールド・トラッフォードで観戦した中で、最も脳裏に焼き付いているプレーは何か。ギグスのドリブルと言いたいところだが、同じ左利きでも、ドリブラーではない選手のドリブルになる。
2000年4月19日。CL準々決勝第2戦で、魅せたのはレアル・マドリードのキャプテン、フェルナンド・レドンドだった。魔術と言いたくなるドリブルを披露したのは後半7分。バックスタンドのタッチライン際だった。
3-3-3-1のアンカーは、トレードマークである金髪のロングヘアをなびかせながら、そのタッチライン際を疾走した。どちらかと言えば深い位置でボールを配球する左利きのパッサーだ。左ウイングのポジションに進出し、相手の右サイドバックに1対1を仕掛ける姿は、意外というか、見慣れぬ光景だった。
そこでレドンドは、左足のかかとに近いインサイドで、立ち足である右足の後ろからグイと押し出すと、ボールは対峙するノルウェー代表、ヘニング・ベルグの背中を通過していった。「あっち向いてホイ」が決まった瞬間とでも言おうか。ベルグがボールを見失う間に、レドンドはゴールライン際まで進出。えぐるような動きから、中を走るラウル・ゴンサレスに左足で丁寧なラストパスを供給した。
ドリブル&フェイント&ラストパスが、これほど鮮やかに決まるケースも珍しい。決めた選手が貴公子然とした、格好のいい選手であることも輪を掛けた。
筆者はそのちょうど2年前、レドンドにインタビューをしていた。アルゼンチン代表として、1998年フランスW杯に出場するのか、しないのかについて。時のアルゼンチン代表監督ダニエル・パサレラはレドンドに、「長髪を切らなければ招集しない」と、前時代的な要求を突きつけてきた。
レドンドはこちらに、髪の毛を切るつもりはないことと、その理由や正統性について、極めて理路整然と語った。日本人、外国人、サッカー選手、サッカー以外のアスリートにかかわらず、これまでインタビューした中で、最も知的な選手だった。
1999-00シーズン。レドンド率いるレアル・マドリードは、CL決勝でバレンシアを破り、優勝した。レドンドはこの後、ミランに移籍したが、右足靱帯を断裂。ベストフォームに戻れないまま引退した。オールド・トラッフォードで行なわれたCL準々決勝で、レドンドがベルグを鮮やかにかわした時、その何カ月か後の彼の姿を想像した人はいただろうか。
ケガで引退に追い込まれたサッカー選手は数多いが、レドンドほど惜しまれながら引退した選手も珍しい。




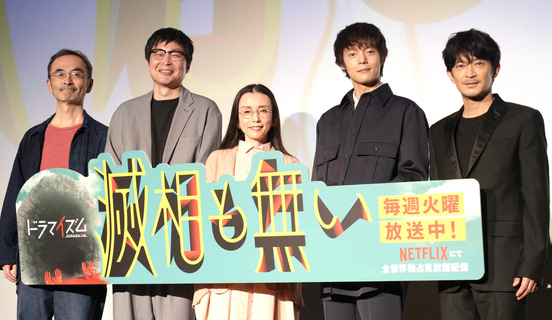















![SOCCER KING (サッカーキング) 2024年 05月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51MCp6KVXfL._SL500_.jpg)
![ワールドサッカーダイジェスト 2024年 4/18 号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61QJZ9yLiNL._SL500_.jpg)
![[アディダス] GALAXY 6 M 陸上 ランニング シューズ ランニングシューズ GW3848 (GW3848) コアブラック 255](https://m.media-amazon.com/images/I/31oXlPpokKL._SL500_.jpg)
![[アンダーアーマー] テック ショートスリーブ Tシャツ(トレーニング) 1358553 メンズ 409 日本 LG (日本サイズL相当)](https://m.media-amazon.com/images/I/41x7vG7Z7oL._SL500_.jpg)
![[アンダーアーマー] テック グラフィックショーツ(トレーニング) 1358551 メンズ 001 日本 XXL (日本サイズ3L相当)](https://m.media-amazon.com/images/I/31xDHubpH2L._SL500_.jpg)

![[ミズノ] フットサルシューズ モナルシーダ NEO SALA CLUB IN ブラック/ブラック 26.5 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/41Mw0p4yfEL._SL500_.jpg)
![[ミズノ] フットサルシューズ モナルシーダ NEO SALA CLUB TF ブラック/ブラック 25.5 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/41aLOC+irUL._SL500_.jpg)


