【短期連載】令和の投手育成論 第6回
第5回はこちら>>
今季のプロ野球で開幕投手を務めた12人のうち、甲子園出場歴を持つのは7人。高橋光成(西武)、北山亘基(日本ハム)、藤浪晋太郎(阪神)、小川泰弘(ヤクルト)、大野雄大(中日)、東克樹(DeNA)、大瀬良大地(広島)だ。
対して山本由伸(オリックス)、千賀滉大(ソフトバンク)、菅野智之(巨人)は国際大会で「日本のエース」と言われた実力者だが、いずれも甲子園とは縁がない。
全体的に強豪私学の出身者が多いなか、小川と千賀、石川歩(ロッテ)、則本昂大(楽天)は公立高校から成り上がった。
高校時代はまったくの無名だったソフトバンク・千賀滉大
以上を踏まえると、スケールの大きな投手を育てるという意味で、甲子園は必ずしも直結しているわけではない。
ただし現実的に見ると、注目の集まる大舞台は学校の名をアピールする格好の場で、とりわけ私学には経営面への影響も大きい。少子化時代の生徒集めにおいて、広告塔となる選手の獲得競争は熾烈さを増すばかりだ。
メディアにとっても数字を稼げるコンテンツで、ドラフト候補にスポットライトを当てることはもちろん、「スーパー1年生」や「スーパー中学生」と"スター・システム"の対象になる選手は若年化している。
スカウトへのアピール
中学生の立場から見ると、全国大会を狙える高校は設備や指導者などに恵まれ、野球人生をより切り拓きやすい環境に映るだろう。憧れの地でプレーするチャンスも高まり、プロのスカウトの目に留まる機会も多い。さらに、大学進学に有利に働く側面もある。
子どもたちの野球には、大人たちの思惑も複雑に絡み合っているのだ。
岡山大学整形外科の島村安則医師は以上のような事情も頭に入れ、野球少年の診療にあたっている。
「故障しないようにすることはもちろん大事ですが、野球には別要素もあります。
島村医師は子どもたちの野球ヒジに対する啓蒙活動を長らく行なってきた一方、近年の育成環境は「過保護すぎる」とも感じている。極論を言えば、多少の痛みで登板回避するのは"機会損失"になるからだ。
「カッコよく言うと、(テレビドラマ『ドクターX』の)米倉涼子的に行きます。『やれよ』と。『最後は手術で戻すから。私は失敗しないので』と言います」
中高生がトミー・ジョン手術に至るような事態は避けるべきだが、最悪、メスを入れて救うことはできる。故障を恐れて勝負の舞台に立たなければ、ただチャンスを逃すことにもなりかねない。
「痛い」と言える環境づくり
"投げすぎ"と"投げなさすぎ"の間で絶妙なバランスをとるには、監督やコーチが一定の医学知識を持つ必要がある。島村医師とコンビを組む高島誠トレーナーはそう指摘する。
「現場の指導者は選手の既往歴から把握し、『この子はいつか故障する可能性もある』と頭に入れておくことが大事です。そのうえで重要なのはドクター選び。適切なアドバイスをもらえれば、『中3から高校生になる前にオペをはさみましょう』とか『手術はせずにいけそう』とか、総合的な判断がしやすくなります。『しばらく様子を見よう』では、治らないケガがある。一方で『ヒジのせいで野球人生が終わってしまった......』とならないようにしないといけない」
選手にとって不可欠なのが、周囲との適切な関係づくりだ。
「周りが『投げすぎ』と過剰に気にするのではなく、選手自身が『痛い』と言える環境をつくってあげることのほうが大事だと思います。本当にヤバイ時は無理しないという選択がとれるように。だからといって、大事なタイミングで投げられないのでは『ちょっと頼りない選手』となってしまいます」
"投げすぎ問題"で記憶に新しいのが、今春のセンバツで準優勝した近江高校のエース・山田陽翔だ。1回戦から4試合連続完投で、準決勝の翌日に行なわれた決勝でも先発マウンドに上がった。多賀章仁監督は「彼の将来を見た時に間違いだった」と反省したが、少なくとも山田自身は降板のサインを送ってマウンドをあとにしている。
投げ込み文化が根強い日本では、"投げすぎ"問題はなかなか決着がつかないテーマだ。現役時代に2度の最多勝を獲得した一方、トミー・ジョン手術を含めて5回メスを入れた元中日の吉見一起は自身の経験を踏まえてこう語る。
「僕は輝いた年もケガをした年も両方経験できて、プロ野球を終えました。そのなかで子どもたちに伝えるのは、『やっぱり元気じゃないと野球はできない』ということ。レギュラーになる・ならない、勝つ・負ける、打つ・打たないはもちろん大事だけど、それ以前に体が元気じゃないといけない」
自分を知ることの重要性
吉見の転機になったのは、鴻江寿治トレーナーとの出会いだった。中日のチームメイトだった井端弘和に紹介されて2009年から体のケアをしてもらい、2011年から骨盤の使い方など投げ方の指導も受け始めた。この年には18勝3敗で2度目の最多勝に輝いている。
その裏にあったのが意識改革だ。
「以前は『寝れば投げられる』という感じで、その程度の知識しかなかったです。それが鴻江さんと出会ってから、今日投げたあとに自分の体がどういう状態かを伝えなくてはいけなくなり、体に興味を持つようになりました。鴻江さんが見た僕の体と、自分の感覚のズレもあるだろうし。それを伝える責任もあったので」
吉見が今の高校球児に「ちょっとは無理することも必要」と思うのも、こうした点に通じている。昨年のセンバツを見に行った際、140、150、160球と投げる投手がたくさんいて、それほど球数がかさむことに疑問を抱いたという。
「単純計算で、ヒットを10本打たれて無四球でアウト27個だったら打者37人。1人につき1球減らしたら、37球減るわけです。ただ投げるだけではなく、どうやったら球数を減らせられるかと考えて投げたら、また違った野球が見えてくると思うんですよね」
以上を実践するのは難しいだろうが、試行錯誤する過程で投手として成長できる。そのためにはある程度投げることも必要だ。指導者が球数を過剰に気にして起用すると、そうした機会まで失われかねない。
大事なのは、身体や感覚を含めて"自分"を知ることだ。吉見がそう気づくことができたのは、プロの世界に飛び込んで以降だった。
「投げることによって体がこうなるとわかれば、『じゃあケアしよう』となると思います。(プロ入り前の)トヨタ自動車時代に『胸を開け』と言われて、その理由も説明してもらったと思いますが、頭に入ってないんですよね。でも、ケガをしてから気づけました」
予防とケアでパフォーマンス向上
吉見は少年野球をしている息子に、投げた日の夜はストレッチポールの上で胸郭のストレッチをさせている。インナーマッスルに刺激を入れ、血流をよくして回復を早めるためだ。
「胸を閉じて投げるのか、常に開いているかで張りも変わってきます。それはプロに入ってから知ったことです。投げ方は"クセ"なのでなかなか変わらないと思うけど、胸郭や手首のストレッチは誰でもできます。『投げ終わったあとにこういうメニューをやろう』とチームで決めごとにしておけば、いつか習慣になるはず。そうやって自分でできることを知っていくのが大事だと思います」
胸郭をうまく使えれば、ヒジへのストレスを減らせると同時により強い球を投げられるようになる。結果、投球パフォーマンスも改善される。高島トレーナーは、そうした視点を持つことが大切だと説く。
「ケガの予防がうまくいけば、パフォーマンスは上がります。目指したいのはそこです。同じ100球を投げたとしても、ヒジへのストレス値が高い選手は、球の質が早く落ちてくるから終盤につかまりやすい。そういった観点を持ってもらえると、『ケガを隠しているようでは試合でいいピッチングをできないから、よくないよね』という考え方になると思います」
球数制限で防げる故障もあるが、その視点だけでは抜け落ちるものもある。重要なのは、両面を知ったうえで個々の最適解を探っていくことだ。
メジャーリーグでは日本のようにブルペンで100球も投げることはないが、あまり伝えられていない一面もある。高島トレーナーはワシントン・ナショナルズで働いた際、アメリカ流のアプローチを知った。
「ブルペンではそれほど投げないけど、フラットピッチで投げる選手は多いです。『力を入れてたくさん投げなさい』ではなく、キャッチボールとか力まないなかで感覚をつくる作業は大事だと思います。数だけを決められると"数をこなす"になりがちですが、中身が伴ってほしい」
なぜ、"投げすぎ問題"が議論の的になるのか----。
くしくも高校野球の「1週間に500球以内」という規定の有効性に"答え"が出た今、あらためて野球関係者はこの問いと向き合うべきだ。
第7回につづく
(一部敬称略)




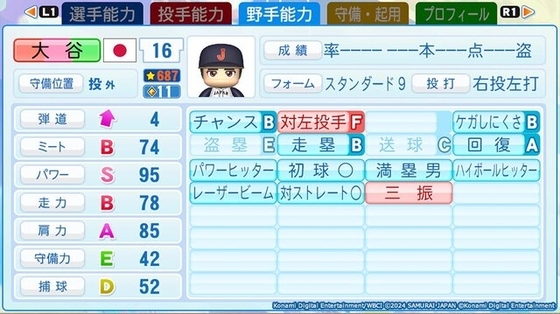




























![大学野球2024春季リーグ展望号 2024年 4/28 号 [雑誌]: 週刊ベースボール 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/61hmnOC4OHL._SL500_.jpg)

![報知高校野球 2024年 05 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61yEaBsfq9L._SL500_.jpg)

![[エスエスケイ] MM23 SBB4037 ブラック×レッド (9020) 84cm](https://m.media-amazon.com/images/I/21ObKcobBFL._SL500_.jpg)




![【メーカー特典あり】プロローグ(特典:ロゴステッカー付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/31gi5M5UkOL._SL500_.jpg)