宮崎監督の下でアニメーターとして初期6話分の作業に携わった友永和秀さんに当時の話を聞いた。
[取材・構成:藤津亮太、沖本茂義]
『名探偵ホームズ 』Blu-rayBOX
https://www.bandaivisual.co.jp/cont/item/BCXA-0908
■ 近藤さんの絵にはかなわない
―友永さんはテレコム(・アニメーションフィルム)の一員として『名探偵ホームズ』の立ち上げから携わられています。当時の雰囲気を教えてください。
友永和秀(以下、友永)
もともとイタリアの持ちこみ企画で、向こうのデザインはグラフィックといいますか、『ピンク・パンサー』のような平面的なデザインでした。ところが、宮崎さんはそれを気に入らなかった。漫画映画っぽい絵柄で、平面的的ではなく現実的な空間を描きたいと。先方と相当揉めましたけどね(笑)。
でもこちらとしては宮崎さんの準備だからそうなるだろうと思っていたところがあって。それで宮崎さんと近藤(喜文)さんがやりとりをしながらキャラクターを作り上げていくのを見つつ、そのデザインを借りてイメージボードを描くところから作業を始めました。
―イメージボードはBD-BOXにも収録されていますが、かなりの数描かれています。
友永
当時のロンドンの写真というのがなかなか手に入らなかったものですから、ブリティッシュ・カウンシル(英国の公的な国際交流機関)に行っていろんな資料をコピーしてきました。そういう資料を見ながら、こんなシーンがあったら面白いだろうと想像していろいろ描いていったんです。宮崎さん、近藤さん、それから富沢(信雄)さん、丹内(司)さん、それに僕で描きました。
原作だと、ホームズが薬物を使うシーンもありますよね。アニメも最初はもうちょっとシリアスで、貧富の差も含めた当時のイギリスの光と影を盛り込もうという方向性もあったんです。僕もそういう部分があるといいなと思いながら準備をしていました。最終的には、もっとあっけらかんとした感じになりましたが。
―近藤さんは当時、どんな感じで『ホームズ』に携わられていたのでしょうか。
友永
どういう作品にすればよいのか、そういう宮崎さんの話には、近藤さんが付き合っていた印象があります。近藤さんの影響やサジェッションも大きかったのではないかと思いますね。近藤さんは、『赤毛のアン』などの印象が強い方も多いと思うんですが、ギャグっぽいも作画もすごくうまく、描くスタイルにとても幅がある方でした。
その一方で、児童文学や社会問題にも関心を持っていた。
■ 『コナン』『カリオストロの城』を経てテレコムに
―トッドとスマイリーは、近藤(喜文)さんと友永さんがモデルだと言われていますね。
―友永
そういう話が流布しているようですね(笑)。宮崎さんはよく周りの人をキャラクターに取り入れていました。たとえば『ルパン三世 カリオストロの城』でルパンたちがスパゲッティ食べている時にやってくるウエィトレス、あの人にもモデルがいるんですよ。『ホームズ』のころの僕はもう少し小太りだったので、宮崎さんからするとキャラの対比が面白かったんでしょうね。
―宮崎さんとの関わりは『未来少年コナン』からでしょうか。
―友永
そうですね。それまではオープロダクションに所属して東映(動画。現・東映アニメーション)のロボットアニメなどの原画をずっとやっていました。ロボットものとはいいつつ、キャラクターデザイン・作画監督などをやられていた小松原(一男)さんも昔のAプロダクションの影響を受けていたりするので、脇のキャラクターには結構、Aプロっぽい要素を取り入れたりしていたんです。だからメカシーンを描く一方で、そういうキャラについてはAプロ的な動きを真似したりしていたんです。
一方、実際にAプロにいた宮崎さんや大塚(康生)さんの仕事についてはずっと外から眺めているだけでした。それでオープロが『コナン』をやるときに、「手伝わせてもらえませんか」とお願いして一緒に仕事をさせてもらったんです。
―なるほど。そしてその後、テレコムで『カリオストロの城』に参加されます。
―友永
『カリオストロの城』のときは、まだオープロ所属で出向でした。テレコムはもともと、東京ムービーの藤岡(豊)社長が、「日本のTVのような小さいビジネスではなく、アメリカに大きく打って出るんだ」と設立した会社です。
そこで現場の叩き上げのスタッフが必要ということで、大塚さんが日本アニメーションにいた富沢さんをはじめ、Aプロ、シンエイ動画、オープロなどから、『コナン』で頼りになった人をどんどん誘ったんです。僕もそのときに誘われてテレコムに出向して、その後、テレコム所属になりました。
■ とにかく絵を動かしたい
―’70年代後半から’80年代初頭のテレコムは今振り返ってもホットな場所だったと思います。
―友永
そうでしょうね。宮崎さん、大塚さんらを筆頭に、みんな「新しい長編アニメをつくるんだ」と息巻いてましたから。僕もオープロにいたとき、「そんな会社ができるんだ、行きたいな」と思っていたぐらいで。
もともと動かすことが大好きで、たとえば東映の長編アニメーション『どうぶつ宝島』や『長靴をはいた猫』、『空飛ぶゆうれい船』のように、とにかく動かしたかった。テレビの3コマアニメより、劇場長編で枚数を気にせず描いてみたい。もっと動きを描きたい、そういう想いが人一倍ありました。『ホームズ』も宮崎さんがつくるということで「思う存分やれるぞ!」と(笑)。
―描いたイメージボードの中で本編に採用されたものはあったんでしょうか。
―友永
具体的にはないですが、戦艦を描きたいっていたので、『海底の財宝』(放送第9話)は、そういう話をつくってくれたかなと思いました。印象深いという意味でも『海底の財宝』の戦艦のシーンはよく覚えています。
―戦艦もさることながら、その上に水兵が鈴なりになるシーンにインパクトがありました。
―友永
東映時代から、宮崎さんが描くようなモブシーンは、いつかやってみたいなと思っていたので、それはもう力が入りました(笑)。先日、この戦艦シーンを観直す機会があったのですが、「よくこんなもん描いたな」と自分でも驚いてしまいました(笑)。今では、とてもじゃないけど描けないです。アニメーターは、運動選手と同じで、常に描いていないと、どんなに上手い人でも描けなくなってしまう。そういう体力の部分と、「描きたい」というモチベーションの両方が重要なんです。戦艦のシーンは、モチベーションに加えて体力にモノを言わせて描いた結果ですね(笑)。若かったんですねェ~。
―当時の印象として、『ホームズ』は昔ながらの漫画映画風でありながら、リアル志向というか画面の情報量が多いなと感じました。
―友永
そうでしょうね。
ただ、実際には宮崎さんが要求する及第点を取るのが精一杯でしたが……。たぶん近藤さんだったらそれ以上のものを出されたんでしょうけれど。
後編に続く
『名探偵ホームズ』 Blu-ray BOX
https://www.bandaivisual.co.jp/cont/item/BCXA-0908





















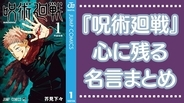
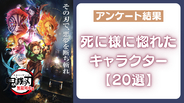






![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








