西暦と呼ばれる時代が終わり、人類はナノマシンが組み込まれた遺伝子を持つナノ種(ナノレース)と純粋な人間・ピュア種(ピュアレース)の2種族に別れていた。そこは特殊能力を持つナノ種がピュア種に管理される世界。ナノ種であり伝説のハンター“レッドアッシュ”の異名を持つ少年ベックは、相棒のタイガーと共にトレジャーハンティングで生計を立てていた。ある時、ひとりの少女がふたりの車に逃げ込んできて、追手の3人組と大騒動を巻き起こす――。
監督はSTUDIO 4℃のCG部門で活躍するCGアニメーターの佐野雄太氏。初監督作品として、STUDIO 4℃初となるフル3DCG作品『RedAsh -GEARWORLD-』を手がける。制作現場をマネジメントしパートナーとして活躍した久江由華プロデューサーにも同席いただき、本作にかけた思いや育成面でどのような工夫を凝らしたのかなど、じっくりとうかがった。
[取材・構成:細川洋平]
――まずはSTUDIO4℃さんが、あにめたまご2017に参加された経緯を教えてください。
佐野雄太監督(以下、佐野)
STUDIO4℃がこのプロジェクトに参加するのはアニメミライ2014 『黒の栖‐クロノス‐』、あにめたまご2016『UTOPA』に続き今回で3回目になります。先の二回ではそれぞれ若手作画スタッフの教育に勤めました。
その中で昨年、武右ェ門さんのCG作品である『風の又三郎』を見て、弊社もCG班の教育をしたいと応募に至りました。
――佐野監督のご参加はいつ頃だったのでしょうか。
佐野
あにめたまごの参加を決めたのは社長の田中(栄子)プロデューサーですが、この『RedAsh』という企画自体はそれより前から進んでいました。フル3DCGを前提に、内容の打ち合わせを繰り返していて、時期的にちょうどあにめたまごの応募と重なっていたので、田中社長から「じゃあ出してみようか」と。作品自体もともと大きな構想だったので、あにめたまご用にまとめるのはかなり苦労しましたね。『RedAsh』はSTUDIO4℃的にもチャレンジの作品だったんです。そこに若手教育も、というのは正直無理じゃないかと最初は思いました。
――「チャレンジ」とはどういったところでしょう?
佐野
「フル3DCG作品」ということです。ウチはもともと作画スタジオなので、『ベルセルク 黄金時代篇』(劇場3部作)にしても『ハーモニー』にしてもCGは作画の補助的なスタンスでした。CGのルックも今までなら輪郭線を付けてベタ塗りするいわゆる作画調にしていたところを、今回は輪郭線をなくして塗りは質感のあるテクスチャを使っています。
――チャレンジに加えて“育成”を両立させる必要があるかと思いますが、育成用にチューニングするという考えはありましたか?
佐野
最初は悩みましたけど、そもそも弊社は、常に新しい表現を模索しているようなスタジオなので、あにめたまごだからと教育に適した作品を選んでも、その後の仕事で経験を活かせないのでは、やる意味がないと思うんです。だからスタジオが本当に作りたいものの中で教育していこうと考えました。
――ルックのコンセプトはどのようなものですか?
佐野
イラストが動いているようなものにしたいと思っていました。
――シナリオは大河内一楼さんが担当されていますね。
佐野
『ベルセルク』でもお世話になっていましたのでお名前はずいぶん前から挙がっていたんですが、大河内さんのご都合がなかなかつかず、ご参加が正式に決定したのが4月前後。新しいチャレンジでも、ストーリーを含め“骨格”がしっかりしてれば安心だろう、ということでお願いしました。
――キャラクター制作についてもお聞かせください。作画であれば描けばできあがり、という作業でも、CGではキャラクターモデリングが必要です。この辺りのスケジューリングはどのようにされたのでしょうか。
佐野
モデリングは1体に5日~10日くらいかけて作ってはリテイクして進めていきました。最初、正面からのイメージイラストしかなかったので、それを3Dにするためにモデリング用の3面図をCG班で作っていきました。
作画だったらキャラクターデザインありきでスタートするものですが、この作品はアニメーション(※)を作りながらモデルがどんどん最新版に更新されていき、最終的なルックが決まったのはアニメーション作業が終わってからでした。
(※アニメーション:この場合「演技付け/動き付け」を意味する)
――若手アニメーターさんにモデリングを担当させたりしたのでしょうか。
佐野
若手にはアニメーション部分だけをやってもらっています。
――今回CGモデルを作るに当たって注意したところは?
佐野
動きに特化したシンプルなモデルを目指しました。最近の傾向ではゲームなどでもCGで甲冑とか、すごくたくさん身につけていますよね。でもCGアニメーターが演技をさせようとすると、めり込み(※)を注意しなくてはいけないんです。だから装飾品を少なくして動かしやすいモデルとしました。アニメーションの勉強に適したリグ(※)になっていると思います。
(※めり込み:体にオブジェクトがめり込んでしまう)
(※リグ:3DCGモデルを動かす為のシステム)
――美術面では、『キルラキル』や『ブブキ・ブランキ』の美術監督を務められた金子雄司さんが担当されています。
佐野
久江プロデューサーのおかげですね。いろんなところに声をかけてくれて金子さんにお願いすることになりました。
久江由華プロデューサー(以下、久江)
美術設定は絵コンテを担当したアニメーターに起こしてもらったのですが、美術ボードは金子さんに仕上げてもらいました。美術設定などが揃ってきた当初から、金子さんには声をかけたいと思っていたのでこの作品を面白がってくれて引き受けてくれる事が決まった時は、この作品の完成が楽しみになりました。
佐野
背景まで全てフル3DCGのシーンがあるんですが、当初は美術で描いたものと3DCGのギャップが大きくなるんじゃないかと不安でした。
――アニメーションの方向性についてもうかがいたいのですが、本作はフルアニメーションとリミテッドアニメーション、どちらの方に寄せて制作されたのでしょうか。
佐野
3コマ打ちをベースに、と考えていました。そのため、レイアウトは作画監督の清水保行さんを中心に作画で描いてもらいました。3Dでは以降の過程でもカメラを動かせてしまうのでレイアウトに対するに意識が希薄になりがちです。作画の方にお願いするとやはり絵がバッチリ決まりますね。それは大切にしていきたいと思っていて、教育としても伝えていこうと思いました。ものの配置や構図の重要性を学ぶことにもなりますから。
とはいえ、作画でできるような作品にはしたくないという思いがあるんです。なにしろ自分はCGに魅力を感じてこの業界にいますから。できるだけCGならではの表現になるように心がけています。
――育成の面でもうかがいたいのですが、若手CGアニメーターさんたちはどこまでを担当されたのでしょう。
佐野
アニメーション(演技)部分をお願いしました。CGは作画のように原画と動画で分けることができないので、担当カットの演技は全て彼らに任せています。ただ、みんな本当にキャリアが浅い子ばかりなので、まずはイメージポーズというものを各カットで描かせました。
――イメージポーズ、ですか。
佐野
各シーンのアニメーション(演技)の打ち合わせをしたあと、各自でイメージしたレイアウトを紙に描いてもらうんです。やはり背景やパースの描き方で悩むんです。CG畑の人はすぐ3Dソフトで確認しようとするんですけど、「それはダメだよ」と(笑)。CGは嘘をつきませんが、CGの計算や事実だけで作ったものにしたくなかった。アニメは本当のことだけを描いているわけではないんです。「こう見せたい!」という思いが大切で、そのことをちゃんとわかってもらいたかったんですね。そうして描いたイメージポーズを、清水さんの描いたレイアウトと見比べて答え合わせをしてもらう。
――若手CGアニメーターさんは全員STUDIO4℃所属なのでしょうか。
佐野
全員所属です。6人中5人が去年(2016年)に入った若手で、もうひとりも2015年入社。あにめたまごの規定では「原画経験が3ヶ月から3年」とのことでしたが、ウチのスタッフはほとんどが3ヶ月でした。作画は原画になるまでに下積み期間があるので、CGスタッフに比べて現場の経験はありますよね。一方、CGはソフトの関係上、原画からスタートになるのでそれぞれ経験は3ヶ月ではありますが、実際は全然違うんですよ。
――育成で苦労した点というのはありますか?
佐野
そうですね。今回は制作に入る前に教育カリキュラムを作って臨みました。行けると思ったんですけど、実際は人によって感じ方が全然違った。理論的な子、感覚的な子とそれぞれいて、ひとりひとりに合わせて微調整していったところは苦労した点かもしれません。でも人はみんな違うというのは教育するうえで当然のことかなと思っています。もともと僕は教員をやっていたので、その経験も活かせましたし教えるのも好きなタイプなんです。日本のCG業界はまだ教育面が未熟だと思っていたので、こういう機会があってよかったですね。
――育成で意識したところはどういったところだったのでしょうか。
佐野
理論をキチンと叩き込む、ということです。ベテランの作画スタッフだと、たとえ言葉で説明できなくても、実はしっかりとした理論を持っているものなんです。キャラクターが立つ、走る、といった絵には動きの原理があってそれを落とし込んで描いている。でなければ原画になれないですから。でも3Dの場合は何もわからなくてもモデルがあれば動かせてしまう。そのぶん、言葉で理論を叩き込まないとちゃんとしたアニメーターにならないので、普段から「ただ動いているものとアニメーションは違う」と教えていました。ある程度理論を伝えたら、実戦させてつまづいたらまた理論に戻る。そういうやり方をして理論と技術の感覚を繋げていきました。
――人はそれぞれ違う、という話から発展させて伺いたいのですが、例えば手描きだとそれぞれの個性というのがどうしても出てきて、逆にそれが味になったりします。若手CGアニメーターさんの個性というのはどこからか感じ取れるものなのでしょうか。
佐野
そこは面白いところで、やっぱり個性はすごく見えてきますね。同じモデルを使っているからこそ、動きで個性が浮き彫りになってくる。しかも今回は、各自が自分の動きをビデオ撮影して演技の参考にしました。まず演技プランを立てて、僕のチェックでOKが出たら、シューティングルーム(撮影用の部屋)で撮影、それを元にアニメーションを付けていく。するとどんどん本人に近づいていきますし、ダイナミックな動きにこだわる人とか、手のちょっとした動きにこだわる人とか、人によって全然違ってくるんです。ディズニーの3Dアニメを見てても「この動きを作ったのはあの人だろうな」とやっぱりわかってくる。それと同じですね。
――若手CGアニメーターさんたちの成長は実感しましたか?
佐野
ものすごく成長したと思います。動きもかなりよくできていて、作画監督の清水さんも「これだけの動きはそう簡単には作れないよ」と言うくらいです。そんなCGアニメーターが6人も揃ったCGスタジオは中々ないと思います。みんなものすごく頑張ってくれましたね。
――通常の制作現場とスケジュール感の違いなどはありましたか?
佐野
『RedAsh』で若手の子たちは原画と動画をやっているのでスケジュールとして楽ではなかったですし、僕が妥協せずかなり細かくクオリティーも見ていたので大変だったと思います。この作品をやりきったことで、充分タフになっていますし、他の現場でも動じずやっていけると思います。実際、もうすでに次の現場に入ってバリバリやっている子たちもいるので、すごいなと感心しています(笑)。
――作品を見る人にどのあたりを注目してほしいですか?
久江
細かいところまで作り込まれているキャラクター達の演技ですね。一コマ一コマこだわって作った手付けアニメーションですので、機会があったらコマ送りで見ても面白いと思います。それから、Koji Nakamuraさんに作曲して頂いた音楽も物語の展開に合わせて変化していくので楽しみにしていてください。
佐野
作画の場合、絵として活き活きと描かれているものですが、CGは逆にコマ送りにしたときに絵が死んでいるように見えたりするんですよね。でも今回はそういうことがないように若手の子たちが頑張って作ってくれているのでCGでは珍しいくらいキャラクターが活き活きとして見えるんじゃないかなと思います。ぜひ注目して下さい。
――ありがとうございます。最後に読者へメッセージをお願いします。
佐野
人類がナノレースとピュアレースというふたつの種族に別れた世界に生きる、ベックとタイガーというふたりのハンターの物語です。そのふたりのところに、家出をしたコールという女の子が加わって……という作品です。子どもが見ても面白いアニメーションにしたいという思いで作ったので、純粋に楽しめるアクションやコメディを見ていただきたいです。物語的にはまだまだその先を予感させて終わるので、今後の展開も広げていければなと考えています。STUDIO4℃が作る新感覚のアニメーション、ぜひお楽しみください。
























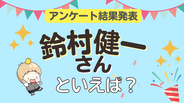



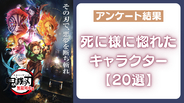

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








