アニメ!アニメ!では初めて作品に触れる人、またはファンだけど忘れてしまったという方のために「『Fate』今さら聞けない“聖杯戦争”」の短期連載をスタート。前回掲載した「『Fate』今さら聞けない“聖杯戦争”―第1回 知っておきたい歴史や基本的なルールを解説」に続き、第2回目では聖杯戦争の成り立ちや御三家の関係を解説する。
※『Fate/stay night』基準の内容なので、他シリーズの聖杯戦争とは内容が異なる部分も含まれます。
※分かりやすく説明するために、砕けた表現をしています。
◆そもそも聖杯とは?
聖杯とは、キリスト教に関する伝説などで登場する聖遺物のこと。「最後の晩餐」で使われたとされるものが有名で、そのほかアーサー王伝説にも聖杯を求めた冒険譚が書かれている。「聖杯戦争」では手に入れれば願いが叶うものとして登場している。
「聖杯戦争」のシステムでは、大聖杯と小聖杯の2つが存在する。大聖杯は土地に巡る魔力を溜めておくもので、最終的な儀式に使う。そしてこの溜めた魔力があるからこそ、サーヴァントを召喚する事が可能となる。
小聖杯はサーヴァントの魂を回収する器。
要約すると、大聖杯のエネルギーを使ってとんでもないエネルギーの塊であるサーヴァントを召喚。それを倒してエネルギーを小聖杯に注ぎ込むと、大聖杯を使えるスイッチになる。ややこしいが、これが儀式として必要なのだ。
◆なぜ聖杯戦争は誕生したのか
始まった理由については、まず魔術師の説明が必要になる。魔術師はそれぞれが家に代々伝わる魔術や、自分が得意とする魔術を研鑚し続けている存在だ。そして誰もが目指すのが「根源への到達」。この「根源への到達」は『Fate』世界の魔術や魔法への深い理解が必要になるので今回は説明を省くが、至る為にはとんでもない力が必要になる。それを成し遂げるためにアインツベルン、遠坂、間桐が協力し「聖杯戦争」を作り上げた。アインツベルンが聖杯戦争のシステムを、間桐は令呪などのルールを、遠坂は土地を提供している。
第一次聖杯戦争は1800年に行われ、その後約60年のペースで繰り返されている。繰り返し行われているのは、全てが失敗に終わったからだ。その度にルールや精度を上げていたが、第三次聖杯戦争でとあるサーヴァントを召喚したために、聖杯が汚染されてしまう。その影響で第四次聖杯戦争では大火災が起こり、500人もの被害者が出た。
■次ページ:アインツベルン、間桐、遠坂の御三家とは?
◆アインツベルン、間桐、遠坂の御三家とは?
アインツベルンは錬金術に長けている名家で、ホムンクルスなどを作り出している。聖杯戦争ではシステムや小聖杯となるホムンクルスを用意。イリヤスフィール・フォン・アインツベルンやアイリスフィール・フォン・アインツベルンもそのホムンクルスである。元は人形に近く、感情があるようなものではなかった。しかし第三次聖杯戦争で破壊されてしまったこともあり、第四次聖杯戦争のアイリからその場の状況によって自ら行動を起こせる自己管理型となった。しかしその時に、アインツベルンのマスターとして参加させた衛宮切嗣が裏切ったため、次の第五次聖杯戦争では小聖杯であるイリヤ自身がマスターとして参加した。目的は第三魔法「魂の物質化」で、要約すると不老不死。
間桐は日本の魔術師ではなく、元は“マキリ”という名前だった。
この間桐家は、魔術を発動するのに必要な魔術回路が代々薄れてしまい、間桐慎二の代にはなくなってしまった。なので魔術師ではない慎二は、元のマスターの令呪を「偽臣の書」という本に移行し、譲渡される形でマスターになっている。
遠坂は冬木の霊脈を管理してきた魔術師の名家。この霊脈があることにより、聖杯戦争のような儀式を行う魔力を扱う事ができる。さらに日本と言う異邦のため、聖遺物に厳しい「聖堂教会」の目を欺く事も可能となった。
遠坂家は宝石への力の転移が得意で、師にキシュア・ゼルレッチ・シュバインオーグを持つ。このゼルレッチは『月姫』など他のTYPE-MOON作品にも登場する魔法使いのスーパーおじいさんで、その界隈では超有名人。
ちなみに『Fate』世界では魔術師と魔法使いは大きく違うもので、魔術というのは人間の力でも可能な「火を付ける」や「壊れたガラスを直す」といったものを指す。そして魔法は人間では不可能な「不老不死」や「過去・未来・並行世界に行く」といったものがあり、第六魔法まで存在している。
この三家は協力し合いながらも、相手を殺さなければ目的が達成できないという立場なので、仲良くはない。ただし、お互い利となることのために何らかの干渉は行っている。
第五次聖杯戦争ではイリヤスフィール・フォン・アインツベルンがバーサーカーのマスター、間桐慎二がライダーの仮のマスター、遠坂凛はアーチャーのマスターとなって戦っている。それぞれの運命は、ストーリーによってかなり大きく変わるので、ぜひ追ってほしい。
第二回はここまで。次の第三回目は「サーヴァント」を解説予定、お楽しみに。
















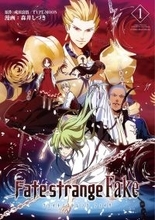
![SawanoHiroyuki[nZk]、Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)とTAKUMA(10-FEET)をゲストボーカルに迎えた新曲「PROVANT」がTVアニメ『Fate/strange Fake』OPテーマに決定!](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FLisani%252F92%252FLisani_0000291693%252FLisani_0000291693_1_s.jpg,zoom=360x220,quality=100,type=jpg)


















![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








