本来“喰う者と喰われる者”の関係であるオオカミのレゴシとウサギのハルが、スクールライフの中で不思議な心の交流を重ねて、自身の本能に気づき向き合っていく。
本作のアニメ化を手がけるのは、気鋭のアニメスタジオ、オレンジ。『宝石の国』で初めてTVアニメーションを単独で請け負い、作画さながらの細やかな表現を3DCGで行う独自の手法が注目を浴びた。
そんなオレンジが2作目に選んだTVアニメーション『BEASTARS』は、いかなる狙いと勝算があったのか? 松見真一監督とCGディレクターの池谷茉衣子さんにお話をうかがった。
知ると見え方が変わって今後の放送がますます楽しみになる、絵作りの試行錯誤とドラマを見せるための細やかな工夫とは――。
[取材・構成=奥村ひとみ]
■作画アニメとは少し違う、3Dモデルに落とし込むためのキャラクターデザイン
――TVアニメ『BEASTARS』について「3DCG」軸でお聞きしていきたいのですが、松見監督は同じくオレンジが手がけた『宝石の国』にも演出として参加されていますよね(※)。
※4、7、9話演出、11話演出補佐で参加。
松見:ええ。『宝石の国』で初めてオレンジさんと関わらせてもらいました。その流れでの参加になります。
――一方、オレンジ所属の池谷さんは「CGディレクター」とクレジットされていますが、具体的に何を担当されているのでしょう?
池谷:最初の第1~3話は私をふくめた全CGディレクター共同で作りましたが、その後の第5、8、11話でアニメーションのディレクターを担当しています。
――「アニメーションのディレクター」というのは?
池谷:弊社はキャラクターのモデルを作るモデラーと、それを動かすアニメーターを分業しているんです。私はアニメーターのほうで、キャラクターを動かしてアニメーションを作るディレクションを担当しています。
――今回、オレンジで『BEASTARS』をアニメ化することになったのは、作品と3DCGの親和性を見出されたからだと思いますが、企画はどのようにスタートしたのでしょうか?
松見: オレンジの特徴は、2Dと3Dが融合していることです。動物を題材にした作画アニメは過去にもたくさんありましたが、たとえば動物の毛の表現は作画だと大変なので、CGだからこそ挑戦できる強みがあります。
それにアメリカのディズニーやイルミネーションのようなバリバリのフル3DCGアニメとも違う、2D的なアニメと3DCGを掛け合わせた新しいものを提示できると思ったのです。
――キャラクターをモデルに落とし込むにあたってのプロセスを教えていただけますか?
松見:どうしても3Dモデルにすると線が整理されますから、絵ならごまかせる部分、要するに「目の位置が多少ズレていても、カッコよければOK」といったことが通用しません。
骨格の論理性を保ちつつ、板垣巴留先生のタッチを再現できる、ちょうどあいだのバランスを狙って調整しました。
池谷:キャラクターデザインのほうでも、モデリングしやすいように描いてもらいましたよね。
松見:そうですね。手描きとCGでは、キャラクターデザインの目的に違いがあります。
作画アニメの場合は、今話したようなカッコいいズレも再現できるので、そのニュアンスも含めたデザインをする必要があります。
オオカミのレゴシは口が前方に突き出ていますが、作画アニメだったらアングルによって多少鼻っ面を短くしたりもできるのです。
しかしCGではモデルを作ってそれを動かすので、カットごとに鼻っ面の長さを変えたりはできません。レゴシが正面を向けば、正直に鼻が前に出てしまう。
――なるほど、作画だったら鼻っ面を短くして処理できますが、3Dではそういうわけにはいかない、と。
松見:はい。キャラクターデザイナーの方とは、「ここは巴留先生がこだわるはず」「こんなに膝を長くするとモーションキャプチャーがハマらない」など、双方の意見を入れてもらいながら何度もやり取りをしました。
最初にレゴシ、ハル、ルイの3体を作りました。頭の膨らみ、手の長さ、首の付け根のあり方といった本当に細かな手直しを繰り返し行って、巴留先生に見てもらい、また調整して。時間をかけてしっかり作り込んで、以降はそのルールに則ることができたので、比較的スムーズに進みました。
→次のページ:動物キャラクターのモデルを動かすためのトライアンドエラー
■動物キャラクターのモデルを動かすためのトライアンドエラー
――たとえば主人公のレゴシのモデルはどの部分をこだわって作ったのでしょうか?
レゴシ
松見:オオカミらしさを残しつつも、リアルなオオカミにし過ぎてもレゴシではなくなってしまうので、どちらも兼ね備えられるようにこだわりましたね。鼻を微妙に直したり、おでこの角度を微調整したり、本当に細かい差で印象が変わります。
作り方に関して、今回は顔をちゃんと3Dで動かしているんです。
――「3Dで顔を動かしている」とは?
松見:これまで制作した『宝石の国』などは2Dの絵の感じに合わせるために、卵のような状態の顔に、目や口のパターンを貼り付けて表情を作っていました。
でも今回はキャラクターが動物で、それこそオオカミの口は前方に突き出ていますから、口を貼り付けて表現なんてことはできません。
顔を3Dで動かすのはオレンジとしては新たなチャレンジで、どうやれば演技を付けられるかみんなで話し合いました。
池谷:今回、初めて顔にもモーションキャプチャーを取り入れたので、レゴシのように人間と違う部分が突き出ているキャラをどうするかは、スタッフ総出で議論を重ねました。
フェイシャルのコントロールのほか、部分的に変形できるリグを組んだりして、表情のバリエーションが付けられるように工夫しました。
松見:ひとつだけ気が楽だったのは、オオカミの笑った顔の正解を誰も知らないことです。
人間キャラクターに対しては視聴者もシビアで、変な表情をさせると「こんな顔はぎこちない」とすぐにバレてしまいます。
その点、動物はリアルな笑顔なんてものがないので、みんなが「笑っているな」と思える表情さえ作ればいいのは気がラクなところでした。
――動物としてのリアリティはどの程度、追求する方針でしたか?
松見:最初は体全体に毛を生やすパターンも試しました。作ってみて、実際にアニメーションをさせると何が問題になるのか、他のキャラクターや美術とは馴染むかなどを検証しながら、毛を生やしたり減らしたり、長さの調整や毛先を変えるなど、トライアンドエラーを重ねました。
動物図鑑を見て毛並みの仕組みを調べたりはしますが、もともとの原作のキャラクターがありますから、原作以上に動物性を出す必要はないだろうな、と考えていましたね。
――第3話でハルがレゴシの身体に触るところは、他のシーンで以上に毛のフサフサ感が出ていましたが、ポイントごとの動物らしさはどうやって表現しているのでしょうか?
松見:キャラクターの表現は何パターンも用意しているので、フサフサ感が欲しいときはそういうパターンを使います。
他にも第1話でテムが逆光を浴びて毛が光るカットは、このシーン用の毛を作って光らせています。
松見:要所要所で動物らしさを見せられればいいので、常に同じモデルを使っているわけではないんです。
――ひとつ気になるのが、動物らしさを出すことは、同時に動物が人間のようなアクションをする、いわゆる“不気味の谷現象”を引き起こす可能性もあったと思います。
松見:これも、やってみてですね。たとえばレゴシなら、あまり大きく口を開閉してしゃべると、見た目にもよろしくありません。
CGチーフディレクターの井野元英二さんとは、「口が突き出た動物は、口の先だけでしゃべってもおかしくないような表現に」と話していました。
気持ち悪さを感じるかどうかは全体のバランスですので、やってみて違和感がなければ、新しい表現であっても問題ないと考えていました。
なので、現場のアニメーターが人と違うことをやっても、それが面白ければ「いいね!」と使われて、今までにない表現に変わっていったりしましたね。
■動物らしさを演出する細かなアクションに注目
――実際にモデルを動かすのは池谷さんの担うところでしょうが、キャラの芝居で気をつけていることを教えていただけますか?
池谷:ちゃんとしゃべっているように見せることです。たとえば日本語のマ行は唇を閉じるので、そこはしっかり唇を閉じさせる。細かいですが、そういうことをしないとただ口がガバガバ開閉しているだけになってしまいます。
セリフに合わせて閉じ口を入れるだけでも、随分と見え方は変わります。
――まったく違和感なく見ていましたが、裏側にはそんな工夫が。
池谷:少しでもズレると「録音した音がバックで流れているだけ」という感じになるので、作業はセリフの音源を聴きながらタイミングをはかっています。
それと、人間の言葉を話してはいますが、みんな動物なので感情に合わせて牙を見せたり、ボソボソしゃべるときは口を広げないようにして差を付けます。
――しゃべる以外の身体の動きではどんなことに留意されますか?
池谷:肉食動物に力強いポージングをさせたりはしますね。逆に草食動物は、あまり人間のキャラと変わらないような作りです。
それから、しっぽやヒゲといった人間にはない揺れものがありますから、そこは柔らか過ぎず硬過ぎず……というのは意識します。
松見:しっぽも3Dモデルですから、何もしないとカチッと無機質なものになってしまいますからね。揺らしたり、原作でもありましたが嬉しさを表すのにしっぽを動かしたりもします。
あとは耳ですね。人間は視覚動物ですから何かあったらすぐ見るんですが、視力が良くない動物は耳で反応するので、そういうアクションで動物と人間の違いを演出しています。
――時おり動物らしいアクションが入るのが面白いです。ハルの食事シーンは、ウサギが口を小刻みに動かす食べ方に似せていましたね。
松見:はい。アニメーターには、できればウサギっぽく食べる表現をしてほしいとお願いしました。『BEASTARS』の草食動物キャラクターは、歯が人間と同じ形状なんです。
動物らしい動きの入れどころはルールをハッキリ決めているわけではなく、シーンごとに「ここは表現できるかな?」と考えて加減しています。
→次のページ:実はけっこうキツかったモブ動物たちと、あのニワトリキャラ登板のひみつ
■実はけっこうキツかったモブ動物たちと、あのニワトリキャラ登板のひみつ
――キャラクターが動物であることで、人間キャラのアニメより作業量が増えた部分はありましたか?
松見:モブがけっこうキツかったですね。学校にいる名もなき生徒たちですけど、見た目でシカだとかクマだとか何の動物か明確にバレてしまいますから、ともすれば名前のあるキャラに見えてモブの役割が成立しなくなってしまう。
それに、人間だったらバーッと増やしてもそれなりに群衆に見えるんですが、本作はいろんな動物がいるのでそれができない。
――たしかに、人間のモデル以上に使い回しは効かなそうです。どうやってモブを成立させたんですか?
池谷:まず、メインキャラと被る動物はモブに使いませんでした。ですから、群衆の中にはハイイロオオカミ(※レゴシ)やアカシカ(※ルイ)はいません。
松見:なので、モブに多いのは羊や狐など。ウサギも形態ですぐバレるから使えないし。
ただ、モデルの使い回しという点では、骨格が似ている動物はいるので、テクスチャの違いや、髪色、模様などでバリエーションを増やすことはできました。つまり、ウマに縞模様を付ければシマウマになる、みたいなことはできるわけです。
――それでもけっこうな種類の動物を作られていますよね。その中で、「実は表現が難しい」といった動物がいたら教えてください。
池谷:アリクイはアングルが難しいですね。口の表現や、あとは正面を向いたときのバランスが。
松見:角度によっては目がまったく見えなくなって、ツルっとしたバナナみたいになっちゃうんです。それこそ2Dだったら目をズラして描けるんですが。
――2Dだからこそ成り立つ、ウソの表現ですね。
松見:アリクイは影を付けるなど調整してようやく立体感が出てくるので、意外とめんどくさかったりします。
――今後のアリクイやモブ動物キャラの見え方が変わりそうです。
池谷:あとは各話にどんな動物が登場するかによって、モブ動物の種類もバランスを調節していただいたりしましたね。本作はメインキャラとまではいかずとも、名前のあるキャラクターが多いので、モブが目を引かないように気を遣いました。
――名前のあるキャラといえば、公式サイトのキャラクター紹介にニワトリのレゴムが既に掲載されていますね。原作では一話完結のサイドストーリー的なエピソードだったと思うのですが、レゴムの登場は板垣先生からアニメ化に対するリクエストだったのですか?
レゴム
松見:いえ、特に先生の指定にはありませんでしたし、もともと初期のシリーズ構成ではレゴムの話は入らなかったんです。でも、レゴムの話は原作の中でも人気のあるエピソードだし、巴留先生は公の場に出るときにレゴムのマスクを被るので、やっぱり外せないよね、と。
なので、ニワトリもモブ動物の中にはいません。そもそも、レゴムって、『BEASTARS』の中でもとりわけキャラクター化されていない、ニワトリそのものですよね。もしモブの中にニワトリがいたら、それこそ全部レゴムに見えちゃいそうです(笑)。
――それでは最後に、おふたりから今後の見どころを教えてください。
池谷:物語の展開で、制服が長袖から半袖になったり、ジャージやタンクトップ、演劇部の舞台の衣装など、意外と服装が変化します。
CGアニメはモデリングの数が増えるのは避けたいので、本来は衣装換えもセーブするんですが、本作はかなり多いです。そこはぜひ注目してご覧いただきたいですね。
松見:シリーズも中盤に差しかかり、ハルとレゴシはお互いの本音を出して理解し合っていきますが、それを邪魔する者も出てきます。
今までじっと動かなかったレゴシが動き出すところを見届けてもらえればいいかなと思っています。じっくりストーリーを楽しんでもらえたら嬉しいです。




























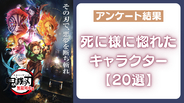

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








