『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は「奇妙にねじれた夢」のような作品だ。画面に見覚えのあるものがでてきても、記憶の中のそれと画面の中のそれは微妙に異なっている。どこかで見たことがあるようなシチュエーションであっても、記憶の中の映像とは意味合いが異なっている。“記憶”の断片が連想ゲームのように紡がれていく本作はその点で、とても“夢”に似ている。“夢”はシリーズ後半、作中でもキーワードのひとつとして浮上してくるが、本作の視聴体験そのものが“夢”に似ているのだ。 この“夢”の感覚は、この作品を構成する二重構造から生まれている。
一番下にあるのが「設定のレイヤー」。『GQuuuuuuX』はもともと、TV『機動戦士ガンダム』とよく似た世界から分岐した、もうひとつの世界を舞台としている。そこではTV『ガンダム』では負けたはずのジオン公国が勝利を収めている。このため、この世界の歴史や状況そのものが「知っているものとちょっと異なる」形で成立している。当然TV『ガンダム』とその続編『Zガンダム』に登場したキャラクターも、微妙に立場を変えて登場している。
この「設定のレイヤー」の上に「映像の記憶のレイヤー」がある。
視聴者は、この2つのレイヤー越しに『GQuuuuuuX』の物語に触れることになる。重ねられたレイヤーがもたらす「奇妙な夢」のような体験は本作の狙いのひとつであっただろうから、『GQuuuuuuX』を語ろうとすると、どうしてもこの「2つのレイヤー」の話に終始してしまいがちだ。
しかし、ここではこのレイヤーの存在を念頭におきつつも、そもそも『GQuuuuuuX』という物語が、どういう構造で組立てられていたかと考えてみたい。本作のあらゆるピースは、シャロンの薔薇で眠る少女がこの世界で発したただひとつのセリフ、「ありがとう。こちら側のニュータイプさん」へと繋がっている。
第1話「赤いガンダム」から第3話「クランバトルのマチュ」までは、(前日譚に相当する第2話「白いガンダム」を含めて)物語のセッティングを行うパート。ここで主人公のマチュ(アマテ・ユズリハ)、ニャアン、シュウジという3人の関係性が出来上がる。また、本作を貫く主題もこのパートの中で示されている。それは「自由」というキーワードだ。
また第1話ではもうひとつポイントとなるキーワードも示される。それはマチュの「私たちを地面に押し付けているこの力は、本物の重力じゃない」という台詞などから示される……「偽物/本物」という主題だ。しかしこちらはキャラクターのドラマを牽引するキーワードではなく、作品の本来的な意味での「世界観」――この作品は偽物/本物という視点で世界を切り取るというその姿勢――を示している。
第4話「魔女の戦争」から第6話「キシリア暗殺計画」までは、一旦出来上がった3人の人間関係を崩していくパート。ここで各キャラクターの葛藤を通じて「自由」という主題が深められていく。重要なのは「自由」と対になる概念として「執着」が浮上してくるところだ。
第4話は、元連邦軍のユニカム(撃墜王)であるシイコが登場。「戦争に負けても私は負けてない」という台詞のとおりシイコは、引退し結婚・出産したにもかかわらず、赤いガンダムを倒すため、クランバトルという“戦場”に戻ってきた。シイコは、マチュにとって初めて会った“他者”というべき存在。同じ“母”でありながら、実母のタマキとはまったく異なる生き方を選んだ存在としてシイコはマチュに強い印象を残す。
シイコとマチュの関係性はTV『ガンダム』において、敵として登場したランバ・ラルが、主人公アムロにとって“他者”でありまた実父テムとは違う“父性”を体現した存在として登場することと重なって見える。舞台挨拶などでは、脚本開発の段階で「マチュが地球に降りた後、ランバ・ラルとハモンのように、マチュに影響を与えるキャラクターと出会ったほうがいい」という議論があったことが紹介されているが、シイコもは十分ランバ・ラルに近い役回りであったといえる。
同時にシイコは勝利への「執着」を持ったキャラクターとしても描かれる。そして死という形でその執着から解き放たれるシイコ。
死の直前、ニュータイプ同士の交感を表現する“キラキラ”の空間の中で、シイコは「ガンダムの向こうに誰かいる」と感知する。そこにシュウジは「僕の願いはひとつだけ」と答える。そこには黄色に染まった“キラキラ空間”が広がっている。シュウジのいう「願い」とはつまり「執着」である。それを知ってシイコは少し笑う。これは「あなたもまた執着に囚われているのね」といった雰囲気の、自嘲も含んだような笑いである。
死の瞬間、シイコは幼い息子の姿を思い出すが、それは執着から開放され自由になった彼女の魂が還ろうとした場所なのだろう。
物語の展開を先回りして書いてしまうと、シュウジの執着は向こう側からモビルアーマー・エルメスとともにやってきたララァの存在である。
シュウジが“キラキラ”のグラフティを描いている理由について、ニャアンが「誰かに見せるため?」と聞くと、シュウジは「マチュは知っている」と彼女に視線を送りながら答える。マチュはその言葉と様子にドギマギしてしまう。
ただここでシュウジが語っているのは、マチュ自身のことではない。第4話で“キラキラ”空間の中でマチュが「ガンダムの向こう側にいる存在=ララァ」を感知しているであろうことを想定してのひとことなのである。この感情のすれ違いによって、マチュが一層シュウジを意識することとつながる。
マチュは、狭いコロニー=自分の日常から解き放たれたかった。だからこそ非合法のクランバトルに自由を感じてのめり込むのだった。そしてそこでシュウジと彼が見せてくれる“キラキラ”の世界と出会った。しかし、皮肉にもマチュは「自由」に接近しているつもりが、結果としてシュウジに執着するという形で縛られていく。
こうしたマチュの心の動きはひどく子供っぽい。
一方ニャアンはサイド6のイズマ・コロニーにやってきた難民で、居場所がない。女子高生を偽装した姿で運び屋のバイトをしているのも生活のためだ。居場所のないニャアンにとって、自由とは「自分が自分でいられる場所」を得ることだ。そんな彼女は、第5話で“キラキラ”の空間に入り、「私が思うとおりに世界が合わせてくれる」とこれまで感じたことのなかった「自由」を感じる。ただこちらも皮肉なことに、この「自由」を味わったことで、マチュ、シュウジと出来上がっていた「自分の居場所」を失ってしまう。
こうして「自由になったつもりが執着に縛られるマチュ」と「自由を感じたことで居場所を失うニャアン」がすれ違い、第7話「マチュのリベリオン」では「3人の楽しい時間」の終わりが描かれる。シュウジは姿を消し、マチュは強襲揚陸艦ソドンに捕らえられ、ニャアンはキシリアのもとへと誘われる。
第8話「月に墜(堕)ちる」から第10話「イオマグヌッソ封鎖」まではクライマックスの大転換に向けて、マチュとニャアンのドラマがそれぞれ展開されるブロック。
ニャアンの場合は、キシリア配下のパイロットとして自分の居場所を見つけていく様子がストレートに描かれる。一方でマチュは、第9話「シャロンの薔薇」での地球でこの世界のララァとの出会い、第10話でのシャリア・ブルとの対話を通じて内面が変化していく。
第9話「シャロンの薔薇」でマチュが、ソドンを抜け出し地球に行って再びソドンに合流するまでの行動は極めて受け身で、ある意味“ご都合主義”な展開に見える。だが全編を通してみると、ここでのなにものかに導かれて“受け身”であったことが、この後マチュが自分の意思で決断していくことの前提になっていくのである。
この世界でマチュが出会ったララァは、娼館で働く少女だ。彼女は、“向こう側”の世界の出来事を何度も夢見ている。夢の中では、若いジオン軍の将校が彼女を身請けして、娼館の外へと連れ出してもらう。そこから「自由」になった彼女の人生が始まるが、ジオンの将校は白いモビルスーツに殺されてしまう。そんな夢を何度も見ているララァ。
マチュとララァが“キラキラ”の空間で会話をしている、その画面の奥は第4話などと同様に黄色に輝いており、そこに“向こう側”のララァの気配が感じられる。またララァの言葉も途中で「何度やり直してもいつも白いモビルスーツが彼を殺してしまう」と、「夢を見ている」のではなくまるで「ジオンの将校を救うために世界を繰り返している主体」のような言い回しも出てくる。第12話の後にこのシーンを振り返ると、この世界のララァはシャロンの薔薇の少女(=“向こう側”のララァ)と心の深いところでそれとは気付かないうちに通じ合っているようでもある。こちら側のララァは“シャロンの薔薇”についてなんらかの感知をしているらしい発言をするのも、その可能性を感じさせる。
マチュはこちら側のララァを宇宙へと誘う。しかしララァはそれを断る。ララァは娼館に残って「夢で見た彼」が迎えに来るのをここで待つというのだ。しかし彼女はおそらく、そんなことは「夢の中」だけの出来事で、自分の身の上にそのようなことが起きないこともわかっている。しかし彼女は自分の意志で「残る/待つ」ことを選ぶ。なぜならば彼が自分と出会わないということは、彼は死に向かう人生を歩んでないであろうということだからだ。ララァは自分の意思で自分の未来を決めているのである。それこそがこの世界のララァの「自由」なのである。
続く第10話では、シャリア・ブルが「自由」について語る。彼はエネルギー確保のための木星船団に参加した。しかし船団は、技術的なトラブルで地球圏への帰還ができなくなってしまう。そのとき、目標も失い、何もできなくなったことで、シャリア・ブルは「自由」を感じる。そして本当の自由になれたまま死ぬのもいいかもしれないと、拳銃を自分の頭に突きつける。国家への執着から解放され、自らの意志で「死」を選ぶということ。これもまたひとつの「自由」の形である。
こうして第9話と第10話で「自分の意志で未来を選び取ることこそが自由である」というテーゼがくっきりと浮かび上がる。しかも第10話では二丁の拳銃が登場し、「自由」の主題を補強する。「銃(じゅう)」と「自由(じゆう)」をかけるのは、さまざまなところで見られるのはいうまでもない。
ひとつめの拳銃はシャリア・ブルからマチュに手渡される。これは受け身だった第9話の経験を踏まえて、「お前はどのような未来を選び取るのか」という問いかけそのものである。そしてこの銃は、最終的に“向こう側”のララァを殺そうとするシュウジを止めるため、オメガサイコミュのリミッター(それは起動デバイスとしてエグザベに渡されていたものだ)を破壊するために使われる。
2つめの拳銃はキシリアからニャアンに渡される。これはキシリア配下であることがニャアンの居場所になったという絆の証のように見える。だが、最終的にニャアンはこの銃で、マチュを守るためにキシリアを撃つ。それはニャアンが自分の意思で、マチュ(とシュウジ)のいる世界を求めたということでもある。ふたりは自らの「自由」のために銃を使うのである。 こうして物語は第11話「アルファ殺したち」、第12話「だから僕は」でクライマックスを迎える。
ここで中盤姿を消していたシュウジが再登場し、彼の願いが“向こう側”のララァを“殺す”ことにあることが明かされる。
シュウジの理屈はこうだ。
娼館のララァが何度も夢でみたとおり、“向こう側”の世界でララァはシャアを失い、それによって世界が分岐をした。そこでララァは「シャアの死なない世界」を求めて何度も世界を作り出したが、その試みはなかなか成功しなかった。そして“この世界”はようやくシャアが死なない世界を作ることに成功した。
しかし、この世界のシャアはこの世界を否定しようとしている。それは“向こう側”のララァにとって、耐え難いことである。そのため“向こう側”のララァが傷ついたとき、この宇宙は、向こう側の世界を巻き込んで、崩壊してしまう。だからララァが傷つく前に、ララァを殺し、この宇宙を終わらせることで、ふたたびララァが別の宇宙を作るようにする。これまで何度もそうしてきたように。
シュウジが設定上、どういう存在下は映像をみただけではわからない。ただシュウジの執着はこの世界を作ったララァにあることは間違いない。
マチュはシュウジをこの執着から解き放とうとする。自由に憧れ、翻弄された少女が、“こちら側”のララァの強さを見て自由とは何かを知り、今度は少年を解放する立場になるのである。ここに少女の通過儀礼としての失恋が重ねて描かれているのである。そしてシュウジを解放しようとしたマチュが発するのが「ララァはそんなこと望んでいない」という台詞だ。
どうしてここでマチュはララァの代弁者として振る舞えるのか。この台詞の直前に短くいくつか映像がインサートされる。おそらくマチュの脳裏を横切ったイメージということであろう。それは彼女のスマホに送られてきた、送り主不明のメッセージの映像である。最後に映し出されるのは第1話に送られてきた「Let's get the beginning.」(さあはじめましょう)のメッセージである。
どうして台詞前にメッセージの映像がインサートされたのか。これはマチュが、自分のこれまでの歩みが「“向こう側”のララァが自分の意思を伝えようとしていたサイン」であると洞察したからではないだろうか。何かのサインということを感じさせるために第9話は、マチュは受け身な役割を演じたのだろう。
もちろん、メッセージの送り主を作中の情報だけで特定するのは難しい。別の可能性としては、GQuuuuuuXに搭載されたエンディミオン・ユニットであることも考えられる。だが、もしそうならマチュがこのとき洞察するのが「ララァの心情」ではなく、「ララァはそんなこと望んでないと、GQuuuuuuXは言っている」という台詞の形にならないと整合しない。そして、それならわざわざエンディミオン・ユニット自体にシュウジを説得する台詞をいわせることもない。
むしろ娼館のララァがシャロンの薔薇の影響を受けていたと思しきことから考えると、少なくとも“向こう側”のララァの意思がこの世界にこぼれ落ちているというふうに考えたほうが整合性はまだとれるように思う。第10話でイオマグヌッソが宇宙要塞ア・バオア・クーを消し去った後、マチュは「シャロンの薔薇が泣いている」と反応している。そこからも“向こう側”のララァの思いは、無意識の形でこぼれだしているのだろう。
では、どうして“向こう側”のララァの意思がこの世界にこぼれ落ちてくるのか。“向こう側”のララァはシャアを救いたい一心で世界を何度も作り出したが、同時に自分に執着するシュウジも救いたかったのではないか。シュウジはララァの望む世界が出来上がらなかったときに、何度も世界を壊してきたと語っている。ふたりがどういう関係かは、映像ではわからないが、「作り出す者」と「壊す者」として一対のものであるということはわかる。そして「壊す者」はどうしても「作り出す者」に執着せざるを得ない。
マチュはシュウジに「そんなシュウジが自分の心を縛ったりしないで。ララァのことが好きなんでしょ」と語りかける。これはマチュが失恋を引き受けた台詞でもある。
「私にはわかるララァはそんなこと望んだりしていない。シュウジが守らなくたっていいんだよ。誰かに守られなきゃ生きていけないなんて、そんなの本物のニュータイプじゃないう。(略)明日のわたしはもっと強くなってやる。誰にも守ってもらう必要のない! 強いニュータイプに!」と叫ぶ。この瞬間、“向こう側”のララァが覚醒する。
そして、すべてが決着した後、“向こう側”のララァが口にする台詞が「ありがとう。こちら側のニュータイプさん」である。どうして“向こう側”のララァはマチュに「ありがとう」と言ったのか。これは単に自分の生命を守ってくれたとかそういうことではないだろう。シュウジに殺されたとしても、世界を夢見る主体であるララァは存在し続けるとシュウジが説明しているとおりだからだ。
そう考えると、マチュはララァの思いを代弁し、シュウジを解放してくれたことを感謝したのではないか。シュウジがマチュに「きっとこの世界はきみと僕が出会うために作られたのかもしれない」という台詞も、ララァがマチュに自分の思いを託したことを考えると、ロマンチックな言葉以上の意味を帯びて聞こえてくる。
眠り姫を守るために殺そうとする純粋なナイト。そんなシュウジに、マチュは「お前はもうナイトを務めなくてよいのだ」と言い渡す役としてララァの思いを代弁したのだ。それはシュウジに執着していたマチュが自由になったということでもある。これは子供だったマチュの成長である。
さまざまなことが“向こう側”のララァが、不毛な世界の創造と消滅の繰り返しを越えて生きたいと思った、その思いから端を発していると考えるとわかりやすくなる。マチュやニャアンを取り囲む偶然はある意味必然であり、だからこそ「ありがとう」という言葉ですべての出来事は締めくくられたのではないか。こうして“向こう側”のララァによる夢は終わり、地続きのまま、誰も知らない未来が始まる。こうして「偽物の世界」は「本物」となっていく。本物の世界とは「自分の自由意思で選択された世界」のことなのである。
作中でシャリア・ブルはニュータイプを「自由のために傷つくもの」という言い回しで語る。これは「未来を自分の意志で切り開く」という言葉でも言い換えられるだろう。未来を切り開くためには、自分の執着を捨てなくてはいけなくなることもあるだろうし、未来が見えたことでなにをすべきかわからなくなることもあるだろう。そのときに恐れずに一歩を踏み出すことができる人間をこそ、シャリア・ブルは“ニュータイプ”と呼びたいと――考えたというよりは――願ったのだろう。
シャアを失った“向こう側”のララァは、何度も絶望の果てに強くなったのではないだろうか。「来るはずのない相手を待ち続ける」という決断のできた“こちら側”のララァの姿を見ると、そういう想像も許されそうな気がする。
こうして「自由」と「執着」というキーワードで見返すと、第12話の巨大化したガンダム(TV『ガンダム』と同じデザイン)は、“向こう側”の世界への執着の大きさの象徴であり、そのまま現在のガンダム・ビジネスとそれを支えるファンの執着の姿のようにも見える。そして未来は、その執着に立ち向かい、乗り越えた先にしかない――といっているようにも見えるのだ。そうなるとシュウジとは「ガンダム」に心惹かれた人々の集合無意識のようなものではなかったのか、というふうにも見えてくる。これはいささか深読みが過ぎるとも思うが、その執着を、これから作られていく新しいガンダムがばっさりと切り捨てていくことで、未来が開けていくのは間違いのないような気がする。
【藤津 亮太(ふじつ・りょうた)】
1968年生まれ。静岡県出身。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』、『チャンネルはいつもアニメ ゼロ年代アニメ時評』、『声優語 ~アニメに命を吹き込むプロフェッショナル~ 』、『プロフェッショナル13人が語る わたしの声優道』がある。最新著書は『ぼくらがアニメを見る理由 2010年代アニメ時評』。各種カルチャーセンターでアニメの講座を担当するほか、毎月第一金曜に「アニメの門チャンネル」で生配信を行っている。




























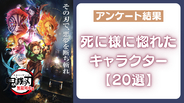

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








