恐らくほとんどの人が一度は使ったことがあると思われる消臭剤。
そこで、消臭スプレーの成分欄を見ても「トウモロコシ由来成分」「ブドウ糖由来天然成分」などと記載されており、抽象的すぎて詳細な成分がわかりません。
今回は、これらの商品がどのような原理で消臭しているのかを検証しつつ、消臭剤を選ぶ目安と注意点、さらに病院などで使われている除菌テクニックについても紹介します。
●悪臭の原因ところで、そもそも不快なにおいの原因はなんでしょう?
消臭剤メーカーが行ったアンケートによると、特定の悪臭を指すというより、「なんだかわからないけど、鼻につく生活臭」という回答が多数を占めています。
たかが生活臭程度と思うのですが、知人の家を訪問した時などに生活臭が気になるのと同様に、「自分の家も、他人には気になるにおいを出しているのではないか」という強迫神経症めいた恐れを感じる人が想像以上に多いのかもしれません。
家には、それぞれのにおいがあります。それは畳などの建築材や、壁紙に含まれる溶剤、さらにペット、頻繁に使う調味料、生ゴミ、家にあるあらゆるモノから微量に発せられる臭気成分とそこに住む人によって個性ともいうべき生活臭ができあがります。
そういった生活臭の中には、アセトアルデヒドやノルマル酢酸、ウンデカン酸、チオール、アンモニア、吉草酸、硫化水素、キシレン、トルエン、ホルムアルデヒドなど、際だって悪臭となりやすい臭気成分があります。
これらを分析すると、抱合(分子的に抱き込んで無臭の状態になる)、酸化、還元、吸着など、20種類前後の方法でほとんどの生活臭を消し去れることがわかっています。
このような方法でにおいを消すことができる性能を持った成分(消臭成分)を、メーカー各社がそれぞれに配合しているのが消臭剤です。その成分については表示義務がないため、適当な表現になっているといえます。逆にいうと、濃度次第で毒にも無害にもなるような成分ばかりで、成分名だけ表記しても意味をなさないのです。
それを取り上げて、「見えないから怪しい」「わからないから危ない」と騒ぎ立てる人が出てきますが、まずはきちんと理解することが必要です。
ちなみに、なんでも無臭にクリーンにしたがるのは潔癖症気味な、日本人という国民性を反映しているようで、実際、ここまで消臭剤が前面に押し出されて市場を築いている国は日本以外にはほとんど見当たりません。アメリカやEU諸国のドラッグストアでは、芳香剤はあっても、日本のような消臭+芳香という商品は売られていません。
●消臭のメカニズム各メーカーが設けた芳香消臭脱臭剤協議会で定めた商品区分によると、芳香剤(空間に香りを出す製品)、消臭剤(臭気成分を無臭化する成分を有する製品)、脱臭剤(臭気成分を物理的に活性炭などに取り込み除去する製品)、防臭剤(臭気の発生や拡散を防ぐための成分を有する製品)に分けられます。
これらは、使い方や場所に応じていくつかの商品パターンに分類できます。当然、例外的な商品もありますが、まずはそれぞれのカテゴリーの商品がどうやって臭いを消しているのか知っておきましょう。
(1)据え置き式(ゼリー状、活性炭などの吸着剤タイプ)
プルンとしたゼリー状の物質に、消臭成分が固定された製品が一般的です。ゼリーの正体はゲランガムやウェランガムという食品添加物としても使われる成分で、常温でも崩れない羊羹ほどの軟らかさの固形物をつくるゲル化剤です。その中に双性界面活性剤などの消臭成分を閉じ込め、さらに商品によっては香料も添加されています。
ゼリータイプの商品は、空気に触れた部分のゼリーがしぼんで水が抜けていく際に、表面に出てきた消臭成分がにおい物質を吸着するメカニズムです。従って、このタイプで無香料の商品は、消臭成分などが放出されるわけではないので、生き物の横などに置いても安心な、最も穏やかな消臭方法といえます。また冷蔵庫用などの活性炭消臭剤も完全に臭気成分を吸着するだけなので、ほとんどの製品が無害です。
(2)スプレー式(ガス圧スプレーと霧吹き型)
スプレー式は、消臭成分が据え置き式と似ていても、能動的にまくので吸い込む可能性もあり、安全性が気になります。大まかに2種類、コカミドDEAなどのアミノ酸系シャンプーにも使われている両極性界面活性剤と、オリゴ糖の一種といえるデキストリン(メチル化βシクロデキストリン)が使われています。
いずれの成分も、臭気成分を分子の中に収納するように閉じ込めてしまいます。その後は、無臭の物体となったまま乾燥して床に落ちます。
つまり、ヌイグルミやベッドカバーなどに消臭剤をかけても、臭い物質が消えたわけではなく、臭いを感じなくなっているだけなので、定期的に洗濯などで洗い落とす必要があります。
一部では、「ゴキブリに消臭剤をかけると死ぬ……だから消臭剤は毒だ」と危険性をあおる人がいますが、ゴキブリが死ぬのは両極性界面活性剤が気門(呼吸のための穴)に詰まる窒息死、またはアルコール類が体内に浸透することによるショック死であり、神経に作用し生命活動を止める殺虫剤とは根本的にメカニズムが違うので、人間にとっても有害であるという解釈は間違いです。とはいえ、ペットや肌が敏感な子供がいる家庭では、十分に注意して使用しましょう。
ただ、いずれの成分にもパラベンなどの防腐剤が含まれており、直接皮膚に接触し続けることは望ましいといえないので、汗臭いからと素肌に触れる衣類に毎日のように吹き付けるのは避けたほうがいいでしょう。
(3)電動式(コンセントタイプ)
電動式は、スプレー缶がセンサーで動作して噴霧するタイプと、電熱によりゆっくりと消臭成分が揮発するタイプに分けられます。成分が熱に強いものでなければならず、加熱蒸散で消臭効果を持つ成分は限られるので、スプレー式に比べると消臭力は弱いものが多いです。
ただ、植物由来の香りの良い成分で、蒸発しにくくスプレータイプに使えない成分も強制的に蒸発させることで、香りを安定的に持続させることができるという利点があります。寝室などに好みの香りを維持しておきたい人などにはうってつけといえます。
ところが、こうした消臭剤の中には、注意すべき商品もあります。それは、除菌や殺菌、抗菌を掲げる商品群です。
昨今の潔癖すぎる衛生ムードの中で、消臭剤に殺菌成分を加え、より衛生的であるとのイメージの商品が販売されています。殺菌剤は銀イオン系成分や、四級アンモニウム塩などの逆性石けん成分が使われており、一時的な除菌には便利ですが、肌に触れ続けた場合は、薬品焼けなどを起こす危険もあります。
これらの除菌剤入りの消臭スプレーは、直接肌が触れることがなく、かつ臭いが発生しやすい下駄箱や、靴の中などに使うべきで、部屋の中など人が吸引する可能性のある場所でまくのは避けるべきでしょう。製品に注意書きはありますが、あまり目立つように書かれていないので、気付かずに常用している人も多いかもしれません。
本来、銀イオンは、危険な温水中のレジオネラ菌の繁殖抑制などに使われるべきであり、身の回りの除菌などに頻繁に用いることは注意が必要です。
表面だけの殺菌をしても根本的解決にはならず、こまめな掃除洗濯が基本です。過度な除菌は、健康に良いとはいえず、衛生的な暮らしをしているつもりが、有用な常在菌すら除去した挙げ句に人間の抵抗力を低下させ、果ては刺激性の高い化合物でコーティングされた日用品だらけになっては本末転倒です。
●効率的な除菌・消臭雑菌が悪さをする典型的な例として、洗濯物の嫌なにおいが挙げられます。洗濯物を室内干しした結果、独特なにおいが残ったという経験は誰しもしたことがあると思います。しかも、一度付いたにおいは、その後洗ってもなかなか落ちないものです。
これは布地に付いた雑菌の数が多くて、洗浄しても落とし切れない状態になっているものです。そのにおいを消そうと除菌消臭スプレーをかける人や、泣く泣く服を捨ててしまう人もいますが、実は、薬局に売っているある薬品で簡単に解決できるのです。
それは、ベンザルコニウムです。
聞きなれない名前ですが、除菌消臭剤に配合されている成分の一つです。ベンザルコニウムは歴史と実績のある殺菌剤であり、病院のタオルやシーツなどの洗浄にも使われています。ほとんどの薬局で取り扱いのある薬剤で、クエン酸や重曹などと同じコーナーに置いてあります。「逆性石けん」ともいわれ、通常は水溶液の状態で売られており、洗濯の場合は100倍程度に希釈して使います。
原液は刺激性があるので、なるべく触らないように注意しましょう。また通常の洗剤と併用すると中和してしまい、逆に落としにくい汚れが発生してしまうので、絶対に混ぜないでください。
普通の洗剤と同じように使用しても問題ありませんが、すすぎ回数を1回多くしておくと安心です。あとは普通に干せば、いやなにおいを放っていた衣類もすっきりするはずです。それでもにおいが落ちない場合は、100~150倍に薄めた液に一晩つけ置きしておくとよいでしょう。
(文=へるどくたークラレ/サイエンスライター)
●へるどくたークラレ
数々の大型書店で理系書売り上げ1位となった『アリエナイ理科ノ教科書』著者。本連載をまとめ、さらに加筆した『薬局で買うべき薬、買ってはいけない薬』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)が発売されました。












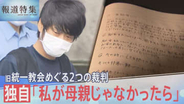


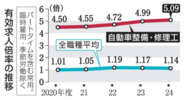


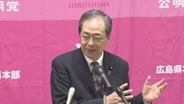








![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



