今年も2019年に卒業予定の大学生による就職活動が3月1日に解禁された。
厚生労働省および文部科学省が発表した就職内定状況調査によると、2018年3月卒業予定の大学生の2017年12月1日時点での就職内定率は、前年同期比で1.0ポイント改善の86.0%。
そんな近年の就活市場は、空前の“売り手市場”といわれているが、“買い手”のなかには新たな策を講じる企業も少なくない。たとえば、北海道の大手ドラッグストア「サッポロドラッグストアー」を運営するサツドラホールディングス(以下、サツドラ)は、2018年3月1日から新しい新卒採用制度「えらべる制度(入社時期等選択制)」を導入した。
●否定的な意見相次ぐ
サツドラが導入する「えらべる制度」と従来の採用制度の最大の違いは、対象が大学1年生まで引き下げられている点だ。つまり、この制度を利用すると最短で大学1年生のうちに内定(厳密に言うと内々定、詳細は後述)を獲得できるということである。
このように大学1年生を対象にした採用制度は、2013年からすでにユニクロを運営する大手アパレルのファーストリテイリングや、大手食品飲料のネスレ日本など、一部の企業でも行われている。いずれの企業も、採用活動を大学1年生のみに絞ったというわけではなく、通常どおり大学4年生の採用活動をメインで行っているが、それでも大学1年生のうちから内定(内々定)を出すというのは、賛否両論起こるだろうことは想像に難くない。
このような大学1年生を対象にした採用制度は、1997年に日本経済団体連合会(経団連)によって策定された「倫理憲章」に違反するが、倫理憲章には法的拘束力がないうえ、ファストリやネスレは経団連に所属していないため、大きな問題とはなっていない。
しかし、この採用制度をめぐっては「大学での学びを軽視している」といった批判的な声や、「学業が疎かになるおそれがある」といった不安の声も相次いでいる。
果たして、大学1年生採用制度は企業や就活生にどのような影響をもたらすのだろうか。大学を含む教育ならびに就職やキャリアなどを専門に扱い、『キレイゴトぬきの就活論』(新潮新書)の著書もある大学ジャーナリスト、石渡嶺司氏に話を聞いた。
●学生側にとってはメリットが大きい制度
まず、大学1年生採用制度における、就活生のメリットとデメリットは何か。
「就活生にとって最大のメリットは、大学1年という早い時期からチャンスがあることです。どんな業界に進みたいかといった卒業後の進路が明確になっている学生にしてみれば、かなり魅力的な話でしょう。さらに学生は、1年生から選考に参加することで面接を含めた就活の練習ができますし、うまく内定を勝ち取ることができれば無料で研修を受けられ、社会人として必要なスキルを一足早く習得することができるのです。
反対にデメリットは、企業側がどこまで人材教育をするかによって若干変わってきますが、学業に支障を来す可能性があるという点。学生に人材教育をするとなると、おそらく最初はアルバイトとして入ってもらうことになり、そのアルバイト業務が終わってから研修をするといったかたちになるでしょう。ということは、通常のアルバイト以上に拘束時間が長くなりますので、多少なりとも学業に支障が出ます。場合によっては、単位を落としてしまう危険性もあります」(石渡氏)
就活生へのデメリットを考えると、大学側としても歓迎できない制度のように思える。
「大学側からすれば不愉快でしょう。人材教育をする分、大学の勉強の時間が削がれるわけですからね。学業が二の次、三の次になってしまう可能性があるのは明白で、糾弾したい気持ちもあるでしょう」(同)
本制度を利用する場合、本来大学の学業にあてるべき時間を早いうちから就活にあてることになってしまう。確かにそれでは本末転倒だろう。
●企業側からすると、実はかなりハイリスク
では、本制度を導入している企業の狙いは一体なんなのだろうか。
「企業の狙いは大きく2点あります。まず就活対象を1年生に引き下げることで早めに人材を確保できるという点と、時間をかけて人材教育を行えるという点があるでしょう。一般的な新卒採用のように卒業後に短期間で内定者研修を行うよりは、毎日ではないにしろ、まとまった長い研修期間を設けることができるため、卒業後に即戦力として期待できるということなのです。言わずもがな、これは導入するにあたって企業のメリットでもあります」(同)
一般的な採用制度であれば、数週間や1カ月程度の期間しか設けられない内定者研修が、大学1年生採用制度となると数カ月間などのまとまった期間をあてることができるのだ。企業にとって即戦力は魅力的なのだろう。
一方で、企業にとってのデメリットとは何か。
「デメリットは、就活生にとってのメリットと表裏一体でもありますが、内定を辞退される可能性がある点です。たとえば、今回、大学1年生採用制度を導入するサツドラが、大学1年生を採用し、2年間研修をしっかり行ったとします。
実はその学生が、他の企業からすると非常に魅力的な人材に映るのです。社会人としての人材教育をしっかり受けているわけですからね。同業社であっても、まったく無関係の企業であっても重宝されるでしょう。すると、なかにはサツドラよりも良い条件を提示して引き抜こうとする企業も出てくるわけです。
一応、法律上、正式な採用内定通知が出せるのは大学4年生の10月以降ですから、それまでは内々定という扱いになります。もちろん、内定であっても内々定であっても辞退することは基本的に認められていますし、企業側は辞退されたからといって研修費用を請求することはできません。
つまり、学生は内定、内々定を辞退することで不利益を講じることはないため、迷わず条件の良い企業に寝返る可能性は十分あり得るのです。そうなると、せっかく労力とお金もかけた人材教育が無駄になるのですから、企業にとっては大きな損失になるでしょう。要するに、この大学1年生採用制度は、企業側のリスクが非常に高いのです」(同)
企業にとってはハイリスクな採用制度。そこまでのリスクを冒しても、企業はこのような採用制度を実施するのは、なぜだろうか。
「これはあくまでも私の推測ですが、大学4年生から採用を始めて、大学卒業後に内定者研修を行うのは遅すぎると考えているからでしょう。かといって、大学3年生でインターンシップを行ったところで、それは同業他社、あるいは他の業界も含めて多くの企業が行っている。ということであれば、インターンシップを飛び越えて、大学1、2年生から内々定を出すのもアリだと考えたのではないでしょうか。
ただ、このような発想には、おそらく多くの企業が一度は行きつくはずです。ネスレは例外ですが、ファストリとサツドラには小売り流通という共通点があります。また、実はアパレル大手のGAP JAPANも同様の採用制度を導入していた時期があるのです。
昨今、小売り流通は、アルバイト不足が深刻化しています。そこで、大学1年生採用制度を導入することで、アルバイトの確保にもなります。一石二鳥と考え、サツドラはこの制度を始めるのではないかと考えています。
とはいえ、そもそもこの大学1年生採用制度は、新しいようで古い話なのです。ファストリとネスレよりずっと以前の02年に、GAPは大学1年生採用制度を取り入れていました。しかし、結果的にうまくいかなかったのか、05年には制度を終わらせているのです」(同)
13年の時点で「ファストリがユニークな採用方法を開始した」などと大きく報道されたが、GAPはその10年以上前にすでに実施し、数年でひっそりと終了させていたのだ。
●大学1年生採用制度は主流にはならない
最後に、大学1年生採用制度が就活市場に与える影響については、どうか。
「この制度は、そこまで市場に影響しないでしょう。というのも、GAPの前例がありますし、制度自体を疑問視する声も多いため、同業社を含めて導入しない企業が大半だと思います。また、大学との関係を悪くする危険性もありますし、手間暇やお金をかけて人材教育をしたところで、他の企業に引き抜かれるリスクも極めて高い制度です。そのため、主流にはならないでしょうし、就活市場や就活生に与える影響もそこまで大きくないとみています」(同)
失敗に終わった前例もあるからこそ、迂闊に導入できない。まさに“ハイリスク・ハイリターン”な制度なのだ。
(文=A4studio)


















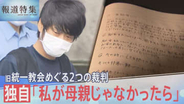











![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



