夢のコラボが実現した「イナダン」フォトギャラリー
「本作をご提案いただいた当初、実は僕はコラボ反対派でした」
本作制作のきっかけについて尋ねると、いきなりそう切り出した日野氏。意外な答えに記者の目も丸くなった。夢のコラボレーションにも思える本作だが、なぜ日野氏は当初、制作に慎重だったのだろうか。
「2つとも自分で作ってきたタイトルだからというのもあるのですが、世界観がごちゃごちゃになって両方にとってよくないコラボになるのではないかという疑問があったんです。たとえばよく仮面ライダーと戦隊物のコラボってありますよね。あれは同じタイプの作品だからありえるのであって、サッカーとロボットがどうやってコラボすればいいのか、非常に大変だと感じていたんです」。
自分で創りあげてきた世界だからこそ、安易に融合させるわけにはいかない。悩みに悩んだという日野氏だが、あるとき2つの作品を汚さずにコラボさせるための答えが見つかったのだという。
「私はお話を作るとき、主人公たちキャラクターが何に悩んでいて、それをどう乗り越えて結末にいくか、ということを一番考えます。この“悩み”がコラボをためらっていたポイントでした。
とはいえ、実際に制作に入ってみると、日野氏は思っていた以上の苦労を味わうことになる。
「私は両作品に関わってきた立場ですが、キャラクターや技などの情報が膨大になりすぎていて、そういう部分の細かいところまですべてを把握しているわけではないんです。たとえばイナズマイレブンやダンボール戦機にはどんな技がどれくらいあって、それがどういうときに使われるのかとか、それぞれのキャラクターの最新の技とか、キャラクター同士の関係性とか、全部に整合性が取れてないと子どもたちは納得しないんです。『もっと強い技があるのになんで使わないの?』ってね」。
苦労のかいあって、熱心なファンも納得できるような熱い作品に仕上げることができたと自信をのぞかせる日野氏。本作の見どころについて日野氏は次のように語る。
「2つの作品が融合された『ダブルバトル』は熱くなりますね。ただ、私は前半25分だけで映画は十分楽しめると思います。その25分で2つの世界観がきちんと融合して熱い気持ちになれますから。最初の25分で出てもらってもいいくらいです(笑)」。
もちろん、その言葉は「最初の25分を見たら最後まで席を立つことなどできない」という自信の裏返しである。
「エンターテインメントとしてかなり成功していると思います。映像もかなりすごくて、子どもだと特に後半は息ができなくなるくらい興奮すると思いますよ。今回の劇場版は映画でないと見られない映像になっていますね」。 不可能にも思えた2つの作品を融合し、見事に違和感のない大作として創りあげてきたレベルファイブ。これまでにも同社は「レイトン教授」シリーズをはじめとして多数のヒット作を世に送り出してきたが、それらのすべてに関わっている日野氏に“ヒット作を生み出す秘訣”を聞いてみた。
「自分流の考え方であって秘訣というわけではないんですが、一番大切なのは子どもの気持ちになることだと考えています。だけどやっぱり自分が子どもの気持ちに100%なることはできないんですよ。そこで私は過去の自分に聞くんです。過去の作品には当時の自分を楽しませてくれた要素がたくさんあって、それを今の子どもたちに届けるにはどうすればいいのか、ヒントを得ることができます」。
ヒット作を生むには過去の作品に学ぶべきという日野氏。では具体的に「イナズマイレブン」や「ダンボール戦機」はどのようにして生み出されたのか。
「たとえば昔、『ミクロマン』という作品があったのですが、実際に作品と同じ大きさのおもちゃが販売されていたんですね。物語の外にちゃんとリアルなものとしてあるおかげで、子どもなりにリアリティを感じて楽しむことができていた。その経験を活かして作ったのが『ダンボール戦機』なんです。あれもLBXのプラモデルが実際に売られていて、作品の設定がそのまま現実にもありますから。『イナズマイレブン』は、『キャプテン翼』や野球漫画の『キャプテン』ですね。ただ、今の子どもたちは『ドラゴンボール』やもっと過激なものも見ていますから、消える魔球くらいで必殺技と言えるかというと難しい。そこで炎をまとったり竜が出てきたりするわけです。それくらいしないと今の子どもたちを驚かせることはできない。子どもたちの本質は今も昔も変わりませんが、見て育った作品は違うので、受け入れてもらうためにアレンジしないといけないのです」。
最後に、今回のようなコラボをまたやるとしたらどんな作品を作りたいかを聞いてみた。
「ヒーロー同士のコラボが大好きなんですよ。だから『アベンジャーズ』みたいに、子どもたちに人気のヒーローが一緒になってすごい悪と戦うような作品を作ってみたいですね。
“どうすれば子どもたちを喜ばせられるのか”――稀代のヒットメーカーの目はすでにはるか先のエンターテインメントを見据えていた。(取材・文・写真:山田井ユウキ)



























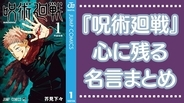


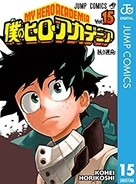

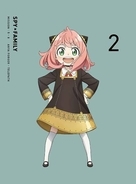


![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








