“町おこし”に成功した「ガールズ&パンツァー」のフォトギャラリー
近年は、映像ソフトのみで展開を行うOVA(オリジナルビデオアニメーション)や、劇場シリーズアニメなどの展開が増えているが、やはり「アニメ」の主役は依然として「テレビアニメ」である。
そんな「テレビアニメ」において、よく大手メディアで取り沙汰されるのは、アニメを利用した「町おこし」という言葉だ。そろそろ「アニメによる町おこし」という言葉も聞き飽きて、耳にタコができている方も居られるだろう。だがここはあえて、2012年のアニメを振り返るという名目のもと、そのタコを再確認・再分析してみよう。
出自は諸説あるが、アニメファンによる地域への経済的効果が知られることになったのは、2007年に放送された京都アニメーションの人気アニメ「らき☆すた」の登場からだろう。舞台となった埼玉県久喜市に、3年間で20億を超える経済効果をもたらした、まさに「アニメによる町おこし」の親とも言えるタイトルだ。
もちろん、現実の地域を舞台としたアニメ作品をネタにした地域振興が、どれもこれも成功しているわけでもない。現在では地域とのタイアップを前面に押し出した作品もあるが、むしろ「らき☆すた」のように具体的な数字を叩き出せた例は非常に少ない。その正否を分ける鍵は、一体どこにあるのだろうか。 まず、ファンの母数を確保するため、作品のクオリティが一定以上に達していることは大前提だろう。
また、地域との連携は必要だが、進んでそれを行なっている作品が、ファンの誘致に成功しているわけでもない。「町おこし」を開拓した「らき☆すた」が分かりやすい例で、「ファンが自分の足でアニメの舞台を訪れる」という行動は、当然ながらファンによって自発的に行われるものだ。あくまで作品への愛情ゆえに行われる行動なので“地域密着アピール”自体に、人を集める力があるとは言い難い。つまり「町おこし」とは、一定の条件と、一定以上の魅力を備えた作品の周囲に発生する“自然現象”のようなものなのだ。
となると「アニメによる町おこし」の成功条件はかなり厳しく、意図してその現象を発生させるのは難しいように感じられる。しかし、今年放送された作品の中に、その数少ない成功例があった。そのタイトルは、茨城県大洗町のローカル祭り「大洗あんこう祭り」の来場者数を前年比約2倍以上の6万人まで押し上げたアニメ「ガールズ&パンツァー」である。 本作では、日本の伝統芸「茶道」や「華道」と同列に、戦車同士で戦う「戦車道」なる武道が存在する世界で、女の子たちが戦車に乗って戦い、日本一を目指すストーリーが展開される。この「ガールズ&パンツァー」を、上記に挙げた条件に当てはめてみたらどうだろう。
基本は「王道スポーツ根性モノ」のラインに沿いつつ、「戦車」(ミリタリー)というニッチな題材を扱うことで、ライトな若年層と、比較的年齢が高い層を同時に取り入れることに成功。さらに、作品の舞台・茨城県大洗町を作中で大々的にアピールしているか、と言えばそうでもない。あくまでストーリーや背景にリアリティを持たせる手段として、キーワードや風景が登場する程度に留めている。
あくまで作品の魅力によって適切な層のファンを集め、ファンの意思によって行動を起こさせる。というスタイルで「ガールズ&パンツァー」は、意図して「町おこし」という“現象”を発生させることに成功した。本作の例は、今後「アニメによる町おこし」を行うための、重要な鍵となるかもしれない。
日本を舞台とした作品では、これからも様々な「町おこし」の施策が行われることだろう。2013年の初頭を飾る作品群にも、埼玉県飯能市が舞台の「ヤマノススメ」や、名前通り歴史モノの「幕末義人伝 浪漫」など、町おこしに関わりそうなタイトルがある。今後これらの作品、またはこれに続く作品が、どのような道を進むのかに注目しておこう。
「テレビアニメ」に続いては、近年大きな躍進を遂げた「劇場アニメ」というジャンルに目を見てみよう。
ここで取り上げるのは、公開1週目にして興行収入28.5億円を記録し、まだその勢いが衰えない「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」や、完全オリジナル作品にも関わらず興行収入40億を突破した「おおかみこどもの雨と雪」など……ではない。それら“大物”の躍進については同タイトルの関連記事をご覧いただくとして、2012年のまとめとして注目したいのはそれ以外。
今年公開されたアニメ映画はゆうに70本を超え、前年の40本台から大幅に増加。まだ公開されて間もない作品もあるので一括りには言えないが、深夜アニメを原作として持つ「ストライクウィッチーズ 劇場版」や「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」、人気漫画作品をアニメ映画化した「劇場版ベルセルク」シリーズなど、平均して興行収入1~3億円を突破する奮戦ぶりを見せている。
……と言っても、実写映画の興行成績から比較すれば、穏やかな数字に見えるかもしれない。しかし、その後に発売されたパッケージ商品、およびその他グッズの売れ行きを見てみると、また見方が変わってくる。先に挙げた作品を例に取るならば、「ストライクウィッチーズ 劇場版」のBlu-ray/DVDは発売初週で売上3万枚を突破し、シリーズ歴代最高の販売枚数を記録。「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」のデータには、劇場内外におけるキャラクターグッズの売上が興行収入(初週)を超えた、という記録もある。それほどに、アニメファンの購買意欲は高いのだ。
筆者も実際にいくつか、アニメ映画の初日上映が行われている劇場へと足を運んだが、そこでは一種の“お祭り”のような空気が感じられた。ファンは、まるで祭りの出店で商品を買うかのように、グッズを購入するのだ。
総合して、ファンの意欲が高いコンテンツである「アニメ」は「映画」という媒体と非常に相性が良い。ということが、2012年のアニメ映画の成績によって分かってきた。今後「映画」という表現手法は、テレビ放送に続く、アニメというコンテンツの展開方法の新たな“軸”になるかもしれない。(文:蒼之スギウラ)























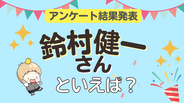



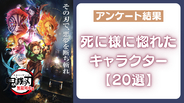

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








