【関連】素晴らしき「妄想科学」が含まれるアニメたち<画像拡大>
超弩級戦艦が宇宙を旅したり、火山口に落ちてもマグマに耐えたり、超加速して目にも止まらない速度で動いたり……。そんな荒唐無稽な世界を、あたかも「もしかしたらありえるかも?」と思わせる。そんな魅惑のこじつけ……もとい「妄想科学」たちを、今回は大きく2つのジャンルに分けて紹介してみる。
■超・拡大解釈
まず、シンプルかつ使われる頻度が最も多いのは“技術と現象の拡大解釈”だ。バトル漫画でよく登場する「力の受け流し方」などの極論科学はだいたいこれ。最近では、西尾維新氏による『刀語』や、同氏が原作を務めた『めだかボックス』などで、活きの良い新鮮な拡大解釈にお目にかかれる。
スケールが大きいものから小さいものまで様々な“拡大解釈”だが、中にはとんでもなく壮大な拡大っぷりをみせる物も存在する。その中でも特筆すべきは『トップをねらえ!』の旗艦・ヱルトリウムだろう。こちらは、「物質の最小単位は素粒子であり、素粒子以下の単位は無い=つまり素粒子は破壊できない」という理屈を元に「じゃあ単一の素粒子で作った戦艦は最強だろ!」という理屈の元で作られた巨大宇宙戦艦だ。
この戦艦は、新たに作られた“人工の”素粒子「ヱルトリウム」で構成されており(戦艦の形をした1個の素粒子と考えると分かりやすいだろう)、物質的な破壊が絶対に発生しない。この圧倒的な説得力に「何かすげえ!」と心躍らされた同士は少なくないはずだ。……「で、結局それをどうやって作ったの?」なんて聞くのは野暮というものである。
こちらは「科学や物理の法則が障害になるなら、新しくルールを作ればいいじゃない!」という考え方だ。壮大な技術に説得力を持たせるための方法として、SF的な要素を含む作品の多くに採用されている。『ストライクウィッチーズ』における「魔力」(このキーワードは色々な作品に登場する)や、『ゲッターロボ』の「ゲッター線」などはこれだ。
最もよく知られている代表例としては『機動戦士ガンダム』シリーズの「ミノフスキー粒子」(ミノフスキー物理学)が挙げられる。初代『機動戦士ガンダム』から始まる宇宙世紀シリーズを観ていると、この言葉がどれだけ便利に使われているか分かるはずだ。
地上で空を飛ぶ技術(ミノフスキークラフト)も、メガ粒子砲もビームサーベルも、ビームバリア(Iフィールド)ですらも、ミノフスキー粒子の存在があってこそ。ガンダム世界の超技術の大半はミノフスキー物理学の恩恵なのだ。なんと素晴らしきミノフスキー物理学! 現実にもおひとつ頂戴したいところである。
重要なのは、これらの「空想」が現実に寄り添っているか否かではない。空想世界の「科学的なもの」や「理屈のようなもの」が如何ほどにファンタスティックで、如何なる感動を与えてくれるか……。それだけが唯一無二の正解なのだ! あなたは、どの作品のどんな「妄想科学」がお好きだろうか?(文:蒼之スギウラ)





















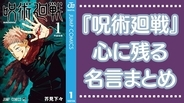







![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








