相続において土地は最も重要な資産の一つですが、その中でも「農地」は特別です。
宅地や駐車場とは異なり、農地には「農業の維持」を目的とした厳格な法律(農地法)が存在します。
そのため、
自由に売ることができない
相続しても農業を継ぐ意思が必要
転用(宅地化)には許可が必要
といった制約が数多くあります。相続時に何も考えずに手続きを進めると、名義変更すらできない、あるいは相続後に税金だけが重くのしかかるという事態も起こりえます。
農地は「農地法」で守られている
農地法の第3条~第5条では、農地の「所有」「賃貸」「転用」などを制限しています。つまり、農地は農業従事者でなければ基本的に所有・利用できないのです。
相続そのものは許可不要ですが、名義変更後に転用や売却を行う場合には、必ず許可が必要です。
相続税の評価も「農地」は特別扱い
農地の相続税評価額は、宅地や雑種地等とは異なり、「農地評価単価(路線価)」が別に設定されています。農地は、収益性が低く、取引制限があるため、宅地よりも評価額が低くなる傾向があります。
たとえば、同じエリアで宅地が1平方メートルあたり10万円でも、農地の評価は1平方メートルあたり2~4万円程度になることもあります。
しかし、「宅地並みの価値がある農地(市街化区域内農地)」は話が別です。将来の転用可能性が高いため、評価が宅地並みに上昇することもあります。
この「地目」と「区域」による違いを理解していないと、想定外に高い相続税が課される場合があるのです。
農地の種類を整理しよう
農地には、相続税法上、次の4種類があります。
つまり、同じ「農地」でも評価や税金の扱いはまったく異なるのです。
「相続しても使わない」場合のリスク
農業に従事しない相続人が農地を引き継ぐと、次のような問題が発生します。
維持管理が困難(草刈りや近隣トラブル)
固定資産税・相続税の負担だけ残る
売却しようにも買い手がつかない
実際、都市近郊では「遊休農地」と呼ばれる放置地が増加しており、行政からの勧告・指導対象や課税強化の適用を受けるケースもあります。
農地の場合、「相続=引き継ぐ」ではなく、どう活用・処分するかを生前から設計しておくことが不可欠です。
農地を売却・転用したい場合の注意点
農地を相続後に売却や活用を検討する場合、次のようなステップが必要です。
地目と区域の確認(登記簿・都市計画図で確認)
農地法許可申請(第4条または第5条)
転用後の登記・税務手続き
特に、農地を宅地や駐車場に転用する場合は、多くの場合開発許可申請が必要で、
都市計画上の制限(市街化調整区域など)
下水道・道路への接道要件
固定資産税の上昇(宅地並課税)
造成工事費用
など、慎重な検討が必要です。また、「売却益は出たが、翌年の税金で赤字」という例も少なくありません。
農地の相続税軽減策:「納税猶予制度」
農地を相続する場合、一定の条件を満たすと相続税の納税が猶予される制度があります。これは「農地等に係る相続税の納税猶予の特例(租税特別措置法第70条の6等)」と呼ばれるもので、相続人が農業経営を継続する意思を示し、実際に農業経営を行うことを条件に、相続税の納税が一時的に猶予されます。
ただし、この制度には厳しい条件があります。
相続人が農業を継続しなくなった場合:猶予税額+利子税を一括納付
農地を転用・売却した場合:猶予取消
認定農業者や相続時の届出期限を過ぎると適用不可
つまり、「相続税を安くしたいからとりあえず申請」は通用しないということです。
「農地を持つ家系」こそ、事前対策が必須
農地を保有する地主や家族は、「誰が農業を継ぐのか」「継がない場合どうするか」を早い段階で決めておく必要があります。
具体的には以下のような事前策が有効です。
農業委員会に相談し、地目変更や転用の可否を確認しておく
将来的な活用を見据え、農地の集約・分筆を検討
相続税シミュレーションを通じて`納税資金を確保
相続登記の義務化(2024年施行)に備え、名義整理を済ませる
農業経営を継続する相続人を確定しておく
こうした準備を怠ると、「相続したはいいが、何もできずに放置」という状況に陥る危険があります。
農地は“資産”であると同時に“責任”でもある
農地は、宅地や賃貸不動産とは性格が異なり、「守る」「活かす」「引き継ぐ」という3つの視点が必要です。
農地は自由に売れない
売却や転用には行政の許可が必要
相続税・固定資産税の扱いも特別
納税猶予を使う場合は「農業経営継続」が前提
相続の場面では「誰が継ぐのか」「どのように使うのか」を明確にしておくことで、家族間のトラブルや税務リスクを大幅に減らすことができます。
また、農地の相続は、登記・税務・農地法・都市計画法など、複数の法制度が絡む複雑な領域です。まずは登記簿上の地目を確認し、農地法の制限を理解することが第一歩です。そのうえで、相続税評価額や生産緑地の指定有無、将来的な活用方針を早期に検討しましょう。
不動産の中でも農地は特に扱いが難しい資産です。放置せず、専門家(不動産コンサルタント・税理士・行政書士等)に相談しながら、家族にとって最適な相続・活用の道を選ぶことが、円満な資産承継への近道です。
佐嘉田 英樹 さかた ひでき アテナ・パートナーズ株式会社 代表取締役。1991年に東京大学卒業後、富士銀行(現・みずほ銀行)入行、主に融資営業・マーケティング戦略企画に携わる。その後不動産・建設業界に身を転じ、建売分譲、賃貸アパート、介護福祉施設等の企画開発・売買などに従事し、2023年8月に独立。
アテナ・パートナーズ株式会社:https://athena-ptr.co.jp/
アテナ・パートナーズ株式会社は、お客様のニーズや目的を詳細にヒアリングして、物件や市場の調査を行った上で、所有不動産の有効活用、開発、建て替え、リノベーション・用途変更、売却、交換など、多角的・戦略的な企画提案・マネジメントを行う。企画計画から資金調達、テナント誘致、設計、工事、引き渡しまで一貫してプロジェクトをマネジメントすることで、独自のビジネスモデルを展開する。 この著者の記事一覧はこちら










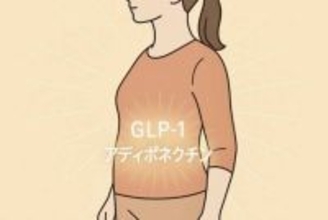








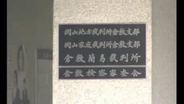






![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)
![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)



![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)





