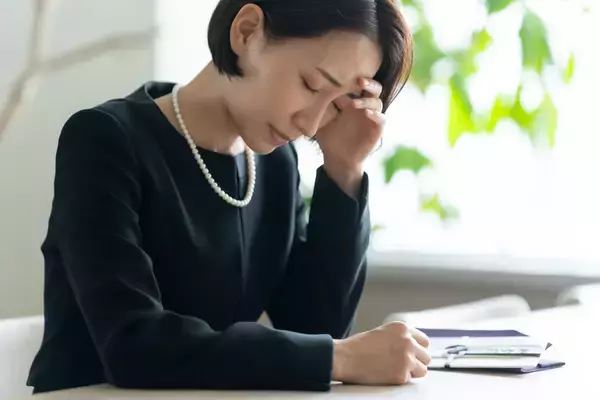
「『家族葬50万円~』という広告を見て申し込んだんです。それなのに、参列者15人の家族葬で、見積額は224万円ですよ!」
そう憤るのは埼玉県のA子さん(60代)だ。
青森県のB子さん(60代)も「希望を無視された」と憤懣やるかたない。施設で急変した父を病院に搬送したがすぐに死亡。病院から「2時間以内に遺体を引き取って」と言われ、大慌てで電話帳を見て葬儀社に連絡したという。
葬儀社には何度も「お金がないので家族葬で」と依頼。6時間も話し合ったが「150万円の一般葬」で押し切られ契約したという。
葬儀関連の契約トラブルが増えている。国民生活センターへの相談も増加し、2024年度は過去最多を記録した。
「今思うと、身内の死に直面して冷静でなかったのかも」と言うのはCさん(50代)。
葬儀後、請求書に「アフターサービス8万円」という項目を見つけ、自宅にしつらえる「あと飾り」のことだろうと思っていた。だが、いくら待っても届かない。葬儀社に聞くと、返礼品の追加がないか、仏具などに不足がないかの確認をアフターサービスと呼ぶらしい。「ただの御用聞きが8万円なんて!」と怒り心頭だ。
こんなご時世でも、D美さん(50代)は葬儀トラブルとは無縁だと思っていた。母が葬儀社と生前契約をし、支払いも済ませたと聞いていたからだ。
だが母の死後、葬儀社から「支払い済みは会場費だけ」と聞かされる。母の契約書は見つからず真偽はわからないが、コロナ禍で小さい斎場への変更を依頼しても「故人の意思だから」と断られた。
母は子どもに迷惑をかけないように生前100万円以上を払ったのだろう。それなのに追加で50万円以上払うことになり、母の思いが踏みにじられた気がすると嘆く。
「多くの葬儀社は親身になって働いてくれますが、なかにはあくどい葬儀社があるのも事実です」
そう語るのは葬祭カウンセラーで特定行政書士の勝桂子さん。
「最近は家族と近しい親族だけで行う『家族葬』を望む人が多く、通夜に親戚や友人が大勢集まって夜通し故人の思い出話をするような従来の葬儀は少なくなりました」(勝さん、以下同)
終活関連サービスを行う鎌倉新書が’24年に実施した調査でも、葬儀を行った人の50%が家族葬を選んでいる。
「家族葬は“密”が禁忌だったコロナ禍で一気に広がりました」
しかし、「家族葬の定義はあいまいだ」と勝さんは指摘する。家族葬は10人までの家族だけで行うものという認識の人もいれば、親戚含めて参列者は30人程度と考える人も。なかには、約50人の葬儀まで家族葬と呼ぶ人もいる。
「定義のあいまいさがトラブルを招くこともあります。参列する人数が違えば、斎場の広さのほか、飲食の費用も変わるでしょう」
加えて核家族化が進み、葬儀に関わることが減っている。伝統的な宗教儀式だけでなく、葬儀費用の相場などを知る人は少ない。
「以前は『故人を立派な葬儀で送りたい』という人が多かったと思います。葬儀費用は、多くの香典でまかなえ、費用の心配があまりなかったからです。
ですが最近は、それらを知る機会が少なく、『葬儀費用はできるだけ抑えたい』という人が増えました。安い葬儀を売りにする業者も現れ、葬儀のやり方もさまざまです。
葬儀トラブルを防ぐには、葬儀「費用の相場」を知ることが大切だ。チャートに沿って整理しよう。まず、家族葬とは“参列者が親族のみで30人までの葬儀”を指すと考えるのが一般的だ。30人を超える「一般葬」はおよそ150万円~で、区別して考えよう。
家族葬を分けるのは「通夜」だ。以前は通夜と葬儀で最短でも2日かかるものだったが、最近は通夜を行わず1日で済ませる選択肢も。
また、葬儀社などの斎場を借りず、火葬場で手を合わせるだけという直葬や火葬式(以後、直葬)と呼ばれる形式もある。
「直葬でも僧侶を呼び、火葬後に料亭で故人をしのんで100万円かかったという事例もありますが、一般的には35万円~でしょう」
通夜はなく、葬儀社の斎場で葬儀、そして火葬を1日で済ませるのが「1日葬」。費用は50万円~。従来どおり2日間で行う「一般的な家族葬」は70万円~だという。
ただし、費用はこれだけではない。1日葬でも一般的な家族葬でも、飲食で費用は大きく異なる。
「通夜では『通夜振る舞い』を、火葬後には親族で『精進落とし』を食べる地域が多いと思います」
葬儀社に依頼すると、通夜振る舞いは1人2千~5千円、精進落としが1人3千~8千円が多い。料理のランクや提供する人数によって飲食代が上乗せされる。
ほかにも忘れてはいけないのが、「御布施」など僧侶に払う費用だ。これは宗派によりさまざまだが、数十万円かかる場合も。
また、たとえ火葬場で行う直葬だとしても、葬儀費用とは別に「火葬料金」が必要だ。火葬場は自治体が運営する地域がほとんどで、火葬料金は無料から高くても1万円前後という自治体が多い。
「東京都だけは別です。公営の火葬場が23区内に2カ所しかなく、民間の火葬場を利用する人が多いのです。そのため火葬料金は約10万円かかると覚悟してください」
そのうえ、香典を受け取ると返礼品を贈る習慣のある地域が多い。多くは「半返し」といって半額程度の品を後日送ることになる。
「費用は香典でまかなえますが、手間がかかるので、最近は香典を受け取らない葬儀もあります」
こうした葬儀の費用は「上限は示せない」のが恐ろしいところだ。
「祭壇も簡素なものから、生花をふんだんに敷き詰める『花祭壇』などもあります。
親が亡くなった直後に、「祭壇はどれにしますか? 花好きの故人には花祭壇が喜ばれますよ」などと持ち掛けられたら、どうするだろう。葬儀の相談は、骨壺は、棺は、遺影は……と細部にわたって決断がつきまとう。身内の死に直面し、心身ともに疲れた状態で冷静な判断など無理なのでは。
「“少しだけいいもの”を選んだら費用が思ったよりかさんだけど、もう一度やり直す気力がなくてそのまま契約する人もいます」
これは、どんなに善良な葬儀社でも起こりうることだ。
「どんな葬儀にしたいのか。その費用はどれくらいが妥当かは、その場に直面してからでは難しい。事前にしっかり考えておくべき」
しかし、高齢とはいえ元気な親に「葬儀の見積もりをとりたい」とは言い出しづらいが……。
「まずは、自分の葬儀を見積もってみましょう。今はネットで一括見積もりができますよ」
だれでも明日死ぬかもしれない。中高年ならなおさら、自分の葬儀代を知っておくといいだろう。
「葬儀を考えるのは、自分の人生のゴールを見つめること。日々の暮らしを振り返るきっかけにもなりますから、おすすめです」
50代後半の記者がネットで一括見積もりを行ってみると、3社から回答がきた。
「項目が細かく分かれ、具体的な金額がわかるところがいいと思います。そのうえで、見積書の不明点や『参列者が思った以上に増えたらどうなる?』といった質問をぶつけてみると、葬儀社の本質が見えます。真摯に柔軟に対応してくれそうな葬儀社を選びましょう」
その後、親に「終活ブームだから、自分の葬儀の見積もりを取ってみた」と見せてから、「お母さんの分も取ってみる?」と勧めるとスムーズだという。
ただ家族葬に固執するのは考えものだと勝さんは言う。
「家族葬で親を送った後、親の友人が『手を合わせたい』と次々に訪れて、かえってめんどうだったという話はよく聞きます」
菩提寺があるなら寺の部屋を借りて通夜葬儀を行う手もあるそう。
「会場費をとらない寺が多いので、御布施を少しはずんでも、葬儀社の斎場を借りるより安上がりです」
人はみんないつか死ぬ。元気なうちから死をもっと身近なものとして話し合っておくことが大切だ。




























![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



