クリエイティブというアウトプットのためのインプット
――現在開催中の「Smile Group presents アニメ音楽のこと!マッチング・オーディション2021」で黒須さんは審査員として参加されていますが、その前に黒須さんのプロになるまでのキャリアをお伺いします。元々黒須さんはクリエイターとして活動する前はバンドをやられていたんですよね。
黒須克彦 そうですね。元々ずっとバンドをやっていまして、いくつかバンドを経たのち、2004~2005年くらいから現在のようなスタンスでクリエイターとしての活動を始めました。
――現在のようなクリエイター活動を始めるきっかけはなんだったのでしょうか?
黒須 きっかけは、その当時いくつかバンドをやっていたのですが、そのときに知り合ったとある出版社の方がいらっしゃいまして。その方と知り合ったときのバンドは解散したのですが、そのときから曲は書いていたので、その方がそのことを覚えていてくださっていたんですよね。それで久々に連絡をくださって、それが今でいうコンペのお話だったのですが「参加してみない?」というお誘いをいただいて、参加させていただいたのが最初ですね。
――以降も膨大なコンペ、あるいは指名という形で楽曲依頼を受けられているわけですが、やはり曲を作るうえではアーティストのことを考えながらの制作になるわけですか?
黒須 そうですね。例えばとあるアーティストさんのコンペで事前情報がそのお名前だけだったら、それまでどういう活動をされてきたのかだったりどういう曲を歌っているのかというのを自分で調べて、声質や音域のヒントにしていますね。
――そうした楽曲制作というアウトプットのためのインプットというのも普段からされているのでしょうか?
黒須 僕の場合は楽曲制作のほかにもライブ演奏などのサポート業もやらせていただくので、色んなジャンルの曲を演奏する機会が多いんですよね。その楽曲を実際にリハーサルに向けて聴き込んで準備をするときもそうですし、実際のスタジオでのリハーサルのときに「ここはどうなってるんだろう?」とかトラックを細かく聴き込むこともあります。
――なるほど。黒須さんは“リスアニ!LIVE”でリスアニ!バンドのベーシスト兼バンマスとして参加されていますが、毎年多くのアニソンに触れる機会があるわけですよね。
黒須 そうですね。それは自分にとってすごくプラスになっていると思っています。クリエイターとして日々新しいものにアンテナを張ってはいますが、ライブで演奏するタイミングで色々なジャンルの音楽に触れることができるのは大きいです。それこそ“リスアニ!LIVE”のように毎年開催されるものは、その年の旬みたいなものでもありますし、その期間にヒットしたものや話題になったものであれば、その空気感も含めて「こういうのが受けているんだ」ということを知ることができるので。
“判断するのは自分ではない”ということ
――さて、そんな黒須さんが審査員として参加される「Smile Group presents アニメ音楽のこと!マッチング・オーディション2021」ですが、まずこのオーディション開催を聞いた感想はいかがでしたか?
黒須 ぶっちゃけ、自分は人を審査できる立場にはないと思っているんですけど(笑)。でも、甲(克裕。スマイルデイズ代表)さんやリスアニ!さんには普段からお世話になっていますし、お声がけいただいたのは光栄でありつつ、何か力になれればというのが正直な感想でしたね。
――ちなみにこれまで、黒須さんはオーディションに応募した経験はありますか?
黒須 スタジオに行って目の前に審査員の方がいて、「ベースを弾いてみて」みたいな経験はないんですよ。唯一それに近いのが、2004年前後だったと思うのですが、自分のデモを色々な作家事務所に送るという……。
――クリエイター業を始めるにあたっての、いわゆる営業というやつですね。
黒須 そうです。作家事務所などのホームページなどで作曲家募集というのがあったので、結構たくさん送りましたね。
――そこから返事があるものもあれば……。
黒須 もちろんなかったところもあります(笑)。
――先ほどコンペのお話がありましたが、現在もコンペに参加されるなかで採用される一方で落ちるケースもあるんですか?
黒須 もちろんです。落ちていることのほうが多いくらいですから。
――黒須さんほどのキャリアの方でしたら指名だけで活動できるのでは、という印象があるのですが、そこでコンペをやられる理由はなんでしょう。
黒須 やっぱり驕らずにいられる、常に地に足をつけられているといいますか。コンペに通らないということはその曲に魅力がなかったということなので、「もっと頑張らなきゃいけないな」と初心に帰ることができるんですよね。
――ちなみに落ちたほうが多いとおっしゃっていましたが、コンペの結果が出たあとの分析などはされますか?
黒須 そのコンペで採用された楽曲が数ヵ月後に世に出たときに、自分から探して聴くことはあまりしないですが、ふと耳にしたときに、「あ、あのときの曲だ……」ってなるわけじゃないですか。そこで分析するほどではないですが、「あの案件はこういうところが求められていたんだ」とは思いますね。
――それを次に活かすこともある?
黒須 例えばですが、同じアーティストさんのコンペが来たときのヒントになりますよね。どういう形で選定されているかわからないですが、コンペのときにこういうタイプの曲が選ばれたということは、こういう方向性を今このアーティストは進んでいるだな、というのがわかるので。
――なるほど。では黒須さんが楽曲制作で気をつけていることを教えていただけますか。
黒須 念頭に置いているのは、“判断するのは自分ではない”ということですね。まずコンペの段階で、提出したものを聴かれるのはディレクターさんやプロデューサーさん、レーベルの方、またはアーティストさんであって、そこでジャッジが下されるんですよね。結局どういうものが求められているのかは案件によっては違いますが、その求められている方向性などの判断をするのは自分ではないということ。ただ、自分的にはそれだけでは面白くないと思うので、そのなかで自分らしさみたいなものや自分が満足できるポイントをどこに置くか、というところのバランスが大事なんだと思います。
――クライアントが求めるものを理解して、そこに自分らしさを込める。
黒須 そうですね。自己満足になりすぎても伝わらないような気もしますし、とはいえ擦り寄りすぎても自分の中で満足感があまり得られないので。いずれにせよ判断するのは自分ではないし、仮にもしその曲が世に出た場合、届ける相手は聞き手なので、そのリスナーがアーティストからどんなものが出てきたら満足するのかというところは頭に置いています。
――クライアントが何を求めているのかを汲み取る感覚も持っているべきだと。
黒須 例えば指名で事前に打ち合わせをしていれば話は別ですが、コンペだとそういうわけにはいかないので、発注書からヒントを探しながらその先にある温度感みたいなものを見つけなくてはいけないなと思いますね。
デモをより伝えやすくするためには?
――音楽的な技術がありつつ、そうしたオーダーに対応できる力もあったほうがいいわけですね。黒須さんから見て、現在求められている人材はどんなタイプだと思いますか?
黒須 今活躍している若い世代のクリエイターにとって、音楽のクリエイト環境は僕らの世代よりも整っていると思いますし、すごく器用にクオリティの高いものが作れると思うんですよね。実際僕もそういう若いクリエイターにお願いする機会も多いのですが、そういう器用なクリエイターって30歳前後にたくさんいらっしゃるんですよ。なので今、“なんでもできる”というのはそんなに強みにはならない気がしていて。
――なるほど。
黒須 今はなんでもできるというよりは、「この人はこういう感じだよね」という特化したものがあったうえ制作をできるのがベストだと思います。例えばヘビーロックが得意、ジャズがすごく得意とか、そういうものがあれば。
――1つ何か光るものを持っているべきだと。また作曲についてですが、メロディはじっくり考えて作るものですか?
黒須 メロディ作りに関しては頭を悩ますことはしていない気がしますね。感覚的に出てくるものを優先するというか。
――直感的に出たメロディを、耳馴染みや歌いやすさというものも考えながら完成形に近づけていくと。そのほかにデモ提出で意識することはありますか?
黒須 許される環境であれば、できるだけ歌と仮の歌詞はついていたほうがよいのではと思いますね。あえて「シンセメロでください」「ラララでください」というオーダーもあるのですが、制限がない場合は人の声で歌われていることと、そのメロディにハマったワードがしっかり乗っているとインパクトが変わると思うんですよね。リフレインされる言葉だったり、作っている段階でこのフレーズにはこのワードだろうということがあった場合、それがラララになると流れてしまうので、そこに印象的な言葉がハマっていくことで聴く側の印象はだいぶ変わってくるような気がします。
――仮歌詞を入れて歌うことでよりイメージが伝わりやすくなるわけですね。
黒須 全部じゃなくてもいいですが、サビの最初のワンセンテンスは決まった言葉があってもいいですよね。例えばそれが曲タイトルになっていって、それが連呼されるんだと印象づけられることがありますしね。
――それこそ黒須さんが作詞まで手がけた「夢をかなえてドラえもん」も、仮歌詞を入れたデモが歌詞ごと採用されたケースでしたよね。あのサビの「シャララララ」というフレーズもデモの段階からあったわけですか?
黒須 そうですね。そこの部分に関しては、作ったときからあのワードが乗っていて、あれが普通の文章だとインパクトが違ったと思うんですよね。それが後々になって「シャララララっていう曲だね」って言われるのはそういうことなのかなって。
――曲の魅力をより伝えるために仮歌詞を入れるというのは大きなヒントですね。
黒須 あとコンペも今回のオーディションもそうですが、聴く側はすごい曲数を聴かれることが多いじゃないですか。提出した曲が良いことは一番ですが、数を聴くなかでどれだけ印象づけられるのかというのが重要になってくるのかなと。奇を衒う必要はないと思いますが、「どう印象づけられるか
というインパクトの与え方という部分でぱっと僕が思いつくことでいえば、歌と仮歌詞なのかなと思います。
次のステップに進んだシーンで暴れ回れる才能を
――今回は募集形態の中に“バンド”というものがありますが、バンドサウンドでの音源というものも1つの魅力になりますよね。
黒須 それは大いにありますね。僕はバンドや生音が好きなので、実際に楽曲提供するアーティストさんでライブをやられている方であれば、この曲がライブで歌っている景色や音をイメージすることはありますね。
――バンドで鳴らすライブというものを、制作からイメージさせる楽曲を作ると。
黒須 シンガーさんであれば、景色的にライブハウスや大きなホール、スタジアムで歌われている場面を想像することもあります。あと、生で歌う何曲かの内の1曲なので、あまりハイカロリーで歌っていてしんどくないものというのも考えたりしますね。やっぱり制作のなかで、その先にあるライブというものは切り離さず考えています。
――バンドサウンドというものがライブの醍醐味の1つでもありますからね。
黒須 生音で鳴らしていることのアドバンテージってものすごくあると思うんですよ。バンドの熱量だったり空気感であったり、例えば4ピースで全員が自分で演奏していくことで温度は上がっているはずなので、技術はある程度必要ではあるものの生で出している空気感がすでにプラスになっていると思いますし、応募する人はそこを大事にしてほしいですね。
――そうしたバンドで活躍するのはもちろん、そこから黒須さんのようにアーティストのサポートで活躍される可能性もありますしね。
黒須 それこそバンドをやりながらサポート活動をされている方もいますしね。ヒトリエさんやPENGUIN RESEARCHさんもそうですが、世代的には30代前後のバンドマンたちが自分たちの音楽も出していて、その傍らでサポート業もフットワーク軽くされているのは素晴らしいなと思いますね。
――そうした例も含めて、業界としてもアーティストとしてもバンドマンの音を求めているということはありますよね。
黒須 そこは決して技術だけではなくて、バンドマン的な音色だったり空気感だったり、アティテュードだったりというのがあると思います。
――バンドマンらしく華のあるプレイヤーも求む、ですね。
黒須 楽しみにしています。
――そのほかにもシンガーの募集なども行っていますが、クリエイターとして黒須さんはどんな歌を聴いてみたいですか?
黒須 それもやっぱり、ライブでかっこ良く歌っている姿が音源から想像できるような人、ですかね。ここも技術ではなくて、リズムが悪かろうがピッチを多少外していようが、それが勢いになっていればきっとかっこいいなと思えるので。
――技術的なものはそのあとの要素でもある?
黒須 そうですね。技術的な部分って長く続けていれば嫌でも洗練されていくので。
――では最後に、黒須さんからアニソンシーンの未来を担う、オーディション参加者の皆さんにメッセージをお願いします。
黒須 ここ1~2年はエンタメ業界が大変な時期でしたが、これからまた1つ次のステップに向かっているような気がしています。そんな過渡期のなかで、今後世の中の情勢的に落ち着いていくとして、音楽がエンタメが息を吹き返したときにはその姿が少し変わっているんだと思います。こういった時期に応募してくれるのはありがたいですし、この業界が次のステップに行ったときに暴れ回るようなアーティストさんやクリエイターさんが出てきてくれたらいいなと思いますね。皆さんにとってすごく良いタイミングだと思いますので、楽しみにしています。
INTERVIEW & TEXT BY 澄川龍一
■「アニメ音楽のこと!マッチング・オーディション2021」特設ページはこちら
●オーディション情報
「アニメ音楽のこと!マッチング・オーディション2021」
<応募資格>
・応募部門自由(ソロシンガー、ユニット、バンド、作詞、作曲、編曲、その他)
・年齢、性別、国籍:不問
<審査員>
渡辺 翔 / 作詞・作曲・プロデュース
黒須克彦 / 作曲・編曲・作詞・ベース・プロデュース
渡辺拓也 / 作曲・編曲・作詞・ギター・プロデュース
PA-NON / 作詞・プロデュース
sana(sajou no hana)/ ヴォーカリスト
甲 克裕 / 音楽ディレクター
<応募方法>
応募フォームよりエントリーをお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGSGRRlK5smi7d9dYN3eE-Nmwmp4ETdwazQeromfgI74pqUA/viewform
<募集期間>
2021年11月17日(水)~2022年1月31日(月)23:59
<応募上の注意>
・審査結果は通過者のみにご連絡させていただきます。
・審査状況や選考結果に関するお問い合わせには一切応じておりません。
・オーディション参加費、選考費、またその後にかかる費用は一切ありません。(ただし、審査会場までの交通費は各自ご負担ください)
・未成年の場合は保護者の承諾が必要です。
・お送りいただいた応募資料は選考以外の目的で使用することはありません。
関連リンク
「アニメ音楽のこと!マッチング・オーディション2021」特設ページ
https://www.lisani.jp/0000187094/
「アニメ音楽のこと!マッチング・オーディション2021」公式Twitter
https://twitter.com/smile_audition
黒須克彦 公式Twitter
https://twitter.com/krossy





















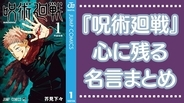
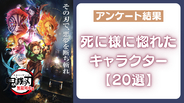






![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








